�ߋ��̃R�����iColumn201�`260�j
�@���ĺ�шꗗ���@�@�@�ŐV�̼��ĺ�т�
![]()
Column260�@�@ �@2008/9/20 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@![]() �@�@�@
�@�@�@![]()
�@�� �u������O�v��������
�@�@�����A�F�X�Ȏ������N����A�N�������ƈ��S�͑����Ǝv���Ă����̂��ߋ��̘b�ƂȂ�܂����˂��B
�@�@�����͑��v���A�L�q�͑��v���A���Ă͑��v���Ɛ_�o���点�Ă���ƁA���Ă̂n�P�T�V�ɂ��H���Ŏ�����
�@�@����́A�܂Ȕ����ł�����A�g�}�g��䥂łĔ甍�����Ă��������v���o���Ă��܂��܂��B
�@�@�A���Ɖ߂���Ή��Ƃ��ŁA���Ԃ��o�ĂA���C�ŋ�����H�ׂ���A�����H�ׂ�悤�ɂ��Ȃ��Ă��܂��킯�ł����A
�@�@����ł����\�A�H�̈��S�Ɋւ�鎖�����������ł��邱�ƂƁA�����ȎE�������̑���������A���S��������O�Ȑ���
�@�@���ł͂Ȃ��Ȃ��ė����ȁA�Ƃ��A�����̐g�̈��S�́A�����Ŏ��Ȃ�������Ȃ����̒��ɂȂ��Ă����ȁ@�Ɛ^���ɍl
�@�@����悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�@���Ă̓�����O���A������O�ł͂Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��v���m�炳��邱�̍��ł��B
�@�@���́A����Șb�́A�d���̏�ʂł����X�������Ă܂��B
�@�@�Ⴂ�Ј��Ɏd���������Ă��Ă��A�u����ȊȒP�Ȃ��Ƃ͒m���Ăē�����O�A�o���ē�����O�B�펯����ˁB�v�Ȃ�Ē��q
�@�@�ŁA���������̎w�������悤���̂Ȃ�A�u�Ȃ�����Ղ�Ղ�B���N�̐V�l�A���ɂ��o���Ȃ��W�����B�v�Ȃ�Ă�
�@�@�ƂɂȂ肩�˂܂���B
�@�@�Ƃ��������ۂɁA���͂ő������Ă���܂��B
�@�@�ł��A�悤�����͂��ώ@���Ă݂�ƁA�ʂɐV�l����łȂ��Ă��A���́u������O����ˁv�Ƃ�������Ȏv�����l�b�N�ƂȂ�
�@�@�āA�������y�ɔC�����d�������܂��i�܂Ȃ��B�R�~���j�P�[�V�������`�O�n�O�B�Ȃ�ł���B�Ȃ�Ă��Ƃ͓��풃��
�@�@���ł��B
�@�@���ŕ����Ă��āA���ł��������ׂ����w�����Ȃ��̂��낤�B���ŁA�����Ԃ��Ȃ��̂��낤�B�Ƃ����d���̉�b���S���S����
�@�@�Ă��܂��B�����Ƃ��݂��ɁA�u�����Ŕ����ȁB�v�u�����Ƃ����Ӗ�����ȁB�v�Ə���ɑz����������Ă���̂ł��傤�ˁB
�@�@�����ő厖�Ȃ̂́A
�@�@�����̓�����O�A�`�N�̓�����O�A�a�N�̓�����O���@������Ƌ^���Ă݂āA������ƍĊm�F���Ă݂邱�Ƃł��B
�@�@�܂萢�̒�������O�Ȃ�ĂȂ��ƁA���݂��̏펯���^���Ă݂�K�v������킯�ł��B
�@�@������Ƒ���Ɋm�F����Ȃ�����A������O���Ƃ��A�펯���Ƃ��v���Ă������Ƃ��A�P�Ȃ����ςɉ߂��Ȃ���
�@�@���ȂƋC�Â����Ƃł��傤�B
�@�@�܂����ɁA��������ςōl����Ȃ́A�x�e�����Ј���A�����̌o�����Ŏd����i�߂�悤�ȕ��ɑ����悤�Ɍ���
�@�@���܂��B����ȕ��ɁA����ɂ�����ƍׂ��ȕ������܂Ŋm�F�����ق����ǂ��ł���B�Ȃ�ď������悤���̂Ȃ�A
�@�@�u�n�������Ă��Ȃ��B �����Ă�Ɍ��܂��Ă邾��B�v�Ȃ�Č����Ԃ��ꂻ���ł����A���Ȃ�A����ȕ��Ǝd����
�@�@����̂͂��f��ł��B
�@�@�ł��A�ł��A
�@�@�u�ߍ��̎Ⴂ�҂́v�Ə펯�̈Ⴂ��Q�����t���A�G�W�v�g�̌Ñ㉤���̈�Ղɏ�����Ă����̂��m�F���ꂽ������
�@�@������B������O�Ƃ��A�펯�Ȃ�Ēʗp���Ȃ���Ƃ����̂͗L�j�ȑO�̂��ƂȂ�ł���B
![]()
Column259�@�@ �@2008/9/19 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ���̉��l�̓}�C�i�X���Ɏ����ǂ�
�@�@�}�C�i�X���������ɂ�����Ɠ`���邩�B
�@�@����͂���Șb�����܂������A���̒��ɂ̓}�C�i�X�����t���Ȃ���i�A�s�n�o�����܂��B
�@�@�g���u���̕ł����悤���̂Ȃ��̂��Ƃ��{�肾���A�{�l�����ł͂Ȃ��A���͂̕����������܂�Ȃ����炢������
�@�@�ӂ߂܂����i���āA���Ȃ��̂��ł��������܂��H
�@�@����ȏ�i�̕����ɂȂ������ɂ́A����ۂǂ̂��Ƃł��Ȃ�����A��i�Ƀ}�C�i�X������镔���Ȃǂ��܂���B
�@�@�悵��A�}�C�i�X������Ȃ������Ȃ�܂���Q�͏��Ȃ��ł����A�}�C�i�X���v���X�ƋU���ĕ���₩��
�@�@���o�Ă���ł��傤�B����͐��̏�B ���R�̂��Ƃł��B
�@�@��i�ɂ��Ă݂�A�d����v���W�F�N�g�����܂��i��ł���Ǝv���Ă����̂ɁA�W���J���Ă݂���A�܂������Ђǂ����
�@�@�Ŏ�x�ꂾ�����Ȃ�Ă��Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B
�@�@�ł��A���Ǝ����A�����Ŋ�������ł�����B
�@�@�E�E�E�Ƃ́A�{�l�͌����Ďv��Ȃ��ł��傤�˂��B �����ƁA�m�����̂悤�Ȍ`���œ{��̂ł��傤�˂��B
�@�@�����Ȃ�ƁA�}�C�i�X�����Ȃ������ł͂Ȃ��A���Ƃ����̏�i�����炩�ɊԈ���Ă��Ă��ӌ������Đ�����
�@�@�������͂��Ȃ��Ȃ�܂��B�܂������Ă݂�Η��̉��l�B
�@�@�l�Ƃ̊W�ɃR�j���~�P�[�V�����̉ʂ����������傫���͓̂�����O�ł����A���̃R�~���j�P�[�V���������ʓI�Ɋ�
�@�@�p���A�o�����̈ӎv�a�ʂ̗�����m�����邩�A����Ƃ�����ʍs�̈ӎv�`�B�ɂ̂ݗ��p���邩�ŁA�R�~���j�P�[�V
�@�@�����̌��ʂ͑S�������̂��̂ƂȂ�܂��B
�@�@�����̕��́A���ӎ��̂����ɁA�����̔|���Ă����R�~���j�P�[�V�������@��ǂ��Ƃ��邩�A�������́A���������R�~���j�P
�@�@�[�V�����Ȃ�ĊT�O���Ȃ������m��܂���B�ł����ɂ́A�����̃R�~���j�P�[�V������@���l�ԊW��r�W�l�X�Ɉ�
�@�@�e��������ڂ��Ă��Ȃ����Ƃ��A����̘b��������Ƃ����Ă��邩�Ƃ���_�����Ă݂邱�Ƃ͐�ɕK�v�ł��B
�@�@���̓_����ӂ��Ă��܂��A���̂�����Ȃ����A���l���F�l���Z���Ԃ��������Ȃ��Ƃ��A
�@�@�r�W�l�X��̘b�Ȃ�A�O�q�̂悤�Ɏ����ɐ�������W�܂�Ȃ��āA���������f���o���Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃɂ��Ȃ�܂��B
�@�@�����đ�U���Șb�ł͂���܂���B
�@�@�ł��A�R�~���j�P�[�V��������������i�߂āA���l��F�l�Ɏ����̍l���������t����̂ł͂Ȃ��A����̍l������
�@�@��A�r�W�l�X�ł���A�~�X��Ƃ���������ӂߗ��ĂĐS�̓�������D����������̂ł͂Ȃ��A�~�X�̌�����q�˂�A
�@�@ ���_���m�F������A����l��������ƈ�����m���ɃR�~���j�P�[�V������[�߂邱�Ƃ� �A�Ĕ��h�~�ƁA������
�@�@�����̈�Γւƃ~�X�������邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł��B
�@�@�}�C�i�X���Ɏ����ǂ��Ȃ����ƁA��������i��ŁA�����̃R�~���j�P�[�V������_�����邱�ƁB
�@�@�ǂ�������ɗ����܂���B���̉��l�ɂȂ�Ȃ����߂ɁB
![]()
Column258�@�@ �@2008/9/18 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �}�C�i�X���������ɓ`���邩
�@�@��Ɠ��ł̏��`�B�A���L�Ɋւ��邨�b�ł��B
�@�@�����A�s�ڎ���i�g���u���ʼnE�����������Ƃ��R�قǂ���܂����A��ƃg�b�v�ɂ���ȓ˔��I�ȏo������}�C�i�X��
�@�@������Ɠ`����Ă����Ƃ��Ă���̂ł��傤���ˁH
�@�@�������A�]�ƈ��������Ƃ����\�l���x�Ȃ�A�����⎖�̂̊T�v�͂s�n�o�ɂ�����Ɠ`���ł��傤���A ����ȏ㑽���̎�
�@�@����������A�c�Ə����̍H�ꂾ�̂��e�n�ɕ��U���Ă����ƂȂ�A�{���̂Ƃ���A�ǂ�Ȏ������N�������̂��A �����͉�
�@�@�Ȃ̂��A �N�������̂��@���X�̏ڍׂ́A���X�A�s�n�o��S�������A�Г��̐ӔC�����ɂ͓`���Ȃ����Ƃ́A �z���ɓ��
�@�@���ł��B
�@�@�o�c�w�����爫���Ɏ����߂Ă���̂Ȃ炢�����炸�A���X�A��������`����Ă��Ȃ����Ƃɂ��炾�o�c�w�͑�����
�@�@���傤���A�R���v���C�A���X���@�Ǘ��ɗ͂����悤�Ƃ��Ă����Ƃł́A�������J���Ă���ł��傤�ˁB
�@�@�Ƃ��A���́A
�@�@�����A�Ζ���Г��̊�Ɨϗ�����@�Ǘ��ɓ���Y�߂Ă����l�ŁA�R���v���C�A���X�ψ���𗧂��グ����A���C��A
�@�@��������J�Â�����Ɠw�͂͂��Ă��܂����A������Ƃ��������̏����Ă��Ȃ������肵�ċ�J���Ă���Ƃ���ł��B
�@�@�Ⴆ�A���Ə��̂��遜�����Ők�x�T�̒n�k���������Ă��A��Q���L�����̂��A���������̂�����Ȃ��B
�@�@�������A���n�ɓd�b���Ă��d�b���q����Ȃ��B �E�E�E�E ����Ȃ��Ƃ͂�������イ�ł��B
�@�@���̂Ƃ���A���̕ӂ�̏��`�B���[���͖��m�ɂ��Ă���̂ł����A�K�������A���[����������Ɨ������Ă�������A����
�@�@��ɂ���Ƃ͌���܂���B
�@�@������Ƃ����������̂��炢�Ȃ�A�}�C�i�X���ł��邪�̂ɁA��������ň���ׂ���鎖�����āA���̒��ɂ͑��X�����
�@�@���傤�B�܂��A���̒��Ƃ͂���Ȃ��̂ł��B
�@�@�ォ�炨�����ƂɂȂ��āA���Œm�点�Ȃ������B�Ȃ�Ăs�n�o���{�邱�Ƃ͉��X�ɂ��Ă���܂��B
�@�@�Ƃ͂����A�����Ȃ��Ƃ܂œ`���Ă��A���f�ł��傤���A�`���鑤�����������������͂Ȃ��B
�@�@�E�E�E���ꂪ�A��ʓI�Ȋ�Ɛl�̍s���A�v�l�ł��傤�B�˂��B
�@�@�ł��A����́A�Ƃ��Ă��O����I�B �E�E�E�E �Q�O���I�̍l�����ł���B
�@�@����ȍl�����̂��Ƃł́A��L����@�Ǘ������蓾�܂���B
�@�@���܂̎���ł���A��Ɠ��̏o�����̓v���X�̏o�����A�}�C�i�X�̏o�����A���̕ϓN�̂Ȃ��o�����ł����Ă��A����
�@�@�S�Ă̓������A�o�c�w�ɗ���A�������̑I������̂͑���ɔC����B
�@�@�Ƃ������l�����ŏ��Ǘ����Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�@�@�ł��A����Ȃ��Əo����̂��H�E�E�E�����炱���A�����Г��ŋ�J���Ă���̂ł����B
�@�@������������Ǝ����ȂƎv���Ă��炤���炤���߂ɂ́A�u�����v�Ƃ���������ł͂Ȃ��A
�@�@�u�}�C�i�X�ȏo�����v���u�}�C�i�X���v�Ƃ��ĕ��ނ��A�傫�ȃ}�C�i�X���A����I�ȃ}�C�i�X���Ɋւ�炸�A������Əo��
�@�@���̓��e���L�^����A��@�Ǘ�����ʼn{���\�ɂ��邱�Ƃ��A�������͂��߂Ă��܂��B
�@�@�����������邩�A�傫�ȏo�������A�͂��傹�ߕt���̔��f�ł������ނł��Ȃ��̂ł��B
�@�@�܂��́A�`���邱�ƁB��L���邱�ƁB���f�͂s�n�o������悢�B�E�E�E����ȍl�����ł��B
�@�@��������ƁA�����������Ƃł��Ȃ��̂ɁA�`���`�������܂ꂽ��A���o������Ă��₾�B
�@�@�E�E�E�܂���������A�������_��������Г��ɂ͂��܂��B
�@�@�ł��A��Ƃł���ȏ�A �C�ɂȂ邱�ƂɁA�o�c�w���@�Ǘ����傪���������͓̂�����O�ł��B���o�������̂�����
�@�@���Ƃ����r�W�l�X�̐i�ߕ���A�����ŏ����͂�����Ō��ʂ����`����悤�Ȏd���̐i�ߕ��́A�o�c���f����点��ő�
�@�@�̌����ł���A�ƂĂ��A�ƂĂ�����x��Ȃ̂��ƁA���x���A���x���������邵������܂���B
�@�@���ɂ́A�s�ˎ����N��������Ƃ̎�������ɁA����Ղ��A���́A����ȑ��Ƃ��������邱�ƂɂȂ����̂��ƁA
�@�@���������Ⴂ�܂��B
�@�@������A�����̐g�ɓ��Ă͂߂āA�^���ɍl����������Ȃ��B�������A�o�c�w�ɂ�����ȕ��������̂��A������Ɠ��ɂ̎��
�@�@������܂����B
�@�@�܂��A��������Ȃ��ł��B
![]()
Column257�@�@ �@2008/9/15 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �x�@�h�ꂳ��́w���[�_�[�V�b�v�̖{���x
�@�@�{���̓��[�_�[�V�b�v�ɂ��āB
�@�@���͎d�����A�V�C�Ǘ��E�̕��X�ɁA���[�_�[�V�b�v�Ƃ͉����Ɛ������邱�Ƃ�����A�����g���A���[�_�[�V�b�v��
�@�@�ĉ����Ƃ��A���[�_�[�i�w���ҁj�ƃ}�l�[�W���[�i�Ǘ��ҁj�̈Ⴂ���ĉ����낤�Ɛ�发���Ђ��������Ƃ������̂ł�
�@�@���A�w��Ђ�����o�������l�A�P���ς�ł��ق����l�x�̒��҂ł�����x�h�ꂳ��̏������w���[�_�[�V�b�v�̖{���x
�@�@�ɖʔ������Ƃ�������Ă��܂����B
�@�@�H���A�g�D�ɂ́A�����ɐl���W�܂����ړI������B
�@�@��Ƃł���A���v�n�o���ړI�Ǝv��ꂪ���ł��邪�A�r�W�l�X�̊�{�͗��v�����`�Ȃǂł͂Ȃ��A�t����
�@�@�l�̑n�o�ɂ�����{������B
�@�@�g�D�̒��Ń��[�_�[�ɂ́A���m�ȃr�W�����������A�����Ɏ���ڕW�A�헪�A���@���l���A�����o�[�ɓO�ꂵ�A �g�D
�@�@�̖ڕW��B�����Ă������Ƃ����߂���B
�@�@�܂����[�_�[�ɂ́A�ڕW�B���̂��߂ɁA�u�l�E���E���v�̎�����K�ɔz���A�z�u���錠��������B
�@�@�܂��A�����g�D�����ׂɂ́A �őO���œ��������o�[�̖����𐁂����邱�Ƃ��K�v�ł���A�J��Ԃ��A�ڕW����
�@�@���A�����Ɍ������ă����o�[�����������Ă������Ƃ����߂���B
�@�@�����āA�����o�[�ɐӔC���������Ȃ����Ƃ������g�D�ɂ͕K�v�ł���B
�@�@�������A����ŕs�łȉߋ��̍��X���[�}�鍑�������]�˖��{���A�i���ɑ������Ǝv���Ă����̂Ɍ��ǂ͖ł�
�@�@�����A���Ԋ�ƂȂ珮�X�ŁA�i���̈���Ȃǂ��肦�Ȃ��B�i���[�}���u���U�[�Y������ł��ˁB�j
�@�@�����āA���݂̂悤�ɍ����̓x������[�߂�Љ� �E�o�ς̊��̕ω��̂悤�ȁA���o���̐V�����ɑ��Ă��A
�@�@ ���[�_�[�͐��������f�����A��������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �̂ɁA���[�_�[�͓�������̒�����A�ω�
�@�@�̐��i�A�������Ă�������A�{�����ł��邾�����m�ɓǂݎ��A�L�����\�Ǝv�����i��s�������Ƃ���
�@�@�߂���B
�@�@�]���āA�ǂ̊p�x��������߂���_��Ȕ��z�������Ƃ������Ƃ��ĕK�v�ł���B
�@�@�A���A��Ƃɂ����ẮA�Ǘ��E�ɔC������Ďn�߂Č����������ƂɂȂ邪�A ���̎��͂��߂ă��[�_�[�V�b�v��
�@�@�������悤�Ƃ��Ă��A�����ĕω��ɂ��Ă����郊�[�_�[�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��B
�@�@���[�_�[�V�b�v�͓V���̂��̂ł͂Ȃ��A�b��������̂ł���A�Ǘ��E�\���R�ɂ́A�����̗L�閳���Ɋւ�炸
�@�@�������A����̍l�����ƍs���Ń��[�_�V�b�v�����Ă������Ƃ����߂��Ă���B
�@�@�E�E�Ƃ����悤�ȓ��e�ł��B
�@�@���[�_�[�V�b�v�_�ɐ����ȂǂȂ��Ǝv�������B���ɔ���Ղ����e�ł��B�����A�قƂ�ǂ̓��e�ɓ����ł��B
�@�@�ł��A������Ă��邱�Ƃ��ǂ����H���悤���Ǝv���ƁA��������ȂƂ̎v�����c��܂��B
�@�@�����Ζ���̊Ǘ��E�̕��X�Ɍ��C���Ő������Ă��邱�Ƃ́A���̖{�ɏ����Ă��邱�ƂƂ́A��̈Ⴂ�͂����
�@�@�����A�܂��A�{���͓����ł��傤�B
�@�@�ł��A�ǂ�Șb�������Ƃ���ŁA �����̃r�W�l�X�X�^�C����[�_�[�V�b�v�X�^�C����ς��Ă܂ŁA�d���̐��ʂ�
�@�@�グ�悤�Ƃ������͂قƂ�ǂ��܂���B�v���ɁA���[�_�[�̕��X�ɕς���Ă���ׂɕK�v�Ȃ̂́A�{�l�̃j�[�Y
�@�@�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�@�@��Ђɂ́A�Ǘ��E��Ǘ��E�\���R�̃��[�_�[�V�b�v�����コ���ċ����g�D�A�����ɘj���Ĉ��肷��g�D�ɂ���
�@�@���ȂƂ����v���͂����Ă��A���[�_�[�{�l�ɂ͂���Ȏv���͂Ȃ��ł��傤�B
�@�@�厖�Ȃ̂́A���[�_�[�V�b�v�̖{������邱�Ƃł͂Ȃ��A���[�_�[�����̋C�ɂ����鉽�����K�v�B
�@�@�����v�����̍��ł��B
�@�@�ł��A���̋C�ɂ����鉽�����āA�����������Ȃ̂ł��傤�˂��H�@��V�B�n�ʁE���_�B��肪���B
�@�@��肪���ȊO�́A���肪����A���Ƃ̕�����S�Ă̊Ǘ��E�̗~���������Ƃ͓�����ł��B
�@�@�E�E�E�E �ƂȂ�ƁA��Ƃ��Ј��ɂ��Ȃ�����̂́u��肪���v�Ȃ�ł��傤���˂��B
�@�@�ł��A��肪�����ĂƂĂ���������ł��ˁB
�@�@�l�����傫���ł��傤���A�y�����d�����肾������A��Ђ��Ј�������ꗿ������ł��傤���ˁB
�@�@�s�u�h���}�œ����b��������ăo���o�����n�k�Ȃ��o�ꂷ��ƁA�L�肦�Ȃ���s�u�̒������ł���B
�@�@�Ȃ�Ďv���Ă��܂��܂��B
�@�@���X������ł��˂��B
![]()
Column256�@�@ �@2008/9/13 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ���������̎��_�Ō���
�@�@��T�̓y�j�̖�m�g�j�Őŋ��Ɋւ��铢�_�ԑg�����f����Ă��܂����B�ɐ�����������b�A�|����������b�A�X�i
�@�@��Y����A�c����y���y���� ���̌o�ς̐��Ƃ̕��X�̑��A�F�X�ȗ���̈�ʂ̕��X���Q������Ă��܂����B
�@�@�ŋ��̎g�����̘b�Ƃ��Ă̔N����蓙�̎Љ�ۏ�⒆����Ǝx���̘b���A����Œl��_�c���A�ŋ����L�[��
�@�@�[�h�Ɍ������c�_�ł��B
�@�@�ŋ��_�c�ɂ��ẮA�F�X�ȗ���A�F�X�ȍl����������̂��Ȃ��Ǝv���Ȃ��猩�Ă����̂ł����A�ƂĂ��C�ɂȂ��
�@�@�ʂ��������܂����B
�@�@����́A�����̕��X���A�����̗���ł����҂����Ă��Ȃ��A�l���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@�@���ɁA��ʎQ���̕��X�̈ӌ��̑吨�́A����Ŕ��A���Ƃ��炽���Ղ�ŋ�������āA������Ƃ��x�����ׂ��B
�@�@ �E�E�E�E �Ƃ����悤�Ȋ����ł��B
�@�@���X�N���o�債�A�撣���Đ��ʂ��グ���҂́A�l�ł����Ƃł���A����Ɍ��������Ԃ����̂����R�o�ς�
�@�@�����B
�@�@�����Ƃ���Ƃɍ��܂ňȏ�̉ېł��ۂ��̂́A�o�ς̒�������܂���A�Ƃ����c��y���搶�̎咣��������
�@�@���ꂪ���ł��B��ʏ������������ꂵ���Ȃ��Ă܂�����˂��B
�@�@�Ƃ͂����A�����܂ő��Ƃ�G�����钆����ƌo�c�҂̕������l�����܂����B
�@�@�h�q��Ȃ�Ă���Ȃ��B�����ɊҌ�����Ƃ��������o�c�҂̕��̌������́A�����̍����̐��ɋ߂��Ƃ͂����A���܂�
�@�@�ɂ��ꌳ�I�Ȃ��̂̌����������Ă��Ȃ��̂��Ȃ��B�E�E�E�Ƃ��������Ȃ̂ł��B
�@�@�В�����́A���Ƃł���A������Ƃł���A��Ƃ��o�c���Ă���ȏ�A�����̐挩���ƁA�����̂��܂��A�l�̎g��
�@�@���̂��܂��ŏ������A�i�C���ǂ���Ζׂ��邵�A�i�C�������Ƃ��ɒׂ�Ȃ��悤�ɁA�����Ⓤ���̈��S�m�ۍ������
�@�@���Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�@�@�d�����o���Ă��A�o���Ȃ��Ă��A���ɂ͕a�C�ŋx��ł������������炦��T�����[�}���Ƃ̑傫�ȈႢ�Ȃ킯�ł��B
�@�@�ߋ��ɖׂ������������Ă���ł��傤�B�Ƃ��������B
�@�@���ƁA�h�q��B
�@�@�Q���҂̕����A��̓I�Ɍ������̂́A���\���������Ԃ��s�@�̍w����p���������B�̎x���ɉƂ�������
�@�@�ł����B
�@�@�����g���C�����Ƃ��ẮA�S�������Ȃ̂ł����A��Âɍl����A���q���̐�Ԃ��s�@���{���ɂ���Ȃ��Ɖ���
�@�@�������̂��B�E�E�Ƃ��v���܂��B
�@�@���O�̖h�q�����������Ȃ��̂Ȃ�A�ČR�Ɏv�����\�Z�ǂ��납�A�����l�����S�Đ������邾���̔�p��
�@�@�S�����߂���ł��傤�B
�@�@�ČR������Ă���Ȃ�������B�@�N������Ă����̂��H
�@�@�N�����{�ɍU�߂ĂȂ��Ȃ��B�����̕����Ȑ��E�̒��ŁA���̎Q���҂͌������̂ł��傤���B
�@�@�������A���̂���ȍl������̈ӌ��ɉ߂��܂���B
�@�@�S�����̈ӌ��̕����炷��A���E�͕��a����B�@���Ȃ��͕��Ă�ƌ���ꂩ�˂܂���B
�@�@���R�A�����Ȃ��݂��܂��A�F�X�Ȍ��������邩�炱���A�o�����X������킯�ŁA�F�ňӌ����o���������_
�@�@��Ȃ�A�ǂ�ǂ�F�X�Ȉӌ��A�������o�Ă����̂ł����A�Q���҂̕��X�̕������́A�ǂ��l���Ă���������������
�@�@���ƐM���A���̈ӌ��������������Ƃ��Ă���悤�ȕ��͋C�ł����B�܂�ŁA�����Ƃ̓��_��B
�@�@���������A�ɐ���b�̈ӌ��́A���Ƃ��Ƃ��A��ʎs������������Ȃł���悤�Ȋ����ŁA����́A�t�ɁA��ʂ̕�����
�@�@���藧���Ă���悤�Ȋ��������܂����B
�@�@�܂��A�J��Ԃ��܂����A���_�ł����āA�őP�̌��_�����߂�킯�ł͂Ȃ��ԑg�ł��B
�@�@�F�X�Ȉӌ���������̂��Ɗm�F�o���������ŗǂ��Ƃ���ԑg�Ȃ̂ł��傤�ˁB �E�E�E�E ������ƃ����������܂����B
![]()
Column255�@�@ �@2008/9/10 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ��E�A�E���͈�x�Ɉ�����I
�@�@�������Ă�����o�Y�ƐV���ɁA��E�A�E���i�z�E�����\�E�j�Ɋւ���L�����ڂ��Ă��āA�Г��R�~���j�P�[�V���������܂�
�@�@�s���R�c���F�X������Ă��܂����B
�@�@��Ƃɂ���������A���̓��̐��Ƃ�g�n�v�s�n�{�̒��҂̕��̃m�E�n�E����D������āA�r�W�l�X�X�L�����Љ�
�@�@����R�[�i�[�ŁA���͂����y���݂ɂ��Ă��܂��B
�@�@���́A����̋L���̒��ŁA�C�ɂȂ����̂́A�ǂ���E�A�E���̗���A������E�A�E���̗�ł��B
�@�@���̂Ƃ���A��Ђ̈̂������A�V���Ј�����O�ɂ��� �u��E�A�E���������v �ƌ����V�[����p�ɂɌ������܂��B
�@�@�ł��A���̎��_�ł́A��i�ɂ́A������ �u��i ��E�A�E��������C�ɂȂ�v ���͋C���Ƃ������̂��K�v���Ǝv���܂��B
�@�@�Ⴆ�A�ǂ�Ȃɂ�����ƕ⑊�k�����Ă��A����ɑ��閾�m�ȃt�B�[�h�o�b�N���Ȃ���A�����͕�E�A�E������
�@�@��Ӗ������o���Ȃ��Ȃ�ł��傤�B
�@�@�������Ȃ���A����ȓw�͂�S�����Ȃ��ŁA��E�A�E������Ȃǂƌ������̑������Ƒ������ƁB
�@�@�R�~���j�P�[�V�����ׂ̈̓w�͂�ӂ��i�́A�ǂ�ȉ�Ђɂ��吨����̂ł��B
�@�@�ւ��������킩�����Ⴂ�܂���B�S���B
�@�@���Ă���ł́A�L���ɖ߂�A��E�A�E�������鑤�̐S���Ƃ��Ĉ��������B
�@�@�� �R�̕�����B
�@�@�@�@����Ȃ��ƃ_���Ɍ��܂��Ă܂����A���X�ƁA�����Ȃ�N�ł�������R��t�����́A���܂���˂��B
�@�@�� ��ς�v�����݂�������������B
�@�@�@�@���������A�����̎v�����݂ŁA�ςȕ����ɐl�̍l����U�����Ă��܂��������܂��B
�@�@�@�@����ȕ��Ə�i���~�X�W���b�W�����Ⴂ�܂��B
�@�@������ɔ��f�̉��ʂ�a���A�����̍l�����Ȃ��B
�@�@�@�@������A����܂��B��̌N�͂ǂ��������B�Ȃ�đ吺���o�����Ⴄ��i������ł���B
�@�@�@�@�ł��A�ʂɑ吺�グ��K�v�͂���܂���B�N�̍l�������Ă���B�@�ƁA���i���猾���悤�ɂ���A������
�@�@�@�@�i�X�Ǝ����ōl����悤�ɂȂ�܂��B
�@�@������āA�R�[�`���O�̍l�����Ȃ�ł���B
�@�@�ł��A��ԋC�ɂȂ����A������E�A�E���̎d���B����́A
�@�@�� ��x�ɂR�ȏ�̎���`����B
�@�@�@�@�����Ȃ�ł��A�l�͈�x�ɂ�����Ɨ�Âɕ������l���邱�Ƃ��o����͈̂�����Ȃ�ł��B
�@�@�@�@�������q�͕ʂƂ��āB
�@�@�@�@�Ⴆ�A��x�ɂR�̎��������Ă��A�R�߂Ȃ�Ċo���Ă܂����H
�@�@�@�@�����Ă��̕��́A�����P�������ł���B
�@�@�@�@���������f�A�A�h�o�C�X��Ⴈ���Ǝv���̂Ȃ�A��E�A�E���Ɍ��炸�A�P�x�Ɉ�����Ƃ����̂̓R�~���j�P�[�V�����p
�@�@�@�@�̓S���Ȃ̂ł��B
�@�@�@�@�ǂ����Ă��A����ɂR�ȏ�̂��Ƃ�`�������̂Ȃ�A�Œ���A��x�ɂR�`���Ĉӌ������߂��肹���ɁA���
�@�@�@�@�A������葊��ɍl���Ă��炢�A������ƊԂ�u���Ȃ��珇�ԂɎ��̘b�Ɉڂ�܂��傤�B
�@�@�@�@�������A����ł��v�l���~�܂����Ⴄ����A�l�������ꂿ�Ⴄ�����܂���B
�@�@�@�@�Ⴆ�A�N���Ɏw��������ꍇ�������B�@��x�Ɉ�����B�o���Ă����܂��傤�B
�@�@�@�@�J��Ԃ��܂����A�R�~���j�P�[�V�����̓S���ł��B
![]()
Column254�@�@ �@2008/9/8 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �d����C�������炢�ŁA�o���邩�H
�@�@��T���́A��Ђ̍s���Ńe���e�R�}�C�ł����B
�@�@�ł��A���T�����\�A��c���l�܂��Ă܂��B�������A���̑����̎i����B
�@�@�Ƃ�����蒆�g���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����Q�T�Ԉʂ͎��t�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@����Ȃ킯�ŁA�d�������͂ɐU��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A��T���̍s���ł́A�����i�K����C�����S���҂��ǂ���
�@�@���A�����ɂ��o���s���ŕs�\���B
�@�@���ƒS���҂̊Ԃɂ���Ǘ��E�̕����́A�S���ɔC��������ƁA�ׂ������Ƃ͋�����C�͖����l�q�B
�@�@�܂��A������P�̋�����@�ł͂���܂����A����ɂ�肯��B
�@�@���̍s���A�Г��s���ł͂Ȃ��A�O���[�v��ЂP�O�Ђ����������Ĕ��\���s�����\�傫�ȍs���ł��B�@�����́A���Ђ����
�@�@����������̂ŁA�ނ�̓��������߂Ă����Ȃ��Ă͂����܂���B
�@�@�Ƃ��낪�A�҂Ăǂ��点�ǁA�������i�܂Ȃ��B�@�e�Ђ��甭�\�������W�߂�����A���܂łɂ́A�W�߂��Ȃ��B
�@�@���܂ɖ{�l����A�������ނ��o���Ă��Ă��A���̏��ނ��悭����܂���B
�@�@�������A���Ԃ̕�����ʂ��čÑ����Ă��A�u�{�l�ɂ͌����Ă��ł����ǂ˂��v�B�ƌ����킯����B
�@�@�������Ȃ��S���҂ɁA�d�������ׂ��Ɏw�����A�ǂ����Ă��A�ނ��\�͓I�ɏo���Ȃ����� �i�s���̐i�s�\�ł��j �͒@�����
�@�@����Ă����܂����B
�@�@�������A���x�́A���̒@��������ƂɁA�e�S���Ƃ̑ł����킹���o���Ȃ��B
�@�@�v�́A�o���s���A�\�͕s���ɂ��A�S���A��ւ͐i�߂Ȃ��̂ł��B
�@�@�������A���ׂ��ɋ������w�������s�����ɁA�ނ͑傫�Ȏ��s�����܂����B
�@�@���\�҂̃s���}�C�N���A���\�҂���シ��x�ɋ����ɕt���Ă����āA�X�Ƀ}�C�N���g���g���ƒ@���āA�����o�邩�܂Ń`�F
�@�@�b�N������悤�Ɏw�������̂ł����A���ꂽ�Ȃ��猩�Ă���ƁA���\�҂̋����Ƀ}�C�N��t���������ŁA�����`�F�b�N����
�@�@���܂���B
�@�@�������A�����`�F�b�N������ƍ��}�����悤�Ƃ��Ă��A�������S�����Ă��܂���B
�@�@�X�ɂ́A���ہA�X�C�b�`�������ĂȂ��āA������̕��X�ɂ͑S���������Ȃ������̂ł��B���\�҂̐����Ⴊ�����悤��
�@�@�������������Ƃ��Ђ����܂����B
�@�@�����悤�ȗނ̎��s�́A�s���̊Ԓ��A���x������܂����B
�@�@���̏ꍇ�́A���O�Ƀ`�F�b�N���@�܂Ŏw�����Ă����킯�ŁA�ނ́A����Ɏ��̋�̓I�Ȏw��������Ɏ����̓��̒��Ńf
�@�@�t�H�������A�u�}�C�N�\�҂ɕt����v �Ƃ�����x���ȍ�Ƃɒu�������Ă����̂ł��傤�B
�@�@�v�́A�����Ă���������Ȑl�ԂƂ����킯�ł͂Ȃ��̂ɁA�R�O�˂��Ă��A�G�p�ȊO���ɂ��o���Ȃ��B���ۂɂ���ȕ�
�@�@�������ł���B
�@�@���ǁA���҂��Ďd����C�����Ӗ��́A�{�l�I�ɁA�傫�ȍs����S�������C�ɂȂꂽ�Ƃ����ȊO�́A�w�ǖ��������悤�ȋC
�@�@�����܂��B�\�͈ȏ�̎d����C���Đ��������҂��邩�A������x���[�����������d���𒅎��Ɏ��s�����邩�A�Ј��̋�
�@�@��ɂ����ẮA��ɔ��f�ɖ����Ƃ���ł��B
�@�@�܂�́A��̓I�Ɏw�������邩�̂ƁA�{�l�ɍl��������̂ƁA�ǂ���͖{�l�̐����ɂȂ��邩�H�@�Ƃ������Ƃł��B
�@�@�����āA����̏o������ʂ��āA�m�M��[�߂��̂́A�d���̖ړI���l������l�Ԃ��ǂ����ŁA�d���̔C�����f
�@�@���ׂ����Ƃ������Ƃł��B
�@�@�Ⴆ�A���ׂ��Ƀ`�F�b�N���@��������Ă��A�}�C�N��t����̂��d���Ǝv���̂�����t�̐l�ԂȂ̂��H
�@�@����Ƃ��A���̕��X�ɑ��A���\���e���m���ɕ�������A������������A�����o�����Ԃ����̂��A�����̖�
�@�@�����ƁA�����o����l�ԂȂ̂��H�Ƃ������Ƃł��B
�@�@����́A�ȑO�ɂ����Љ���R�l�̃����K�E�l�̘b�ɂ��ʂ��܂��B
�@�@�ʂ肪����̗��l���A�������ƍ�Ƃ��郌���K�E�l�ɉ������Ă���̂��Ɛq�˂�ƁA
�@�@��l�ڂ́A�����̓����K��Ϗグ�Ă���ƌ����A
�@�@��l�ڂ́A���������͉Ƃ�����Ă���ƌ����������ł��B
�@�@�����āA�O�l�ڂ̐E�l�́A�V���v�w���K���ɕ�点��Z�܂�������Ă���Ƌ����Č����܂����B
�@�@�����̎d�����Ƃ��ǂ��F�����Ă���̂��́A���̎d���̐��ʂ�傫�����E����͂��ł��B
�@�@�����āA�N�����A�O�l�ڂ̃����K�E�l�̂悤�ɍl���Ă���Ƃ͌���܂���B
�@�@�܂��A������ɂ��Ă��A����ꂽ�Ј��Ŏd�������Ȃ��ɂ́A����𓊂��o���킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ����͎���
�@�@�ł��B
![]()
Column253�@�@ �@2008/8/23 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ���z�̓]���ɂ���
�@�@���Ă��āA����̑����ł��B
�@�@�����̍l����������Ƒ���ɓ`���邽�߂ɂ́A����̗���Ŏv�l���邱�Ƃ��K�v�Ƃ����b�����܂������A�ł��A
�@�@��������l����ƁA���X�A�����̍l�����甲���o���Ȃ������āA����A���z�̓]�����o���Ȃ����Ȃ̂ł�
�@�@�Ȃ����ȂƎv���܂��B
�@�@���Əꍇ�ɂ����܂����A���Ȃ�ɍl����ƁA�����̔��z���ւ���őP�̕��@�́A������Ƃ����A���z��
�@�@�]�����悤�Ȃ�Ă��Ƃ͍l�����ɁA���Ƃ��́A��_�ɔ��z��ς���Ƃ������Ƃł��B
�@�@�Ⴆ�A�o����T���A�P�O���팸���悤�Ȃ�čl����ƁA������������ĂP���A������������ĂP���Ȃ�Ęb�ɂ�
�@�@��܂��B
�@�@�ł��A�o����T�O���J�b�g���悤�Ǝv������A�d���̐i�ߕ��A�����̍l�������܂�����������ϓ_�ōl���Ȃ��Ă�
�@�@�Ȃ�܂���B
�@�@�o���l�ɒu�������Ă������B�P�O�l�ł���Ă����d�����W�l�ł�낤�Ǝv���A�Q�l���̎d�����c��̂W�l��
�@�@���S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�F���當�傪�o��ł��傤�B
�@�@�ł��A�P�O�l�ł���Ă��d�����T�l�Ƃ��A�R�l�ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƂȂ�A���͂₻��ȕ��Ƃ̘b�ł͂�
�@�@���A���܂ŕK�v�Ǝv���Ă�����Ƃ��������̂Ă���A��Ƃ̑唼���O�����āA�c��̂R�l�ŊO����̊�
�@�@�����s���Ƃ����悤�ɂ��邵���Ȃ��ł��傤�B
�@�@�����܂ŁA��Ȃ̂ŁA����ȒP���Șb�ł��Ȃ��ł����A���z�́A����т���ѓ]���͏o���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@�@�����d���̏�ł́A���z�̗��K���Ǝv���āA�`�Ƃ������@�����ǂ���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�a�Ƃ����V�������@
�@�@��T���悤�ȁA���z�̓]����S�����Ă��܂��B
�@�@�����Ď��ɂ́A�`�f�ƁA�a�̂ǂ������������Ɣ�r��������������܂��B
�@�@��_���āA�����������Ɏg����ˁB�Ȃ�Č����Ȃ���B
![]()
Column252�@�@ �@2008/8/18 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �����ԈႢ�̐[�w�S��
�@�@�������ق��A����������u���̉�ŁA�����������ԈႦ�������A���Z�֘A�̃}�X�R�~�W�҂̊ԂŘb��
�@�@�ƂȂ��Ă��邻���ł��B
�@�@��ɂāA�u�i�C�̒���āA������N���O�D�T���ɐ����u���v�Ɣ��\���ׂ��Ƃ�����A�u�N���O�D�V�T���v �ƌ���
�@�@�ԈႦ�Ă��Ă��܂��������Ȃ̂ł����A���������O�D�V�T���ɋ������グ��v�悪�������̂ł͂Ȃ����Ƃ̉�����
�@�@�Ă�ł���̂ł��B
�@�@���̃}�X�R�~�̓ǂ݂́A�S���w�I�ɂ͌��\�����������Ă܂��B
�@�@�Ƃ����̂��A�S���w��ł͂����ԈႢ�́A���́A�����ԈႦ���{�l�̖{���������Ă���ƕ��͂����̂���ʓI
�@�@�Ȃ̂ł��B
�@�@�P���ɍl����ƁA�S�̒��ɋ������ݕt�����{�l�̎v����A���O�̍�Ƃʼn��x���ڂɂ�����A���ɂ��Ă���ԂɁA
�@�@�{�l�̓��̒��ɍ��荞�܂ꂽ�������A�Q�Ă��ۂɁA����������o�Ă��܂��킯�ł����E�E�E�B
�@�@�L���ȐS���w�҂̃t���C�g�́A
�@�@��c�̊J���������ۂɁA��ƌ����Ă��܂����i��҂��A���́A�����ƂɋA�肽�����Ă����Ƃ���������m����
�@�@���Ƃ���A�����ԈႢ�̌������s���A�����ԈႢ�́A�P���ȃ~�X�Ȃǂł͂Ȃ��A�ԈႦ���{�l�̐[�w�S���Ɋ֘A
�@�@���Ă���ƌ��_�t���������ł��B
�@�@���̍l���ɉ����A
�@�@���쑍�َ��g�́A����������̂T�O�������̂O�D�V�T�܂ŏグ�����Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ����ł���킯
�@�@�ł��B
�@�@�F����A�����āA�����ԈႢ�Ŗ{�������ʂ悤�A�����Ӊ������B
![]()
Column251�@�@ �@2008/8/15 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �l�ɕ���`������
�@�@����ɓ`���������Ƃ��A���܂��`���Ȃ��B����Ȃ��Ƃ͂���܂��H
�@�@���Ȃ�������イ�Ȃ̂ł����A�悭�悭�������l���Ă݂�ƁA���́A�������Ė����Ȃ�ł��B
�@�@����Ɏ����̓`���������Ƃ��`���Ȃ������́A�����܂ŁA�������g�̉��l�ρA�������g�̒m���A�������g�̗���
�@�@��E���̊ϓ_�ŕ������l���A���̓��e��ɓ`���悤�Ƃ��Ă��邩��ł��B
�@�@���R�Ȃ���A����ǂ��Ȃ����Ƃ��A���ꗊ�ނ�Ƃ��A�������Ƃ��������́A�m���ɂ��̏�ԂɊׂ��Ă��܂��B
�@�@���ׁ̈A��قǂ̈ȐS�`�S�̊ԕ��ł��Ȃ���A�b���Ă��鑊��ɂ��Ă݂�A���Ȃ����������������̂���
�@�@����Ղ�Ղ�����A���ɁA�������܂��`������悤�ȋC������ꍇ�ł��A�̐S�v�̈�ԓ`�������������`��
�@�@���Ă��Ȃ��B
�@�@ �E�E�E�Ȃ�Ă��Ƃ��B
�@�@������₷���Ⴊ�A�@�B����ꂽ���ɁA�C���̋Ǝ҂̕������p����܂������Ăĉ����Ȃ��킩��Ȃ��B
�@�@�Ȃ�Ă��Ƃł��B
�@�@�܂�́A�����̎��_���甲���o���Ȃ��B����ȕ��́A����`���悤�Ƃ��Ă��A����ɓK�ɂ͓`���Ȃ��ł��傤�ˁB
�@�@�܂��A�N�ɂƂ��Ă��A����̋C�����A����̖ڐ��ɂȂ�͓̂�����̂ł��B
�@�@�ł́A�ǂ�����Ηǂ��̂��H
�@�@���̏ꍇ�́A���̐l�i����j�̒m�肽�����Ƃ͉����낤�H
�@�@���̐l�i����j�̒m���͂ǂ̂��炢���낤�H�@�ƍl���Ă݂邱�ƁB
�@�@�z�����Ȃ���A�{�l�i����j�ɕ����Ă݂�̂�1�̎�B �E�E�E���炢�ɍl���Ă��܂��B
�@�@����ɒ��ڕ����̂��A����Ȃ�A�����Ƒ���́A���̌��ɂ��Ă͏��S�҂Ɠ����B
�@�@��x�ɐF�X�`�����ɁA�P���m���ɗ������Ă��炨���B �E�E�E�Ƃ��v���Ă��܂��B
�@�@�����āA����Ȏ��́A�܂��́A�傫���`���A�������Ă��邩��F�����������āA����Ɋ��ݍӂ��ē`����������܂��B
�@�@�������A��������ԏd�v�Ȃ��Ƃ́A����ɂƂ��Ă͎����i���j������ׂ������Ƃ�A�`���悤�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA��
�@�@�ۂɗ����o���āA�`��������Ƃ��A�S�āB�E�E�E�Ƃ������Ƃł��B
�@�@����ȍl��������Ɉӎ����邱�Ǝ��̂��A�o�����̃R�~���j�P�[�V��������������Œ�������Ǝv���̂ł��B
![]()
Column250�@�@ �@2008/8/10 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �g�n�v �s�n���̌��p
�@�@�����ǂ�ł���o�ώ����L����ƁA�u�u���v ����]�͂�b����I�v�B
�@�@����ȃ^�C�g���ŁA�d���̐i�ߕ��A���̎g�����Ɋւ���L�����œ��W����Ă��܂����B��ɁA�R�~���j�P�[�V�����p�A
�@�@�^�C���}�l�[�W�����g�p�̏Љ�ł��B
�@�@���[�_�[�͑Θb�Ɏ��Ԃ������B
�@�@����ɍl��������ׂɂ͎���ɍH�v���B
�@�@������A�������Ƃ��M���W�ɂ͑�B
�@�@����̗���ōl����B����ɖڐ���������B
�@�@�����𐿂��p����Ɍ�����B
�@�@����͋�̓I�ɁB
�@�@��b�Ƀ��Y�����B
�@�@�����A���Ƃ��g���B
�@�@�܂��́A�������蕷���Ă���A����Ő[�x�肵��B
�@�@�d�p�i����̒m�\�w���j�����p������𗝉��A�S�̋������߂Â���B
�@�@�ڕW�B�����C���[�W����B
�@�@�ڕW�B��������t�Z���ăX�P�W���[���𗧂Ă�B
�@�@�Q�O�F�W�O�̖@���łQ���̂��Ƃɗ͂�����B
�@�@������`���~�߂W���Ŗ�������B
�@�@�L�����ł́A�����l��A���̓��̐��Ƃ��A�T�˂���Ȃ��Ƃ�`���Ă��܂��B
�@�@���́A���̓��e�Ƃ́A�قځA���̃u���O�⎄�̃z�[���y�[�W�œ`���Ă������ƁB
�@�@�����āA�������݂̏o����̖����E�S�Ǘ��E�ɂR�N�Ԃɘj���ă��[���}�K�W���œ`���Ă������ƁB�@��
�@�@�قڈ�v������e���A�L���L�ڂ���Ă���̂ł��B
�@�@���́A���������ŋ߂͂��̃R�[�`���O�̃e�N�j�b�N��������A�t�@�V���e�[�V������������A�S���w��������A����
�@�@�p��������A���Ԋ��p�p�������肷��A����ΑO�����ɐ����邽�߂̐��X�̃e�N�j�b�N���A�ꊇ��ɂ܂Ƃ߂ăR�[
�@�@�`���O�ƌĂ�ł��܂��Ă���܂��B
�@�@���̏�ŁA�����̎�i��p���āA����̃��`�x�[�V���������߁A�O�����ɐ����悤�Ƃ��邱�Ǝ��̂��A���́u��
�@�@���v�ȂƏ���Ɏv���Ă��܂��B
�@�@�ł��A�����g�̊�����ʂ��āA���z�����킹�Ă��������ƁA�c�O�Ȃ��ƂɁA ���̂悤�ȃe�N�j�b�N�����s���葽��
�@�@�̕��X�ɏЉ�Ă��A����������̂��̂Ƃ��Ă��܂��g���Ă�����́A�قƂ�ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�@�����Ă���1�A���̂悤�Ȃg�n�v�s�n�����g�����Ȃ�����ɂ́A�厖�ȏ���������Ƃ��A�m�M���Ă��܂��B
�@�@���̏����Ƃ́A�܂��d���ł��A�v���C�x�[�g�ł��������猻��ɍ����Ă��邱�ƁA�Y�݂�����B�܂����̌����́A��
�@�@�����g�̐l�Ƃ̊ւ�����A�d���̐i�ߕ����ɖ�肪����Ɩ{�l���g���C�Â��Ă���B
�@�@�X�ɂ́A�������g�̕��i�̔�����s���̃X�^�C���B�Ɍ�����ΐ��������̂��̂������Ǝv���Ă��邱�Ƃ��A
�@�@���������g�n�v �s�n ����������Ɗ��p�o���邽�߂̍Œ�����Ȃ̂��A�Ǝv���܂��B
�@�@����ȋC�̖������ɁA�ǂ�Ȃɖ𗧂� �g�n�v �s�n ����������Ă����ʁB
�@�@�S���A�̊����Ă��Ȃ����X�ɁA���̐��͔����������琥����݂Ȃ����ƌ����悤�Ȃ��̂ł��B
�@�@���͍��܂ł̊����ł�����m�M���܂����B
�@�@����������Ȃ̂́A�����I�ɂ͑����̕��X�̃R�~���j�P�[�V�����ɂ͖�肪���邵�A ���͂̕��̃��`�x�[�V��
�@�@���������Ă���������\�吨���āA���X�̐�����d���Ɏx��𗈂����Ă���悤�ȋC�����邱�Ƃł��B
�@�@�v�́A���f�ȕ��͂����ς�����̂ɁA�قƂ�ǂ̕��͎������g�̍l�����A�����A�s�����̃X�^�C�����Ԉ����
�@�@����Ȃ�Ďv���Ă͂��Ȃ��̂ł��B
�@�@���̂悤�ȕ��X�ɁA���ʓI�ȃR�~���j�P�[�V�������@�����������A�ʒk���@�Ɋւ���r�f�I���������肵�Ă��A
�@�@���̃X�^�C���Ƃ͈Ⴄ�B�Ȃ�Ăւ����Ȃ����Ă��܂��܂��B
�@�@�{���̂Ƃ���A�g�n�v�s�n���ɏ����ė~�����̂́A�L���e��e�N�j�b�N�̏Љ�Ȃǂł͂Ȃ��āA�i��Ŏ�����
�@�@�ς��悤�Ƃ͎v���Ă��Ȃ����X���A�ǂ�����Ες�����̂��B�E�E�Ȃ�ł����ǂ˂��B
�@�@�܂��A�i���̉ۑ�ł��ˁB
![]()
Column249�@�@ �@2008/7/31 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �����̂n�k�}�j���A���̓R�[�`���O���W�I
�@�@�@�@�@�@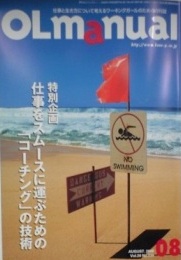
�@�@
�@�@�����́u�n�k�}�j���A���v�̓��W�̓R�[�`���O�ł��B
�@�@�����A�n�k�}�j���A�����āA���̋Ζ���ŏ����ɉ��Ă���`�T�łP�P�O�y�[�W���x�̌������ŁA�ߋ��ɂ����x����
�@�@�Љ���Ă��������Ă���܂��B
�@�@ �������@http://www.kens-p.co.jp/info/olmanual.html
�@�@�c�O�Ȃ���A���X�ł͔����Ă��Ȃ��̂ł����A�d���Ɛ������ɂ��čl���郏�[�L���O�K�[���̂��߂̌������Ƃ�
�@�@������̒ʂ�A���`�x�[�V��������Ƃ������͖{�l�̑O�����Ȑ���������̎x����ړI�Ƃ��āA�r�W�l�X�X�L����
�@�@�����^���w���X�̏Љ�A�E��ł̖������ɂȂ��������ڂ���Ă��܂��B
�@�@�ȒP�����̃��V�s�A�o�Ϗ��̌����A�c����l�t�������̃}�i�[�A�l�ɂ�����ŋ��̒m���A�����Ď��ɂ͓]�E��
�@�@���j���̃g���u������p���f�ڂ���Ă���������܂��B
�@�@���́A���N���w�ǂ��Ă���ƁA�����悤�ȃe�[�}�����J��ʼn���Ă�����̂ŁA�킪�Ђ̏����w�͎ߓǂ݂��āA�Y��
�@�@���Ⴄ���x�̑��������Ƒz���ł��܂����i����j�A���͌��\�͂܂��Ă��āA�K�v�ȕ������R�s�[���āA�e��X�L�����d
�@�@����Г��ł̃R�~���j�P�[�V�����ɗ��p����������Ă��܂��B
�@�@�������A�R�[�`���O��^�ʖڂɏЉ�Ă���Ă��邱�Ƃ�����A���̃u���O��g�o�̖{���̃e�[�}�ɂ҂���Ɠ��Ă͂�
�@�@���Ă���̂ł��B
�@�@�����ƁA
�@�@�悭����ƁA�������̃R�[�`���O���W�̎��M�́A���x������������Ƃ̂���R�[�`�E�g�D�G���e�B�����̕��ł͂Ȃ�
�@�@�ł����B�c�ƒS���Ƃ��Ď��̋Ζ���ɂ������^��ł���Ă�����ł���ˁB �E�E�E�E �撣���Ă��ł��˂��B
�@�@�܂��A���������̂��̂ɂ��Ă����̂͂��������Ȃ��G���B����Ȋ����ł���B�ق�ƁB
![]()
Column248�@�@ �@2008/7/22 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �O���b�O�E�m�[�}���Ƀp���[��Ⴄ
�@�@���̂g�o�⎄�̃u���O��K�₵�Ă�����������X�ɂ́A�S���t�D���̕��͂قƂ�ǂ��Ȃ��悤�ȋC�����܂����A
�@�@�O���b�O�m�[�}�� �Ƃ����v���S���t�@�[�������m�ł��傤���B
�@�@���͂ւ����҂ł��������߁A�S���t�i���v���[����́j�������Ȃ̂ŁA�������N���S���t���牓�̂��Ă��܂����A
�@�@�m�[�}���̖��O�͉ߋ��̉p�Y�Ƃ��ċL�����Ă��܂����B
�@�@�m�[�}���́A���Đ��E�����L���O�P�ʂɂȂ�A����ȃR�[�X�œ�����S�p�I�[�v�����Q�x�������j�ł��B
�@�@�E�E�E����Ȕނ����͂T�R�B
�@�@���̔ނ����N�̑S�p�I�[�v���ʼn��i���B�ꎞ�͎�ʂɂ܂ŁB
�@�@��ʂŌ}�����ŏI���̌��ʂ͂R�ʂł������A�Ⴋ���̊����f�i������ȏ�ɁA���������R�[�X�ɋꂵ��
�@�@�Ȃ���킢�������f���炵�������ł����B�i�S���t���Ă���܂莎�����Č����܂��B�j
�@�@�S���t�͔N��Ɋւ�炸�y���߂�X�|�[�c�B�����͌����܂����A������V�т̃S���t�ł̘b�ł��B
�@�@�^�C�K�[�E�b�Y�ɑ�\�������I�肪��ʑ���������̂�����Ȃ̂ł��B
�@�@�`���̈��ɂ�����T�O��̃m�[�}���̊撣��́A�����̒����N�ɂ��C��^�����ł��傤�B
�@�@�e�j�X�̈ɒB����̊撣��̂P�O�{���炢�͋���������܂�����B�����ĂT�O���ł�����˂��B
�@�@������������Ȓ����Y��Ȃ��T�O��A�U�O��ɂȂ肽�����̂ł��B
![]()
Column247�@�@ �@2008/�V/21 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �X�P�W���[���ɕq���Ȗ�
�@�@���k����A�w�������͂����ċx�݂ł��ˁB
�@�@���w���̖��i�����j�̕����ɍs���ƁA�z���C�g�{�[�h�ɏm�₨�Ղ�A���̑��̗\�肪�L�ڂ��Ă���܂����B�̂���A
�@�@�X�P�W���[���Ǘ��ɂ͕q���Ȃ̂ł��B
�@�@�������O����A�����������́A�ǂ��ǂ��ɍs������˂ƌ����̂��A�ޏ��̌��Ȃł��B
�@�@���́A���Z���̒������A�N���܂Ŏ��������̂ŁA�m��͎�����������A�ŋ߂ł́A�������Z����������ƁA
�@�@�x���ɉƑ��ŊO�o�ł�����������Ă��邩��Ȃ̂ł��B
�@�@�܂��A�������g���U�N���ɂȂ��āA���ɂ��̉ċx�݂͏m�������Ă���A�F�B�ǂ����ŏo������������M�d�ɂ�
�@�@���Ă��܂��B
�@�@���Ƃ��ẮA�Ƒ��ɂ�����Ɨ\�āA�m���ɗV�тɍs�������킯�ł��B
�@�@����ꂽ���Ԃ�L���Ɏg�����߂ɂ́A�X�P�W���[���Ǘ����������Ȃ��B�E�E�E��l�Ƃ��Ă����K���������̂ł��B
![]()
Column246�@�@ �@2008/�V/1 �����@ �@�@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �C���t�H�[���[�V�����ƃC���e���W�F���X�̈Ⴂ
�@�@����A���̋Ζ���Г��ŁA�e����̋Ɩ����{�咷�����A��������ё��̕��咷���A�h�o�C�X��w��
�@�@�E�w���������q������c������܂����B����g���čs�Ȃ��̂ł����A�i��͎��ł��B
�@�@���̉�c�ɂ����āA����̕��傩��A�������� �i�I�t�B�X���݁j �̌��������̂��Ă̕�����܂����B
�@�@���Ђ̕����Ƌ������闧�n�ɂ��镨���ɂ��āA�{�݂̏i�O���[�h�j���W�������͂������e�̕ł��B
�@�@����������Ȃ��A�i��҂̎����C�Â��܂����B
�@�@�F�X�撣���Ē��ׂĂ���̂ł����A���C�o�����育�킢�̂��m�F���������̕��͌��ʂ̂悤�ȋC�������̂ł��B
�@�@�s�n�o�̖����͌����܂����B
�@�@���ׂ��w�͔͂������A�i�C�̈����Ȃ��Ă�����ɁA�ǂ�������C�o���̗D�ʂɗ��Ă�̂��́A���N�����Ă�
�@�@���̂��낤���H
�@�@�����A���̂܂܂ł́A���傤���Ȃ��˂ƈԂ߂������A���݂��ӔC�Ȃ���˂Ɗm�F��������c�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�@��������ɂ���A����̕�ɂ́A��Ƃ��̎��{�ۂ̋c�_������̂ł��傤�B
�@�@���āA���āA
�@�@���͂��邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A���͂��������ǂ����߂��A�ǂ��Ή����Ă������ƍl���邱�Ƃ��ړI�ł��邱�Ƃ�
�@�@�Y��Ă��܂�����Ȃ̂ł����A���͖{���A�ڂɂ����G���ɁA�厖�ȍl�������ڂ��Ă��܂����B
�@�@���́A�{�����A�N�i�x�E�O�������� ���� �D ������̎���B�@�u���m�o�ρv�̋L������Ȃ̂ł����B
�@�@�������́A����̋Ɩ��� �u�C���e���W�F���X�v �Ə̂��Ă��܂��B
�@�@�C���e���W�F���X���m ���H�@�Ȃ�Ďv���Ȃ���A�����̉ߋ��̈�A�̋L����ǂ�ł������Ƃ�����̂ł����A
�@�@�������̌����C���e���W�F���X�͏�͂ł��B�v�́A���O���̓����͂���킯�ł��B
�@�@�ł́A���ƁA�C���e���W�F���X�͂ǂ��Ⴄ�̂��H����Ȓ�`�̘b���ڂ��Ă��܂����B
�@�@�H���A�@���́A�C���t�H�[���[�V�����ƃC���e���W�F���X�ɋ敪�����B
�@�@�C���t�H�[���[�V�����́A�����W�A�ώ@�A�A�摜���A�e��̎��W���ꂽ �u�}�e���A���v �ł���B
�@�@���Ȃ킿���]���A�����H�̏�Ԃł���B�ƁB
�@�@����ɑ��āA
�@�@�C���e���W�F���X�� ���W���ꂽ�C���t�H�[���[�V������ ���H�A�����A���́A�]���A���߂����u�v���_�N�g�v�ł���B�ƁB
�@�@����₷�������ł��B
�@�@���̐����ɏ]���̂Ȃ�A���Ђ̕�ł́A�C���t�H�[���[�V�����i�}�e���A���j�̓��e�ɂ��� ���������������̂́A
�@�@�C���e���W�F���X�i�v���_�N�g�j�ɂ��Ă̐����͂Ȃ������킯�ł��B
�@�@�K�v�Ȃ̂́A���C�o���̋������ǂ����́A���߂��A�ǂ��������ł̂��B����ȃv���_�N�g�ł��B
�@�@�C���e���W�F���X�̑�����A�䂪�g�������ĉ����A���� �N�i�x�E�������́A�d���ɂ����đ厖�Ȃ͉̂������A����
�@�@���悭�����Ă����̂ł��傤�ˁB
![]()
Column245�@�@ �@2008/6/30 �����@ �@�@ �@�@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ��x�ɂQ���A�R���w������ȁI
�@�@���́A����̓y�j���́A���w���̖��̎��ƎQ�ςł����B
�@�@�����Ȃ��A�O���[�v���ɈႤ���t���ŏ��Ԃɉ��t����Ƃ������y�̎��Ƃł��B
�@�@�܂��A�S���Q���̎��Ƃł�����A���t�̃��x���͂���Ȃ�ł�������܂��A�����́A���\ �i���t�j ��ɁA�F
�@�@�X�ӌ����o�����������ł����A�����Ǝ��O�̏����i�K�ł́A�ǂ�Ȋy��ŁA�ǂ�ȃA�����W�ŁA�`�[�����[�N�́A
�@�@���K�́A�ƐF�X�l������A�b����������Ɗw�Ԃׂ����Ƃ��������Ȗʔ������Ƃł��������Ƃ��z���o���܂��B
�@�@���\�����Ă��邾���ł��A���X�ǂ������ł��B
�@�@�ł����́A�C�ɂȂ������Ƃ���B�@���Ƃ��n�܂�O�ɑ��̋������v���v�����Ă������̂��Ƃł��B
�@�@���̃N���X�ŁA�������ړ����悤�Ƃ��Ă������k�B�ɁA�搶���F�X�w�����o���Ă��܂��B
�@�@�}���Ȃ����A���ꂵ�āA���ꂵ�āA���ꎝ���āA���ꎝ���āA������A������ƁA����̎w�����т����肷�邭�炢
�@�@ ��p�����ɏo���Ă��܂����B
�@�@���k�͊F�A���Ԃ�A����ꂽ�w���̓��A���������o���Ă��Ȃ����낤�ȁB����ȋC�����܂����B
�@�@������
�@�@�R�[�`���O�ł͂悭�A����̗����𑣂����߂ɁA��x�Ɏ��������͈̂�����B�Ƃ����l���������܂��B
�@�@�R�[�`���O�́A����Ɏ����ōl����������A �C�t����^�����肵�āA ����I�ȍs���𑣂��ׂ̃R�~���j�P�[�V
�@�@�����p�ł���A������ƍl�������邽�߂ɂ́A���肪������Ɨ����ł���悤�ɘb������K�v������܂��B
�@�@�Ⴆ�A���s���������ɑ��āA
�@�@�@�u��������Ă���H�v�ƌ������Ƃ��Ă��A
�@�@�@�u�����͉������Ă���̂��낤���H�v�Ǝ��₷��̂ł͂Ȃ��A�{��ꂽ�Ǝv�������ł��傤�B
�@�@�ł��A
�@�@�@�u���������Ŏ��s�����낤�ˁH�v�ƁA�}�������ɖ₢������A
�@�@�@�u���s�̌����́A�����낤���H�v�ƍl����ł��傤�B
�@�@�����Ԃ������āA
�@�@�@�u���̌����́A�r���o���Ȃ��̂��H�v�Ǝ��̎��������A
�@�@�@�u�����������߂ɏo���邱�Ƃ͉����ȁH�v�ƍl���邱�Ƃ��o���邩������܂���B
�@�@����̎v�l���m���ɑ������߂ɂ́A��p�����Ȏ���̓}�C�i�X���ʂł��B
�@�@�@�u���[���ƁA���[���ƁA���������B�v�ƍ������邾���ł��B
�@�@������A��x�Ɏ���͈�����B�Ƃ�����ł��B
�@�@����́A��x�Ɏw���͈�����B�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�@���Ȃ��������A�l�ɓ���q�˂āA
�@�@�@�u�������܂������s���āA�Q�ڂ̐M�����E�܁A���̌�A�T�O���ʍs���āA���ԏ�̊p�����܁A
�@�@�@�@��������T�A�U���ڂ̔����Ƃ̘H�n������ĉ�����R���߁B�v
�@�@�Ȃ�Č���ꂽ��A�m���ɍs��������ł��傤���B
�@�@�����ɏ����Ă��炤���A
�@�@�Ċm�F���Ȃ���A�������蓹�̃C���[�W��`���Ȃ��ƁA����ł��傤�B
�@�@������
�@�@�܂��A�w�Z�̐搶�́A�吨�̐��k���Z���ԂɈړ�����̂ɁA���ꂼ��̌W��ɑ��A�Y�ꕨ�Ȃ��A�܂��A
�@�@�s�����ԈႦ�Ȃ��悤�Ɏw���������������̂ł��傤�B
�@�@�ł����Ԃ�A���k�́u���邳���ȁv�Ǝv���������ŁA�w���̒��g�́A�قƂ�Ǖ����Ă͂��Ȃ��ł��傤�B
�@�@���Ȃ��Ƃ��A�F�̕\��͂���Ȋ����ł����B
�@�@�w�����e�������ɂ��āA����ɓn���̂ł͂Ȃ��̂Ȃ�A
�@�@��x�Ɏ���͈�����B��x�Ɏw���͈�����B�E�E�E�R�~���j�P�[�V�����p�Ƃ��Ċo���Ă����đ��͂Ȃ��ł��B
![]()
Column244�@�@ �@2008/6/29 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �t�@�V���e�[�V�����̎���
�@�@����A����n����w�̏A�����q�w����ʐڂ����̂ł����A
�@�@�ޏ��́A�u��w�ŁA�[�~�ȊO�ōŋߊw���Ƃ������ĉ������B�v �Ƃ������̎���ɑ��A
�@�@�u�t�@�V���e�[�V�������w�т܂����B�v �Ɖ����܂����B
�@�@����͕ς�������̂��ȂƁA������Ƃт����肵���̂ł����A�ޏ����w�t�@�V���e�[�V�����Ƃ́A���̃T�C�g��
�@�@�u���O�ł����Љ���A�����̍l������A��c�ł̈ӌ���������Ɛ�������u�t�@�V���e�[�V�����v�ł��B
�@�@�t�@�V���e�[�V�����̃e�N�j�b�N�ɂ́A�R�[�`���O�ƃ��b�v����Ƃ��낪������ł����A
�@�@�Ⴆ�A��c�ɂ����āA���̖������ʂ����̂��t�@�V���e�[�^�[�B
�@�@�t�@�V���e�[�^�[�͒P�Ȃ�i��҂ł͂���܂���B
�@�@���ꂪ�Ⴄ�o�Ȏ҂����̎咣��Η��Ƃ����`�ŕ�����������̂ł͂Ȃ��A�قȂ�ӌ���������Ɛ������A���݂�
�@�@�̈ӌ��̈�v���镔���A�Ë��ł��镔���m�ɂ��A�o���邾�������̏o�Ȏ҂��[���ł��錋�_���܂��B
�@�@�n�ʂ������A�����傫���A�_���I�Ɏv����A�������A�����ӌ��������A
�@�@����ȗ��R�����_���o�����Ƃ��������̒��ŁA�g�D��`�[�����~�X�W���b�W���Ȃ����߂ɂ́A�t�@�V���e
�@�@�[�V�����̎�@�𗝉����A���������_���o������̑��݂͏d�v�ł��B
�@�@���Ȃ݂ɁA�����ӌ����������āA�܂�͑������ŁA�����I�Ȍ��_�������o����Ă���悤�ȋC�����܂����A��
�@�@����Ђɒ����߂Ă�����X��A�����ƊE�ɐg��u���Ă�����X�������W�܂��ĉ�c�����悤���̂Ȃ�A���̏W
�@�@�c�ɂ����鑽�������āA�����č����I�ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�@�����āA���������ɒ�������A�l�����͎��Ă�����̂ł���B
�@�@�l�����������X���c�_���Ă����Ԃł́A�q�ϓI�Ȕ��f�͓�����̂Ȃ̂ł��B
�@�@�Ⴆ�A�D�_���T�l�ŏW�܂��āA�D�_�͂����Ȃ����Ƃ��Ƌc�_�������āA
�@�@�Y�����ɓ���̂͂��₾����A�����~�߂悤�Ƃ������_�ɂ͂Ȃ邩������܂��A�����Ȃ����Ƃ������߂�
�@�@���Ƃ������_�ɂ͂Ȃ�ɂ����ł���B�E�E�E�����ƁB
�@�@�����ȑO�A���l�҂ł���x���r�搶�̍u������u���܂������A�t�@�V���e�[�V�����͂���Ӗ��A�u�ӌ�(���_)
�@�@�̌����鉻�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂����B
�@�@�`�Ƃ����咣�i���@�j�Ƃa�Ƃ����咣�i���@�j�̃����b�g�E�f�����b�g��\�ɂ��Đ����ł���A��͂������h�ȃt�@�V
�@�@���e�[�V�����ł��傤�B
�@�@�X�ɂ́A���Ƃ����ϓ_�ł͂`�̃����b�g�͉��A�f�����b�g�͉��B���Ƃ����ϓ_�ł́A�E�E�B�Ƒw�ʂł���Α債����
�@�@�̂ł��B
�@�@���́A�Z���t�R�[�` �r���������Q�U �u����ꂽ���Ԃ�L�����p����v�ł��G�ꂽ�u�p�b��@�v�ɂ́A
�@�@�W�O�F�Q�O�̖@���ɂ��A�Q�O���̓��蕔�ʂւ̏W���U���I�ȑ��ʂƁA�t�@�V���e�[�V�����ɂ��A�l�����̐���
�@�@��w�ʂƂ������ʂ́A�����̗v�f��������ƌ������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@�@���̊��ɂ͂p�b�́A���̍l���̉ߒ����������e�펑���̍쐬��A���\���@���d������A���\�̏����Ƃ���
�@�@�̖ʓ|�����������݂̂��N���[�Y�A�b�v����A����x��̂悤�Ȉ������Ă���悤�ł��B
�@�@������Ǝc�O�B
�@�@���́A���̋Ζ���ł́A�p�b��@�Ŗ������悤���Ȃǂƌ������Ƃ���A
�@�@�@�u���[�B�p�b�ł����B���Ԃ����邵�A��肽���Ȃ��ł���B�v
�@�@�@�u����ɂ���Ă��������B�v
�@�@�@�u�`��������Ƃ��܂��傤�B�v�@�@�@�Ȃ�ăZ���t����ь����܂��B
�@�@�p�b�Ŕ��\���d�������̂́A�ǂ����̕����ł��܂���������������@���A�Г��ɐ����W�J���邽�߂Ȃ̂�
�@�@�����ǁA�s���߂���������̂ł��傤�˂��B
�@�@���Ԉ�ʂɂ����Ă��A�p�b�͖{���A�����������ׂ���@ �i���ߒ��j �Ȃ̂ɁA���\�̂��߂ɁA�܂��A������
�@�@���₷���������l���Ă����āA�ǂ�����ē������o�����i���ߒ��j�����A��t���Ŏ��������镗��������
�@�@�������߁A�p�b���ʓ|�N�T�C�A�p�b�����_���肫�̎�@�Ƃ����悤�Ȍ�����Q�����Ă���̂ł��B
�@�@�������ȑO�A�Ζ���Г��ŁA�t�@�V���e�[�V�������Љ�郌�|�[�g�𗬂����̂ł����A�p�b�̍l�����ƁA��{
�@�@�͂قړ������ƋC�t�������͂��܂���ł����B
�@�@�܂�A�u�t�@�V���e�[�V�����v �Ƃ��A�u�����鉻�v �Ƃ��́A�����ĐV�����l�����ł͂Ȃ��̂ł����A
�@�@�����܂ŁA�l�����̎�@�Ƃ��Ē��ڂ��A���܂����p����邱�ƂŁA�����������Ă��Ă���悤�ȋC�����܂��B
�@�@���āA�`���̏��q�w���́A�A�E��Ƀt�@�V���e�[�V���������܂���������ł��傤���˂��H
![]()
Column243�@�@ �@2008/6/28 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �N�i�x�E�O�������� ���� �D �̃v���X�v�l
�@�@�F����A���� �D �Ƃ������O���o���Ă܂����H
�@�@���݁A�{�l�̎��̂���Ƃ���ł́A�N�i�x�E�O���������B
�@�@�w�C����ыU�v�Ɩ��W�Q�e�^�őߕ߂��ꂽ�O���Ȃ̊����ŁA�P�A�Q�R�ł̗L�߂�s���Ƃ��āA�ō��قŌW�����Ȃ�
�@�@�ł����A��؏@�j�c���Ƃ̊W����肴������A�O���Ȃ̃��X�v�[�`���Ƃ܂Ō���ꂽ�����̒j�ł��B
�@�@���́A���̍������i�L�ߊm��O�Ȃ̂ŁA�Ăю̂Ă͂�߂Ă����܂��B�j�A�u�T�� ���m�o�ρv �Ƀr�W�l�X�}���Ƃ��Ă�
�@�@�����p�̂悤�Ȃ��̂�{�l�̃m�E�n�E����̌��𒆐S�Ɏ��M���Ă���̂ł����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��̂��́B
�@�@���Z�E�����I�ȕ����������A�܂������A�R�[�`���O�ł���A�R�~���j�P�[�V�����p�Ȃ̂ł��B
�@�@�Ƃɂ����A����ȓ��̂�����A����������̒��ɂ����̂��Ƃ����悤�Ȋ����B�����đߕ߂��ꂽ�O�������Ƃ�����
�@�@�̓��̒��̃C���[�W�����S�ɕ��@����Ă���܂��B�@�������͋��ɂ̑O�����j�Ȃ�ł���B
�@�@�ߕ߂̌����ƂȂ����A���㓇�̃f�B�[�[�����Ɠ��D�ł̎O�䕨�Y�ւ̕X���^��A�C�X���G���̖��Ԋw�҂̏�
�@�@�ٔ�p�̎x�����i�����o���ĂȂ��ł���A����Ȃ��Ɓj���A�������~�ł͂Ȃ��A�O���ȓ��ł͓��풃�ю��̋������A
�@�@���Z�E�����I�Ȏd���̐i�ߕ�����؏@�j�����ł��������߂ɁA�c���^�I�q��b�i�����j�Ɗ��S�ɏՓ˂��Ă��܂�
�@�@���̂������Ƃ��v���Ă��܂��܂��B
�@�@�@�i�����܂ŁA�ނ̕��͂���ސ�����ƂƂ����Ӗ��ł���A�^���͂킩��܂��B�j
�@�@�Ƃ���ŁA���̏T�����m�o�ς̕��͂̓��e�ł����A
�@�@�@�E�`�[���̐l�S�����ׂ̈ɂ́A�����̎�����A�J�ߕ��͂ǂ�����ׂ����B
�@�@�@�E�d����ʂ��������̖ړI�E�ڕW��B�����邽�߂ɁA�ǂ��O�����Ɏd������Ɏ�g�ނׂ����B
�@�@�@�E������E���ǂƂ̒�����L���ɐi�߂邽�߂ɂ́A�ǂ��������p����g���ׂ����B
�@�@�S�Ă����̌��ŏ�����Ă��܂��B���@�_�����Ō��ʂ������Ă��Ȃ��A�{���ɕ����X�̃r�W�l�X�X�L���w��
�@�@�{��R�[�`���O���发�̐��i����s�����e�ł��B
�@�@�������A���ɂ́A����ȃR�~���j�P�[�V�����p���A��؏@�j�������܂��g���āi��ނ킯�ł͂Ȃ��j�A���̕��ǂ�
�@�@���͂��������@�ɂȂ��Ă����킯�ł��B
�@�@���V�A��g�ًΖ��ł́A���W����̃t���A�Ɍ��n�̐��|�l������Ȃ����߁A�����[�Ƃ��āA�l�����₪��
�@�@�g�C���|�����A�ϋɓI�ɂ��Ȃ����Ƃ������Ƃ܂ŏ�����Ă��܂��B
�@�@����o�g�ł͂Ȃ��������������Ƃ��Ă����ɁA�v���X�v�l�ł̏����p����g���A�q�[���i�����j�ɓO���Ă̂����
�@�@�����A�����ė��������̎��^�Ƃ��Ă��ʔ����A�P�s�{�Ƃ��Ă̏o�ł��y���݂ł�����܂��B
�@�@�Ƃ������A
�@�@�ŋ߂́A�����̍s�����A�n���ɂ���Ă��鐢�̒��ɂȂ��Ă��܂������A�����̕��X���āA�\�͓I�ɂ͂��������
�@�@���˂��B
�@�@�ł��A�ǂ������Ɋ�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���˂��B
![]()
Column242�@�@ �@2008/6/26 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �I�[�g�}�Ј�
�@�@�ŋ߁A���ł�����������āA���삪�ȒP�ȋ@�킪�����Ă��܂����ˁB
�@�@�܂��A�g�c�c���R�[�_�[�݂����� ���@�\���i�͕ʂł����ǁA �f�W�J�������āA�l���E���i�ʂɎB��
�@�@�Ȃ�V���b�^�[�����������ł��B
�@�@����@�����āA���ъ킾���āA�w�̉��D�����āA
�@�@�{�^�����������A�J�[�h���������A������O�̂悤�ɋ@�B������ɔ��f���ē����Ă���鎞��ł��B
�@�@�ł��A�Г��łƂ���o����������A������Ƃ���l���������܂����B
�@�@�Ƃ����Ƃ���ʎЈ��ɐ�������ׂ̎������A�R�O�˂̎Ј��ɍ�点���̂ł����A�g�p���Ă���f�W�J
�@�@���ŎB�����ʐ^�̉f�肪���Ȃ舫�������̂ł��B
�@�@�u�������������ĂāA��������Ȃ���B�}�j���A���ŎB���Ă�����B�v �Ǝ��B
�@�@�u�͂��A����Ă݂܂��B�v �ƔށB
�@�@�������A���̌��蒼�����ʐ^���A��͂�ʂ肪�����B
�@�@�u����ǂ������́A�}�j���A���Œ���������Ȃ��́H�v
�@�@�u�}�j���A���ŎB������ł����ǁB�������ƕς��Ȃ���ł���B�v
�@�@�J��������ɂƂ��Ă݂�ƁA�_�C�����͂l�i�}�j���A���ݒ�j�̈ʒu�B
�@�@�����ɁA�I�o�����{�^�����Q���āA�Â߂ɐݒ肵�ĎB�e���A���j�^�[�Ŋm�F������Y��Ɏʂ�܂����B
�@�@�u���������A�Y��ɎB��邼�A������Ă��́B�v
�@�@�u���[�B�_�C�������l�ɂ��ĎB������ł����ǂ˂��B�v
�@�@�u�_�C�������l�ɂ��ĎB�����H�ł��A�ǂ����������́H�v
�@�@�u�����I�������āH�}�j���A���i�l�j�ɂ���A�������Y��Ɏʂ�̂���Ȃ���ł����H�v
�@�@�u�����Œ�������邩��`�������Ȃ�ł����āA�}�j���A���͎����Œ�������Ɍ��܂��Ă邾��B�v
�@�@�u�����A�����Ȃ�ł����B�m��܂���ł����B�v
�@�@�u�J�����́A�s���g��V���b�^�[�X�s�[�h��A�I�o �܂薾�邳�����Ȃ����邾��H
�@�@�@�`�������Ȃ�J����������ɔ��f���Ē������邯�ǁA�}�j���A���ł͎����Œ��������B�v
�@�@�u�����A�J�����̖��邳���Ē����o�����ł����H�{�^�����������̂��ƁE�E�B�v
�@�@�u�Ԃ����āA�����ŃM�A���ς�邩��I�[�g�}�Ȃ�A�蓮�ŃM�A��ς���̂̓}�j���A���ł���B�v
�@�@�u���������A���K���ł̓}�j���A���Ԃł����ˁB�v
�@�@�@�i�ނ��I�[�g�}�Ƌ���������A��Ȃ��b�������ŏI����Ă�Ƃ���ł�����B�j
�@�@�u�d���Ƃ��āA����������Ă���Ă����A����Ȃ���������ǂ�ʼn������Ȃ�����_���ł���B�v
�@�@�u�͂��B�v
�@�@�����ł��A�ނ́A���������{�^�������������Ŏʂ�J���������m��Ȃ������̂ł��B
�@�@�}�j���A���Œ�������J�����Ȃ�Č������ƂȂ��Ƃ������Ă܂����B
�@�@�E�E�g�ѓd�b�̃J���������āA�B�e�V�[���ɕ����ĐF�X�����o�����ł����ǂ˂��B
�@�@���������ΈȑO�A�s�����r�f�I�B�e��������A�₽��f�肪���������̂����������Ǝv��������܂����B
�@�@�@�i���̖��邳�����r�f�I�̎��������͈̔͂��Ă����̂ɁA�������Ȃ������̂ł��B�j
�@�@���[��A����Ȏ���Ȃ̂ł��B
�@�@�r���v�����āA�d�g�Ŏ���������������鎞��ł��B
�@�@�R�O���炢�܂ł̎Ј��ɂ́A�u���̒��ɂ͎����Œ������Ȃ���g���Ȃ�����������B�v �Ƃ�����
�@�@���A���J�Ɍ���Ȃ���C�J���̂ł��傤���˂��B
�@�@�@�i�Q�O�P�T�N���߁j
�@�@�@�@�S�O�ɂȂ鍡�̕����̕������f�W�^���J�������}�j���A���ŘI�o�������ł��邱�Ƃ�m��܂���
�@�@�@�@�ł����B���������I�o��i��Ƃ������ʒ����̌��t��m��Ȃ��悤�ł��B�߂�������ƂȂ�܂����ˁB
�@�@�������A���̐���̋��ʓ_�́A�ǂ����Ƀ}�j���A�� �i�������̈Ӗ��̃}�j���A���j �͂Ȃ��ł����H
�@�@�Ƃ����������������ƁB
�@�@�ނ�A�Ƃقق��I�ȎЈ��̂��Ƃ� �u�}�j���A���Ј��v �ƌĂ�ł����̂ł����A
�@�@�ǂ���� �u�I�[�g�}�Ј��v �ƌĂԂق����A�K�ȌĂѕ��̂悤�ȋC�����Ă��܂���
![]()
Column241�@�@ �@2008/6/1 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �S�̈Łi�a�݁j
�@�@�Q���������J���~�݁A�{���͂����ĕς���āA�u�₩�Ȓ��ł����B
�@�@������Ɨ������ł����A�O�i�����āj�ɏo��Βg�������ł��B
�@�@�c���}���\��������悤�ł����A����₷���ł��傤�ˁB�ނ���A���������B
�@
�@�@�ł��A�����́A�Ƒ��Œ��H���Ƃ�Ȃ���A�s�u�̂m�d�v�r�����Ă����̂ł����A�]����̂n�k�E�l�����̔�
�@�@�l���A�����Đ�c���q�A�i�E���T�[�̎��E���Ƃ肠���Ă��܂����B
�@�@���́A�]����̂n�k�E�l�����̌���́A���̋Ζ��悩���r�I�߂��̂ł��B
�@�@��̂��o���o���ɂ��Ď̂Ă��Ⴄ�Ȃ�āA��I�ŕ|���Ƃ����O�ɁA �ŋ߂̎����́A������Љ��
�@�@���ŗǂ��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�@�@�E�l��Ƃ��B��̂��o���o���ɂ���B����ȋ֔�I�Ȃ��Ƃ��A����ƒ�R�Ȃ��s����悤�ɂ鐢�̒�
�@�@���̂��̂����狰�낵���ł��ˁB
�@�@
�@�@�����́A�n�k�E�l�Ƃ͎q���̍�����A�]�Z���J��Ԃ��A�ЂƂ�ڂ����ŁA��Ђɓ����Ă�����l�t��������
�@�@���肾�����B���i���䂪��ł��܂����̂ł͂Ȃ����Ƃ����悤�Ȍ��ߕt���I�ȓ��e�B
�@�@�m�d�v�r�����Ă������������܂����B
�@�@�u�F�B�́��������ȂU��������z���Ă���悤����B�v�i���w���łU��͂������B�j
�@�@�ł��A�]�Z���J��Ԃ��Ɛ��i���䂪�ނ̂��H
�@�@���i���䂪�ނƁA�l���E���̂��H�E�E������āA����ό��ߕt���Ȃ̂ł́B
�@�@�����Ď��グ��ꂽ��c����̎��E�ɂ��ẮA�ŋ߂̂���Ԃɂ��Ẵu���O��A���z���̎�
�@�@�͂̊W�҂̏،�����̐��@�B
�@�@�Q�O�`�R�O��̏����̑������A�A���P�[�g�ɑ��A ��c����̎��E�̌������s���ł���ɂ�������炸�A
�@�@�������s���ȋC�����A���ɂ͎��ɂ����Ǝv���B�Ɖ��Ă�����e���Љ�Ă��܂����B
�@�@���k���肪���Ȃ�������A�ǂ�Ȃ��ꂢ���Ƃ������Ă����ۂɂ͑��݂���Љ�̐��ʂɑ���i���B
�@�@�撣���Ă���i�����A�����j�������Ȃ��B�����Ă��闝�R�E�ړI���킩��Ȃ��Ȃ����B�����Ă���Ԃ��甲
�@�@���o���Ȃ��B
�@�@�E�E�E����ȕ��͑吨����̂��낤�ȁB
�@�@�ł��A���̌�Ō����ԑg�ŁA���o�J�|�l�Ƃ��Ęb��̈�l�ł���X�U���k���A���������܂ꂽ�Ӗ���
�@�@�����Ƃ�������Ɂu�K���ɂȂ邽�߁v�Ɠ������Ƃ����G�s�\�[�h���Љ��A�u���̒����܂��̂Ă����̂ł�
�@�@�Ȃ��ȁB�v�Ȃ�Ďv���Ă��܂��܂����B
�@�@�]����̎E�l�Ƃ͂R�R�ˁA��c����͂Q�X�ˁB�N��Ƃ��Ă͂قړ����Q�l�̐S�̈ŁB �����̓��e�͑S����
�@�@�����A�Q�l�̂������������̎�ނ��S�R�Ⴄ�悤�ɂ͎v�����ǁA�a��ł��鐢�̒����_�Ԍ����Ă���悤
�@�@�ł��B
![]()
Column240�@�@ �@2008/5/31 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �ԈႢ�̌����Ƒ���l����
�@�@����ǂ�ł��������ɂ���Ȃ��Ƃ������Ă���܂����B
�@�@�u�ԈႢ���J��Ԃ��l�Ԃ́A�o���悤�Ƃ���C���Ȃ��l�Ԃ��A
�@�@�@�����łȂ���A���̔C���ɑ��鎑���Ɍ�����l�Ԃł���B�v
�@�@�Ƃ��錵�����C���Ɋւ���I�������ɂ��Ă̎��^�����ł��B
�@�@�o�ꂷ�鋳���́A�O�q�̃Z���t�������Ȃ���A�o�b�^�o�b�^�ƌP���������i�ɂ���̂ł��B
�@�@���ۂ̐g�̉���U��Ԃ��Ă݂�ƁA�����ԈႢ�����x���J��Ԃ��҂͉��l�����邵�A����ȕ��ɉ��x���ӂ��Ă��A
�@�@�ނ̍s�������P����C�z�͑S������܂���B
�@�@�����̂悤�ɁA���̎d���ɑ��鎑�����Ȃ��̂ŌN�͎��i�B�Ɛ�̂Ă�������ł����A���ۂ̐��̒��ł́A
�@�@�u���]�є��N���v���炢�̋C�����Ŏw�����Ȃ��ẮA�Ј�����l�O�Ɉ�Ă邱�Ƃ͏o���܂���B
�@�@�����g�����āA�\�����Ȃ������ɂ��ւ�炸�A�����ԈႢ�����邱�Ƃ͎��X����܂��B
�@�@�u���������ȁA�C�����Ă����͂��Ȃ̂ɁA���œ����ԈႢ�������̂��낤�B�v����Ȕ��Ȃ��J��Ԃ��Ă��܂��B
�@�@�v���ɁA�u�ԈႢ�v�ɂ́A�u�ԈႢ�Ɏ��铹�v�������āA�u�Ԉ���Ă���v�Ƃ���������A�P�ɂ��́u�ԈႢ�̌����v��
�@�@�C�t���������ł́A������ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�����ƁA�u�ԈႢ�̌����v�����������ɁA���̌�̍s�����A�u�ԈႢ�Ƃ������ʁv�ɂȂ���Ȃ��悤�ɁA�����̍s����
�@�@�R���g���[���o����Z�\���K�v�Ȃ̂ł��傤�B
�@�@�����炭�u���̔C���ɑ��鎑���̂�����v�ɂ́A�ȒP�Ȃ��Ƃł���A���ɊԈႢ��Ƃ��Ă��A�Q�x�ڂ͊ԈႢ�Ȃ��s
�@�@���ł���̂ł��傤�B
�@�@�ł��A�����̐��̒��ł́A�u�ǂ����Ԉ���Ă�Ǝv���H�v�Ƃ��A�u�ԈႢ�̌����͂ȂƎv���H�v�A�u�ǂ��s������A
�@�@�ԈႢ��h����Ǝv���H�v�Ȃ�Ď����ɂԂ��A�{�l���g����������A��������P����l���āA�����̍s��
�@�@�Ƃ��Ē蒅�����邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�@�����āA���ꂪ�R�[�`���O�̍l�����Ȃ̂ł��B
�@�@�������A�����ŊԈႢ�ɋC�t�����Ȃ�A���₵�Ȃ���A���P����l�������Ă����킯�ł��B
�@�@�܂�́A�Z���t�R�[�`���O�ł��B
�@�@�u�ԈႢ���J��Ԃ��l�Ԃɂ́A�������E���P�����������ƍl��������B�v�@����Ă݂܂��傤�B
![]()
Column239�@�@ �@2008/5/30 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �ߋ��̍s�����疢����z������
�@�@���̋Ζ���ł́A�����̗p�V�[�Y���B
�@�@�Ƃ����킯�ŁA�w���̖ʐڂ�p�ɂɍs���Ă��܂��B
�@�@�����A���w���̕��X�ɕK���u������̈�ɁA�u�A�E�����玩���̒��ʼn����ς��Ǝv���܂����H�v�Ƃ������̂�
�@�@����܂��B���ɃA�o�E�g�Ȏ���ł����A�A�o�E�g�����炱���A���̊w���̍l�������킩��܂��B
�@�@�u�Љ�l�Ƃ��āA���ȐӔC�ōs�����Ă����Ǝv���܂��B�v�Ƃ������悤�ȃ��x���̕Ԏ������҂��Ă���̂ł����A����
�@�@����͂���܂���B
�@�@���ɂ́A�u�����Ȃ肽��������ڎw���āA�ڕW�����N���A���Ă������ƍl���Ă��܂��B����́A�w���̍����A��
�@�@��l�ɂȂ��Ă��ς�肠��܂���B�v�Ȃ�Ă��Ƃ��������������h�Ȋw�������āA�т����肵��������܂��B
�@�@������O�ł����A
�@�@��Ƒ����ʐڂŒm�肽�����Ƃ́A�w�������Ђ��A��Ђ̒��ŁA
�@�@�@�@�E�����ǂ�Ȑl�ԂɈ���H
�@�@�@�@�E��Ђɍv���o����l���ɂȂ�̂��H
�@�@�@�@�E��y���w�����ă`�[���Ƃ��Đ��ʂ��グ���悤�ɂȂ邩�H
�@�@�Ƃ����悤�Ȃ��ƂȂ̂ł��B
�@�@�������A�����������A
�@�@���́A�w������ɑ��鎿��̂قƂ�ǂ́A�ߋ��̍s������тɑ�����̂ł��B
�@�@�ǂ�ȕ��������̂��H
�@�@���i�͉����擾�����̂��H
�@�@������A���o�C�g�ŋ�J�������Ƃ͉����H
�@�@���X�B
�@�@�ߋ��̍s�����疢����z������B���̎�����͂ށB���ꂪ�A�̗p�ʐڂ̍ő�̖ړI�Ȃ̂ł��B
�@�@�Ⴆ�A�ǂ�ȕ������Ă����́H�ƌ���������A
�@�@�ʂɁA���̕�����ЂŖ𗧂��ǂ�����m�肽���킯�ł͂Ȃ��A�������ꐶ������������ǂ�����m�肽��
�@�@���Ƃ͂������A���Ԃ���Ɨ��Ƃ����Ή����ĕ����Ă��邱�Ƃ��A�ǂ������Ă���̂��A���̐��ʂ�{�l
�@�@���ǂ����߂��Ă���̂���m�肽���̂ł��B
�@�@�ł����ɂ́A�u���₠�A���܂�����Ă��܂���B�v�Ȃ�ē�����w�������܂��B
�@�@���̎�̕��́A���\�����̂ł����A���ꂾ���āA�{�l�̒��ŁA�w�Ƃ�a���ɂ��閾�m�ȗ��R�⑼�̖ڕW��
�@�@����A�܂������̂ł��B
�@�@�ł��A���������́A�u�Ԃ����Ⴏ�A���͌����Ȃ�ł��B�v�Ȃ�ė��R�������肵�܂��B
�@�@���������A���Ⴀ�A�s�����Ȏd��������Ə�i�Ɍ���ꂽ��A�蔲����������肩�B
�@�@������A���o�C�g�̐�y�ƎG�k���Ă������ɂȂ��Ă���̂��B�@�E�E�E�Ȃ�āA���C���^���Ă��܂��܂��B
�@�@���́A�{���̌ߌ���A�ʐڂ�����܂��B
�@�@�`���̎���ɁA�ǂ�ȕԎ���������̂��y���݂ł��B
![]()
Column238�@�@ �@2008/5/11 �����@ �@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �撣��ɒB����A���ς炸�����Ă���̏C�O
�@�@�ɒB���q����̊撣��A�����ł��˂��B
�@�@�P�X�V�O�N�X�����܂�ł�����A�R�V�ł����B
�@�@���C��������A�N��͊W�Ȃ��B�E�E�E�Ȃ�Ċ����ŁA������ƗE�C��^���Ă���܂����B
�@�@�F�X�Ȕn���������Ƃ��A���X�ƋN���鐢�Ԃ̒��ŁA������ƁA���������Ƃ��܂����B
�@�@���ۂɂ́A���E�Ő�����o�����̂��̂�B���̌o�����炭�鐸�_�͂�����I��������͂ƂȂ����̂ł��傤���A
�@�@���̃X�����ȑ̌^���ێ����Ă��邱�Ƃ�����A�����̗͈̑ێ��ւ̓w�͔͂��[�ł͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�@�@�����܂őz���ł����A�N�ɂł��o���邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤�B�@
�@�@�Ƃ���ŁA�e�j�X�̘b��Ƃ����ƁA�K���̂悤�ɏ����C�O����TV�ԑg���ŃR�����g������������܂����A
�@�@���ς炸�A�����w���̐��k�������Ă����ʂ���ʂɗ���܂����B
�@�@����ȉ�ʂ������x�ɁA�l���������܂��B�A
�@�@�{���Ă��A�����ŕt���Ă����͂��̗D�G�ȃe�j�X���N����W�߂āA�{���Ď����Ċ撣�点�悤�Ƃ���w��
�@�@���@�́A�{���ɐ������̂��H�E�E�E�Ȃ�Ċ����ł��B
�@�@�������A�C�O����ɂƂ��Ă͐������̂ł��B
�@�@�����ƁA���Ƃ��ƗD�G�ȑI��ɕK�v�Ȃ̂́A�X�Ȃ�w�͂ƕ����������̍����Ȃ̂ł��傤�B
�@�@�����Ȃ�����A���P�b�g�����o�����A�w�͂𑱂���q���������ATV��ʂƂ��Ă̊G�I�ɂ͔������ł��B
�@�@�ł��A���������ł́A������������ł��Ȃ����X����������グ��A���̂��߂ɂǂ�ȍH�v�������̂��B
�@�@����ȃ��[�_�[�������Ƙb��ɂȂ鐢�̒��ł����Ă��ǂ��̂ɂȁB�Ȃ�Ďv����������܂��B
�@�@�ȂA��̑O�̊w���h���}�I�Ȏv���ł͂���܂����B�@
�@�@�@�@�i���������A�u��������v�͂�����ƈႢ�܂��ˁB�j
�@�@���������撣��C���A�ڕW���Ȃ��B�@�\�͂��m�����Ȃ��B
�@�@����ȕ��X�����[�h���A��������Ɛ��������Ă������Ƃ��A���̐��̒��Ń��[�_�[�ɋ��߂��邱�Ƃ̂悤�ȋC������
�@�@���B�i�������A�����ɉ߂��܂��B�j
![]()
Column237�@�@ 2007/11/26 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �����Ɖe���A�s���ƌ���
�@�@���͍��T�A�Ζ���Г��Ń����^���w���X���C�̍u�t���߂܂��B
�@�@���ׂ̈̎�����ʏ�Ɩ��̍��ԂɃp���[�|�C���g�ō쐬���Ă����̂ŁA�����Q�T�Ԃ��炢�͌��\�Z���������̂�
�@�@�����A���Ƃ��������܂����B
�@�@��N�擾���������^���w���X�}�l�W�����g����̎Q�l����A�����̃z�[���y�[�W�̋L�ړ��e�������炢���A���\
�@�@�ȓ��e�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�@�쐬�ߒ��ɂ����āA�S�Ɍ����e����A�g�̂Ɍ����e���A���͂ɂ��z���A�����Ă��̂g�o��u���O�ł��Љ�
�@�@���Ă���R�[�`���O���n�߂Ƃ���R�~���j�P�[�V�����p�ȂǁA�����^���w���X������ɘj���Ă��邱�Ƃ��Ċm�F����
�@�@�������A���̒��ł��A�C�ɂȂ������Ƃ�����܂��B
�@�@�����������āA�e��������B�s���������āA���ʂ�����B�E�E�E�Ƃ����悤�ȕ����ł��B
�@�@�Ⴆ�A���������̓�������U������A�A�h���i������m���A�h���i�����̕��傪�������A�����_�o�╛
�@�@�����_�o�̊������R���g���[������U���\�́i�s���͂┽���j�����܂�����A�h��́i�����o�����̎����́j
�@�@�����܂����肷��̂��n�߁A�S��g�̂ɗl�X�ȉe�����o�܂��B
�@�@�����悤�ɁA�X�g���X�v���i�X�g���b�T�[�j�������āA�S�g�ւ̉e�����o��̂́A�S�����R�Ȃ��Ƃł���A���̌���
�@�@�Ɖe����������ƔF���ł���A�X�g���X�ɂ��e����������x�̓R���g���[���o����悤�ɂȂ�͂��ł��B
�@�@�܂��A�S�̕s����A�ߑ���߁A���Ȋ֘A�t���ȂǁA�}�C�i�X�v�l�ݏo���A�X�g���X��S�̕a�̉e���ɂ�
�@�@���A
�@�@�E�����������̍s������������A�����̉e��������B
�@�@�E�����́A�����ā����Ȃ��Ƃ����Ă��Ȃ��̂ŁA�����ɂ͊W�Ȃ��B
�@�@���A�����Ɖe���A�s���ƌ��ʂ�������ƍl����A������x�A��ÂɂȂ��͂��ł��B
�@�@�܂�A�F�������������߂Ă���B�Ȃ�ă}�C�i�X�v�l�́A�l������ŁA���ꂪ�����Ȃ̂��A�P�Ȃ�ϑz��
�@�@�̂������m�ɂȂ�̂ł��B
�@�@���ہA�����̓p�j�b�N�nj�Q�ł͂Ȃ����Ǝv����s�����������Ƃ��Ă��A�s���ɖ��m�Ȍ���������̂Ȃ�A�P
�@�@�ɕs�����傫�������A�s���̊������ɂ͌l��������A�Ǝ�����[�������邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł��B
�@�@�t�ɁA���������ɂ��Ȃ��̂ɁA�傫�ȕs����������̂Ȃ�A�����͐S�g�ǂ�������Ȃ��̂ŁA��t�̎��Â���
�@�@�����ق����ǂ��Ɣ[����������B
�@�@�Ƃ����킯�ŁA
�@�@��ɁA�s���ƌ��ʁA�����Ɖe�����l����B���T�͂�����F�ɓ`���悤�Ǝv���Ă܂��B
�@�@�����āA������B �w�͂���Ό��ʂ����Ă��邱�Ƃ��t�������悤���ȂȂ�āB
![]()
Column236�@�@ 2007/11/10 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �J�N�e���p�[�e�B����
�@�@�����ɋ��������ƁA���̂��ƂɊւ����A���̂����R�Ǝ��X�ɖڂ⎨�ɓ����Ă���B
�@�@����Ȍo���͂���܂��B
�@�@�V���ɎԂ����Ǝv���Ă���ƁA���܂ŋC�ɂȂ�Ȃ������X�𑖂�Ԃ̎Ԏ킪�C�ɂȂ�����A
�@�@�����I�܂������������Ă���B�Ȃ�ċC������������܂��B
�@�@������J�N�e���p�[�e�B�[���ʂƌ����܂��B
�@�@���X�����p�[�e�B�̒��ł��A�������ӎ����ăA���e�i�𗧂ĂĂ���ƁA����Ɋւ����W�܂��Ă���B
�@�@�P���Ɍ����ƁA�������ƁA���̖��ɋ߂Â��s�������R�ɂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B
�@�@������ƑO�ɂ��Љ���u�����h�n�b�v���Z�I���[���A�J�N�e���p�[�e�B�[���ʂƂ����Ă܂����A
�@�@�u�����h�n�b�v���̏ꍇ�́A�����̃A���e�i���グ��Ƃ������x���ł͂Ȃ��A�����̂��邱�ƂɑS�͂𒍂��Ŋ撣��
�@�@�Ă���ƁA���R�̂悤�ɁA�F�X�ȑO�����ȏo�����N���Ă���Ƃ������̂ŁA�Ӗ������͑傫���Ⴄ�̂ł����A
�@�@�ǂ�����A�����ɂ�����Ƌ����������ƁA�S���������ƂŁA�����̓���A������������ƌ����Ă��Ȃ����킪�A
�@�@�K���b�ƈ�]���܂���Ƃ������Ƃł��B
�@�@����́A�l�Ƃ̊W�ł������ł��B
�@�@����ɊS�������ɐڂ��Ă���ƁA����̂��Ƃ͂قƂ�nj����Ă��܂���B
�@�@������̂́A�����Ƃ̒��ړI�ւ��̕��������ł��B
�@�@�ł��A������Ƌ����������đ�����ώ@����A����̂����Ƃ�����i�����Ƃ�����j�����ς������Ă��܂���B
�@�@����ɋ����������ƁA�S�������Ƃ́A�������y�̎w���A�E��̓����Ƃ̕t�������A����ȏ�ʂŁA����
�@�@�̗���ɂȂ��čl���A�s�����邽�߂̊�{�ł�����܂��B
![]()
Column235�@�@ 2007/11/6 �����@ �@�@�@�@ �@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �����̂Ē��ɏo�悤
�@�@�u�����̂ĊX�ɏo�悤�B�v�@�ȑO�A����Ȍ��t���悭���ɂ��܂����B
�@�@���R�C�������́A����ȃ^�C�g���̏������������悤�ȋC�����܂��B
�@�@�ǂ��Ƃ͂Ȃ����A����I�ɂ�����肸���Ə�̔N��w�̊ԂŁA���s�����̂ł��傤�B
�@�@�����āA�����Ⴍ�͂Ȃ��ł����B
�@�@�ł��A���̌��t�̉e�����L��̂������̂��{��ǂނ��A�܂����s����B�Ȃ�čl���̕��������悤�ȋC�����܂��B
�@�@�{��ǂނ��Ɓ����ł������B�܂��͍s�����Ă݂āA�̂Ŋo���Ȃ���ΐg�ɂ��Ȃ��B�g�n�v�s�n�{�Ȃ�Ė��ɗ����Ȃ���B
�@�@����Ȏv��������Ă���������̎���ɂ��吨���܂��B
�@�@�m���ɁA�o�c��`�x�[�V�����֘A�̖{�ɏ�����Ă��鎖���A���̂܂��s���Ă��A���܂��͍s���o���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�@�����āA���̖{�����������ƁA�ǂ��́A���̍l������s���̃x�[�X���S���͓����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤����˂��B
�@�@�`�����܂��s�������@���A�a����ɍ����Ƃ͌���܂���B
�@�@���ɁA�{�ɏ����ꂽ�G�b�Z���X��������Ƃ������������ł͂Ȃ�����ł��B�@�m���Ɉꗝ�B
�@�@�������A�悭�l���Ă݂ĉ������B��{��m�炸�ɉ��p�Ȃ�Ė����ł��傤�B�˂��B
�@�@���̏ꍇ�́A�F�X�ȍl������m������ŁA�����ɍ����s�����@��͍�����B���̂��߂̓Ǐ��ł��B
�@�@�܂��A�l���ꂼ��ł��B
�@�@����ǂ�ł��璬�ɏo�悤�B�@����Ȑl�Ԃ����Ă��A�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
![]()
Column234�@�@ 2007/11/3 �����@ �@�@�@�@ �@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �L�����A�R���T���^���g
�@�@�L�����A�J�E���Z�����O�A�L�����A�R���T���^���g�W�̎��i�ɂ́A���Ԏ��i���������Ă��āA�����������悭��
�@�@����Ȃ���Ԃł����A�ǂ��������J���Ȃ����Ǝґ�ɖ{��������悤�ŁA���N���獑�Ǝ��i���n�݂���
�@�@��Ƃ���������܂����B
�@�@�ǂ����A�Z�\����Ƃ��āA�L�����A�E�R���T���^���g�P���A�Q���̂Q�̍��Ǝ��i���o����悤�ł��B
�@�@�����J���Ȃ͌��X�Q�O�O�Q�N����Q�O�O�V�N�̊ԂɔF�莑�i�擾�҂T���l��ڕW�ɁA�e��c�̂̎��i���s�ɂ��n
�@�@�t����^���Ă��܂������A�ǂ̒c�̂̎��i�擾���A�Q�O�`�R�O���~���x�̎�u����������u���̎�u���قڕK
�@�@�{�����ƂȂ��Ă��܂����B
�@�@�����A������������A���i���̂��F�X�����āA�F��c�̂��Ƃ̃��x���悭�킩��Ȃ���A���Ǝ��i�ł��Ȃ���
�@�@�ɁA���z�̎�u��p�������Ď擾����Ӗ�������̂��ȁA�Ȃ�Ďv���Ă��܂����B
�@�@�e��c�̂ł̎��i�擾�҂͂Q�O�O�U�N�܂łɁA�S�D�R���l�قǁB
�@�@�F��c�̂ɂ��A���i�擾�҂̃��x�������ɂȂ��Ă����悤�ŁA���N�x����͕�q�ƒ�����̏A�E�x���i�W��
�@�@�u�J�[�h�ƌ����炵���B�j���J�n����̂ŁA�A�E���k�̎��̌���A�܂�R���T���^���g�̎�����{������ꂴ��
�@�@�Ȃ��Ƃ������Ƃ���Ȃ̂ł��傤���B
�@�@�ƂƂ��ăL�����A�R���T���^���g���s�����X�����̎��i�ł��傤����A������i�ƂȂ�̂ł��傤���ǁA
�@�@���I�ɂ́A��Ɠ��ŃL�����A�J�E���Z�����O���o������𑝂₷�Ƃ������n�ŁA�ǂ̒��x�̓�Փx�̎��i�ƂȂ�
�@�@�̂��A�����[�X�ł��B
![]()
Column233�@�@ 2007/10/28 �����@ �@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �u�Q�S�v�̃X�P�W���[���Ǘ�
�@�@�R���T���E���C��Ђ��瑗�M����Ă��郁���}�K�ɃX�P�W���[���Ǘ��Ɋւ���R����������܂����B
�@�@�W���b�N�E�o�E���[���X�P�W���[���\���������ꂽ��A���������Ɏ̂ĂĂ��܂����낤�Ƃ����悤�ȓ��e�ł��B
�@�@�ӂ�ӂ�A�X�P�W���[���\�Ȃ��Ă���A���̍s���͂ł��낤�ȁB
�@�@
�@�@�Ǝv���Ȃ�����悭�l����ƁA
�@�@���������o�^�o�^�ƂQ�S���ԑ������Ă�킯�͂Ȃ�����B
�@�@���i�͌g�ђ[���ɃX�P�W���[���������Ă��āA��������Ǘ����Ă�ɈႢ�Ȃ��B�@�Ȃ�Č��_�ɒB���܂����B
�@�@�����āA�Q�S�����Ă���ƁA�o��l���S�����A�f�W�^���@��̌����̂悤�Ɋe��̂h�s�@����g�����Ȃ��Ă���ł�
�@�@�Ȃ��ł����B
�@�@�g�ђ[���Ɏ��������ł͂Ȃ��A�`�[���S�̂̃X�P�W���[���������Ă���ɈႢ����܂���B����\��Ȃ�
�@�@���邩���B
�@�@�Ȃ�Ă��Ƃ��l���Ă�����A�ӂƐ̂̂��Ƃ��v���o���܂����B
�@�@�܂��p�\�R���Ȃ����A�d���ł͑�^�R���s���[�^�̒[���@���g���Ă������i����j�A���̓�����̉�
�@�@�Ђł̎d���̓��e���L�������ē������Ă��܂����B
�@�@�������`�������A�����d��
�@�@�������`�������A�����ō���
�@�@�������`�������A�@�푀��
�@�@�Ƃ����悤�ȒP���ȓ��e���L���ɕς��Ē[��������͂���̂ł��B
�@�@�Ј����ǂ̂悤�ȋƖ��ɂǂꂭ�炢�̎��Ԃ������Ă��邩�͂��Č�������}�낤�Ƃ������݂ł��B
�@�@���ʂ́A�������A�������ȂS�����������A���������B
�@�@�r�W�l�X�}���ɂƂ��ăX�P�W���[���Ǘ��͏d�v�ł����A
�@�@�����������邩�ƁA�d�����̗D�揇�ʕt�������o���Ă���A������Ȃ��B�@���͂����v���Ă��܂��B
�@�@�o�E���|�������v���Ă���ɈႢ�Ȃ��B
![]()
Column232�@�@ 2007/10/24 �����@ �@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ���ƕa
�@�@���ƕa�Ƃ���g�D�a�Ƃ������t���悭���ɂ��܂��B
�@�@���́A���Ђ͑��ƕa�ɂ������Ă���ƌo�c�������g�������Ă����Ђ̋L�����������܂����B
�@�@�����m�̒ʂ�A�d����i�߂��ŁA�O���`���p�ɂɊ���o������A���v�E���P��i�߂悤�Ƃ���ƁA�K����R��
�@�@�͂������Ă�����ƁA�g�D���傫���A���G�ɂȂ肷���Ē��X���ق��o���Ȃ���Ƃ�A���肵�Ă���Ǝv�����݂ʂ�
�@�@�ܓ��I�ɂȂ��Ă���g�D���w�����t�ł��B
�@�@�������A�����v���ɁA�܂��A�������I�Ƃ������t������܂����A�������͕ʂƂ��āA���ƕa�ɂ���������ƂȂ�
�@�@�Ė{���ɂ���̂ł��傤���B
�@�@���ƕa�ɂ������Ă���̂́A��Ƃł͂Ȃ��A�Ј��ł��傤�B
�@�@�������A�a�C�̌��͖{���Ȃ烊�[�_�[�V�b�v�����ׂ��o�c�������g�ł��傤�B
�@�@�Ј��̒��ɂ́A��Ђ�ς��悤�Ǝv���Ă�����͑吨����͂��ł��B
�@�@�����Ă��̑����͏���̂��C�̂Ȃ��������������Ԃł��B
�@�@���ƕa�ɂȂ��Ă�Ȃ�Čo�c�������g�������Ă����Ђ́A
�@�@���ƕa�ł͂Ȃ��A���Ɗ����a�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@����A�a�l���g�����_�`�i�āj�ɏ���āA���x���Ȃƌ����Ă���悤�Ȃ��̂ł��B
![]()
Column231�@�@ 2007/10/20 �����@ �@�@�@ �@�@�@ �@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �l�̉\��M���邩�H
�@�@�l�̉\���W�T���Ȃ�Č��t������܂����A���Ȃ��́A�l�̉\��M���܂����H
�@�@�d���̏�ʂɂ����ẮA�u�����N�́A�����Ȑl�Ԃ��B�v �Ȃ�Ă����l���]���悭���ɂ��܂����A
�@�@�����N�̓����Ⓖ����i���A�u�����N�́A�������Ǝv���B�v �Ɩ��m�Ɍ����̂����ɂ���A���Ȃ��ɂƂ��āA����͂�
�@�@���\���͂����Ɛ^���ɋ߂����̂��Ǝv���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@����ł���͂�A���Ȃ����A�����̖ڂ⎨�Ŋm���߂������N�̍s���łȂ�����A
�@�@�u�����N�́A�����Ȑl�Ԃ��B�v �́A�\�Ɩw�Ǔ����x���̃��b�e���B�@�܂茈�ߕt���������肵�܂��B
�@�@���ہA�u�����N�̂ǂ����A�ǂ��������́H�v �Ƙb�̎�ɕ����Ԃ��ƁA���܂��̓I�ɂ͐����ł��Ȃ�����������܂��B
�@�@���ɂ́A�u���A�ǂ��ŁA���̂悤�ȏ��N�����́H�v�ƍX�ɋ�̓I�ɐu�˂�ƁA�b�̎傪�������f���������͂�����
�@�@�P��̏o�����ł���A�b�̎厩�g���A�l���畷�����b���グ���肷�邱�Ƃ������̂ł��B
�@�@�܂�A�������P��̍s���ƁA���̐l�̘b����A�u�����N�́A�����Ȑl�Ԃ��v �ƌ��ߕt���Ă����肷��̂ł��B
�@�@�����Ȃ�ƁA�قƂ�ǂ̐l���]�͒P�Ȃ郌�b�e���������肷��킯�ł��B
�@�@�F�������̂����玖���ɈႢ�Ȃ��B
�@�@����Ȑ���ςł��Ȃ����A�����N�ɐڂ��Ă��܂��ƁA�{�l�Ƙb���Ă��Ă��A�s�������Ă��Ă��A�����ȍs���Ɏv���Ă�
�@�@�܂��ł��傤�B
�@�@�N���Ƀ��b�e����\���Ă��܂��ƁA�����A����ςȂ��ɂ͑��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@�@�����ɁA����̈Ⴄ�����̕��X�ɁA�����N�̐l���]���Ă݂܂��傤�B
�@�@��i�⓯���͊m���ɁA�u�����N�́������B�v �ƌ����܂��B
�@�@�ł��A�ނ̌�y������ɕ����Ă݂�ƁA
�@�@�u��������͎d�����������苳���Ă����B�v
�@�@�u�����N���A��������j�[�Y�𑨂��ĎГ������Ă��ꂽ�B�v �Ȃ�āA�������Ԃ��Ă��邩������܂���B
�@�@�A���A���Ƃ��v���X�̐l���]�ł����Ă��A���ꂾ���Č��ߕt�������m��܂��B
�@�@�v�́A���Ȃ����g���A����ς�r�����āA�����N�̌������������茩�����Ȃ��ẮA�����N���ǂ�Ȑl�Ԃ��Ȃ�āA
�@�@��ɂ킩�蓾�Ȃ��̂ł��B
�@�@���肪�ǂ�Ȑl�ԂȂ̂��́A�K���A�����̖ڂŁA���Ŋm�F���܂��傤�B
![]()
Column230�@�@ 2007/10/8 �����@ �@�@�@�@ �@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �u�Q�S�v �̐E��
�@�@���₠�A��ӂ� �u�Q�S�v �������Ⴂ�܂����B���T����V�[�Y���u���t�W�s�u�ł���Ă��ł���˂��B ���� �����B
�@�@�r�f�I������Ŏ��ƁA���������Ȃ������肵�ăC���C�����邵�A���������Ǝ葱����̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA�V
�@�@�[�Y���u�͌��Ă��Ȃ������̂ł��B
�@�@�������A�u�Q�S�v�����邽�тɎv���܂����A�h���}�̒��Ƃ͂����A�o��l���̎w���͂�s���́A��Â��A�����Ė�����
�@�@�͂������������܂����Ȃ�܂��B
�@�@�@�i�A���A�o��l�����̃��[�K���哝�̂͌��f�͂̂Ȃ��l�ԂƂ��ĕ`����Ă܂����B�j
�@�@�F����̐E��ɂ��A����ȃ^�t�ȓz��͂��Ȃ��ł���H
�@�@�����̐��E�Ȃ�A���남�낵����A���Ⴀ����l���悤�Ȃ�Č����Ă���ԂɁA���͖c��オ��A��œI���ʂɂ�
�@�@���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@����ǂ��납�A�}���̎d�����w�����������ŁA�炪�c��邾���łȂ��A���ʂ����Ă��Ȃ��̂ł́B
�@�@���Ԃł́A�ŋߕ���������Ȃ���i���������A�������͊Ǘ��\�͂̂Ȃ���i���������Ȃ�Č����܂����A�u�Q�S�v��
�@�@�E��ł́A�d���ɏA���Ƃ������ƂƁA�g�D�╔����������ƊǗ����A�K�v�ɉ����ĕ����������Ă��܂����������Ƃ����`
�@�@��ł��������̂悤�ȍ��o���o���܂��B
�@�@�����e�l���A�N�ł���A�����̒S���E����K���ł��Ȃ��A������A�w����������Ă���Ə�i���猾����A����
�@�@�܂��A�N�ł����Ă������Ȃ�w�������n�߂��肵�āA�{���������炷�����ȂƂ��������ł��B
�@�@�܂�A�u�Q�S�v �̐E��ł́A�u��������Ă�v�Ȃ�ĊT�O�͂Ȃ��A���łɎd�����\���ɂ��Ȃ��\�͂̂���l
�@�@�Ԃ��A���̔\�͂������ĐE�ɏA���Ă���Ƃ��������Ȃ̂ł��B
�@�@�����A�Q�S�̐E��ŁA�����̓��{��Ƃ̂悤�ɁA����̏������̈琬�ɖc��Ȏ��ԂƔ�p�������Ă�����A
�@�@�u�N�͎A�����A���Ă����B�v �Ȃ�ăZ���t�͏o�Ă��Ȃ��ł��傤�B�@�����ƁB
�@�@�m�����Ȃ��̂Ŕ���܂��A���������]�E��������O�̕č��ł́A����Ȋ����Ȃ̂ł��傤���ˁB
�@�@�V���Ј��ł����Ă��A��w�łl�a�`���Ƃ��Ċ������Ƃ��ē��Ђ����҂́A�ŏ����猩�K���Ǘ��E�ɂȂ��āA�ł�
�@�@���āA����ȊK�w�̕��ƁA�P����Ƃ��������K�w�����m�ɕ�����Ă���Ƃ��B
�@�@�E�E�E�ȂA����ȃC���[�W������܂��B
�@�@�R���Ō����A���т��y�ѓ��̏��Z�ɔC������A���Ƃ��ᑢ�ł����Ă������Ƃ͖��m�ɋ�ʂ���Ă���悤�ȁA
�@�@����Ȋ����ł��傤���B�ł��R�������āA���Z�͂�����Ƌ��炳��Ă܂��B
�@�@�ꂩ���Ă悤�Ƃ����ƂƁA������l�Ԃ��ٗp���悤�Ƃ����ƁA�܂�A�l�̏����̉��l�i�����j�Ɋ��҂��邩�A
�@�@���݂��łɂ��鉿�l�i�\�́j��]�����邩�A����͑傫�ȈႢ�ł��B
�@�@�ǂ��炪�����̂��́A�o�c�҂̍l��������ł͂���܂����A���Ƃ��A��ĂĂ��ސE���邷��������������A�Y�܂�
�@�@�����ł��B�������A���ɗD�G�Ȑl�Ԃ��W�߂邱�Ǝ��̋�J����Ǝv���܂����B
![]()
Column229�@�@ 2007/10/7 �����@ �@�@�@�@ �@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �@����A���{�l�̐K��@��
�@�@�u���ꂵ���Ȃ�����{�̐l���v �E�E�E �@ ���F����̖{���܂��ǂ�ł��܂��܂����B
�@�@����������₷���̂ŁA���ǂ݂����Ȃ��Ă��܂��̂ł���˂��B
�@�@���̕��̘b�̓X�g���[�g�ŁA�����Ă��邱�Ƃ��悭����̂ł��B�����A�����B�̂���Ă������Ƃ��A�T�ˊԈ���Ă���
�@�@���Ƃ������Ă��܂����e�Ȃ̂ł��B
�@�@�{�l�́A���{�ł́A�����l�����炱���̍l�����̂悤�ɂ����邯�ǁA���Ɏ����͂��Ȃ���{�I���Ƃ����������
�@�@����܂��B
�@�@�\�t�g�u���[���̉�ł���@����́A��������l�Ȃ̂ł����A���{�ł̃r�W�l�X�������Ȃ蒷���A�O���[�o��
�@�@�X�^���_�[�h�Ɣ�ׂ����{�����̈����ʂ���ɂƂ�悤�ɔ���̂ł��傤�B
�@�@�����āA���̒����̑����ŁA�����̉�Ђ�A�����g�����A���z�Ƃ��čl���Ă����Б���l�����x���Ɠ����悤�Ȃ�
�@�@�̂��A���������̂Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B
�@�@�E�E�܂�A�����́A���łɊF�m���Ă�����e�B�����画��₷���̂��ȁB�Ȃ�Ċ�����������Ƃ��܂��B
�@�@�ł��A�厖�Ȃ��Ƃ���B
�@�@���̗��z���ƁA�����Ƃ̃M���b�v���ǂ�������A�����ł���̂��H
�@�@���{�I�Ȃ܂܂���_�����ƊF�����Ă��邯�ǁA�ł͂ǂ�������ǂ��̂��H�E�E���̓������Ȃ��̂ł���ˁB
�@�@�ǂ߂Γǂނقǐӂ߂��āA������̌�����Ȃ���X�́A�ǂ�ǂ�ǂ��l�߂���悤�ȋC�����܂��B
�@�@���{�l��������O�̂悤�Ɏv���Ă��܂��Ă��鈫�������B�ł������Ȃ����������B�ӂ߂�ꂽ�����ł͂ǂ��ɂ���
�@�@��܂���B
�@�@�����̕��͕ς��Ȃ�����āA�v���Ă܂���B
�@�@�@����A���{�l�̐K��@���B����ȓnj㊴�ł��傤���B
![]()
Column228�@�@ 2007/9/27 �����@ �@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �d�v�Ƌً}�̗D�揇��
�@�@�d�v�Ȏd���A�ً}�Ȏd���̗D�揇�ʂ������Ȃ������悭�������܂��B
�@�@�D�揇�ʂ������Ȃ��Ƃ������A�ً}�Ȏd�����A�d�v�Ȏd�����ɕЕt���悤�Ƃ�����������̂�������܂�
�@�@��B�}���ŒN���ɗ��d�����A���܂ꂽ�{�l�ɂƂ��Ă͏d�v�Ǝv����ʂȎd���̌�ɂȂ��āA���X�A�I
�@�@�����Ȃ��Ƃ��B
�@�@�Ñ����悤���̂Ȃ�A
�@�@�@�u���݂܂���B�������̎d���ɂĂ�����������āB�v�@�Ȃ�ĕԎ�������������܂��B
�@�@���Ƃ��A�d�����x��Ă��A���܂ꂽ���ɂ́A���C�͂���܂���B
�@�@�E�E�����āA�d�v�Ȏd���Ɏ��|�����Ă���̂ł�����B
�@�@�������̂��ƁA�D��x�������L���������ɒu�������āA
�@�@�@�u���̎d���́A�`�N���X����B�v�Ƃ�
�@�@�@�u���̎d���́A�E�G�C�g�X�O�Ȃ̂ŁA���������Ă���E�G�C�g�T�O�̎d������ɕЕt���Ă���B�v
�@�@�Ȃ�Č���Ȃ��ƃ_���Ȃ̂��ȁA�Ǝv��������B
�@�@�������A�d�v���Ƌً}���͒P���ɂ͔�r�ł��܂���B
�@�@���Ƃ��A�d�v���ƁA�ً}���̊W�ɂ́A
�@�@�@�E �d�v�ŁA�}���̎d���A
�@�@�@�E �d�v�ŁA�}���ł͂Ȃ��d���A
�@�@�@�E �d�v�ł͂Ȃ��A�}���̎d���A
�@�@�@�E �d�v�ł͂Ȃ��A�}���ł��Ȃ��d���@�@�@�Ƃ����悤�ȃ}�g���b�N�X������͂��ł��B
�@�@�d�v��ً}�̓x�������A�d�v���d�v�łȂ��������łȂ��A
�@�@�d�v�x �P�`�T�A �ً}�x �P�`�T �Ȃ�Ă��ƂȂ̂�������܂���B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�����A�b���₽�畡�G�ɂȂ�܂������A�v�́A�������Ȃ����d������������Ă���Ȃ�A�Ђ��[���������悤
�@�@�Ȃ�Ďv�킸�ɁA������Ɨ�ÂɂȂ��āA�������d���̗D�揇�ʂ��������茩�ɂ߂�K�v������Ƃ������ƂȂ̂ł�
�@�@�傤�B
�@�@�܂��A�d�����˗����鑤���A�u����Ƃ��āI�v�Ȃ�Čy�������̂ł͂Ȃ��A���肪�A�d�v�x�A�ً}�x�̔��f���o����
�@�@�悤�Ȏw��������ׂ��ł��B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@���̒��ɂ́A�p���[�g�̖@���Ƃ��W�O�Q�O�̖@���Ȃ�Ă��̂�����A�D�揇�ʂ̍����Q�O���̍�Ƃ����Ȃ��A��
�@�@�ʂ̑���͒B���ł���Ȃ�čl�������x�[�X�Ƃ����s��������킯�ł��B
�@�@�܂��A���̂������ƁA����Ɏc��̂W�O���̂����A�{���͂��Ȃ��Ă��ς�ł��܂��Q�O���Ȃ�R�O���̎d��������
�@�@�o���܂��B
�@�@���̑�O�A�S�Ă̎d���ɗD�揇�ʂ����邱�ƂȂ̂ł��B
�@�@���̑O�̃{�[�h�ɂ́A���̐������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�����L���ꂽ����\���āA�˂Ƀj�����b�R���Ă���
�@�@���B
�@�@�F����A�D�揇�ʂ��Ă܂����H
![]()
Column227�@�@ 2007/9/17 �����@ �@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �d���͊y���߂邩�H
�@�@���[�_�[�V�b�v��`�x�[�V�����Ɋւ��鏑����ǂ�ł���ƁA�d���͊y����������ق��������Ə����Ă��邱�Ƃ����\
�@�@����܂��B
�@�@�d���̐i�ߕ��ɂ����ẮA���R�Ȃ���A�l���猾���čs���i��Ɓj������A�����ŕK�v�Ǝv���čs���i��Ɓj�����
�@�@�����A���C���o�܂����A������Ƃ������ʂ��o����ł��傤�B
�@�@�܂�A�O���I���@�������I���@�̂ق��������Ƃ������ƁB
�@�@����ȓ����I���@�������Ɗg�債�čl����A�����̐����̂��߂ɁA�Ƃ��A�������C���ꂽ�d��������Ƃ��A�O������
�@�@�������ɂȂ��肻���ȍl�����v�����܂��B
�@�@�Ƃ��낪�A�Ƃ��낪�A�X�|�[�c�I�肾���āA���҂����āA�����̎d���ł���X�|�[�c�║����y����ł͂��Ȃ��悤�ł��B
�@�@�G���̑Βk��ǂ�ł�������A�X�|�[�c�G���̃C���^�r���[��ǂ�ł�������A���̓��Ő��ʂ��グ�āA�L���ɂȂ���
�@�@���X�̑����́A�����A�炢�v�������āA���X�����̂��ł����Ƃ����悤�Ȕ��������Ă��܂��B
�@�@��ł��������̂��A�d���ɂȂ����Ƃ���ɐh���Ȃ����B�@�݂����Ȕ����ł��B
�@�@�q���̍�����e�ɂ�炳��āA�h�������Ȃ�ăo�C�I���j�X�g�̋L��������܂����B
�@�@�d�����y���ނ��ƂȂo���Ȃ��B���`�x�[�V�����{�ɏ����Ă��邱�Ƃ͗��z�ł����Ȃ��B����Ȏv���������т܂��B
�@�@���ۂ̂Ƃ���A�d�����y�����Ƃ����L�����������Ƃ͂���܂����A��T�́A�撣���Ă��鏗�����Љ��V���L���Ȃ�
�@�@�ŁA�Z�������y�����߂������ł����N��ɂȂ��Ă��܂����B�Ƃ����悤�ȏ������B
�@�@�������A�C���^�r���[�L���ł͂Ȃ��̂ŁA�{�l���{���ɂ����v���Ă���̂��͕�����܂���B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�ł��A���͎����g���d�����y���ޕ��@�������āA���H���Ă���܂��B
�@�@�������P�������B�@�d���̈ꕔ�����d������藣���āA��ɂ��Ă��܂��̂ł��B
�@�@���X���Â�����������ł��傤�B
�@�@���̂g�o��A���̃u���O�A�Г��ŗ����Ă��郁�[���}�K�W���́A���ׂĎd������n�܂�����Ȃ̂ł��B
�@�@��ł�����A�Ζ����Ԓ��ɂ͂��܂���B�@�d���ł͂Ȃ��̂ŁA�d����̃m���}�͂���܂���B
�@�@���Ȃ݂ɁA�u�R�[�`���O�ƃe�B�[�`���O�̊�{�v�Ƃ����l�^���A�q��ЋΖ�����ɎГ������}�K�Ƃ��ĎГ��̑S�����E��
�@�@���E�ɔz�M�������̂ł���A�u���O�ł͂�����W�ɕ������āA����ɉ�����L�������̂��f�ڂ��Ă��܂��B
�@�@�t�ɁA�u���O�l�^���܂Ƃ߂āA�P�{�̃����}�K�Ƃ��ĎГ��z�M����p�^�[��������܂��B
�@�@�܂��A�����Ȃ�ƁA����y����ł���킯�ŁA�d���ł͂Ȃ��̂ł����A�d����̐��ʂɂ��Ȃ����Ă���܂����A
�@�@�h�����Ƃ͂���܂���B
�@�@���R�ł����A�ǂ�Ȏd���ł���ɏo����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��O�I��������܂��B
�@�@�܂��A���Ԃ��Ԃ����A�j�R�j�R������ق��������ł���B
�@�@���͂����v���܂��B�F����͂ǂ��ł����H
![]()
Column226�@�@ 2007/9/9 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �n�C�^�b�`�A�n�C�R���Z�v�g
�@�@���]�͌��t�␔����F�����A�E�]�͊G�≹�y��F������B�@����Ȃ��Ƃ���x�͕��������Ƃ�����Ǝv���܂��B
�@�@�ł��A�m���Ă��܂������H�@�E�]�͍����g���R���g���[�����A���]�͉E���g���R���g���[�����Ă���B�@�ƁB
�@�@���̂ʼnE�]�ɏ�Q���N����ƁA�����g�������Ȃ��Ȃ���������邻���ł��B
�@�@�܂��A�E�E���̈Ⴂ�͕ʂƂ��Ă��A���]�͒����I�ɏ������A�E�]�͑S�̓I���u���ɏ�������Ƃ����@�\�̈Ⴂ�������
�@�@�͎����̂悤�ł��B
�@�@�܂�A���]�́A�����ǂ����_���A���͔\�͂������ꂽ�]�B
�@�@�E�]�́A�����I�Ȏv�l�����A�p�^�[���F���⊴��E��\���̗����ɗD�ꂽ�]�B�@�Ƃ������ƁB
�@�@�Ⴆ�A���[�c�A���g�ً͑��ɗǂ��A�Ȃ�Č����܂����A
�@�@���[�c�A���g�͊y���ƃj�����b�R���č�Ȃ����̂ł͂Ȃ��A���ɕ������y�����̂܂܊y���ɗ��Ƃ��A�E�]�I��Ȃ���
�@�@�����炾�Ƃ������Ă��܂��B�@�E�]�ō�������y�͒����l�̉E�]���h������Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
�@�@�����I���������B
�@�@���̃n���h���l�[����amadeus_factory�Ȃ̂͒a�����ƃC�j�V���������[�c�A���g�Ɠ���������ł��B
�@�@�E�E�E�ǂ��ł������ł����B
�@�@���́A���̉E�]�A���]�̘b�́A
�@�@�u�n�C�R���Z�v�g� ����@�V�������Ƃ��l����l�̎���v�i�_�j�G���E�s���N���A��O�����j�Ƃ����{�ɏ�����Ă�����
�@�@�ł��B
�@�@�����āA�R�~���j�P�[�V�����ɂ����Ă��A�E�]�͑傫�Ȗ������ʂ����܂��B
�@�@���]�݂̂ōl������́A����̘b���Ă��錾�t���~�߁A���̈Ӗ����l����B����ɑ��āA���]�݂̂ł͂Ȃ��E
�@�@�]���g���ăo�����X�悭�R�~���j�P�[�V�������s�����́A����̌��t�����ł͂Ȃ��A����̕\���ԓx�Ȃǂ̔�i�m
�@�@���o�[�o���j�̕����𗝉����A����̋C�����������Ƃ�B�Ƃ������Ƃł��B
�@�@�R�[�`���O�ł́A����ւ̈ӎv�̓`�����́A���t���R�O���A����ȊO�������V�O���ƌ����܂��B
�@�@�������A���t�̂��� �W�O�����x�͎��ۂ̌��t���̂��̂����A���̃g�[���₵��ׂ���ł��B�܂�A����ɓ`����
�@�@�v�̂����A���ۂ̌��t�œ`���̂͂��������U���Ƃ������ƁB�܂��悭�ĂP�O���ł��傤�B
�@�@�E�] �E ���]�̘b�ƌ��ˍ��킹��ƁA
�@�@�E�]���g���āA�R�~���j�P�[�V���������Ȃ����ɂ́A����̌��t�̕��������������Ă��Ȃ��i�����Ă��Ȃ��j�B
�@�@����̋C�����̂��������P �����炢�����A�����o���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�@�u�n�C�R���Z�v�g�v �ɂ��ƁA
�@�@����̋C�����̋@����������\�́A����Ƌ�������\�́A����̏o�����ɂ��̖ړI��Ӌ`��Nj�����\�́A
�@�@����Ɋ�т�������\�́A�����ȊO�̐l����т�������̂��菕������\�́B
�@�@������u�n�C�^�b�`�v �ƌ��������ł��B
�@�@�ł��A���ꂩ��̐��̒��ŋ��߂���̂́A����Ɉ���i�݁A
�@�@�p�^�[����`�����X�����o���\�́A�|�p�I�Ŋ���ʂɑi������ݏo���\�́A�l��[��������b�̏o����\�́A
�@�@�ꌩ�o���o���ȊT�O��g�ݍ��킹�ĐV�����\�z��T�O�ݏo���\�́B
�@�@�������u�n�C�R���Z�v�g�v �ƌ����̂������ł��B
�@�@�܂��A�n�C�R���Z�v�g�͒N���ɂ܂�����Ƃ��āA
�@�@���̂g�o���A�u���O���u�n�C�^�b�`�v��Nj����Ă��������Ǝv���܂��B
![]()
Column225�@�@ 2007/9/8 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �h�̐l�A���̐l�A���̐l
�@�@�L���������}���g����́u�h�̐l�A���̐l�A���̐l�v�Ƃ���������ǂ݂܂����B
�@�@����́A�u�Ē����̃r�W�l�X�_���v �ł��B
�@�@�h�̐l�A���̐l�A���̐l�Ƃ́A�܂�č��l�A�����l�A���{�l�Ƃ������Ƃł��B�@�킩��ł���B
�@�@�e���̕��X�̍s���_���ɂ��āA�ǂ��ǂ��̍��̕��͈ӌ����͂����茾���Ȃ�Ĉ�ʓI�Ɍ�����Ⴂ��
�@�@���x���ł͂Ȃ��A�����ƍ��{�I�ȈႢ��������Ă��܂��B
�@�@�܂��A�č��l�ɂ��āB
�@�@�č��l�͊��厖�ɂ���B�����āA�������Ɗ������ẮA���E���Ɏ����B�̊�i�A�����J���X�^���_
�@�@�[�h�j���������肵�čL�߁A�����O��I�Ɏ�点�悤�Ƃ��܂��B
�@�@������Ȃ��҂������ċ����܂���B
�@�@�����Ȃ炷���ɑi�����܂����A�O���Ȃ玞�ɂ͌R���܂Ŏg���Ď�点�悤�Ƃ��܂��B
�@�@�l�a�`
�@�@���[�f�B�[�Y�̊i�t��
�@�@�s��J��
�@�@�S�O�P�j
�@�@�}�N�h�i���h�A�X�^�[�o�b�N�X
�@�@���t�[�A�O�[�O��
�@�@�����ăA�����J���̖����`
�@�@���ׂĐ��E�ɉ������肳�ꂽ�A�����J���X�^���_�[�h�Ȃ̂ł��B
�@�@�ł́A�����l�B
�@�@�����l�͂P�P�̊W�A�M����厖�ɂ���B
�@�@���̊W�́A���ʂȌ��q�i�`���G���c�����ԁj�ƂȂ��Čq����������܂��B
�@�@���̌��q�́A�E��Ƃ��w�Z�̃N���X�Ƃ����������P�ʂł͂Ȃ��A������ł�������A�����������ď�����
�@�@�������ł�������A�Ƃɂ����u�ނ͗F���Ăԁv���̏W�܂�A�T�[�N���Ȃ̂ł��B
�@�@���q�̒��ԂŎd���̏����������邾���łȂ��A�Ƒ�����݂ŐH����������A�V�тɂ��s���܂��B
�@�@�E���ς�͍̂\���܂���B�Ƃ������p�ɂɓ]�E���ă��x���A�b�v��ڎw���܂��B
�@�@�ł��A�]�E�E�]�Ή����ֈ����z���Č��q�̊W�������A�d�����܂܂Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�@�܂��A�ނ�̍s����̓��X�N���U�ł��B�����Ђ�����������Ă����킯�ł͂Ȃ����Ƃ͗��j�I�ɏ��m
�@�@���Ă܂��B
�@�@�q�������l������A�O���Ŋw������A�O���ɉł�������A���Ƀ��X�N���U�ɂ͗]�O������܂���B
�@�@�����āA���{�l�Ɠ������ʎq�����\�厖�ɂ��܂��B
�@�@���{�l�͏�̋�C��ǂ݁A�����ł̘a���ɂ��܂��B
�@�@����Ȃ̌Â���B�@�����v���Ⴂ���������Ƃ��Ă��A�����̓��{�l�ɓ��Ă͂܂�͎̂����B
�@�@����Ӗ���X�̂c�m�`�Ȃ̂ł�����B
�@�@�܂��A���{�l�ɂ��Ă̏ڍׂ́A������U��Ԃ��ĉ������B
�@�@�ʔ����{�ł���B
![]()
Column224�@�@ 2007/9/3 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �v�����h�E�n�b�v���X�^���X�E�Z�I���[
�@�@�v�����h�E�n�b�v���X�^���X�B
�@�@���̌��t�A�Ȍ��Ɍ����A�u�v�悳�ꂽ���̂悤�ȋ��R�B�v�Ƃ����Ӗ��̌��t�Ȃ̂ł����A
�@�@�܂�́A
�@�@�����A���Ȃ����O�����ɍs������A�Ӑ}���Ă��Ȃ������o�������A���R�̂悤�ɋN����A�܂�Ōv�悳�ꂽ��
�@�@�̂悤�ɂ��Ȃ��̃v���X�o���ƂȂ��Ă���B�Ƃ������ƁB
�@�@�܂�A���R�͕K�R�ł���B�E�E�E����ȈӖ������Ȃ킯�ł��B
�@�@���̌��t�A���́A���ǂ�ł���u�l�����ς��A��Ђ͕ς��v �Ƃ����{�ɏ�����Ă����̂ł����A�L�����A
�@�@�J���A�L�����A�J�E���Z�����O�p��Ȃ̂ł��B
�@�@�D��S�A�������A�_��A�y�ϐ��A�`���S �̂T�̗v�f���g���āA�v�����h�E�n�b�v���X�^���X�����o�����Ƃ�
�@�@�l���̎���[�߂悤�Ƃ����l����������悤�ł��B
�@�@�K�R�Ƃ�������R�����o���B
�@�@���[��B�Ȃ����̐����ɂ��̂������䂩��Ă��܂��܂����B
�@�@�����̍s�����������Ă���錾�t�̂悤�ȋC�����܂��B
�@�@�u�v�����h�E�n�b�v���X�^���X�v�A����ɂԂ���x�ɁA�������n�߂�x�ɁA��l���Ƃ��ĂԂ₫�����ł��B
�@�@�E�E�E�E�E�B
![]()
Column223�@�@ 2007/8/29 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �w�т́A���[�_�[�̃X�^�[�g���C��
�@�@����A���Љ���u��łȗr�̓��������v�ƌ����{�́A���߂ĕ����������ƂɂȂ��������A�ǂ�����ă}�l�[�W��
�@�@���g���s�Ȃ������A�w��ł����X�g�[���[�Ȃ̂ł����A������ƐG�ꂽ�悤�ɁA���̎���ł́A���[�_�[�ɂȂ�������
�@�@�ƌ����āA�������ǂ��Ǘ�����ш琬���Ă���������������w�ڂ��Ƃ���悤�ȕ����������܂���B
�@�@���R�Ȃ���A�V�C�Ǘ��E�̕��ɂ́A��������R�[�`���O���A��Ђ���߂��ЊO���C�������u���Ă�����
�@�@���Ă���܂����A�����āA����I�ɂ��̂悤�ȃ��[�_�[�V�b�v���w�ڂ��Ƃ��Ă�������������邱�Ƃ͖����̂ł��B
�@�@�������A���̒��ɂ́A���߂ĉ������w�Ȃ������āA���[�_�[�̑f����������͊��ł�����ł��傤�B
�@�@�ł��A�����ɔw���������Ďd����������Ȃ�ē��X�ƌ����悤�ȃ��[�_�[�V�b�v�ł́A �ǂ�Ȋ�ƁA�`�[��������
�@�@����ł��傤�B
�@�@�܂�́A���[�_�[�̃X�^�[�g���C���ɗ��ĂĂ��Ȃ����[�_�[�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�@���������A�o���}���ɂȂ�̂Ɍo���̕��A�c�ƃ}���ɂȂ�̂Ƀ}�[�P�b�e�B���O�Ƃ����悤�Ȑ��I�m����������
�@�@���Ċw�ڂ��Ƃ��������A���ʂȐE��̕��������ẮA�قڌ������Ƃ�����܂���B
�@�@����ׂ̈̔�p�⏕���x�����邾���Ɏc�O�Ȍ���ł��B
�@�@�v�́A�^����ꂽ�d���A�^����ꂽ�n�ʂR�ƍs���A���̉߂��s���܂܂ɉ߂����Ă����Ƃ����̂���ʓI�Ȃ킯
�@�@�ł��B
�@�@�܂��͊�{���w�ԁA
�@�@�����āA�����ɂ��������[�_�[�V�b�v��w�����@�A�Ǘ����@�A�d���̐i�ߕ����l���Ă����B
�@�@���̂悤�ȍl�������A���[�_�[�̃X�^�[�g���C���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A�������ł��傤���H
�@�@�K���ɂ���Ă݂āA���ƂȂ����܂������A�E�E�E�ƂĂ�����Ȏ���ł͂���܂���B
�@�@�R�������āA�������w�Z �i�m���w�Z�j �Ȃ�Ă��̂�����ł��傤�B�@�˂����I
![]()
Column222�@�@ 2007/8/26 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �X�X�D�X��
�@�@�܂����Ă����]�ł��B�@����́u�X�X�D�X���͉����v�Ƃ����{�B
�@�@�v�����݂Ŕ��f���Ȃ����߂̍l�����E�E�Ƃ�������ɂ���Ƃ���A�����͂��ꂪ�{���Ɏ����Ȃ̂��H
�@�@�Ƌ^���āA���������f�����Ȃ����Ƃ����{�ł��B
�@�@�^�C�g���� �u�X�X�D�X���v �ł����A���g��ǂތ���A���̒��͂P�O�O�������ƌ����Ă���悤�ȓ��e�ł��B
�@�@�����āA���̒��̂قƂ�ǂ̂��Ƃ́A�Ⴆ�A���Ɉ�ʉ����Ă���Ȋw�I�ȗ��_�ł����Ă��A�����ɉ߂����A���S��
�@�@�͉𖾁A �ؖ�����Ă��Ȃ����Ƃ��肾���A��s�@����Ԃ̂����āA�S�g�����������̂����Ď��͉Ȋw�I���t��
�@�@���s���m�ƌ����̂ł��B
�@�@���ꂱ���A�L���ȃK�����I�� �V������ے肵�Ēn�����������āA����ɂ���Ȃ������b�͗L���ł����A�^�C�~���O
�@�@�I�ɖʔ����̂́A�Ȋw�ɂ͞B���Ȋ�A���f�������A���������f�����Ƃ����̂��������Ƃ��ď����Ă��܂��B
�@�@�E�E�E���łɁA�f���ł͂Ȃ��A�P�Ȃ鏬�f���Ɋi�����ɂȂ��Ă��܂���ˁB
�@�@�n�����g���ɂ��Ă��A�b�n�Q�r�o�ʂ������Ă��邩�牷�g�������Ƃ����̂́A�����܂ŏؖ�����Ă��Ȃ�������
�@�@����A���g���ɂȂ�������b�n�Q���������̂����m��Ȃ��ƁB
�@�@�܂�A���x�㏸�Ƃb�n�Q�����̑��֊W��������Ă��邾���Ȃ̂�����A�펯�Ƃ���Ă��邱�Ƃ̔��Α�����
�@�@���邱�Ƃ��A�Y�ꂿ��_������Ƃ������ƁB�i�����āA���݂̗L�͂Ȑ���ے肵�Ă���킯�ł͂���܂���B�j
�@�@�܂��A�Ȋw�ł��낤�ƂȂ낤�ƁA�S�ĉ����ɉ߂��Ȃ��̂ŁA���̒��Ő������Ƃ���Ă������Ƃ��A������ˑR�A
�@�@�������Ȃ��Ȃ�����A�������Ȃ��Ƃ���Ă������Ƃ��A���������Ƃ��Ƃ����펯�ɕς�����A�Ɛ��̒��̍l�������̂���
�@�@���s�ςł͂Ȃ��Ƃ��B
�@�@�����Ă悭����b�Ƃ��āA�ƍ߂�Ƃ����҂̒m�l���A�u�܂��߂����������B����ȕ��ɂ͌����Ȃ������v�ƌ����̂��A
�@�@���ǂ̂Ƃ���A���̕��̈�ʂ݂̂����āA�u�܂��߂������v�Ɖ����𗧂ĂĂ����̂ɉ߂��Ȃ��B�Ƃ��Ă���܂��B
�@�@���̂Ƃ���A����Ⴛ�����낤�B�Ǝv�����Ƃ���ŁA����قNJ�������{�ł͂Ȃ������̂ł����A
�@�@�ǂ����Ă��A�펯 �i���Ǝv���Ă���ɂ����Ȃ��l���j�A �Œ�ϔO���ɂ����Ă��܂����ɂ́A�l�������߂邽�߂�
�@�@������ƂȂ�ł��傤�B
![]()
Column221�@�@ 2007/8/22 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ��łȗr
�@�@�ŋ߁A���]�߂��Ă��܂����B�@���͍���܂��A�}���قŖ{����ēǂ݂܂����B
�@�@�^�C�g���� �u��łȗr�̓��������v�B
�@�@���߂ĕ�����������搶���w��������e�̏����d���Ăł����A�Q���Ԃ���Ίy�ɓǂ߂���e�ł��B
�@�@���[�_�[�V�b�v��A�w���Ɋւ���g�o��u���O�������Ă���ƁA���X�A�����d���ĂȂ�ĂƂ����C�����܂������A���\�ǂ�
�@�@�₷���A�ʔ����{�ł����B
�@�@�r�������A��l�łP�O�O�C�ȏ�̗r���A����g���Ȃ���ʓ|�݂�̂��ɁA����Ղ�������Ă��܂��B
�@�@��͒@�����߂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�U�����A���E��������ׂɂ���̂��B�Ȃ�Ċ����ł��B
�@�@�܂��ɐV�C�Ǘ��E�E���[�_�[�̕����ǂނׂ��{�B
�@�@�ł��A���[�_�[�ɂȂ���������āA�w�����@�̖{��ǂސl���Ď��̎���ł͏��Ȃ��ł��B
�@�@�w�Z�̐搶����Ȃ�����B�@�Ȃ�Č�����������������イ��������܂��B
�@�@���{�I�Ȋ�Ƃɂ����ẮA�d�������Ȃ��\�͂�����̂ƁA�����E�g�D�E�`�[�����Ǘ� �i�}�l�[�W�j ����\�͂�����̂́A
�@�@�ʂ̂��Ƃ��Ɨ��������ɁA�Ǘ��E�ɏ��i�������Ⴄ��Ђ������̂ł��傤�ˁB
�@�@�܂�A�Ǘ��E�Ƃ��Ă̔\�͂����邩��A�Ǘ��E�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�d���̐��ʂɑ��邲�J���Ƃ��āA�Ǘ��E�ɂ��Ă�
�@�@�܂��B�@������A�Ǘ��E�ɂȂ��Ă��A�����̎w�����Ǘ������܂��o���Ȃ��B
�@�@�E�E�E�E�������Ă܂��H
�@�@���ɍŋ߂́A�d���̐��ʂɑ��āA�������̂t�o�ŕ邱�Ƃ�������̒��ɂȂ��Ă��܂����B
�@�@�N������@���@�N�ł��A�E���Ĉ��̔N�����o��Ώ��i������Ƃ����l�������A������̒��Ȃ̂ŁA�@���ʂɑ���
�@�@��V�����i�ł���̂́A�ٗp�ґ����猩��Η��ɂ��Ȃ��Ă���̂�������܂���B
�@�@�ł��A���̂��߂ɁA��Ƃ̒������[�_�[�̎w���͂��ቺ���Ă��Ă���͎̂����̂悤�ȋC�����܂��B
�@�@�č��̑��Ƃ悤�ɁA�l�a�`���C�����A�o�c�w��}�l�[�W�����g�̊�{��m���������A�������Ƃ��č̗p�����̂�
�@�@��ʓI�Ȃ̂́A��Ђ�A�`�[���� �K�� �u�Ǘ��v ���邱�Ƃ̑厖���𗝉����Ă��邩��Ȃ̂ł��傤�ˁB
![]()
Column220�@�@ 2007/8/19 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �I�����[�����헪�̓y�U
�@�@�Ƃ���{��ǂ�ł���Ɗ�Ɛ헪�ɂ��Ėʔ����L�q���B
�@�@�ꎞ���A�R�A�R���s�^���X�Ȃ�Č��t�����s���Ă��܂����B���p�o�c�����ĎΗz���}������Ƃ��������A�{�Ƃ��
�@�@���ɂ��A��Ƃ̐l�E���E���������ɏW�����ׂ��Ƃ����l�����ł��B
�@�@���� �u�R�A�R���s�^���X�o�c�v �Ȃ�Ė{��ǂ��炢�ł��B
�@�@�������A��Ɛ헪�ɂ����đ厖�Ȃ̂́A�܂��͂��߂ɁA�키�y�U��I�Ԃ��Ƃ��ƌ����̂ł��B�����Ă��̓y�U�ł̃I
�@�@�����[�����ƂȂ邱�ƁB
�@�@�������C�o���̂���ƊE�ŁA����Ƃ̗͂��W�����Ċ撣�Ƃ��Ă��A�@�������̏��Ր�ɂȂ��Ă���̂ŁA���Ƃ���
�@�@���c���Ă��A��Ƃ͗͂��g���ʂ����Ă��܂����Ƃ������Ƃ̂��ƁB
�@�@�Ⴆ�A�h�a�l�́A�R���s���[�^�[���[�J�[�Ƃ���������������悤�ȓy�U������P�ނ��A�R���T����ƂƂ��đ傫���y
�@�@�U��ς��Ă��܂��B�E�E�E�m���ɁB
�@�@��Ƃ��{�C�Ő킦��y�U�͂��������R�O�N���������Ȃ��B
�@�@�����āA����L�����p�o�c����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A��Ɏ���������Ƃ��Đ킦�A�V�F�A������y�U��T���Ƃ�����
�@�@�Ƃ̂悤�ł��B
�@�@�C�g�[���[�J�h�[���Ƃ��ƂƁA�Z�u���C���u���ɏW�����A�V���b�s���O�Z���^�[���Ƃ���P�ނ��Ȃ��ƁA�_�C�G�[�̓��
�@�@���ނƂ�������Ă��܂����B�@���������̒��ł��B
�@�@�܂��A���d�C���[�J�[�Ȃǂ́A�j�b�`�Ȑl�C���i��o�������[�J�[�̌�ǂ��ł����Ă����̃V�F�A�����
�@�@��̔��X�n��������Ă��āA�����ɓ��l�̐V���i���o���ăV�F�A��}���Ă��܂��Ƃ����\�����ێ����Ă����̂��A
�@�@�ŋ߂ł́A�ʔ̓d�@�X������Ƃ����̔�����ł̏��Ր�ƂȂ�A���Ɍ������Ȃ��Ă��Ă���悤�ł��B
�@�@�܂�A�P�ƂŃV�F�A������y�U����������Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��ˁB
�@�@�\�j�[�ȂǁA�v���X�e�̂悤�Ƀ\�t�g�܂ŗ}���ď��߂ăV�F�A����ꂽ�킯�ŁA������p�\�R����Ɠd�ƌ��т���
�@�@���Ƃ���ƁA�p�\�R���A�Ɠd�͖{�̂Ŗׂ��A�Q�[���@�̓\�t�g�Ŗׂ���ׁA�l�i�ݒ肪�قȂ��Ă��邱�Ƃ������A��
�@�@��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��悤�Ȍ��ۂ��N���Ă��܂��킯�ł��B
�@�@�Q�P���I�́A���Ȃ茵�������̒��ɂȂ��Ă��Ă�Ǝv���܂��B
�@�@���̋Ζ���̏ꍇ�A�ǂ��l���Ă��{�Ƃ��̂Ă邱�Ƃ͗L�蓾�Ȃ��̂ł����A
�@�@���ӎ��Ƃɂ��{�C�ɂȂ�Ă��Ȃ��Ƃ�����������Ă��܂��B�@�U�߂Ǝ��̃e���|���x���̂����m��܂���B
�@�@�Ƃ��Ă��S�z�ł��˂��B
![]()
Column219�@�@ 2007/8/18 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �����O�e�[��
�@�@�����O�e�[���B�@�ŋ߂�����҂藬�s���Ă��錾�t�ł��B
�@�@�u�����O�e�[���̖@���v�@�Ȃ�ČĂ�����Ă��܂��B
�@�@�b�̔w�i�Ƃ��āA�p���[�g�̂Q�W�̖@���Ƃ����̂�����A�����͑厖�ȂQ���̕������撣��ΑS�̂̂W���̌��ʂɌq
�@�@����Ƃ����l����������܂��B
�@�@���ɂp�b���K�������Ƃ�������Ȃ�A�P����P�O�܂őS�Ă̖��_�ɑΏ�����̂ł͂Ȃ��A�U�߂ǂ���������đΏ���
�@�@��ΊT�˖��͉�������Ƃ����p���[�g�̖@���ƌ��������m�ł��傤�B
�@�@�����������B �Q���̍U�߂ǂ�����ꐶ������낤�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A �����O�e�[���̖@���͂�����ƈႢ�܂��B
�@�@�F���U�߂Ȃ��c����̂̂W���ɂ����@������Ƃ����l�����ł��B
�@�@�������A�������蒷�������Ă����郍���O�e�[���ł���B�Ƃ����̂ł��B
�@�@������\�ɂ����̂� �h �s �B�@�Ƃ������A�ŋ߂̃l�b�g�ʔ́B
�@�@�Ⴆ�A�}�]���h�b�g�R���̂悤�ȃl�b�g�ʔ̂ł́A����ǂ���̂Q���������̂͂������A���X�̓X�ܔ̔��ł͍�
�@�@������ ����Ȃ��悤�ȂW���̂���j�b�`�ȏ��i�ɂ����������킶��Ɨ���悤�ł��B
�@�@���R�Ȃ��炱�̂W�����ɂƂ��Ď��̂͏����̌����ɔ����܂��̂ŁA���������������_�ŏo�Ō��ɔ�������̂ŁA
�@�@�[�i�ɑ������Ԃ͂�����܂����A�ʔ̂Ȃ�A�������Ă����Δz������܂�����A�q�ɂƂ��Ă͋C���y�ł��B
�@�@�A�}�]���̏ꍇ�A�P�T�O�O�~�ȏ㑗�������ł����B
�@�@�m���Ɏ����悭���p���Ă��܂����A��łɋ߂��{��T�������Ƃ����x������܂��B�����A�}�]���̃����O�e�[�����x����
�@�@����̂����m��܂���B
�@�@�����O�e�[���ɂ��ď����ꂽ�{���A�ŋߗǂ��������܂����A�p�b�I�ȍU�߂ǂ���Ƃ��Ẵp���[�g�̖@�����Q�P���I��
�@�@�Ȃ��ĕ������̂������܂��B
�@�@���̒��͊m���ɕω����Ă��Ă���B�@����Ȋ����ł��B
![]()
Column218�@�@ 2007/8/11 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �{��ǂޗ��R
�@�@�F����A�ŋߓǏ����Ă��܂��ł��傤���H
�@�@���́A�ʋ��b�V���̃X�g���X��a�炰����@�̈�Ƃ��āA�{�̐��E�ɓ��荞�ނ��Ƃɂ��Ă��܂��̂ŁA�o����
�@�@�����ǂ����ƍl���Ă��܂��B
�@�@���́A���͂������Ă��Ă�����ɂ́A������Ɖ��߂ɖ{�������A�ڂ��Â炵�Ȃ���{��ǂނƊዅ�̉^���ɂȂ�
�@�@�Ď��͉ɂ����ʂ�����炵���ł��B
�@�@���̓ǂރW�������́A�������ɖ{�A����w������^���w���X�̎Q�l�{�A�o�ρE�o�c���B
�@�@�o���邾���������Ȃ��ēǂ����ƍl���Ă���̂ł����A�a�������n�����ł��w���ł��镶�ɖ{�͂悢�Ƃ��Ă��A���̑�
�@�@�̖{�͌��\��p�������݂܂��B
�@�@���ɁA�o�ρE�o�c���͐V���������ł����A�V�����{�́A�a�������n�����ɂ͂Ȃ����A�}���قł��\�����ς��ł��B
�@�@�܂��A�����݂��������肵�Ȃ��Ɨ����o���Ȃ������������̂ŁA�Ȃ��Ȃ��̂������͂����čw���ɓ��ݐ�
�@�@��̂ł��B
�@�@�܂��A����Ǝv���Έ������A�����̖��ɗ���������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��m���͍L����܂��B
�@�@�E�E�E����Ȃ��m��������������܂����B
�@�@�����Đ���A�ǂ݂��т�Ă������N���O�̖{��ǂ݂����Ȃ��āA�Ζ���ߕӂ̐}���قɍs���Ă݂�Ƃ��ړ���
�@�@�̖{������A���������Ǝ�Ă��܂����B
�@�@�܂��A���N���O�̌o�Ϗ������痬���ǂ݂ł������A�����̂����������Ȃ��Ǝv���Ă����̂ŁA���Ȃ蓾�����C�ɂ�
�@�@��܂����B
�@�@�Ƃ��낪�A�ݏo���Ԃ͂Q�T�ԁB�{������͋Ζ�����ċx�݁B
�@�@����܂łɁA���̖{�u���N�T�X�ƃI���[�u�̖v��ԋp���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�������ēǂݐi�߁A����Ɠǂ�
�@�@�I���܂����B�u���O��z�[���y�[�W���X�V���鎞�Ԃ��s���C���ł����B
�@�@�u���N�T�X�ƃI���[�u�̖v�́A
�@�@�Ђ�A���E�����畔�i�B���A�����Ɍ��݂����H��Ńg���^���N�T�X�̂悤�ȉȊw�Z�p�̏W���̂��A��������
�@�@�{�b�g�ɍ�点�Ă����Ƃ����邱�̐��̒��ŁA�����ɐA������I���[�u�̖̏��L���߂��鑈�������鍑��
�@�@���܂��ɂ���Ƃ����A�O���[�o�����E�h�s�������Љ�ƁA ��������ۂ���Љ�̑Δ�����ؓI�Ɏ����A�X�D�P�P�̔�
�@�@�������\����������e�ł��B�����Ă��̍�i�́A�X�D�P�P���o�āA�u�t���b�g�����鐢�E�v�Ɍq�����Ă��܂��B
�@�@�ł��A���ǂ����Ƃ��Ă���̂́A�u���Ȃ��̂s�V���c�͂ǂ����炫���̂��v�i�s�G�g���E���{�����j�B �����������Ƃ�
�@�@���o�Ϗ��ł��B�s�V���c���ǂ�����Ď茳�ɗ����̂����A��������A���Y�A�̔��A�z���܂ł̗�����A�O���[
�@�@�o�����̗���ɂ��킹�Ēǂ��Ă������e�炵���A�y���݂ł��B
�@�@���͋Ζ��揊�݂̋旧�}���قɍɂ�����̂����A�Ζ��撼�߂̐}���قɎ��\��������̂ł�
�@�@���A�Ȃ�ƍ�Ӓx���Ɏ������̃��[��������܂����B
�@�@���āB���T�͉ċx�݁A���ɍs���Ȃ��ł͂Ȃ��ł����B���u�����Ԃ͂P�T�ԁB������ƍ���܂����˂��B
�@�@���[��A�P��\�����������āA�ė\����A���u�����Ԃ����т邩�Ȃ��B
�@�@���͂Ԍ����o�ρE�o�c����ǂނƂ��́A�e�[�}�����߂Ă���A�����悤�Ȃ��̂𑱂��ēǂݗ����ǂ��܂��B
�@�@�����ŋ߂̋����̓O���[�o���[�[�V�����B
�@�@�E�E�E���������ς�A�����𗧂C�����āB
![]()
Column217�@�@ 2007/8/2 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �Ղ�ɗL���āA�d���ɖ�������
�@�@�ԉƉčՂ�̋G�߂ł��B
�@�@�ł����́A�F�A���Ղ�ɔM������̂ł��傤�ˁB
�@�@�����̖��͉čՂ�ɖڂ��P�����Ă���A�ߗׂŊJ�Â������̂ɂ́A�S�čs�����Ƃ��Ă��܂���B
�@�@����A�d���ʼn�����Ζ���̒�����̕��X���A���������Ƃ��Đ_�`���K�̏��������Ă���܂����B
�@�@��Î҂̕��X�́A���R�Ȃ��疳���ł����A�����̊y���݂Ƃ��ĔM�����Ă���̂�����A���Ȃ�̖��͂�����̂ł��傤�B
�@�@�����A�d���̏�ʂŁA�Q�������o�[�����ꂾ���M���ł�����A���Ȃ肷�������Ƃ��o�����ȁB �Ȃ�āA���Ղ�ɍs���x
�@�@�Ɏv���Ă��܂��܂��B�@�{���o�����������̕��X���A�������A�p���[�Ɉ��Ă��܂����B
�@�@���~�����Ă����͕̂����邯�ǁA���������Ȃ�ł��̏����̂ɐ_�`��S���C�ɂȂ�̂��A�@�Ȃ�āA�v����������鎄��
�@�@�ق����A�Ղ�̔M�C�̒��ł͕����Ă��܂��܂��B
�@�@�ł́A���Ղ�ɗL���āA�d���ɖ������́@�͉��Ȃ̂ł��傤�H
�@�@�@�E �N�ɂ���������Ȃ�
�@�@�@�E �P�N�ɂP��̃C�x���g
�@�@�@�E �������Ԉӎ� �i���ɐ[��Ղ�͒����̑R�Ȃ̂Ń��C�o���ӎ�������܂��j
�@�@�@�E ���S�̂��Ղ�̕��͋C
�@�@�@�E �{�Ԃ̉₩��
�@�@�@�E �{�Ԃł͊F���d���
�@�@�����A�d���Ɏ�荞�߂���̂́A�ǂꂩ�ȁB �E�E�E�E�E �Ȃ�Ďv���Ă܂��B
![]()
Column216�@�@2007/ 7/28 �����@ �@�@ �@�@�@ �@�@�@ �@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ��X�̓A�b�v���[�h���Ă����I
�@�@�����͂�����Ƃ���������b�B
�@�@���̊�ƃ}�l�W�����g�̑�ƁA�o�c�w�҂o�D�h���b�K�[�́A�Q�O�O�Q�N�ɏ������u�l�N�X�g�E�\�T�G�e�B�v�ɂāA�X
�@�@�Ȃ�Z�p�v�V���N���A�}���Ɍٗp�E�J���`�Ԃ��ω����A���x�ȋ������Љ�ƂȂ鐢�E���߂������ɂ����
�@�@����Ɨ\�����Ă��܂����B
�@�@�Q�O�O�T�N�P�P���h���b�K�[���S���Ȃ�������A�����̃r�W�l�X�}�����A���������ǂ�ȋZ�p�v�V���N����̂���
�@�@���Ƌc�_���������̂ł��B
�@�@�Ƃ��낪�A�Ƃ��낪�A
�@�@�ŋߖ{���ł悭��������W���[�i���X�g�A�s�D�t���[�h�}���́u�t���b�g�����鐢�E�v�́A���ƁA���̐V�����Љ�
�@�@�����Ɏn�܂��Ă���ƁA�؋��t���ŏ�����Ă���̂ł��B
�@�@����ƁA�т�����B
�@�@���̂Q�l�̖��O�⏑����m��Ȃ��������́A���̂܂ܓǂݐi�߂�O�ɐ���A�E�B�L�f�C�A���A�A�}�]����
�@�@���ׂĂ݂ĉ������B�����傱���Ƃ������ׂ�ƁA�b�������Ƃ킩��₷���Ȃ�܂��B
�@�@�E�B�L�y�f�A�@ �o.�h���b�K�[�@�@�@�@�@�@�s.�t���[�h�}��
�@�@�A�}�]��.com�@ �l�N�X�g�E�\�T�G�e�B�@�@�t���b�g�����鐢�E
�@�@���Ȃ݂ɁA�t���[�h�}���͌o�ϊw�҂̃t���[�h�}���Ƃ͕ʐl�ŁA�����u���N�T�X�ƃI���[�u�̖v�ʼn��Đ�i��
�@�@�ƃA���u�̊m�������グ���W���[�i���X�g�ł���܂��B
�@�@�܂��A�o�ϊw�� �h �s �W�̃z�[���y�[�W�ł͂Ȃ��̂œ���b�͔����܂����A
�@�@�h �s �Z�p �E�f�W�^���Z�p�̊v�V�A�p�\�R����l�b�g����̋}���Ȑi���ƈ�ʉ��A�����⋌�������܂߂��e��
�@�@���̌��т� �E �J���A��Ƌ����̌������@�����ˍ��킳���āA�������N�ŎY�Ɗv���ȏ�̌������ω����K
�@�@����邻���Ȃ�ł��B
�@�@�m���ɁA
�@�@�h����d�̂悤�Ȓ����^�g�уf�W�^���v���[���[�Ȃ�āA���N�O�͒N�������Ă��Ȃ��������A�g�ѓd�b�łs�u��
�@�@���邱�Ƃ��R�N�O�͏o���Ȃ������͂��B��T�͂V�V�ɂȂ鎄�̕ꂪ�A�����̌g�тŎB�����摜�̈���̎d
�@�@�������ɐq�˂Ă��܂����B
�@�@�����܂Ō����A�������̒����i�������ȂƊF������C�t����������܂��A��ƃ��x���ł̋Z�p�v�V��
�@�@����ȃ��x���ł͂Ȃ��悤�ł���B
�@�@�����āA�z���_�ɍs���A�l�^���{�b�g���Г����ē����Ă���܂����A�[���b�N�X�́A�s�̂͂��Ă��܂��r
�@�@�j�[���̂悤�ȓ����Ȏ��ɁA�f�W�^���h�L�������g��\������Z�p���J�������ƐV�����\���Ă��܂����B
�@�@�ɂ߂ċ߂������A�d�Ԃ̒��ł����ނ�ɁA�ۂ߂������r�j�[�����`�R�T�C�Y�ɍL���� �s�u�����n�߂�����A
�@�@�ڌ������̂�������܂���ˁB
�@�@���������A�s�u��c�ȂA�ŋ߂͎��ł������ʂɎg���Ă��܂����ǁA����ȃ��x���ł͂Ȃ��A�����āA
�@�@���Ԃ⋗���̏�Q���قڊF���Ƃ��āA���E���� �u�q�������v �؋���������邻���ł��B
�@�@���Ƃ��A�����̑�A�ł́A�l�b�g�ł̓��{��Ƃ̉��������A�܂�œ����̔����҂ׂ̗ɍ����Ă��邩��
�@�@�悤�ɂ��Ȃ������R�قǂ����A�ނ�̂قƂ�ǂ͓��{�ꂪ���{�l���݂ɂ���ׂ�邻���ł��B
�@�@�C���h�ł́A�č��̃l�b�g��ʂ�����������ƒ닳�t�����邽�߂ɁA�����B�̉p���č��̕W���Ȃ܂�ɒ�
�@�@���Г����C�������Ȃ���Ƃ܂ł���悤�ł��B���ۃA�����J�ł̓C���h�ݏZ�̃C���h�l�ɂ��l�b�g�ƒ닳�t��
�@�@���s���Ă��邻���ł��B
�@�@�܂�́A���E�͂��łɕ���ŁA
�@�@�N�����������ɂ��邩�̂悤�Ɍq�����Ă���A�̂ɁA�S�Ă̌l���Γ��ȋ������J��L���鎞��ɂȂ��
�@�@����̂ł��B
�@�@����ƑO�u�������������ł����A����ȓ��e�̖{��ǂ݂Ȃ���A���͋C�Â����̂ł��B
�@�@�u�������A�����A�b�v���[�h���Ă��B�v�@�ƁB
�@�@�����A�A�b�v���[�h�B���̂�������B
�@�@���Ԃ����ޕ��X�ɂ�����Ƃ���������܂��B
�@�@��ʂɂ́A
�@�@�T�[�o��l�b�g����f�[�^��摜����荞�ނ̂��_�E�����[�h�B
�@�@�t�ɁA�T�[�o��l�b�g�Ƀf�[�^��摜���ڂ���̂��A�b�v���[�h�B�E�E�܂��A���̂Ƃ���ł���ˁB���܂�펯�B
�@�@�����t���b�g�����鐢�E�ɂ�����A�b�v���[�h�Ƃ̓z�[���y�[�W��u���O�A�����������̂r�m�r�B
�@�@�܂��A�A�}�]���̏��]��kakaku.com�̌��R�~�B�@�E�B�L�y�f�B�A�̂悤�ɊF������Ă����R�~���j�e�B�̂悤�Ȃ�
�@�@�̂��w���Ă���̂ł��B
�@�@�i��2010�N���j
�@�@�������������Ă邤���Ƀc�C�b�^�[����ʉ����āA���������łȂ��A���Ԏ����傫���ς���������ł��ˁB
�@�@�i��2015�N���j
�@�@���₢��A�X�}�[�g�z���̕��y�ɂ�郉�C����Facebook�̈�ʉ��͂��Ƃ��A�������_�ɑ�����TV�Ƃ����T
�@�@�O����A�l�b�gTV��S�ԑg�����^��̃��R�[�_�[�̓o��ɂ��傫���ς�����悤�Ɏv���܂��B
�@�@�����āA���̃R�~���j�e�B���`���������ʁB�Ⴆ�AWindows �ɑR����A���i�b�N�X �̂悤�Ȗ����\�t�g���F
�@�@�ʼn��ǂ��ĒN�����g����悤�ɂ��āA�������������悤�Ȃ��̂��A�u�t���b�g�����鐢�E�v�ł̓A�b�v���[
�@�@�h�ƌ����Ă���悤�Ȃ̂ł��B
�@�@�܂��A����Ȃɑ�U���ł͂Ȃ����ǁA���������e�ɊF���ӌ����������߂� �u���O�Ȃ́A���h��
�@�@�A�b�v���[�h�s�ׂ̐��ʂł��傤�B
�@�@�����ȑO�́A�A�}�]���̏��]��Akakaku.com�̂n�`���i�̌��R�~���ɕp�ɂɏ������݂��s�Ȃ��Ă������A
�@�@�����A�b�v���[�_�[���Ȃ�Ďv�����肵�Ă��܂��B
�@�@���R�Ȃ���N���ɃA�b�v���[�h���ꂽ��A�{���ɐ��������̂Ȃ̂��Ƃ����^��͑����ɂ��邵�A�}�i�[��
�@�@�����l����ƁA���Ȃ�^����c��܂����A�t���[�h�}���̌����悤�ɁA�Q�P���I�͌l�����E�ƌq����������
�@�@�̂悤�Ȃ̂ŁA���[�����킫�܂�����ŁA�֗��ȃc�[�������������g�킹�Ă��������܂����B
�@�@���������A�t���[�h�}���́A
�@�@�����Q�T�O�L���̐V�����ԓ���c�ɒ��ł��l�b�g�A�N�Z�X���\�ȓ��{�̍��x�ȃ��C�����X�����ɃA�����J
�@�@���ǂ����̂͂W�N������ƌ����Ă܂������A�F����́A���{�̂���ȏ͓�����O���Ǝv���Ă��܂���
�@�@�ł������H
�@�@�傫�ȕω��́A���łɋN���Ă���̂ł��B
�@�@�ł��A�p��ł��Ȃ��ƁA���E�ƌq�����Ă��܂���ˁB�@���ꎄ�����̖{�̘_�_�ɋ^�������d�v�ȃ|�C���g�B
�@�@�܂��A�C���h�l�A���m�l�A�A�t���J�l�́A�����Đ����l�̓z��ł͂Ȃ����A �l����̒Ⴓ�𗘗p������������
�@�@���X�̊��p�́A�l����̍����� �ނ�̌����ӎ��̏����ɂ���Ď�����Ǝv���܂��B
�@�@�E�E�E�܂��A����Ȃ��Ƃ͂��̃z�[���y�[�W�̘_�_�ł͂Ȃ��̂ŁA�����ł͂ǂ��ł��悢���ǂ��B
�@�@�F����A�A�b�v���[�h���Ă��܂����H
�@�@���̐�A���̒��ǂ��Ȃ����Ⴄ�̂ł��傤���ˁB
![]()
Column215�@�@ 2007/7/16 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �R�[�`���O�̑Ώ�
�@�@�R�[�`���O�ɋ��������������Ƃ�������Ȃ炲���m�ł��傤���A�R�[�`���O�Ƃ́A�u�����I�ȍs���𑣂��R�~���j�P�[
�@�@�V�����p�v �ł���ƌ����܂��B
�@�@�R�~���j�P�[�V�����p�ƌ�������ɂ́A�������R�~���j�P�[�V��������S�Ă̑��肪�Ώۂł���A�e�ɂ����āA�ޏ�
�@�@�ɂ����Ďg����̂ł����A�R�[�`���O���Ј��Ɋw���悤�Ƃ����Ђ̑����́A��i���畔���ւ̎w�����@�Ƃ���
�@�@�w�������Ƃ����^�[�Q�b�g���ڂ����Ă��܂����߁A��ƌ����̃R�[�`���O���C����Â�����́A�T�ˁA�Ǘ��E��
�@�@���A���[�_�[�����̌��C�Ƃ��Ċ��E�ē������Ă��܂��B
�@�@���ׁ̈A��u�҂̕��̑������A�R�~���j�P�[�V�����p�Ƃ������A������y�w���p�Ƃ��Ċw��ł���悤�ȋC�����܂��B
�@�@���͂����Ɋ�Ƃ��R�[�`���O�����܂�����������Ă��Ȃ��A����������悤�ȋC�����܂��B
�@�@���́A���̋Ζ���ł��A�Ј��ɃR�[�`���O���C����u���Ă��������Ă���A�Ǘ��E�w�̂قƂ�ǂ���u���I�����A
�@�@���N����́A��ʐE �i��Ǘ��E�j �̕��ɂ���u���Ă��������Ă��܂��B
�@�@��ЂƂ��ĎĂ��������̂ł�����A���R�Ȃ���ړI�́A�Г��̃R�~���j�P�[�V���������������邱�ƂȂ̂ł�
�@�@���A�����āA�����w�����y�w���������ړI�ł͂Ȃ��̂ł��B
�@�@�ƌ������A�u�w�������܂��Ȃ�v �Ƃ� �u�w�����@�̃}�X�^�[�v �Ƃ����ړI�ł͑S���Ȃ��A
�@�@�Ј��̕��X����i�E�����A��y�E��y�A�������m�@�Ƃ����W���āA
�@�@�@ �������g���q�ϓI�Ɍ��āA�����̍l�����������莝�B
�@�@�A ���݂����v�������Ƃ�f���Ɏ咣����B
�@�@�B ���݂�������̘b����������ƕ����āA�v�����݂⌈�ߕt���ł͂Ȃ��A����̋C�����E�l���E���ꂫ����Ɨ���
�@�@����B
�@�@�E�E�E���̏�ŁA��܂������Ă������Ђɂ���̂��ړI�Ȃ̂ł��B
�@�@���̋Ζ���́A�₽��l���̑����}�X�v���I�Ȋ�Ƃł�����܂��A�Ј����ꂼ�ꂪ�A���痦�悵�Ċ撣���
�@�@����ΐL�тĂ͂����Ȃ��ł��傤�B�܂��A�ƊE�I�ɂ��A���� �h �s �Z�p�̍X�Ȃ�v�V���N����A�l�X���I�t�B�X�ł�
�@�@�Ȃ��A����ŋΖ�����悤�Ȑ��̒��ƂȂ�����A�}���ɏk�����čs����������Ă��܂���������Ȃ��ƊE�Ȃ̂ł��B
�@�@����Ȓ��ŁA�Ј��S�����A�����̐����̂��߂̖ڕW�������A���ۂɐ������������Ȃ���d�������邱�Ƃ��A�{�l
�@�@���g�A�����ĉ�Ђ��̂��̂̐����ƍK���ɂȂ�����̂Ǝv���Ă��܂��B
�@�@�R�[�`���O�͒P�Ȃ�R�~���j�P�[�V�����p�ł͂Ȃ����A��i���畔���A���[�_�[���烁���o�[�ւ̎w���ł��Ȃ��B
�@�@�R�[�`���O�͊F���O�����ɐ����镶�����̂��̂ł���A�O�����ȍl���������s���邽�߂̃X�L���ł���B�Ǝ���
�@�@�v���Ă���̂ł��B
�@�@����A�Ј��̕����R�[�`���O���C����u��������ǂ�ł���ƁA
�@�@�u���ɂ͕��������Ȃ����A�`�[�����Ɍ�y�����Ȃ��̂ŁA�g�������Ȃ��B�v�@�Ƃ������z���ڗ����܂����B
�@�@�u�t�́A����R�[�`�Q�P�̎В��ƂȂ��������I�搶�ł���A����������₷���ƎГ�����̎�u�҂ɂ��]������
�@�@���̂ł����A �c�O�Ȃ���A�����������Ȃ����Ђ���Q���҂ɂ́A��i���畔���A��y�����y�Ƃ����W�ł̃R
�@�@�[�`���O�Ƃ����A�~�߂��Ȃ������悤�ł��B
�@�@����搶�͂��̋ƊE�ł͑��l�҂ł����A���C����邾���ł����b�L�[���ƁA���Ȃ�v���Ă��܂����A
�@�@���������A�R�[�`���O�{���̑O�����Ȑ��_��`���Ă����������������Ƃ���ł��B
�@�@���́A�ߋ��Ɏ�u�����Ǘ��E�̕��̒��ɂ��A�X�L���Ƃ��Ă͕����邪�A�����̎w���X�^�C���Ƃ͈Ⴄ�Ƃ������z��
�@�@�q�ׂ�ꂽ�������������܂����A����B��Ǘ��E�Ŏ�u�������́A�����⓾�Ӑ�E�W��Ƃ̃R�~���j�P�[�V��
�@�@���ɉ��p�������Ƃ̊��z���q�ׂĂ���A�~�ߕ��͐l���ꂼ��A�Ƃ��v���܂����A
�@�@�R�[�`���O�̓X�L���ł͂Ȃ��A�����B���ꂾ���͌J��Ԃ��咣�������Ƃ���ł��B
![]()
Column214�@�@ 2007/7/7 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �i���̓G�A�������L����
�@�@����A�i���͂ɂ��āA���b�����܂������A�d�����c�ōŌ�̋l�߂����悤�Ƃ���ƁA�K����R������A�������܂��B
�@�@�W����ƍ��⒲�������Ă����悤�Ɍ����ƁA �u�����܂ł��Ȃ��Ă����v�ł���B�v
�@�@��c�����̌����Ă����悤�Ɍ����ƁA �u�F�A�C�����܂����B�v
�@�@����ɔ����āA�������Ă����悤�Ɍ����ƁA �u����Ȏ���A�o�܂����B�v
�@�@����ȁA�������Ȓ�R�͂��ł��A�ǂ��łɂł�������̂ł��B
�@�@���ʂɂȂ邩���m��Ȃ���Ƃ��ɒ[�ɖʓ|��������B�@����Ό������L�����ł��B
�@�@�F�X�A������R�������邻�̎�r�ɂ͋��Q���܂��B
�@�@�ł��A�ǂ�����́A�債�����ƂȂ���ƂȂ̂ŁA
�@�@�i���Ƃ��ď������Ă����A��l�̏ꍇ�̑Ή����X���[�Y�����A�C�����I�ɂ����S�ł���͂��ł��B
�@�@���ꂪ�����o���Ȃ������ł͂Ȃ��̂ɁA�������L�����̕��X�͕K���ƌ����Ă����قǒ�R�������܂��B
�@�@�u�N�͗X�����c�����Δh���H�v�@�ƌ����Ȃ���A���ǂ͂�点�܂����A�u�c�u�c����������B�@�Ō�̒�R�Ȃ̂ł��傤�B
�@�@����Ȍ������L�������A�d����C����āA�����̐ӔC�Œi��肵�A�o����ς�ł����A�ׂ��Ȓi���͋�����������
�@�@�C�Â��Ă����͂��B�@�Ǝv���Ă��݂܂������A
�@�@�C������C�����ŁA�蔲����ƁB�@��肪����A���o�ł��B
�@�@�ł��A�������L�����́A�������痈���ŁA�u�ق��Ƃ��đ��v�ł���B�v�@�ĂȊ����ŁA����Ă͂��܂���B
�@�@�����̎d�����A�����̐ӔC�ł������Ƃ��Ȃ����B
�@�@����Ȋ�т�X�b�L���������������Ă��������ȂƂ��v���̂ł����A������̂ł��B
�@�@�����Ȃ�Ǝ����W�Ԃ��Ă���R�[�`���O�I�ɁA����Ɏ����ōl�������āA�[�������ł�点����@�́A�c�O�Ȃ�����ʓI��
�@�@�͂���܂���B
�@�@���ǂ̂Ƃ���A�������L�����ɑ��ẮA
�@�@��c��v���W�F�N�g�̖ړI�͂��ꂱ��B
�@�@�d�����ǂ���������ŁA�S�[���ɓ��������炢�����B
�@�@���̂��߂̖��_�͓O��I�ɔr�����āA�X���[�Y�ɃS�[����ڎw������B
�@�@�Ȃ�Ă��Ƃ����`��������A�P�ɉ��ɂ��w���������A�ǂ��Ȃ낤�Ƃ�����o�����ɖق��Ă��邱�Ƃ����ʓI�Ȃ�
�@�@���ȁA�Ȃ�Ďv���Ă���܂��B
![]()
Column213�@�@ 2007/6/24 �����@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �V�h�L���т��ӎu
�@�@�Ȃ����]�������Ă��܂����A���ݏ��̌Y������ �u�V�h�L�v ��ǂݏI���܂����B
�@�@�����͂P�V�N���O�̍�i�B���������Ӗ��ł́A�o�u���^�������̏����ł��B
�@�@���������́A
�@�@�^�c�L�V����剉�̉f����������A�ڂЂ낵����剉�̃X�y�V�����h���}���Q�삭�炢����Ă����̂����܂����B
�@�@���R�A�P�O�N�ȏ�O�̂��Ƃł����A�����Ƃ��ēǂނƁA�S���Ⴄ���e�ł����B
�@�@�S���Ⴄ�ƌ����Ă��A�f���s�u�̃X�g�[���[�͌���ɂ��Ȃ蒉���ł��B
�@�@�ł��A�����h���}�A�|���X�A�N�V�����Ƃ����C���[�W�����Ȃ������A�f���s�u�Ƃ͈���āA�����̊����́A�h��
�@�@�}�̗�����i���Ă��܂��B
�@�@�����̒��ɓǂ݂Ƃꂽ�A
�@�@��l�����x�@�g�D�̏c�Љ�Ɖ��Љ�̂Ȃ���̗����ɔw�������āA���������Ƃ͐������̂��ƐM���āA�{��
�@�@�ɑł����ގp�����A�f��E�s�u�ł́A�P�Ȃ�g�D�ْ̈[�� �Ƃ����\���ŏI����Ă���悤�Ȋ����ł��B
�@�@�^�c����̉��Z�ɂ́A����ȉ��o�����Ă��܂肠��ǂ�������܂������A�ڂ���̉��Z�͂ł͖����B�P�Ȃ�Y
�@�@���h���}�B
�@�@�����̗��v�̂��߂Ȃł͂Ȃ��A���������Ƃ͒N������܂��悤���A�g�D�̂͂ݏo�����̂ɂȂ낤���A��������
�@�@�ƂȂ̂������ɂȂ��Ƃ���B�E�E�E����ȋ����ӎu�������āA�d�������Ȃ��Ă����B
�@�@����Ȑl�A�������͂��߁A�g�߂ɂ͂��Ȃ��ł�����˂��B
�@�@�����������A����Ǐ����B������Ɗ������܂����B
�@�@���Ȃ��́A����Ȉӎu���т��܂����H
![]()
Column212�@�@ 2007/6/22 �����@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �G���f���A�����X���̔E��
�@�@���͍ŋ߁A
�@�@�u�G���f���A�����X���Y���v�Ƃ����A�p���l�ɒn�T���ƃV���N���g���̓�ɒT���ɂ����鑘���̐��ҋL�i���b�j��
�@�@�ǂ݂܂����B
�@�@���N�O�ɁA���[�_�[�V�b�v�̎Q�l�{�Ƃ��Ă��b��Ƃ͂Ȃ��Ă��܂������A���̖{�������ꂽ�̂��ĂP�X�T�X�N �i�}�O��
�@�@�E�q����菉�Łj�Ȃ�ł���ˁB�܂�A�S�W�N���O�B
�@�@�Â��{���Ƃ������������āA�ǂ�ł��܂���ł������A������܂��ܖ{���Ŏ�ɂƂ��āA�w�����Ă��܂����̂ł��B
�@�@�o�ꂷ��̂��A��ƕX�ƊC����Ȃ̂ɂ��Ă͌��\�ʔ����A�ł��A�����܂ł̑O�u���������ȂƂ����̂����
�@�@��ہB
�@�@�����ă��[�_�[�V�b�v�{�ł͂Ȃ��ȁA�Ƃ����̂����̊��z�ł͂���܂����A���҂̃A���t���b�h�E�����V���O�����A��
�@�@�߂ċq�ϓI�ɁA�V���N���g���͂��ߒT������s�̍s����`�ʂ��Ă���̂ŁA�Ɍ����ł̍s���w�Ƃ������A�g�D
�@�@���ǂ��������āA�ǂ����ʂ��グ���̂�����������e�ł��B
�@�@�����V���O���͒T�����̃����o�[�ł͂Ȃ��A���L���̎����╷����肩��{�ɂ����悤�ł��B
�@�@������������z�������҂ɂ͊������o���܂��B�@�����āA �G���f���A�����X �� �E�� �Ƃ����D�����Ӗ��[�ł��B
�@�@�I�[�g�o�C�̑ϋv���[�X���G���f���A�����X���[�X�Ƃ��G���f���[���ƌ����܂�����˂��B
�@�@�ǂ��l�߂�ꂽ�ł����Ă��A�����Ċ�]�����킸�ɑO�����ɍs�����邱�ƂŁA�K�������J����B����ȋC����
�@�@�ɂȂ�܂����B
�@�@�������A����͂��̒T���������b�L�[�Ȍ��ʂɌb�܂ꂽ����ł����āA���҂ł��Ȃ���A����Ȑ��ҋL������
�@�@��Ȃ������ł��傤�B
�@�@�V���N���g���͂��������₷���A�����ł�����A��Âȃ��[�_�[�Ƃ������e���ł��B
�@�@�ł��A����Ȕނ��A��s���i�S�[���ւ̓��j�������Ȃ��Y���E����̒��ŁA�Q�W���̒��ԑS�����ĘA��A���
�@�@�����A�B�ꖾ�m�ȉ��l�ς��S�[���Ƃ��ċ����`���A�F�X�Ȑ��i�̏�g�݈���K�ޓK���Ŏg�������A�s����}���Ȃ�
�@�@��A�S�[���ւ̃��`�x�[�V���������߂Ă����B
�@�@����ȃV���N���g���̍s���́A�i���s�\���ȍs�������������ɂ͌����Ă��A
�@�@�S�Ăɒʂ���i���͂�������^�́[�_�[�Ȃ̂��Ǝv���܂����B
![]()
Column211�@�@ 2007/6/18 �����@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �ڂ͂ǂ����ɉj���H
�@�@�ڂ��j���A���Č�������ǁA�R�����Ă�����́A����̖ڂ�^��������Ȃ��ƌ����܂��B
�@�@�������A�v���̍��\�t�ɂ́A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���ǁA
�@�@�������g�ɓ��Ă͂߂Ă݂Ă��A���₳�ꂽ���e�̓������l���Ȃ���b�����Ă�����A�v���o���������Ɏ��M������
�@�@���Ȃǂ́A���ۂɖڂ������j���ł���悤�ȋC�����܂��B
�@�@�ӂނӂށA�ڂ��j���A�R�����B �E�E�E�E ���͂���Ȃɂ͒P���ł͂Ȃ��悤�ł��B
�@�@�ڂ͂ǂ����ɉj���̂��H�@���͂��ꂪ�厖�ł��B
�@�@�S���w�I�ɂ́A
�@�@�@�� �ӕ\�����ꂽ���́A�܂����B
�@�@�@�� �ߋ��̑̌��A���܂Ō������i���v���o�����́A����������������B
�@�@�@�� ���܂łɌ������Ƃ̂Ȃ����i��z�����鎞�́A�������E��������B
�@�@�@�� ���y�ȂNJ��o�Ɋւ���C���[�W��������ł��鎞�́A�����������������B
�@�@�@�� ���̓I��ɂȂǐg�̓I�C���[�W��������ł��鎞�́A�������E���������B
�@�@�@�� ���|������Ă��鎞�A���]�̈ӂ�������͎������^���������i���ڎg���j�B�@�Ƃ����X���������ɂ��邻���ł��B
�@�@�܂�A�������E��Ɍ�����A���������Ă���B�Ƃ������Ƃł��B
�@�@�������A�l���͂���̂ł��傤�B
�@�@�ł��A�T�ˁA����̎���������A�@�����A�L�����肩�łȂ��ȁ@�Ƃ��A�Q�ĂĂ���ȂƂ����z�����o����̂ł��B
�@�@�����́A���ɂ��R�~���j�P�[�V�����ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����܂��B
�@�@�u����ȂǂŁA�u�t�ɖڂ���������ƁA���̘b�͗ǂ������Ǝv���X���������A
�@�@�ڂ��������Ȃ��ƁA�܂�Ȃ������Ǝv���X�������邻���ł��B
�@�@�܂�A���Ȃ����u�t�Ȃ�A���S���ɏ��J��ƁA�ڂ����킵�Ȃ���b������A������₷���̂ł��B
�@�@�P�P�̉�b�ɂ����Ă��A���ȂÂ��悤�Ɏ��������킹��A�b���������Ă���Ɠ`��邵�A������Ƃɂ��A��
�@�@�ڎg��������A�b��M���Ă��Ȃ��Ɠ`���ł��傤�B
�@�@�����A���Ȃ��͖����̑ō����ŁA�������ǂ����ɉj�����܂����H
![]()
Column210�@�@ 2007/6/9 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �a�@�ɍs�����@�i�a�͋C�̓G�j
�@�@����́A��i�̕a�@�ɍs���܂����B ���́A�����������ĂR�T�ԂقǓ��@���Ă���Г��̕������������ɍs�����̂ł��B
�@�@��i�≺ �i�������g���������̉w�ł��j �����i�_�Љ����ɏ���ɂȂ��������ʂ���オ���čs�����̂ł����A
�@�@�債����ł������̂ɁA�����������ď��������B�@�����āA���܁A������̖؉A�̗��������ƁB
�@�@�a�@�ɒ����ƁA
�@�@�����A�����͐́A�����Ј������ꎖ�̂ŒS�����܂ꂽ�a�@����Ȃ����A�Ȃ�Ďv���o�����肵�܂����B
�@�@�������\�N���O�̂��Ƃł����A�l�������������������A�[��ɕa�@�ɋ삯���A��p������o�Ă���F�l�������Ƒ�
�@�@���Ă����L�����h��܂��B�@�������C���[�W�̒������łȂ��A���ۂɂ��Â��A�����a�@�ł��B
�@�@�ŁA�a���ɍs���Ă݂�ƁA
�@�@�Ȃ��A��F�̂��� �i���Ă����č����j�A�X�|�[�c���ŁA颂��͂₵�����Ȃ茳�C�����ȕ��������܂���B
�@�@�ǂ����Ă��A���@�����Ј��̕��ł͂���܂���B�����ԎႢ���B
�@�@�������A���̕�������~���Ă����̂ł��B �����ƁA�{�l�ł����B
�@�@�b���ƁA
�@�@���@�O�͍����ɂ��āA�w����Q�A�R���̉�Ђɗ���̂��A�x�x�ݕ����Ȃ��Ƃ炭�A�܂���Ђł������Ƃ炢�����
�@�@�Ă��������ł��B
�@�@���ꂪ�A�w���̎�p�������Ƃ���ɐ������q���ǂ��Ȃ�A�����P�T�Ԃقǂ́A�R�O������P���Ԃ̉@�O�U�������n�r����
�@�@�Ă�ɂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B�E�E�E���Ă������炩����������ȏΊ炪���ڂ�Ă��܂��B
�@�@�������A���@�O�͎���� �i�ƌ����Ă��U�O�O�̊����̕��ł���j �������̂ɁA�X�|�[�c�������Ă��ɗǂ���������
�@�@�܂��B���@���ē��Ă������̂ł��傤���B�@颂��A�����Ė���颂ł͂Ȃ��A�X�|�[�c�}���ۂ������Ă܂��B
�@�@�T�C�U�ˁA����V�A�W�˂͎�Ԃ��������ł��B
�@�@�w���̒ɂ݂��قƂ�ǖ����Ȃ����̂ŁA�����ڂ܂Ŏ�Ԃ��āA�����������Ă��܂����悤�ł��B
�@�@���[��B�܂��ɕa�͋C����B �i������ƈႤ���I�j
�@�@�܂��A�C�͂���a�C���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�a�C���������̂ŋC�͂��o�Ă����Ƃ����t�̘b�ł�����A
�@�@�܂�A�a�͋C�i��j�̓G�Ƃ������Ƃł����ˁB
�@�@���A������A�o���o���d��������̂ł��傤�ˁB
�@�@�ǂ����A���q�̈����Ƃ��낪������́A�܂��͕a�@�ɍs���Ă݂܂��傤�B
![]()
Column209�@�@ 2007/6/6 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �݊��͂ւ̒�R
�@�@�ŋ߁A���������Ȗ{�B�@�u�݊��́v �ł��B
�@�@�������A�{���͗ǂ��{�Ȃ̂ł��傤�B���\����Ă��邵�B
�@�@�ł��A���̎��͂̕��X�ŁA�u�݊��́v ��ǂ�ŁA�����{�������Ă�����́A��O�Ȃ��A���X�݊��ȕ��ł��B
�@�@�����̓݊����͐����������B�@�����咣���������B
�@�@�m���ɁA�C�z����肵�Ă��āA��肽�����Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ́A�ʔ����Ȃ��ł����A�d���ł���A�����̒�
�@�@�R��r�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��L�邩������܂���B
�@�@���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���R����悤�Ɏv���Ă��܂��̂��A�C�z��̂��߂��������肷��̂����m��܂���B
�@�@�܂��A�ׂ������Ƃ͂ǂ��ł�������Ǝv���������A�厖�Ȃ��Ƃ����ɏW�����ė͂��ł��邩���m��܂���B
�@�@����̂��Ƃ��l���߂��āA���܂��s�����o���Ȃ����ɂ́A���ɂ͓݊��ɂȂ邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��傤�B
�@�@�ł��A���X�݊��őS���C�z��E�����̏o���Ȃ����ɕK�v�Ȃ̂́A�����̔�����s�������͂̕��ɂǂ���������邩
�@�@�ƁA�l����C�����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�@�u�������Ĉ̂��Ȃ�l�Ԃ́A���肪�ǂ��v�����Ȃ�čl�����ɁA�@�����Ɍ��ʂ����߁A�����ɂł���点��B�v
�@�@���āA���ɂ����������Ă��ꂽ�������܂����B
�@�@���̍l�����͂���Ӗ��������Ƃ͎v���܂��B
�@�@���ʂ����߂�ꂽ�����́A�ǂȂ��Ȃ�����K���Ŋ撣�邵���Ȃ����A�d�����o���Đ������邩������܂���B
�@�@�ł��A�����ɂ���̂͋��|�����Ɠ������A�͂ɂ��x�z�ł��B
�@�@�撣���Ďd�������Ȃ������������������Ƃ��Ă��A�d�������Ƃ������������A���|���瓦���ꂽ�������̂�
�@�@������ł��傤�B�������A���Ƃ��������т��B�@�݂����ȁB
�@�@�m���ɁA�����ς��C�z�肷����A�݊��ɂȂ����ق����y���ȂƎv���邱�Ƃ͑��X����܂��B
�@�@�ł��A���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́A �u�ׂ������Ƃ��C�ɂȂ�v �ł͂Ȃ��A �u�C�z��v �ł��B
�@�@������A�݊��͂ɂ͒�R�𑱂��܂��B
![]()
Column208�@�@ 2007/6/1 �����@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �C���[�W�g���[�j���O
�@�@�e�P�h���C�o�[�̎G���C���^�r���[��ǂ�ł���Ǝ��X�o�Ă��錾�t������܂��B�@�C���[�W�g���[�j���O�Ƃ������t�B
�@�@���ۂɖ{�ԃ}�V���Ŗ{�R�[�X�𑖂��@����[���I�ɐ���Ă���e�P�h���C�o�[�́A���Ă̋L������ۂ�
�@�@���ŕ����Ċm���߂��R�[�X�̌�����v���o���A���̒��ő��s���V���~���[�V�������ăg���[�j���O����̂������ł��B
�@�@�ǂ������̃R�[�i�[�̓����Ńu���[�L�݂Q���ɗ��Ƃ��A�ǂ������܂ł˂�B
�@�@�Ƃ�����̃V���~���[�V�����P����������Ă݂Ď��ۂɃ^�C�����v����������邻���ł��B
�@�@��������x���J��Ԃ��A�����̊��o�ɋ߂Â��Ă����킯�ł��B
�@�@����Ȃ��ƂŌ��ʂ�����̂ł��傤���B
�@�@�������A�C���A�H�ʏ��}�V���̎d�オ��A���ׂĂ��{�ԂƂ͑傫���قȂ�ł��傤�B
�@�@�ł��A���ɑ����̃h���C�o�[���C���[�W�g���[�j���O�����{���Ă���Ȃ�̌��ʂ��グ�Ă���悤�ł��B
�@�@���Ă��āA���������ł�����A���R�̂��ƃ��[�V���O�h���C�o�[�Ȃǂł͂Ȃ���X�̓���ɁA�������p�o���Ȃ�����
�@�@�l���Ă݂܂����B
�@�@�C���[�W�g���[�j���O�̌��ʂ́A�{�����Ȃ������^���̌��B�@����Ӗ����n�[�T�����ʂł��B
�@�@�ł��A���n�[�T���̖ړI�Ƃ͉��ł��傤���H�E�E�E�l���Ă݂܂����B
�@�@���n�[�T���̑��̖ړI�́A�������Ă��������̖{�ԑO�̃_���o���B
�@�@�܂�́A����i�t���[�j���m�F���邱�ƂŁA��ʁA��ʂ�_�i�|�C���g�j�Ŋm�F����̂ł͂Ȃ��A�O��̌q�������i��
�@�@�C���j�Ń`�F�b�N���A���_�i��j���Ȃ������c�����邱�Ƃł��B
�@�@���O�ɖ��_���c���o����A���O�ɏC�����\�Ȃ킯�ł��B
�@�@�ł́A���n�[�T���̑��̖ړI�B
�@�@����́A�����ʂ�^���̌��B
�@�@�N�ł��A���߂Ă̂��Ƃɂ͌˘f���܂����A�Q�x�߂̂��ƂȂ�Q�Ă���͂��܂���B
�@�@�R�x�ځA�S�x�߂Ȃ�A�X�ɗ����������s�����o����ł��傤�B
�@�@�^���̌��Ƃ͂����A�����̍s���̗��ꂪ�\���V���~���[�V�����o���Ă���A�s�������X���[�Y�ɂȂ�̂ł��B
�@�@�����܂ŃN���}�ő����Ă�B�����Ƒ��Ɍ���ꂽ���A
�@�@���Ȃ��́A�����ɂȂ��Ă����Ȃ�N���}�ɏ���āA���ĉE���������A�����������Ɖ^�]���ăX���[�Y�ɖړI�n�ɍs��
�@�@�����܂����B
�@�@�����A�J�[�i�r�ɗ���قǂł��Ȃ��s���Ȃ�A�܂���̂̌����ōs���邩�ȁB�Ǝv���ăN���}���^�]���܂����A
�@�@���A�����_�ŋȂ���Y�ꂽ��A��{��O�̓��ŋȂ������肷�邱�Ƃ�����܂��B
�@�@�C�t���Ȃ������ɁA��������イ�s���ʂȖړI�n�i�w�Ƃ��j�ɍs���s����̂��Ƃ��Ă��܂��̂ł��B
�@�@�ł��A�o���O�ɁA�����̌����_�͉E�A�����̌����_�͍����炢�̗v�_�̒��ŁA�����_�̉f����`������ŃV��
�@�@�~���[�V�������Ă����ƁA���͊ԈႦ���ɍs���܂��B
�@�@���ꂪ�^���̌����ʁB�@�E�E�E�E �ł����ˁB
�@�@�ق�̂�����Ƃ̋^���̌����s�����X���[�Y�ɂ���̂ł��B
�@�@��Ђ̋A��ɐ��������āA�ǂ��o���Ă��Ȃ��̂����ǁA�����ƉƂɋA�蒅���Ă����B����Ȍo���͂���܂��H
�@�@���́A����̍s�����o���Ă����悤�ɏo���Ă���̂ł��B
�@�@���̃��C���i�t���[�j�`�F�b�N���ʁA�^���̌����ʂ����܂��g���A��c�̎i��i�s�����āA�A�E�ʐڂ����āA���܂�
�@�@�����悤�ȋC�����܂��B
�@�@�Ⴆ�A��c�̐i�s���A�P�ɃV���~���[�V�������邾���łȂ��A�������i������Ă���l�q��A�����҂̔������e��
�@�@�������Ă���l�q���v�������ׂȂ���A�J���A�Ō�̋c���̂܂Ƃ߂܂ł��C���[�W���f���Ƃ��ē��Ɏv������
�@�@�ׁA��ʂ�Ȃ����Ă݂�̂ł��B
�@�@�{�ԂŁA����������A����Ă����ȕ��ȂǁA���Ɍ��ʂ�����Ǝv���܂��B
�@�@���������A�Љ�l�ɂȂ�������̂���̃N���u�����i�H�j�ŁA���ŏ����Ă���l�q���C���[�W�g���[�j���O���āA
�@�@�����ɂ̂���ł����o��������܂���B�i���Ȃ݂Ƀ��[�V���O�J�[�g�ł��B�j�j
�@�@�K�����Ă�Ƃ����킯�ł͂Ȃ�����ǁA�X���[�Y�ɉ^�Ԃ��̂ł����B�����ڕW������C���[�W�g���[�j���O����
�@�@�p����̂͌��ʂ�����̂ł��傤�ˁB
�@�@���������A���ۂ̍s�����C���[�W������ʂɉ����āA���܂��s������̎����⒇�Ԃ��C���[�W���邱�Ƃ͖ڕW�B����
�@�@���Ȃ�̌��ʂ����邻���ł��B
�@�@�Ζ���̃R�~���j�P�[�V���������������悤�Ƃ��Ă��鎄���A�F�������������Ƃ��X���[�Y�Ɉӌ������ł��A�����
�@�@���ăj�R�j�R�Ǝd����i�߂Ă���������C���[�W���Ă��܂��B
�@�@�S�[���₻�̐��������ƃC���[�W���邱�Ƃ́A�ڕW��B�������Ԃ̋ߓ��ł��B
![]()
Column207�@�@ 2007/5/30 �����@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �ڂ͂����قǂɂ��̂�����
�@�@�ڂ͂����قǂɂ��̂������B�@�Ȃ�Ă��Ƃ������܂����A����ȑ���̖ڂɕ\���C������ǂނ̂����Ȃ��̖ځB
�@�@�ڂ͐F�X�ȏ��Ƃ̃R���^�N�g �i���ڐG�j �̓�����ɂȂ�̂ł��B
�@�@�Ⴆ�A���N�����鎄���A���A�X���[�Y�ɖڊo�߂邽�߂ɂ���Ă��邱�Ƃ́A�J�[�e���̒[�������Q�O�����قNJJ��
�@�@�Ă������Ƃł��B
�@�@���z���������ނƁA���R�ɖڂ��o�߂�B���R�Ȗڊo�߂́A��ɂ̏��Ȃ��X���[�Y�Ȉ���ɂ��q����܂��B
�@�@����Ӗ��A�S�̌��N�@�ł�����܂��B
�@�@�����Ă܂��A���R�Ȗڊo�߂��ĂԂ��߂ɂ́A�X���[�Y�ɖ���ɗ����邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�@�X���[�Y�ɖ���ɗ����邽�߂ɂ́A�܂��A������O�̂��ƂƂ��āA
�@�@�ߌ� �` �� �̃R�[�q�[�A�Q���Ȃ̓Ǐ��E�h���I�ȃh���}�͔����܂��傤�B
�@�@�܂��A�l�ɂ����悤�ł����A�_�o�̍��Ԃ�̓X���[�Y�Ȗ����W���܂��B
�@�@�R�[�q�[ �i�J�t�F�C���j �ȊO�̎h���͖ڂ������܂��B
�@�@�����āA�����Ԃ̃p�\�R����ƁB
�@�@���ْ̋������łȂ��A���ړI�ɖڂ������h�����_�o�����Ԃ点�܂��B�@�d���ň���p�\�R���Ɍ������Ă���ƁA
�@�@�Q�t���������Ȃ����肵�܂��B�ڂ́A�h�������ړI�ɓ��͂���������ƂȂ�̂ł��B
�@�@�ߌ�̊O�o���ɂ́A�T���O���X��������B
�@�@��A���ɏA�Q������2���ԑO�ʂ��玺���̏Ɩ����Â߂ɂ���B
�@�@����ȏ��Z���A�X���[�Y�Ȗ�������܂��B
�@�@�ŁA���͂��܂�ǂ��m���Ă��܂��A
�@�@���Ă��~�߂����h���Ă��A�ڂ���������������Ă��̌��ɂ��Ȃ�܂��B
�@�@�����I���Ė{���ł���B
�@�@�����������ɃR���^�N�g�����ڂ��A�]�ɂ��̏��𑗂��Ă��܂��̂ŁA�������g�̖ڂ����܂��x���A�]���x������
�@�@���ł���Ƃ����̂��A���̎��_�ł�����܂��B
�@�@�����A�ڂ́A�]�ƒ������A�F�X�ȏ��������A�]�͂��̏������������Ă��܂��B
�@�@�]�������j��������悤�ɑ̓��Ɏw�����o���Ă��܂��̂ł��B
![]()
Column206�@�@ 2007/5/25 �����@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ����̔w�i
�@�@�q������A�u���́A�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��́H�v�@�Ǝ��₪���������A�œK�ȓ����͉����H
�@�@�u�ꐶ����������A�����w�Z�ɓ���邵�A�����w�Z�ɓ����A������Ђ̓���邩�炾��B�v
�@�@����ȓ����́A�q���ɂ͈Ӗ��s���ł��B
�@�@������Ђ��Ăǂ�ȉ�Ђ��H�@�����Ɠ������ł��B�@������Ђɓ�����A�싅�I�肩�A�C�h���ɂȂ�ق��������B
�@�@�Ȃ�čl�������邩���m��܂���B
�@�@�싅�I��ɂȂ���A������Ђɓ���ق����\����������Ȃ�Č����Ă��A�������Ă��炦��ł��傤���B
�@�@���������A������ЂƂ����I�����ɍi�荞��ł��܂����Ƃ��A�q���̏����̉\����ے肵�Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B
�@�@�u���́A�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��́H�v�@���̎���ւ̍œK�ȑΉ��́A����̔w�i���l���邱�Ƃɂ���܂��B
�@�@�������A
�@�@�u���́A���̎d�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł����H�v�@��������̂���Ȏ�������l�ł��B
�@�@���̔w�i�́A
�@�@�����������Ȃ�����A�d�����������Ȃ�����A�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�ł���A
�@�@�u�������Ȃ́H�v�@�Ƃ��@�u���̎d�������ȗ��R�ł�����́H�v�@�Ƃ��������Ԃ��A����̋C�����̔w�i�����������T����
�@�@�݂邱�Ƃ��o���܂��B
�@�@�u�q���͕���������̂��B�v�@�Ƃ��A
�@�@�u�d�������Ȃ��Ђ����߂邵���Ȃ���B�v�@�ƌ����Ă��܂��A�b�͂����܂łł��B
�@�@���������A
�@�@�u�V�����Q�[������肽���B�v�@�Ƃ��A
�@�@�u�����悤�ȃv���W�F�N�g���撣���Ă܂Ƃ߂��̂ɁA�@���ǁA�p�����ꂽ���Ƃ�����܂��B�v�@�Ƃ����悤�ȁA�^�̗��R��������
�@�@���邩������܂���B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�l�����������̂ɂ́A���R������B
�@�@�����l���A����ʂ����̕ԓ�������̂͂�߂܂��傤�B
![]()
Column205�@�@ 2007/5/13 �����@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �S�[����ڎw��
�@�@����͒��w�Z�̉^��������ɍs���܂����B
�@�@���w�Z�ɔ�ׁA�P���Ŗʔ��݂ɂ����܂����A���ׂĂ̋��Z���������������߂鋣�Z�Ȃ̂ŁA���k�̊F����͂����
�@�@��Ɋ撣���Ă܂��B
�@�@�k�����̃S�[���ƂȂ�n�_�Ō��Ă����̂ł����A�ʔ������Ƃ����܂����B
�@�@�ꐶ�����撣���đ����Ă���̂ɁA�S�[�����C���̕z�e�[�v�ɒB���鐡�O�ɁA�X�s�[�h�𗎂Ƃ����k�������̂ł��B
�@�@�S�[���̂T�O�����ʎ�O�ŁA������鐶�k�����\���܂��B
�@�@�擪�ő����Ă��ăS�[�����O�ŃX�s�[�h���ɂ߂���͂Q�l�ɂP�l�ʁA
�@�@����ɁA�Q�Ԏ�̕��ɃS�[�����O�Ŕ��������́A�S�l�ɂP�l�ʂ̊����ł��܂��B
�@�@�S�[���e�[�v���|���킯�ł��Ȃ��ł��傤�B
�@�@�ǂ����F����A�ق��Ƃ�����ɕς��A�S�[����ɒ�~�ł���悤�ɃX�s�[�h���ɂ߂Ă���̂ł��B
�@�@�S�[���͋삯������B
�@�@�搶�������w�����Ă���A�F����Ō�܂ŁA�S�͎�������ł��傤�B�@���������܂�܂ŗ͂��ȂƂ������Ƃł��B
�@�@������āA�d���̏�ʂł��������Ƃ��N���Ă���̂��ȁA�Ȃ�Ďv���Ă��܂��܂��B
�@�@�R�[�`���O�ł͂悭�A�S�[���ŗ����~�܂�ȂƋ����܂��B�@�S�[���ŗ����~�܂�A�ق��Ƃ��Ă��܂��A���̃X�^�[�g��
�@�@�łɎ��Ԃ��������Ă��܂��܂��B
�@�@�����ʂ�C�����S�[�����삯�����Ă������Ƃ�,���`�x�[�V�������ێ�����R�c�Ȃ̂ł��B
![]()
Column204�@�@ 2007/5/5 �����@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �l�̘b�͑f�i���j�ŕ�����
�@�@�l�̘b�́A���̐l�́����Ȑl���Ƃ�������ς��̂āA�f �i���j �ȏ�Ԃŕ����Ă����A���肪�{���ɓ`���������Ƃ���
�@�@�����Ă���B �Ȃ�Ęb���Г��̃����}�K�ɂ��悭�����̂ł����A�ǂ����Ă��A�Г��ɂ́A���ߕt�������s���Ă��܂��B
�@�@�u�ނ͌��ǁA�����ƌ��������̂���B��������������ˁB�v �Ȃ�Ċ����ł��B
�@�@�u���������A�ނ͂܂��b���I����ĂȂ�����B�v �ƌ����Ă��A
�@�@�܂��A�Ō�܂ŕ����Ă݂邩�A�Ǝv���Ă������͏��Ȃ�����������܂��B
�@�@����Ӗ��A
�@�@���ߕt���́A�ߋ��̑�������āA�����m�낤�Ƃ���s�ׂł��B
�@�@����̘b��������ƍŌ�܂ŕ������Ƃ́A���݂̑�����������茩��s�ׁB
�@�@��������āA�����ŏ����A�ǂ��炪���ǂ��s�ׁi�l�����j�Ȃ̂��́A��Âɔ��f�ł��܂����A�F�A���̂����R�ƌ�
�@�@�ߕt�����Ⴂ�܂��B
�@�@�Ⴆ�A����Ȍ��ߕt��������܂��B
�@�@�u�F�A�����v���Ă��B�v �Ƃ����悤�Ȏ����𐳓������锭���B
�@�@���ƂȂ��A�������������̂悤�Ȃ̂ł����A
�@�@�u�T�O�l�̕����̂����A�N�ƒN���������ƌ����Ă�́H�@���̈ӌ��́A�����ɂȂ邩�ȁH�v�@�Ǝ��₷��A
�@�@�l�����w�܂萔���ĂT�O�l���A�T�l�A�P�O���ɉ߂��Ȃ������m��܂���B
�@�@�ł��A���̏ꍇ�A
�@�@�u�F���āA���͏����ӌ�����Ȃ����B�v �Ƃ͂Ȃ炸�A
�@�@�u�������A�������B�v�ƌ��ߕt���Ɉ����Â��Ă��܂��܂��B
�@�@��c�ȂǂŔ��������Ȃ��ꍇ�A
�@�@�N�����ӌ������������_�ŁA���ꂪ���������Ƃ̂悤�ɂ��������Ă��܂����ʂ�����̂ł��傤�B
�@�@�������čl����ƁA
�@�@�l�̈ӌ�����ɑf�i���j�ȋC�����ŕ�������́A
�@�@���������f������ׂ̃c�[����������Ă���̂��Ƃ������܂��B
![]()
Column203�@�@ 2007/4/30 ���� �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �A���n�K�[���̃R�~���j�P�[�V����
�@�@���܂��ܓ_�����s�u�ԑg�ŃR�~���j�P�[�V�����ɂ��čl���������܂����B
�@�@�^�C�g���́u�A���n�K�[���v���������������A�n���C�ł̃T�[�t�B����炵���Љ��悤�Ȕԑg�B
�@�@���̉�̒��ł̘b�B
�@�@�č��l�̕��e�A�؍��l�i�����������m�l�j�̕�e�����A�n���C�ɏZ�ޏ������A�q���̍�����A���e�͐ϋɓI�Ɏ�
�@�@���ɘb�����Ă���āA�X�L���V�b�v�����Ă��ꂽ�B�ł��A��e�ׂ͂��ׂ����Ă͂���Ȃ������B
�@�@�����āA�����i�A���n�K�[���j����l�ɂȂ��čl���Ă݂�ƁA ��̓x�^�x�^�͂��Ă���Ȃ��������ǁA�Ƃ̂��Ƃ��ꐶ
�@�@���������������B
�@�@�č��l�̕��e�Ƃ͈Ⴄ�A���m�l�̕�e���̃x�^�x�^���Ȃ��₳�����A���ꂪ���ɂȂ��Ĕ������B�@�Ƃ̓��e�B
�@�@�x�^�x�^���邾�����R�~���j�P�[�V�����ł͂Ȃ��B�@�Ȃ�قǂƎv�����e�ł����B
�@�@���[��B�@���R�Ȃ���A�Ƒ��ł���A���������荇���@������Ă��邩������܂���B
�@�@�ł��A�d���̊W��������A�������Ȃ������̊W��������ǂ��ł��傤�B�R�~���j�P�[�V�����̋@��͉i�v�Ɏ�
�@�@���邩������܂���B
�@�@�ʂɂ��̕č��l�̕��e�̂悤�Ƀx�^�x�^����K�v�͂���܂��A���m�l�̕�e�̕\�����Ă͕\�����Ȃ����ǐ[����
�@�@��̂悤�Ȃ₳�����́A�d���̊W�ł͗�������Ȃ��\������ł��傤�B�@�c�O�Ȃ���B
�@�@�������A��X�͓��m�l�ł����A
�@�@�l�̉��l�ς����l�����A����̐S��ϋɓI�ɗ������悤�Ƃ������m�I�Ȋ���͒ʂ��ɂ������̒��ɂȂ��Ă���̂�����
�@�@��܂���B
�@�@�v���Ă��邱�Ƃ͐ϋɓI�ɕ\�ʂɏo���B
�@�@���̏�ŗ����������B
�@�@���̐��̒��ɕK�v�Ȃ̂́A����Ȏ��ȕ\���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
![]()
Column202�@�@ 2007/4/22 ���� �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� �ԈႢ�ɋC�t������
�@�@�ԈႢ�͎w�E������̂ł͂Ȃ��C�t��������́B
�@�@�R�~���j�P�[�V�����Ɋւ��鏑���ɂ́A�T�ˁA����Ȃ��Ƃ������Ă���܂��B�@�ǂ��������Ƃł��傤�B
�@�@����ɑ��āA�u����͊ԈႢ����Ȃ��ł����B�v�@�Ɩʂƌ������Ďw�E�ł��镗�ʂ��̗ǂ��͑����̕��̖]�ނ�
�@�@����ł����A���X�����������܂���B
�@�@�Z���̂悤�ɓ�������ŁA������Ɗ�������̂ł���Ηǂ��ł����A���Ɏd���̐i�ߕ��Ɋւ��邱�Ƃ�
�@�@����A���Ƃ��{���ɊԈ���Ă��Ă��A�{�l�������v���Ă��Ȃ���A�ԈႢ���w�E���Ă��A����Ȃ�Ƃ͎�
�@�@����Ă����Ƃ͌���܂���B
�@�@�����ŁA
�@�@�ʂƌ������ĊԈႢ���w�E����̂ł͂Ȃ��A�{�l���C�t���悤�ɂ��܂��U���ł���A�X���[�Y�ɊԈႢ�̏C
�@�@�������Ă��炦��\���������Ȃ�킯�ł��B
�@�@�ł��A��������ł͂Ȃ��A�������y�����ē����ł��B
�@�@�������A��i����u�Ԉ���Ă��B�v�Ǝw�E�����A�ԈႢ���C������ł��傤�B
�@�@�ł��A����A�����i����ԈႢ���w�E������́A�����ŁA������Ǝd�����`�F�b�N�ł���悤�Ɉ�Ă�ׂ�
�@�@�ł��B
�@�@�܂��A������x�o���̂���҂Ȃ�A�Ⴆ��i���猾���Ă��������咣���邩���m��܂���B
�@�@�u�����Ⴒ���ጾ�킸�ɂ�蒼���B�v�@�Ɩ��߂���A�C���͂���ł��傤���A�[�����͗L��܂���B
�@�@�ӂĂ�����Ă��邭�炢�͂ǂ��ł��悢�ł����A�i���ɂ͖��ƂȂ�܂����j�����̌��𗝉����Ă��Ȃ��悤
�@�@�ł́A�Ăѓ����߂����J��Ԃ��ł��傤�B
�@�@�u�Ԉ���Ă��邶��Ȃ����B�v�@���Č������͎~�߂āA
�@�@�u�����Ɂ����̏�����������A�����ɖ�肪�N���Ȃ����ȁA�m�F���Ă݂Ă�B�v
�@�@�Ƃ����悤�ɗU�����Ă݂Ă͂������ł��傤���H
�@�@�������A
�@�@�u��������Ă邯�ǁA���v�ł���B�v�@�Ƃ����悤�ȕԓ����L�蓾�܂����A
�@�@�u�Z�����Ƃ��낷�܂Ȃ����A���̌��́A���S�����������̂ŗ��ނ�B�v�@�ƌ����Ԃ��܂��B
�@�@�ׂ��ȍ�ƂŁA����A���S�����������Ƃ����͕̂ςł����A�傫�Ȏd���Ȃ�A�ӔC�҂��A�����v���͓̂�
�@�@�R�ł��B
�@�@�Q�d�`�F�b�N����T�d�Ȑl�Ԃ��Ǝv���Ă����������m��܂���B
�@�@����Ȃ炻��ŁA�����͖�����ƃ`�F�b�N����ł��傤�B
![]()
Column201�@�@ 2007/4/15 ���� �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�� ���_�@�ł��A���_�@�ł��Ȃ�
�@�@�l������Ƃ��ɁA���̑���̈����Ƃ�����肠���炤�������܂��B
�@�@�܂肻�̐l�̂��̂̌����͌��_�@�Ȃ킯�ł��B
�@�@����ɑ��āA���̑���̗ǂ��Ƃ���������āA�ނ͂����������B�ƍl����͉̂��_�@�B
�@�@�ǂ������ǂ��̂��Ƃ����ƁA���ƂȂ��A���_�@�̂ق����ǂ��B�Ƃ����悤�Ɏv���܂��B
�@�@�����Ƃ��날������Ă��L�����Ȃ����A�ǂ��Ƃ���������ė_�߂Ă�������A�L���Ă������ق����A�{�l��
�@�@���C�ɂȂ�B�܂��A���������Ƃ���ȍl�����ł����B
�@�@�������A���ǁA�����Ƃ���́A�w�E���Ȃ��ƁA�����ƈ����܂܁B
�@�@�܂��A���_�@���ƁA�����Ƃ�������邯�Ǘǂ��Ƃ����������ƁA
�@�@�����Ƃ���͂قƂ�ǂȂ����ǁA�߂����ėǂ��Ƃ�����Ȃ��A�ł��R�c�R�c����Ă�����A
�@�@���̂ǂ���̕����A�����]������Ηǂ��̂ł��傤���H
�@�@�������A�����Ƃ�������邯�ǁA�ǂ��Ƃ����������́A���X�ɂ��āA����̕��ɂ͗ǂ��ʂ���������āA����
�@�@���y�ɂ͈����ʂ������Ă���������܂��B
�@�@���_�@�ł͂Ȃ��A���_�@�B
�@�@�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�S�Ă��������ƌ��߂āA�t�F�A�[�ɔ��f����B�@����Ȍ������K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
![]()
�@�@���ĺ�шꗗ���@�@�@�ŐV�̼��ĺ�т��@�@
�@![]() �@�@�@
�@�@�@![]()