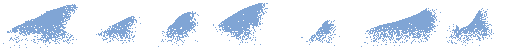
■ かなり影響を受けた本
●「普通人型リーダーが最強の組織を作る」
コーチングを知る前の私のバイブル。カリスマでも威張った管理型でもなく、部下を仲間として育てていくパートナーシップ
型リーダー。そんな考え方に初めて出会いました。リーダーは管理者ではなくビジョンを語る人、変化に適応してチャンスを
掴み組織を変革する人になれ、そんな内容です。
●「メンタリングの奇跡」
これもコーチング以前の私のバイブル。社員の育成に必要なのはよき見本となるメンターの存在。仕事の直接の指導担当者と
は限らず、社会のこと、自社のことその他もろもろをアドバイスしてくれる先輩との関係を指導の一環として構築したらどう
なるか。私の勤務先で採用させていただきました。
●「組織を救うモチベーターマネジメント 個人の潜在力を組織の顕在力に変えるリーダーの条件」
屋根裏部屋からひっぱり出してみると、付箋とマーカーだらけでした。私にモチベーションの源泉は何かを教えてくれた本で
す。15年位前の当時(2002年)、コーチ21の系列であるディスカバー21の書籍を扱っている書店はほとんどなく、入手
にも苦労しました。今では幾らでも似たような内容の本はありますが当時はこれだけ。これも私の部下指導のバイブルでした。
●「ものづくり無敵の法則」
ものではなくものがたり、つまり「こと」を大事にせよ。ビジネスとは何か、ビジネスに大切な何かを教示してくれる本です。
●「ビジョナリーカンパニー2」
かつての一流企業で、今も残っている企業は、行き先の決まったバスに乗客を乗せるのではなく、乗せた乗客に行き先を決め
させてきた。社員を育てるのではなく、優秀な社員を集めた企業だけが、社会情勢の変化に対応して生き残れる企業である。
うーん、そうか。でも難しいなあ。てな感じでした。
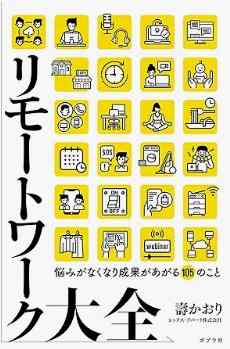
●「ザ・ビジョン」
FULL STEAM AHEAD! とは「全速前進せよ」という意味です。ビジョンの3要素である「有意義な目的」、「明確な価値観」、
「未来のイメージ」など企業におけるビジョンの大切さをストーリー仕立てで教えてくれる本。これを読んでから自分自身の
1年後、3年後、5年後、10年後のビジョンを考えるようになりました。会社のビジョンを考える際、そもそもビジョンと
は、企業にとってどういう役割を果たすのだろうと考えたことのない経営者はいないでしょう。今からビジョンを考えようと
いう方には役立つ本です。ケン・ブランチャードは「社員の力が最高のチームを作る」や「1分間シリーズ」の著者でもあり
ます。
●「見える化・強い企業を作る見える仕組み」
仕組みが見える。結果が見える。ルールが見える。見える化ができないやつの仕事は自己満足でしかない。これも一時期の私
の考え方の基本。本書では5つのカテゴリー(問題、状況、顧客、知恵、経営)の見える化を提唱し、それぞれの事例をかな
り豊富に紹介しています。定番のヒヤリ・ハットの見える化から始まり、病院の患者の声に対する回答の見える化、JRの事
故の歴史の見える化。なんて事例もあります。
●「アイデアのヒント」「アイデアマンのつくり方」
アイデアは天才のものではなく、既存の要素の組み合わせであり、日常を変えなくてはアイデアはやってこない。・・知りた
がりになる。笑われることを恐れない。型にはまった生活から抜け出す。色々なものを組み合わせる。情報をかき集める。い
ったん全部忘れる。ひらめいたら実践する。アイデアが閃いたらそのアイデアが逃げないように扉を閉める などの考え方を、
例えば、13の半分は何かという問いに6.5という真っ当な回答だけではなく「ThirとTeen」 「XⅢの上半分でVⅢ=8」など
色々な答えがあるというような、考えを広げるヒントとともに語ります。そしてアイデアマンそのものを育てるには、部下を
自分のためのメンバーではなく自分と働くパートナーとして扱い、失敗する自由を与える、バカなことをする、褒める、頭か
ら却下しない、任せる、問題の設定を変えるなどの方法論を展開します。この本を読んでしまうと、人と同じ考え方や行動は
できなくなり、時々周囲から変な眼で見られますよ。
●「リモートワーク大全」
図書館で発見。リモートワークに関する105のノウハウを掲載。制度、機器や各種ソフトの選定、効率的に勤務をするため
の工夫、悩みや疑問などの解決策などが満載。本格的な在宅勤務が想定されており、知りたいことが全て書いてある感じです。
自宅、自宅以外での働き方、オフィスの位置づけ、自宅での照明・空調・自宅デスク周りのセット、パソコンの設置方法・メ
ンテナンス・セキュリティの確保、各種コミュニケーションツールの比較、オン・オフの気持ちの切替方法、休憩時間の設定、
休憩の仕方・使い方、業務への集中の為の空気作り、残業時間を増やさない方法(これ経験的にかなり大事)、ペーパーレス
での業務の工夫、WEB会議でのルール・ファシリテーターの役割(かなり大事)・機器設定(雑音を出さない為の設定)・
WEB会議中のトラブル事例と対処方法、考え方の背景・文化が違う方(ローコンテクスト)に伝える工夫。効率が上がらな
い時の対策、効率が上がらない時の対策、相手による効果的なコミュニケーション方法などなど、兎にも角にも、おやつや飲
物の選択方法まで、なんでも書いてあります。新型コロナ初期の2020年の出版ですが、こんな本あったのかという感じで
す。新型コロナもひと段落した後に、リモートワークの導入で、業務に向けたモチベーションの拡大を図ろうとする企業であ
れば、目を通しておいて絶対損はしない本。きめ細かいですよ。非効率的なWEB会議や、集中できないリモートワークをお
こなっているなら、今からでも読んだほうが良いですよ。
そしてコーチング本。私を熱中させ、このHPの前身であるブログを始めさせた本たち。
●「もしもうさぎにコーチがいたら」「絵で学ぶコーチング」「コーチングマネジメント」
コーチングを日本に広め、ビジネスとして確立したコーチ21の伊藤守先生の3冊。「もしうさ」を読んでコーチに転職した
方は大勢いますよ。「もしうさ」でコーチングを知り、「絵で学ぶ」でコーチングを理解する。さらに同じく伊藤先生の「コ
ーチングマネジメント」でもっと深く理解するという難易度設定です。但し、米国のコンサル文化が発祥のコーチングには、
その実践に課題があります。やる気のあるリーダー、やる気のある部下、やる気のない部下にコーチングは役立ちますが、や
る気のないリーダーや、一方的な支持しかできないリーダーにはコーチングが使えない。いや学ぶことはおろか、理解するこ
とすら出来ないのです。そんなやる気のないリーダーには後述のEQ(心の知能指数)を高めてもらう手法が必要と私は思い
ます。
●「やりたいをやるに変えるコーチング」「ストレスをパワーに変えるセルフコーチング」「コーチングのプロが教えるほめる技術」
コーチングとは何ぞやを掘り下げ、コーチングスキルを最大限に活用して、人をそして自分までもを行動に導く実用的な3冊。
平野圭子さんの「やりたいを・・」はコーチングをツールとして活用し、自己実現する為の手引き、コーチとはすなわち「馬
車」、クライアントを目的地「ゴール」に連れて行ってくれる存在という考えです。自分の棚卸し、自分の強みの発掘、ゴー
ルの明確化、1年後、3年後、5年後の自分の行動のビジュアライズ化。その他盛沢山の実践的な書です。ちなみに、コーチ
が良い質問をして、クライアントが真剣に考えて新たな気づきを得る時を「天使が横切る瞬間」と表現するそうです。
ところで火事場の馬鹿力って知っていますよね。そう、ストレスもうまく使えばパワーに変えられるんですよ。高原恵子さん
の「ストレスをパワーに変える・・」は自分の感情をコントールし、マイナス思考から自分を防御し、やる気を引き出すセル
フコーチング指南書です。ちなみに高原さんは、自分の信頼できるサポーターは、口の堅い人、説教をしない人、自慢しない
人の3条件を満たす方であることが条件だと。そんな友人、あなたの周囲にいますか。もしいたら、一生の友人として大事に
したほうが良いですね。
コーチングで言うところのアクノリッジ(承認)は、相手の行動を褒めるのではなく、行動の良い部分をフィードバックする
ことによる存在承認なのですが、「ほめる技術」鈴木義幸さんはあえてほめます。認めて、ほめて、動かす。「ナイスショッ
ト」と言われてやる気がでた経験ありますよね。 平野さん、高原さん、鈴木さんともコーチ21の幹部であった方々です。
■ ストレートに役に立った本
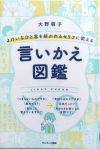
●「初めて部下を持つ人のためのリーダーシップ10のルール」 「リーダーが困った時に読む本」 「新米リーダー10のスキル」 「ポータブルコーチ」
リーダーになったら、まず読むべきコーチ21の3冊。この手の知識に向き合おうとしないでチームがどうこうとか部下がど
うこうとか言うな!・・と真面目に思いましたよ。ポータブルコーチは10年くらいは手元に置いてしょっちゅう見てました。
著者が日本人ではないのでこれらの本には日本の職場独特の例が足りないかな。
●「ファシリテーションの技術」「ファシリテーション入門」
あなたの組織では、意見がまとまらなくて困ってはいませんか。今では当たり前のファシリテーション。この考え方が世間に
広まる以前に読んだ本。ファシリテーターとして、会議やプロジェクトをどう進めていくかが手をとるようにわかる本です。
著者、堀公俊さんのセミナーにもタイミングよく参加出来ました。ファシリテーションを知らずに議論や会議、プロジェクト
などを仕切ろうなんて、いくら何でも無謀すぎです。・・・だから会議時間が長く、結論も出ないのです。社会人なら絶対に
読んでおくべき本。そして一度はファシリテーションの研修に参加すべきです。コーチングとの融和性が高いです。
●「よけいな一言を好かれるセリフに変える 言いかえ図鑑」
タイトル通りの本。人の気分を害するセリフがオンパレードの方っていますよね。気づかないうちに相手の気分を害し、自分
の印象を悪くする一言=よけいな一言を、ちょっと言いかえて、自分の印象を良くする工夫。「要するに何が言いたいの」⇒
「一番言いたいことは何?」、「知りませんでした」⇒「確認不足で申し訳ありません」、「知ってますよ」⇒「先日知りま
した」、「資料の作成は上手だね」⇒「資料の作成も上手だね」、「結局こういうことですか?」⇒「こういう理解でよろし
いでしょうか?」、「その考え方間違ってるよ」⇒「私はこういう考えなんだよね」、「つまらないものですが」⇒「気持ち
ばかりですが」「●●させていただきます」⇒「●●いたします」 ・・・これらの違いがわからない方は、もしかしたら、
相手を見下したセリフ、パワハラになるセリフ、相手を責めるセリフ、言い回しがくどいセリフなどを使っていても、気づい
てもいないでしょうね。そんな方は、解説も載っていますので、即、この本を手に入れて読んだほうが良いでしょうね。とに
かく読みやすいですよ。
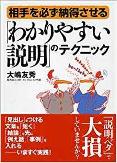


●「勝てる会社の人材戦力」
成果主義を活かし、いかに社員のモチベーションを高めるか。インセンティブ、自己申告、社内FA制度、マイスター制度、社
内公募、メンタリング、キャリアカウンセリング、リファンド(学習補助)、コンピタンシー評価など、今では一般的になった
り、既に廃れたりしている手法を丁寧に解説。
●「勝ち組の人材マネジメント」
人を経営資源と考えるスターバックスはコーチングはもちろん、どのような行動が出来るかというコンピテンシー(行動特性)
に基づく評価制度を採用しています。能力や実績ではなく、実際の行動で評価する。そして社員をコーチ、ファシリテーターと
して育てていく。・・・素晴らしい。実は既に今は無き、かつての勤務先でコンピテンシー評価を採用させていただきました。
コーチング、メンタリングとの併せ技での導入により、皆さん結構やる気になりましたよ。
>>> 目標管理 >>> スターバックス研究
●「相手を必ず納得させる わかりやすい説明のテクニック」
あなたは上司に長々と話をした後にやっと結論を伝えたりはしていませんか? 自分の話し方、身振り、手振り、イントネーシ
ョンをちょっと工夫するだけで、あなたの話はしっかり相手に伝わるようになります。また報告書だって書き方一つで紙くずに
だって、説得資料にだって変わるのです。ケースに合わせた解説が満載。今回読み直してみて「言い淀み・口癖は、まずは自分
にそれがあることを認識しないと直らない」という部分を身近な言い淀む方に教えたくなりました。いつでも手元に持っておき
たい1冊です。
●「上司になったら覚える魔法の言葉」
「大丈夫!」その一言が部下を落ち着かせる。「どうしてはじめようと思ったの。」くじけそうな部下に。「君はどうしたいの」
自信のない部下には・・・。ちょっとした言葉の持つ重みを感じさせる本です。
すごく役立ちますよ。
●「Harverd Bisiness Review いかに高業績チームをつくるか」
編集部編、カッツェンバーグ、マッキンゼーやハーバードビジネススクールなどのそうそうたるメンバーによるチーム論、これ
はある意味教科書ですね。➀「チームはグループとは全く違う。チームは共通の目的、達成すべき目標、目標へのアプローチを
共有し、連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた少人数の集合体。チームに不可欠なスキルは専門スキル、問題解決・意思
決定スキル、コミュニケーションスキル。」・・・まずはこの認識がスタートライン。例えば、リーダーシップはあってもメン
バーとコミュニケーションが出来ないようなお山の大将は、継続的には高業績を残すことは出来ないということでしょう。➁目
に見える組織病「ナットアイランド症候群」=3K職場の優秀で献身的なチームが無能なマネージャーの為に、機能しなくなっ
た失敗例。➂各所に散らばる多様な人材をITで結びつけたバーチャルチームの結束、成果。・・・これやってる人いますよ。
➃通念を見直し学習するチームのリーダーの行動。⑤クロスファンクショナルチームへの権限移譲の必要性。成果重視の評価指
標ではチームはうまく機能しない。・・・成果主義に囚われている組織にとってこれ結構大事ですよ。⑥成功している経営幹部
は皆全て、活気にあふれ、目標達成度が高い集団「ホットグループ」(ちなみに、私は諦めたカマスの水槽に放り込まれた、活
きの良い新たなカマス達と呼んでいますが)の活躍を見たことがあるか、もしくは自分がそのメンバーであったことがある。で
はそのホットグループを生み出し、活躍を継続させるのは誰か。指揮者か、後援者か、熱気維持者か。ホットグループはトリュ
フと同じで栽培が困難であり、整然とした組織はホットグループを窒息させる。・・・これ、理解していない部門TOPの方が
多いのですよね。行動を管理せず、自由にさせるだけで、ダメのレッテルを貼られていた社員がエースにも救世主にもなること
はあるのすけどね。⑦勝つチームの条件、フットボールを例にしたコーチの条件、選手の条件など。⑧職務の多用性は革新には
つながらない(考え方の多用性が重要?)、結束で自由な意見交換を封じるな、高業績への報酬の手法。
・・・・では、この教科書を実際の経営につなげられるのか。少なくとも➂、⑤、⑥の例は通じるところがありますよ。
●「Harverd Bisiness Review いかに問題社員を管理するか」
同上編集部編。ボスザルを成長させる5つのステップ。Cクラス社員対策を妨げている障壁。いかなるマネージャーも社員の性
格は変えられないが、誰にでもあるモチベーションのエネルギーを制止する障壁を取り除く。Bクラス社員の再評価。頭打ちマ
ネージャーの火を消さない。悪癖のある人材の95%は実は有能。心のすきまにつけ入る腹心に注意せよ。部下の言葉ではなく
組織の価値観で判断する。スタープレーヤーの中途採用は悲劇を招く。この本は問題社員の排除ではなく、いかに管理し、活用
するかの教科書。勉強にはなるが、それが実践につなげられるかは、難しい。米国の経営大学院ではこのような講義をたくさん
受けるのでしょうかね。
■ 勉強になった本

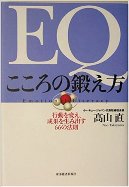

●「なぜ、占い師は信用されるのか?」「ビジネスコールドリーディング」「コミュニケーションの為の催眠誘導」
石井裕之さんのコールドリーディング本3冊。人は操られている。ならば操る側になりたいものです。催眠誘導は人のなんと
なくという意識にうったえるテクニック。そして、交渉上手の方が知らず知らずのうちに使っているテクニックも多いのに気
づかされます。「お茶しに行こうか」ではなく、「コーヒーor紅茶のどっちが飲みたい」そんなコミュニケーションが身に付
きます。
●「パワーマインド 自分を高め交渉に勝つ悪魔の心理術」
細かな行動や演出による自分のイメージ操作からスタートし、自分をしっかりアピールし、自分の意見を通していく為のスキ
ル紹介。世の中にはトランプさんや阿部さんが赤や青のネクタイをしている理由すらわからない方々が大勢いるのです。皆あ
なたの餌食ですよ。(このレビューの時点では阿部さんは存命かつ現役総理でしたので、そのままにしています。)
●「EQリーダーシップ」
ビジネスに成功した者は必ずと言っていいほど他者の感情を理解する能力に優れている。成功者の方々は心の知能指数EQを
活用し、人の心を理解して、人を動かしていくのだという考え方を教えてくれます。またEQはIQとは違って訓練で伸ばせ
るようです。EQに関する基本中の基本の本なのですが、ちょっと難しい本でもあります。
●「EQこころの鍛え方 成功を生み出す66の法則」
EQってわかりにくい本が多いですが、この本は比較的わかりやすいです。EQ能力を高めるためにすべきことは具体的には
掴みきれないのですが、この本とコーチングの入門本を重ね合わせると色々と見えてきます。コーチングを実践することが人
の心の動きを理解することでもあり、逆に、そもそもEQ能力が低い人には、コーチングの活用は無理であり、どちらも密接
に結びついている。両方を平行して学ぶことが、人間関係への応用の近道ではないでしょうか。
●「若者はなぜ3年で辞めるのか」
自らの将来が見通せない。職場の仲間になれていない。自らの存在意義が感じられない。そんな悩み故、多くの新入社員は3
年で会社を辞めてしまいます。では辞めさせないためには真逆の印象を与えればいいのだと私は気づき、将来に向けたキャリ
ア開発をサポートする。職場の大事なメンバー、チームの仲間として扱う、仕事が上手くいったら褒め、上手くいかなくても
ちょっとした進捗や向上を事実としてフィードバックするなどを実行しました。・・・それがコーチングです。
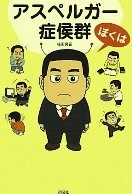

●「ぼくはアスペルガー症候群」
最近ではASD(自閉症スペクトラム)とも言うアスペルガー症候群である著者が語る真実。多くのアスペルガーの方がそうで
あるように著者も子どもの頃から単なる変人と思われてきたが、自分自身がアスペルガーであることに気づきなんとか周囲に適
応しながら生きてきた。皆さんの周りにも必ず何人かいる変人が実はアスペルガーであることにも気づかせてくれます。
周囲のちょっと変わった方、そしてあなた自身の行動のくせが気になる時、もしかしたら、アスペルガー症候群なのかもしれま
せん。そんな方との付き合い方の参考になります。
●「あなたのその気分うつかもしれません」
実例が色々掲載されていてかなりわかりやすい本。心理学者の方が単に理論を紹介する本とは全く違います。病院や治療のこと
はもちろん、治療費や確定申告のことまで書かれています。自分自身の気持ちがすっきりしない方、周囲に心を病んだ方、病み
そうな方がいる方、企業のメンタルへルス担当の方、部下のいる方にとって、とっても役立つ本です。
●「図解雑学ユング心理学」「図解雑学フロイトの精神分析」
ユングが解き明かしたコンプレックスの理屈やうそ発見機の原理、フロイトの夢判断、無意識の行為や言い間違いの理屈など、
心理学の基本を素人にも解るように解説してくれる2冊です。社会人の常識として、一度は読んでおいたほうが良いです。
●「他人の心をつかむ心理テクニック」
コミュニケーションの活性化という切口で色々本を読んだ中で最も読み易く分かり易い本。後になってセクシー心理学等で有名
なゆう先生なのだと分かったのですが、心理学からアプローチした、かなり柔らかめの人との付き合い方強化本といったところ
です。誰でも理解できるし、例として出てくるスキルは周囲とのコミュニケーション強化や部下指導教本として使える本です。
●「しぐさと心理の裏読み辞典」
この手の本は結構多く、しかも中身が頭に残るものは少ないですが、匠先生の本はきっちり頭に残ります。似たようなことが書
かれている前出のゆうきゆう先生の心理本は軽く仕立てて読みやすいのに対し、匠先生はかっちり仕立てて読みやすいです。人
の気持ちを理解することは、人間関係として絶対に避けて通れないところです。この本のおかげで、人の行動の意味がちょっと
ずつ読めるような気がしてきました。
●「好かれる人のしぐさの法則 できる人には言葉以外の何かがある」
しぐさで相手の気持ちがわかる、しぐさで自分の印象を演出できる。本音がばれる。行動パターンは性格を現わす。心理学者渋
谷昌三先生の解説満載。基本を理解出来れば人間関係や仕事に大いに役立ちます。

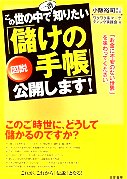
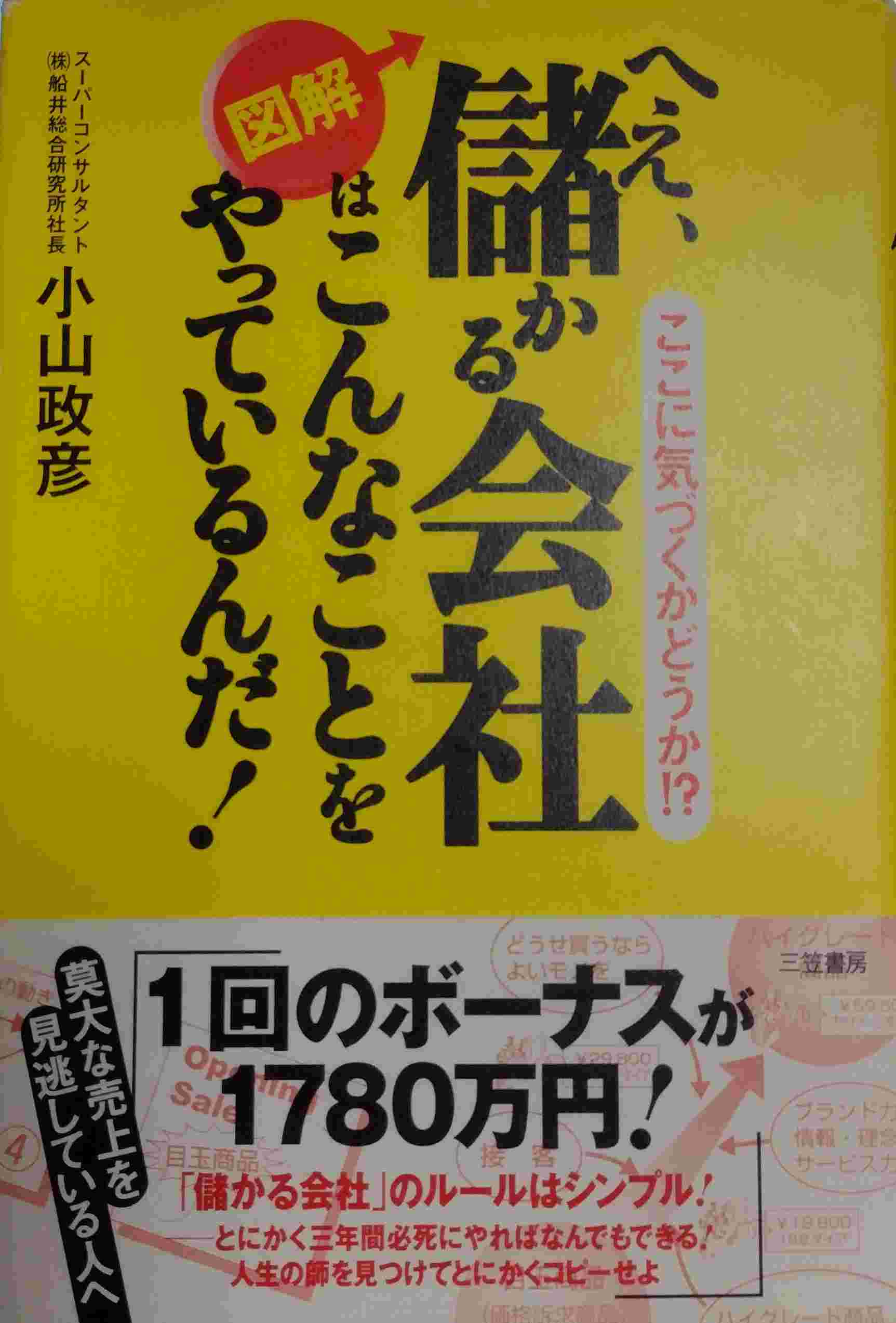

●「スターバックス成功物語」
シアトルのスターバックスに転職したハワードシュルツがいかに困難を乗り越えスターバックスを巨大企業にしたか。社員は経
営の道具ではない。その一言に代表される経営哲学と文化を作ってきた発展の道のりを解説。
●「私でももっと面白いほどわかる決算書」
決算書には危ない会社、伸びている会社を見抜くヒントが満載されています。でも、自分の勤務先の営業利益は知っていても、
純利益が売り上げに対してどれくらいあるのかを知っている会社員ってほとんどいません。営業利益が20%でも、純利益が2
%なら100万円の売り上げに対して2%の値引きをしたら利益がなくなってしまうことを知らないのです。決算書は重要な情
報源ですよ。
●「ソーシャル物理学」
自分一人より、仲間と考える、組織外と情報交換するなど人の交流のネットワークの多様化は発想に明確な変化を及ぼす。そし
て、アイデアの多さ、交流の密度、アイデアの多様性がイノベーションを引き起こす可能性を飛躍的に高めます。アイデアの流
れを生み出す探求ポイントは、①成功した他人の真似をする社会的学習+個人的学習。②情報源を多様化する。③他人と反対の
行動をし、独自の情報源を持っていると思われる賢人を見つけ彼らに学ぶことだ。カリスマ的仲介者とも言えるリーダーはメン
バーの全員に計画的に発言を促し、カフェコーナーや休憩室で色々な立場の者と会話を行い、誰かから得たアイデアを他の誰か
と交換する。問題解決の方策はカフェコーナーや休憩室で見つかる可能性が高い。メンバーの休憩時間を同じにしてコミュニケ
ーションを増やしたコールセンターの生産性が高まったとの事例も。集団知のあり方、発展のさせ方、ソーシャルネットワーク
の効果などを学術的研究により立証した本。ちょっと難しいけど、研究の部分を省けば、そのエッセンスは数ページで全てが語
れる内容にすぎない気がします。良い本ですが、仕事の関係者に奨めるのなら、もっと内容を要約した方がいいですね。
●「トヨタ式改善力 原価2分の1戦略への疾走」
無駄を徹底的に排除するトヨタ式KAIZEN。でも改善が進化すると、無駄は形を変えて現れる。どんぶり勘定ではなくタイ
ムリーかつ正確な数字の管理が原価低減を実現する。間接部門の原価は 低減すべき。など 「無駄とり」をいかに徹底的に行う
のかを解説する本。勉強にはなるけどちょっと難しい。
トヨタ式を導入している建設用レンタル機器会社アクティオさんの整備工場を見学したことがありますが、無駄を削減して少人
数で効率的に運営していたのには結構驚きましたよ。TOPは誰でも「効率化しろ」などと簡単におっしゃいますが。企業の効
率化は、意気込みや取り組み姿勢でなんとかなるものではないと気づかせてくれる本です。闇雲に「無駄を無くせ」なんておっ
しゃる方々は、「無駄とは何か」から学ばないとダメですよね。例えば、「次の工程に待ち時間を作らない。その為に何をする
か。」がトヨタ式の基本です。その考え方を学べる本です。
●「この世の中で一番知りたい「図説 儲けの手帳」公開します。」
これはお客様にお金を使わせるためのマーケッティング論を16の事例から解説。ちょっと前からコンビや商店で独自商品を置
き、ポップで商品の良さを解説したり、入荷時期を説明するのを見かけませんか。きっとこの本を読んだのでしょう。「美味し
いけど入荷が少ない」「美味しいけど高い」なんていう心理学でいう「両面表示」を応用した事例もあり、「売る」よりも「伝
える」に特化し、お客様との関係を築く手法を紹介しています。
●「へえ儲かる会社はこんなことやっているんだ」
創業10年で8割の会社がつぶれる中、儲かる会社は一体なぜ儲かるのか。「通販の売れ筋商品の価格帯」なんて考えたことあり
ますでしょうか。この本は、何故か他社とは違う戦略で設けている会社を分析した書です。「本当は安くないジャパネットたか
たはなぜそんなに人気があるのか」「人が物事に飽きる期間はどれくらいか」=携帯電話のモデルチェンジ消費者の購買心理を
分析し、その情報に対し、「何を知っているか」ではなく、「どう考えるかに」フォーカスしています。「当店のパンは賞味期
限が短いです」という逆説的なキャッチコピーの効用など。分かる人は既に儲けていますよ。どうやって商品を売るかを考えず
に漫然と商売していたら倒産しますよ。確実に。
●「問題解決に効く 行為のデザイン思考法」
プロダクトデザインをそれを利用する人、見る人の行動から考え、改善することを説く本。間違いを招くデザインをバグ、行為
が促進されるデザインをエフェクトという表現で説明。エレベータの開閉ボタンが解り難いに象徴されるデザイナーのバグを退
治、改善する事例を多々紹介。ビジネスマンの発想の転換にも吉と見ました。でも多くのページを割いているワークショップの
くだりは実践的過ぎて、実際のプロダクトデザイナー以外には不要な気もします。
■ 結構面白いし、知識や発想の転換になった本 だけど、仕事の役に立つわけではない。
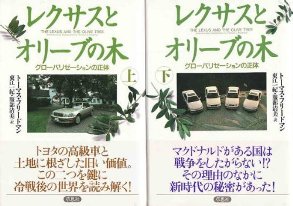

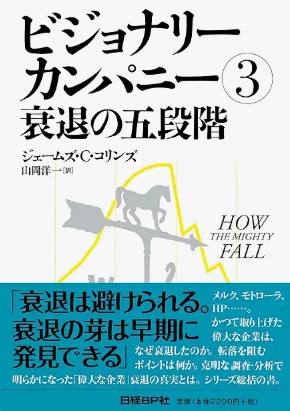
●「レクサスとオリーブの木」「フラット化する世界」
2000年以降、現在のIT化、グローバル化を予測する書が色々書かれました。そしてその予測の一部は当たっています。この
2冊はどちらもニューヨークタイムス記者のフリードマン著。2000年、東西冷戦後の世界。オリーブの木に代表される地域主
義、レクサスに代表されるグローバリゼーション。米国はグローバル化をけん引して世界を支配する。IT企業の急伸を見通
したとも言えますが、自信をなくした今の米国とはかけはなれた予測とも言えます。そして2002年。我々はダウンロードの時
代から自ら持つ情報をアップロードする時代に突入した。世界はインターネットによりその距離を縮めてフラット化し、下請
け業務は既に中国やインド、もしくは米国の片田舎でも行われる時代となった。インターネットは個人にグローバルな競争力
を与え、働き方、ビジネスモデル、国家のシステムさえもが変わりつつある。企業は連合を作り、業務はアウトソーシングさ
れるようになる。うーん確かにその通り。でもその当時としても既に当たり前の予測であり、目新しさはなかったです。そし
て、アメリカの衰退、中国やロシアの台頭による世界経済の不安定化、イスラム国による横暴、アフガンでのタリバン復権、
シリア、ナゴルノカラバフ、スーダン、ウクライナ、パレスチナなど絶え間ないでの紛争や内戦による世界経済の悪化や逆に
軍事産業への恩恵については、全く予測できなかったので、当然触れられていません。
●「ネクスト・ソサエティ」
ITとグローバリゼーションが世界を支配すると2002年にドラッガー先生はおっしゃった。知識に国境はない。万人に教育の
機会があり、万人が知識を手に入れられ、厳しい競争時代がやってくる。企業は雇用規制に対応するため膨大な時間と予算を
消費する。米国の労働組合はグローバル化から身を守るため保護主義化する。企業は成功していないものを体系的に廃棄し、
サービスを継続的に改善しなくては生き残れない。しかし変化は脅威ではなく、チャンスとなる。インターネットの普及を予
期した書ですね。残念ながら出版から20年以上たち、AIの出現や、アメリカ自国主義(アメリカファースト)、また日本
でも日本人ファーストが主張され、一定の賛同が得られる世の中になるとまでは、全く予測できていません。寧ろ未来人を名
乗るジョン・タイター氏の預言の中で、細部は全く異なりますがロシアが強大になるという点のほうが、2025年現在では
リアルです。
●「ビジョナリ―カンパニー」「ビジョナリーカンパニー3」
様々な業界のTOP企業がその業界のそこそこ一流の企業より抜きんでた理由は何か。すなわち、きちんとした理念を持ち、
進化し続けたからであると多くの事例で教えてくれるビジョナリーカンパニーは、努力している企業がどんな活動をしている
のかがわかる面白い本ですが、興味深いのはそこまで。紹介された企業の中には、今は既に消え去っている企業があります。
それでも生き残る企業については前出の後追い「ビジョナリ―カンパニー2」で分析されることになったわけです。
・・・この本は飛ばして最初から「ビジョナリ―カンパニー2」を読みましょう。で、更なる後追い本「ビジョナリーカンパ
ニー3」は読む必要を感じない本ですね。3に書かれていることは、副題である企業の衰退五段階説の解説です。
➀成功が当然との思いからくる傲慢により、最初の成功の要因を見失うこと。➁当初の創造性を忘れ、成功の勢いのまま規模
を拡大すること。➂警戒信号の見誤り。良いデータは強調し、曖昧なデータは根拠もないのに良い方に解釈し、経営陣が活発
な議論をしなくなること。➃一発逆転を狙って大胆だが実績のない戦略、劇的な行動をとること。⑤一発逆転狙いによる失敗
が悪循環して後退し、士気の低下、財務力の衰えに直面し、経営者が望みを捨て、身売りするか、凡庸な企業になるか、消滅
する。バンクオブアメリカやHP、モトローラ、ゼロックス、IBMなど大企業の事例も含めて紹介します。そこで肝心なの
は企業の衰退の予防策。➀段階の予防は「ビジョナリーカンパニー2」で紹介された、「適切な者をバスに乗せ、不適切な者
は降ろし、それからバスの行き先を決める。」つまり、だれを選ぶかを決めてから何をすべきかを決める。➁段階の予防では、
これ私の大好きなストックデールの逆説です。信念を失わないのを大前提に、最も厳しい現実を直視する。➂は規律ある人材
が各人の責任の範囲内で自由に行動する。・・・この辺からよく分からなくなります。➃段階は予防?・・・本当に偉大な組
織は一人のカリスマに頼らず、進歩を促す仕組みを作ることで、何世代にもわたる指導者のもとで反映する。中々ピンとは来
ませんが、衰退を防いだ各社の事例が分かります。読むのは、その事例だけで十分に思いますが。
>>> column08 ビジョナリーカンパニー >>> Column13 ストックデールの逆説(現実を直視する道を選ぶ)
mn
●「ザ・ゴール」、「チェンジ・ザ・ルール」「ザ・キャッシュマシーン」「ザ・ゴール2」「ザ・プロフィット」
「ザ・ゴール」から「ザ・ゴール2」までは一部作者が違うもののシリーズです。「ザ・プロフィット」も非常に似ていて、
どれもストーリー仕立てで企業の問題を解決していきます。「ザ・ゴール」はそもそもエリヤフゴールドラット博士の唱える
TOCと呼ばれる制約理論による生産管理方式の解説書だったのに、読む者を引き込む面白さがあり、本として売れたようで
す。私も引き込まれた1人です。でも自分の仕事に生かせるかと言うと、そんなことはありません。生産方式をきちんと論理
立てて考えるという発想を促してくれる本、程度で考えたほうが良いです。企業コンサルの中身をたかだが3千円もしない本
で種明かしするはずないですからね。
注)TOCとはTheory Of Constraints=制約理論。つながり(依存関係)とばらつき(変動性)がある組織においては、必ずそのアウトプッ
トを決定する制約(ボトルネック)が存在し、制約に集中してマネジメントすることでアウトプットを短期的・飛躍的に向上することが可
能であるという理論。
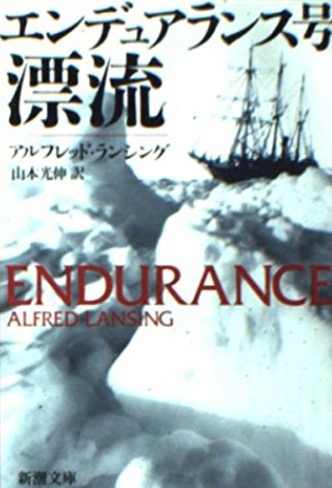

●「V字回復の経営」、「経営パワーの危機」「戦略プロフェッショナル」
倒産寸前の系列企業を立て直してこいと送り出された社員の奮闘を描く物語。ストーリーは全く違うけど、「ザ・ゴール」と
同様にストーリー仕立てで、企業の危機を救っていく内容です。後にミスミの社長となった著者の三枝匡さんは、経営コンサ
ルとして幾つもの企業の再生を指南した方で、V字回復のストーリーはほぼ実体験といううわさもあります。実はミスミの社
長となって1年位の頃に開催された三枝さんの講演会を聴講したのですが、常識に捉われない企業経営の話を伺がって、かな
り発想の転換になりました。とはいえ、この本そのものは「ザ・ゴール」と同じく、自分の仕事に直接は役立たないですよ。
ちなみにこの本は勤務先の研修の際に、事前に読むようにと配付された本です。人事もちょっとセンス悪いな。
●「エンデュアランス号漂流」「そして奇跡は起こった」
エンデュアランスって我慢・忍耐ですよね。名が体を表した船の名前です。1915年に南極沖ウェッデル海で沈没し、つい最近
2022年に発見されたエンデュアランス号を率いた極地探検家シャクルトンの苦難、氷に挟まれて身動きがとれないという極限
状態での行動とリーダーシップ。28名の乗組員と生きて帰るというゴールを決め、そのゴールに向けてどう乗組員を統制し、
17か月を生き延び、いかに全員生還を果たしたたかが客観的かつ克明に記録されています。遭難までの前置きが長いですが、
読み物としては十分面白いですよ。仕事の役に立つ自己啓発本ではありませんが。自己啓発本などあまり書店に並んでいない
時代に感銘を受けた方は、きっと多いのでは。ちなみにこの本はアルフレッド・ランシング著の記録小説ですが、ジェニファ
ー・アームストロング著の「そして奇跡は起こった」という本では、実際何が起きていたのかの解説本となっています。
>>> column212 エンデュアランス号の忍耐

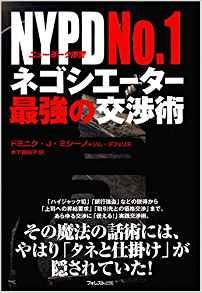
●「イノベーションと起業家精神 その原理と方法(下)」
何故か、企業家精神と訳す本と、起業家精神と訳す本がありますが、原題がアントレプレナー・シップなのだから起業家が正
解だと思います。ものつくり大学の上田先生の訳ですしね。極めて大雑把に言うと企業の改革は今までの常識に捉われていて
はだめで、すべてをぶっ壊して、一から起業するような考え方でなくてはならないと書かれています。起業家精神を発揮する
条件として、変化を脅威でなく機会とみなす。成果を体系的に測定する。組織・人事・報酬について特別の措置を講じる。言
ってはならないタブーを理解する。が上げられていますが、結構難しい内容です。日本の企業がバブル崩壊後の不景気から中
々立ち直れなかった時代に、この起業家精神という言葉がおお流行りし、押し売りのようにドラッカー先生に学べと言う方が
多かったものです。結局は本から学ぶのではなく、失敗を重ねながら理解するしかないようにも思いましたが。
●「なぜ、正しく情報は伝わらないのか 戦争にみる情報学研究」
9.11の攻撃前にCIAが入手していたというアルカイダによるテロの情報が何故活かされなかったのか。戦争の分岐点を
決定した情報の取り扱いに関する詳細な記述が続きます。例えば、パールハーバー。ルーズベルトが情報を握りつぶしたとい
うような解釈もありますが、時代背景や、軍事事情の中で情報がどう扱われ、世界の運命を変えたのかが細かく書かれていて、
読むうちに引きづりこまれました。多少なりとも、戦争に関して興味があれば、一気に読んでしまうでしょう。面白い。その
一言です。しかし、書店では経済書のコーナーにあったので、企業の情報の取り扱いが勝敗を決める的な展開を期待したので
すが、時代のいたずらを解説する印象が強く、企業活性化の参考にはならないでしょう。賛否両論分かれる本かもしれません。
・・・でも、もし、仕事に関する情報が、タイムリーかつ正しい事実(噂などでなく)として、あなたの元に集まらないこと
を気にしているのなら、改善方法はコーチングの方にあると思います。あなたが人に報連相を求めるだけではなく、常に得ら
れた情報に素早く、きちんと対応・フィードバックする人であれば、また、あなた自身が人の話を、遮らず、決めつけずに最
後まできちんと聞くコミュニケーションを行う人であれば、また、あなたが仕事のあらゆる部分に関して、情報の種別に分け
隔てなく、興味のアンテナを立てていることが関係者に知られていれば、おのずと情報はあなたに集まってきます。「そんな
こと知ってますよ」とか、「今、忙しいので後で」「あなたの仕事には興味ない、自分で考えろ」などと言う方には本当に大
事な情報は集まらないのですよね。大事な情報は雑多な情報の中にあり、それを拾いだせるかどうかは各人の興味のアンテナ
の立て方との危機管理能力とに左右されるのですから。
●「NYPD No.1 ネゴシエーター最強の交渉術」
仕事をはじめ色々な人間関係に役立つかと思い、飛びついてしまいました。読み物として結構面白いし、ニューヨーク市警は
こんな交渉術を使っているんだなと理解できる実録本として興味深い内容です。一気に読めます。でも実際の人間関係におけ
る応用という点では難しいですね。せっぱつまった犯罪者と交渉するわけではないですからね。
●「おとなの小論文教室」「あなたの話はなぜ通じないのか」
心の火種を消さない為に自分をうまく表現しよう。「ほぼ日刊イトイ新聞」の連載が本になった「大人の小論文教室」。続編
なのかと思ったら、まさかのコミュニケーションスキルの解説「あなたの話は・・・」。自分の想いを相手に正しく伝える為
の一工夫が目白押し。コミュニケーションのゴールは通じ合うこと。・・・その通りですね。
●「問題な人」
これも心理学者渋谷昌三先生の書。理解できない若者、下品な人、頭にくる上司・部下などイライラさせられる人々に対する
ストレスをどうやって和らげればよいかの指南書。人間関係に疲れた方への処方箋です。読んでいると、うんうんと、うなづ
くことしきりです。うなずいただけでは何も解決はしないのですが。
■ 参考になったけど、しばらくたつと忘れてしまう本
●「部下のやる気を2倍にする法 できる上司のモチベーションマネジメント」
和田秀樹さん他4名の共著。3つの法則「希望の法則」「充実の法則」「関係の法則」を3章に分けて、達成感、充実感、一
体感をいかに持たせて、チームをマネージメントすると良いかが、かなり細かく事例も上げて書かれています。この3つの法
則って、前述「若者はなぜ3年で辞めるのか」にも出てきます。このような本を色々読んでる私には、本によっては、目にし
たことがある内容が多いのですが、この本には、他にはない参考にすべき項目が幾つもあり、また事例による説明も多く、二
重丸の役立ち本でした。メンバーは褒めて使うべきか、鬼となって引っ張っていくべきかは意見が分かれますが、この本には、
心理学的には、実験により、褒めるほうが能力が伸びることが分かっていると記載されています。まあ、説明の中には、この
ような理論、理窟が色々書かれており、「原因解釈」やら「コフート理論」だとか「期待の効用」「平均への回帰(統計論)」
「認知的に不協和」「ピグマリオン効果」とか、それぞれの先生が競い合うかのように難しい理屈を書いて説明してくれてい
るので、私にはへえーと参考になっても、この手の本を読みなれていない方が読んだら、おそらく、難しい理窟が並んでいる
教科書のように思えてしまい、10ページも行かないうちに行き詰ってしまうかもしれません。難しい部分を省いて半分くら
いの内容にするとすごく良いのですが。
●「なぜAさんは好かれてBさんは好かれないのか」
「女の勘はなぜ鋭いのか」「なぜか好かれる女性50のルール」の著者 赤羽建美さんの本。好かれる人と嫌われる人の態度
・行動・ものの言い方はどう違うのか、人からどう見られているのか、好かれるAさんのようになるための24項目の紹介。
すっごく参考になる本ではあるのですが、自分の態度や性格は決して変えられないし、行動も自ら変えるのは非常に難しいで
すよね。・・・コーチでもいなければ。
●「その他大勢を味方につける25の方法」
何故か、その他大勢なんだかんだは本文には全く出てきません。仕事の成功、失敗は人間関係にかかっている。人が自分を知
りたい、関係を築きたいと思えるような人間になる25の法則を、準備、つながり、信頼、投資、相互作用の項目に分けて紹
介。自己中心的にならないためには。問題を起こすボブにどう対処すればよいか。人間関係のスキルのバイブル「カーネギー
の教え」と解りやすいことから、解り難いことまで。米国ではベストセラーになったらしいですが、ちょっと日本人向きでは
ないかもしれませんね。
●「会社で意見が通る人、通らない人」
議論をするな、議論しようのない案を作れ。本命の意見の前に小さな意見を積み重ねろ。交渉を避けたら永遠に意見は通らな
い。挨拶を軽んじる人には味方が出来ない。・・・確かに。なぜ上司は思いつきの指示を出してくるのか。無責任な意見は自
分の首をしめる。などなど結構、面白い解説が続きます、何故か心に残らない非常に残念な本ですね。
●「もうひと押しができない!やさしすぎるひとのための心理術」
軽い、軽すぎる。面白い。面白すぎる。あっと言う間に読めます。ゆうきゆう先生の心のあやつり方の指南本。相手を逃がさ
ない誘い方(ハンドルネーム)。言い間違いで心が見えてくる(ミストウォーカー)。不安な気持ちを一瞬で回復させるには
(エアーズロック)。モテるは才能ではなくテクニック(路地裏のコイン)。交渉も告白も簡単にする左右の心理学(女神の
左手・悪魔の右手)。・・・これかなり大事ですよ。警戒されずに相手を説得するには(B面のメロディ)。自信をつける魔
法の言葉(キャンドゥ・キャンディ)。それぞれのスキルに軽~い愛称がついているんです。やあ軽すぎて読み終わったら忘
れちゃうよなあ。
●「心のサプリ」
こちらもゆうきゆう先生の本。朝読むサプリ、満員電車に乗りたくない。昼読むサプリ、つまらないおしゃべりに嫌気。夕方
読むサプリ、約束をドタキャンされた。そんな気分をちょっとは晴らすサプリが満載。
●「たった一言の心理術」「うつがスーッと晴れる本」
それぞれ大御所 多胡輝さん、斎藤茂太さんの書。「たった一言・・」は、NGワードや役に立つ言葉を色々解説していますが、
全然一言ではないですし、良いことが書いてあるのに、残念ながら非常に読みずらいです。
「うつが・・」は、心がグレー(ブルーでは?)になりそうな時の対処法が網羅されている本ですが、これも目新しさに欠け
ているのですよねえ。
■ うーん。私には役立たないけど、いいこと書いてあるんです。
まずはコーチング、もしくはコミュニケーションに関する残念本たち
●「EQコーチングのスキル」
高度に競争社会となった未来では、高い付加価値をもった組織、個人しか生き残れない。おっと冒頭からドラッカーの引用で
す。その為に企業はコーチングの導入を急ぐ。EQに関する書籍には理屈っぽく解り難いものが多い中で、分かり易い部類の
本です。コーチングがうまく機能しないのは何故か?この辺も的確な説明です。でもEQ的な能力を高めてコーチングを効果
的に行うための答えは、残念ながらこの本からは見い出せません。すごく尻切れトンボなのですよね。本棚の飾りがまた1冊
増えたような気持ちです。
●「カルロスゴ―ン流リーダシップコーチングのスキル」
答えは会社の中にある。メンバーへの期待。考えと行動は完全に一致させる。コンフリクトの場を作り、より良い答えを導き
出す。明確なビジョンを掲げる。それがカルロスゴ―ン流のコーチングとしていますが、それって、コーチングスキルでは全
くないでしょう。この本は、正しくはコーチングスキルをちょっと含むゴ―ン流のリーダーシップの解説本です。ゴーンさん、
今は悪者扱いなのですけどね。強権的なリーダーシップは嫌な思いをする方々を生み出しますし、やはり良くないですね。
●「パワーコーチング」
既存のコーチングは日本人には合わない。部下を説得するのではなく上下のけじめはきちんとつけた上で、自分で動ける部下
にする。コーチングに心理学を応用した手法を細かく解説。部下を褒めたり、動かす為のキラーフレーズ(殺し文句)も沢山
紹介しています。ちょと変わっているけど、コーチングがうまくできない方の実践に効きそうな内容。でも一度普通のコーチ
ングを始めると途中では切り換えられないんですよねえ。だって変でしょ、ある日急に態度が変わったら。
●「ケーススタディに学ぶコーチングに強くなる本 ― 現代の上司の必須のコミュニケーションスキル」
コーチング本を何冊か書いている本間正人さんの本。ケーススタディというくらいですから、企業におけるコーチングシーン
を想定した事例や会話例を中心に紹介。会話部分も結構長くて、入門者には参考になるでしょうね。
●「THE Art of Coaching 仕事上手になるコミュニケーション術」
企業内にいかにコーチングを広めていくかのストーリー。ファシリテーターとしての段取り手法も紹介。読み物として面白
いけど実用的ではないですし、実際の仕事に応用もできません。

●「コミュニケーションを中心とした心に響く教え方 絶妙な教え方の技術」
大学のコミュニケーション学の先生が書いた本書は非常に理屈っぽい部下指導書。有名なジョハリの窓も出てきますが、今更で
すよね。Win-Winの関係作りで上司がやってはいけないこと、ボディーランゲージの使い方、失敗した部下への指導法な
ど部下指導に関する色々な要素が解説されていて、一つ一つがごもっともですという内容ではありますが、コーチングの方がは
るかに解りやすいです。
●「コミュニケーション力が他人の倍つく本 説得力、交渉力、提案力50のヒント」
心を伝える、きちんと聴く、きちんと話す。通常の挨拶に一言加える。心は形にして伝える。敬語の正しい使い方。また、視線
のやりどころ、相槌の工夫や、腹式呼吸まで含めた仕草での伝え方など結構掘り下げた精神論的側面まで入っている立派なコー
チング本です。ちょっとマニアック過ぎるかも。
●「15秒でツカみ90秒でオトすアサーティブ交渉術」
15秒で好感度を与えるスピーチ。90秒で相手の心を動かすトークをする。相手からYESを引き出す交渉術。苦手な相手に
NOという技術。ネタとしては面白いが、実行するのは難しい技が色々紹介されています。一歩間違えると自分の中身の無さを
露呈しちゃいます。
●「伝える力」
池上彰さんのコミュニケーション本。日銀とは何か説明できますか。から始まり、爆笑問題の危機管理、綾小路さんの毒舌。落
語に学ぶ。など、まあ役立ちそうではあっても、実際には全く役立たないことがこ、れでもかと満載され、著者の名前で売ろう
としたしょうもない本という印象を強く受けました。
●「ストレス知らずの対話術」
こちらも有名なコミュニケーション学の先生、齋藤孝さんの本。まず教科書のようで非常に読みにくい。結構役立つことが書い
てあるのですが、ストレスの要因を難しい言葉で解説したりもするので内容も難しいです。学者向けか。という感じで、これも
著者の名前で売ろうという魂胆にしか思えない本です。
●「女のセンスを生かせなくて会社が伸びますか」「女性を活かす会社の法則」
女性活用が当たり前になったのは既に過去のこと。今では男か女かではないのはもちろんのこと、多様な方を能力で判断する時
代です。でも10年数年前はまだまだ斬新でした。「女のセンス・・」男女の違いは能力ではなく、環境の差。女性目線で女性
の活用を実行した著者が、女性の感性、センスを活かすべきと説明。「女性を活かす・・」女性を活用する会社は社員がイキイ
キして業績も良いと。人手不足で女性を活用しなければ企業は生き残れないなどと差別的な考え方がまかり通っていた時代の本
ではありますが、この時代としては、大事な教科書でもありました。
以下は、理窟は理解出来るけど、そんなこと実践できるの、もうひとひねり必要ではと思う残念本。
●「嫌われるやつほど仕事ができる」「上司が鬼とならねば部下は動かず」
それぞれ特定の状況では真理なのですが、どちらも今では流行らない。というより周囲がついてこれないです。チームワークの
阻害要因を作ることを奨励する様な独善的な内容。でも2025年になってもこれを実践している方々が少なからずいるのですよね。
生まれつきなのでしょうけど、コーチングの4つのタイプでいうならコントローラータイプ、俺の言う通りにしろと言う態度の
皆さまです。たいがいは人の意見に耳を貸さない方ですから、大事な情報が本人の耳には入ってこないとか、仕事を超えた努力
はしてくれないという致命的な欠点がありますよ。
●「いいひとをやめれば人生はうまくいく」
午堂登紀雄さん著。電車の広告を見て、読んでみようかと図書館で借りました。まあ無駄な本。何の役にも立ちません。人を気
遣ったり、人に好かれたり、そんなことはやめて、好きなことやって、言いたいことを言えば、自分の能力が発揮されて、周囲
からも実力を認められて、一目おかれて人生うまくいく。・・・そんなはずないでしょ。人は自分の価値観や行動を中々変えら
れないということに気づいていないか、置き忘れた方が書いた本です。そうすれば、いいひとがやめられるのか?・・・その辺
りが薄い薄い。実践は無理でしょ。
●「図解 部下指導 こうすれば人は育つ」
部下の育て方、仕事の処理法、やる気の引き出し方、難しい部下の育て方などを図解を用いて説明。図解がかえって解り難くく
してますよ。部下の課長を鍛える・・なんていいテーマもありますが、教育計画の立て方を図解で説明する必要あるかな。
●「今の3倍仕事が速くなる!時短術の決定版 何故か仕事ができる人の時間術」
一般的な、完璧主義は捨てる、から、決断力を磨くには最悪のパターンを想像する。自分にしかできないことに時間と労力を使
う。など色々書いてありますが、今まで時間の有効活用を気にもしたことがなかった方が読むような初歩的な本です。でも勤務
先で項目をもっと減らして、内容もこれをもっと簡単にしたようなガイドブックが配られましたよ。
●「プロフェッショナルサラリーマン リストラ予備軍から最年少役員に這い上がった男の仕事術」
上司を仕事の仕入れ先と思う。花形部門の行列には並ばない。グループ会社の取引でも値切る。マニュアルをバカにしない。
ライバル社の商品でも案内する。1か月分の給料の10%を封筒に詰めろ(自己投資用に)。など上昇志向を持つ会社員が参考
にすべき仕事術が書かれており、読み物としては結構面白い。半分くらいは実際にやるべきだし、残り半分は思ってもやっちゃ
だめだよというようなことです。
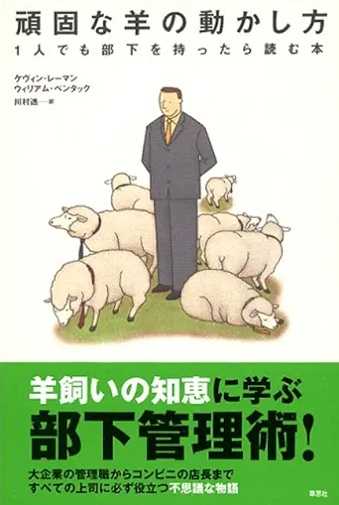
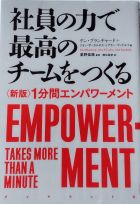


これも何故か小説仕立てのちょっと残念なリーダーシップ・組織改革の指南本5冊、良いこと書いてありますが、決して
目新しいことではないし、ストーリ仕立てなのが回りくどいし、実際の経営や業務の革新には使えないでしょうね。
●「仕事は楽しいかね」
目新しさだけが目についた小説仕立ての自己啓発本の走り。仕事に行き詰る経営者である主人公が、吹雪で足止めされた空港で、
偶然出会った謎の老人マックスに問題解決のヒントを色々と教えてもらう形式で、企業の問題解決手法を解説してくれます。。
「偉人は目標を変えて成功した」「重大な発明は偶然から生まれることが多い」「目標を達成するまで世間は待ってはくれない」
「目標を立てるのではなく、試すことが大事」「試してみることに失敗はない」「明日は今日と違う自分になる」というような言
葉をもらい主人公は色々と試し続ける。・・・物語の主人公出なくても元気づけられる良い言葉が次々出てきます。しかし、現実
の仕事のは全く役に立たないです。薄っぺらい内容ですし。でも、発売当時は本屋に積んであり、飛ぶように売れていました。何
だろうか、サンタクロースの表紙に興味を覚えながらと手に取って、数ページめくると、続きが読みたくなって、買ってしまうの
ですよね。会社帰りに買って帰り、寝る前に読み終われます。・・・帰宅する時間にもよりますが。
ちなみに、AIに「仕事は楽しいかね」と聞いてみたら、以下のような回答が表示されました。
「仕事の楽しさは人それぞれ、目標達成、成長実感、人からの感謝、良好な人間関係などが仕事の楽しさにつながります。仕事が
楽しくないと感じる時には、考え方や行動を変えることで楽しさを見出だすことが可能です」と。おいおい凄いねAI。
う~ん、AIは例の3つの法則(前述)、希望の法則、充実の法則、関係の法則を知っているようですね。
●「頑固な羊の動かし方 1人でも部下を持ったら詠む本」
この本を読んだのを全く忘れていました。このHPのショートコラムを読んでいたら、図書館で借りて読んだ感想が書いてあった
のです。「仕事は楽しいかね」同様、役に立たないので記憶に残らなかったのでしょうね。でも、始めて部下を持つ新任管理職が
行き詰った時には役立つのかもしれません。ということで、ショートコラムからの引用です。・・・2時間あれば楽に読める本。
結構読みやすく面白い本でした。羊飼いが100匹以上の羊を、杖を使いながら面倒を見るのを例に、分かり易く解説しています。
杖は羊を叩くためにあるのではなく、羊を誘導し、境界を教える為にあるのだ。なんて感じです。正に新任管理職、新米リーダー
が読むべき本。と。なるほど。・・・自分のコラムの引用はここまで。
まあ、始めて部下を持ったら、最初の方で紹介した「新米リーダー10のスキル」のような本を読むものだと私は思っていました
が、そんなことを考えもしない方が、新米に関わらず世の中のリーダーの大半を占めているのだと、この25年位の間に気づかさ
れました。それでは、決して、組織をうまくコントロールすることなどできませんよね。大昔、子供のころ、コンバットという戦
争ドラマを毎週見ていましたが、分隊長のサンダース軍曹(ビック・モロー)が、沈着冷静で、何事にも動じず、どんな無理な命
令が小隊長(ヘンリー少尉)から下されてもテキパキと分隊を動かすのに、毎週痺れました。恐らくはサンダース軍曹のような方
は、自分より下位の兵をうまく動かしながら昇進して軍曹になったのでしょうけど、現実の企業の中では、専門能力が評価されて
管理職になるケースも多いように思います。そのような方は自分の専門外である「部下をコントロールする」にはどう行動すれば
良いのかと、もっともっと興味を持って欲しいのですけど。まずは部下の行動に関心を持つこと。それがスタートラインですかね。
>>> Column221「頑固な羊」
●「社員の力で最高のチームを作る 新版1分間エンパワーメント」
「ザ・ビジョン」のケン・ブランチャード他共著。星野リゾート星野代表が監訳。旧版「1分間エンパワーメント」を参考に単な
る温泉旅館の社員たちのモチベーションを大きく引き上げ、今の星野リゾートを作り上げたとおっしゃる星野代表が翻訳を見直し
たエンパワーメント術解説本。初期の急成長中に星野代表は、この改革についてこれない者は、たとえ支配人だって辞めてもらう
と「プロフェッショナル仕事の流儀」だったかの20年くらい前のTVの取材で語っていたのを覚えてますが、それだけの強引さ
と行動力があり、背水の陣をひいて成功を掴んだオーナー経営者だけが、後になってから、参考になったと言える理論に思えます。
もちろん、良いことが書いてあります。➀正確な情報を社員全員と共有し、階層別思考を廃し、社員全員に経営者意識を持たせる。
➁説得力のあるビジョンを設定し、社員が自分の目標と役割を理解できるようにし、行動の根底にある価値観を明確にした上で、
行動の自由を与える。➂全員がチームスキルを学び、チームに自立を促し、コントロールをチームに任す。・・・参考にはなりま
すが、社員の価値観はそれぞれです、自分の仕事はきちんと行うがそれ以上は希望しないという価値観の方は、星野代表が語った
ように退場となり、普通の企業であれば、社員はほとんど残らないでしょう。つまり最初に最大の難関があるわけです。
組織のメンバーが持っている知識、経験、モチベーションを解放し、成果を上げるというエンパワーメント手法は、成功した企業
だけが、同様のエンゲージメント、起業家精神、オーナーシップなど、言葉は色々ありますが、自社にはそれがあると言いきれる
のではないでしょうか。既にある程度の規模があり、一定の顧客がある企業では、社員それぞれの価値観を無視した改革は不可能
と理解したほうが良さそうです。もちろん、有名な言葉「会社は誰のためにあるのか」という思考を無視し、オーナーシップ制度
や、社員全員持ち株制度がある企業を、メンバーを一から募って、立ち上げるのであれば話は別です。
●「1分間セルフリーダーシップ 自らを成功へ導く3つの原則」
これもケン・ブランチャードの1分間シリーズの1冊。ストーリーが結構回りくどいですね。話の筋は、思いこみの枠に挑戦し、
力のポイントを活用して、成功に向けて協力し合うということのようですが、「力のポイントの活用」の項では、ハーレー乗りが、
力を感じるからバイクに乗るのが好きだと言ったことで、力の定義や、職場での力を感じるかなどの話しに展開していくのですが、
力の事例がオートバイの部品番号を覚えることだったり、ハーレーショップに行くまでのくだりがダラダラあるなど、寧ろ小説を
読みながら途中で脱線して、自己啓発をするというようなイメージです。
力のポイントとは「地位の力」「仕事の力」「関係の力」「知識の力」のことで、自分の強みを知ることから始める。また成長に
は4段階あり、➀低い技能かつ高い意欲、➁低~中の技能かつ低い意欲、➂中~高の技能かつ変化する意欲、➃高い技能かつ高い
意欲 としているのですが、何だか途中で意欲が下がっていたりもしていて、まあ自分の今のレベルを自己診断してから考えろと
いうことなのでしょうけど、そもそもストーリ仕立て、かつストーリーの間に解説が出てくるので、流れが悪く、どうしても飛ば
し読みしたくなるので、話の繫がりや意味が、読み進むうちに分からなくなります。そもそも3つの原則ってなんだっけ、という
後味が悪い読後感です。これが、何故か小説仕立ての自己啓発本が多いアメリカらしさなのでしょうかね。まじめな自己啓発書と
して読もうとしていたので、何だか残念です。小説仕立てだと、仮に良いことが書いてあっても、教本やバイブル的に傍に置いて
おくには不向きですしね。あと、思いこみの例として、名刺に穴をあけてその穴に頭を通せるかという発想の転換くらいが頭に残
ったことです。ちなみに私がAIに聞いたの回答は「出来ません」でした。AIも思いこみがあるのでしょうかね。蚊取り線香の
渦巻のように切れば良いだけなのですが。
●「大きな結果をもたらす小さな習慣 周りが思わずあなたに力を貸したくなる」
いくら小説仕立てとはいえ、主人公はのっけから、友人に旦那を取られて、旦那がある朝、突然理由も言わずに家を出ていくとこ
ろから話しがはじまります。おいおい、やりすぎ。内容としては「常に周囲の人に親切にしていれば、いつか自分に返ってくる」
的な内容。この後、業績の低下した主人公は約束されていた昇進をふいにしたのだが、思うに、ストーリーの背景には、社員は会
社に教育されるのではなく、自から技能だけでなく、組織の運営手法を学ぶことで、能力を発揮し、自らの努力で出世を掴むとい
う考え方があるようです。この本の主人公は人事部のスーパーバイザーですが、ストーリー仕立ての自己啓発本の中には悩んでい
るのが経営者であり、しかもMBA(経営大学院=経営修士)卒であることも多いです。つまりは経営を学問として学んだ方が、
従来の経営手法だけでは上手く経営できないことに対し、新たな発想や経営手法伝授する的なイメージなのでしょうかね。・・で、
主人公は心理学者ドクターアレンにアドバイスを受け、➀感情を抑えて相手の話をきちんと聞いて味方にする。➁特別な努力をし
てもらう方を選んで、褒めるだけでなく感動させ、自分の支持部隊を作る。➂自分を貶めようとする同僚(ライバル)を許す。ナ
ンバー・ツー(自分がナンバーワン)の世話をすることを通じて周囲の方々を気遣う。などで加速?させ続ける。この後はつまら
ないサクセスストーリー。いらんな。

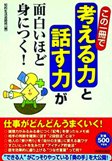

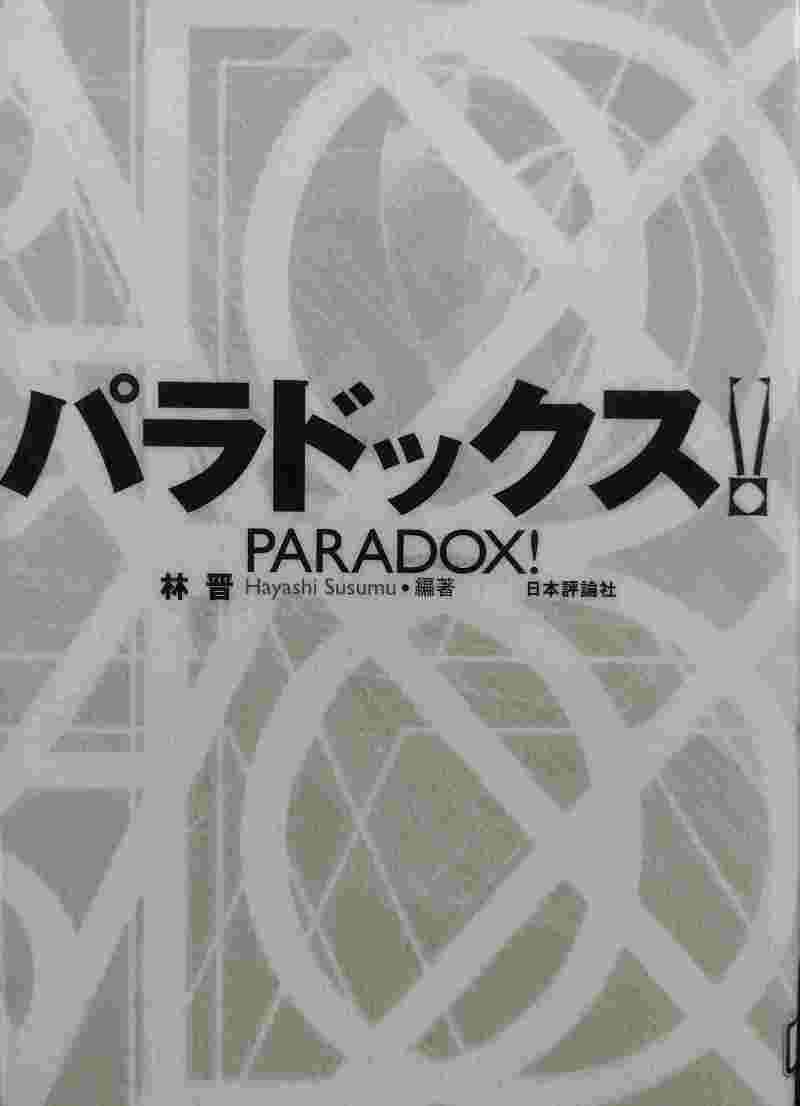
●「人を育てる100の鉄則」
注意は一時にひとつ。報告をしつけよ。人を長所から見よ。応援して自信を与えよ。出来ませんは厳禁、要求水準を高くせよ。
など、かなり上から目線の100の法則。解説も結構詳しいし、良い部分もあるけど、今時どうかなという部分が多いですねす。
●「段取り力 うまくいく人はここが違う」
齋藤孝さんの本。トヨタ流の段取り。イメージトレーニング。列車ダイヤ。アポロ13号。キシリトールガムの出来るまで。な
ど結構面白い切り口で段取りを語ります。段取りの指南本というよりは発想の転換を図る本。体裁がちょっと読みにくいです。
当然、1週間位しか、記憶には残りません。
●「判断力の磨き方 常に冷静かつ客観的な選択をする技術」
和田秀樹さんの本。完璧主義、二分割思考。自動思考。スキーマ。属人主義。集団心理。など心理学的考察で判断ミスの原因を
解説します。また企業の失敗の事例も多々紹介。読み物としては面白いですが、心理学的アプローチの自己啓発本では定番のこ
とばかりで、目新しさは皆無です。心理学本を読んだことが無い方には新鮮で良いと思います。たぶん。
●「突破力 仕事の壁はこうして破れ」
堀紘一さんの本。仕事、人間関係、キャリア、人生における身近な色々な壁を取り上げ、その壁を破る方法を語っているのです
が、他の本でよく見かける内容の寄せ集めになってり、誰に読ませたいのか、焦点がぼけていて、若干判り難い内容です。
●「この一冊で、考える力と、話す力が面白いほど身につく!」
ミスしても相手に良い印象を与える怒られ方。やり手アイデアマンの発想法が身につく魔法の習慣、あがり症の人もたちまちス
ピーチ上手になる映像暗記法。など裏技満載。役立つことも色々書いてありますが、この本も内容がちょっとあっちこっち跳び
すぎてるかな。
●「ブルーオーシャン戦略 競争の無い世界を創造する」
読んだことも忘れていました。2005年の発売後、市場の新しい考え方としてかなり流行りましたが、我が本棚にはないので
図書館で借りたのでしょうね。企業戦略に興味がある方なら、当時読んでいないとそれだけで変な人でした。ほとんどの業界で
は技術もノウハウも一般化し、どんな新しい技術やサービスであっても熾烈な競争、消耗戦にさらされる。そんな状態から抜け
出し、誰にも真似できない技術・サービスを提供する新たな市場(ブルーオーシャン)を生み出し、唯一の企業になるべきであ
る。そんなこと誰もが想像する夢ですよね。ある意味ベンチャー企業になれと勧める書。多くの実例を紹介していますが、一例
として上げられた日本のNTTドコモですらも、ライバルとの競争に晒されています。ブルーオーシャン市場への移行方法を示
した続本「ブルーオーシャンシフト」が12年後の2017年に出ているようです。ちなみにライバルが多い市場をレッドオー
シャン市場と言うそうです。
●「パラドックス」
著者の林晋さんは、何故、パラドックスなのかが理解できないとモゾモゾする。このモゾモゾ感を無視すると本当に根源的なも
のを見落とすことがある。パラドックスは常識や信念に現実が仕掛けた反乱であり、客観的に見える科学・学問でも、その背景
には多くの暗黙の了解、つまり未だに言葉になっていない「思考の枠組み」のようなものがある。と。既に難しい。
ということで、「クレタ人は皆、噓つきだ」とクレタ人が言ったとしたら、クレタ人は嘘つきではないという「うそつきパラド
ックス」などに始まって、大量の事例でパラドックスとは何かを各界の方々が解説してくれます。相当に理屈っぽいですよこの
本。「アキレスは亀を追い抜けないのか」「抜き打ちテストのパラドックス」「シュレディンガーの猫」「バッハ・タルスキの
パラドックス」「ドラえもんのパラドックス」??。後述、宇宙学者である松尾先生は宇宙旅行における「双子のパラドックス
(一般相対論)を数式まで持ち出して解説。タイムトラベルに関する理論、有名な「親殺しのパラドックス」などなど、理解に
は苦しむというか、全く理解できない内容も盛り沢山で、この本を読むと、寧ろモゾモゾすることうけあいです。
でも、聞いたことがあるものも多いので、ちょっと知識としてかじっておく程度で読むなら、普段いい加減に使っているパラド
ックスとは何か知ったような気になれて、実は面白い本です。

●「コア・コンピタンス経営 未来への競争戦略」
コア・コンピタンス。一時期結構流行った言葉です。これからは業界の変革が起きる。未来の競争の為に、過去の成功は忘れ、
今、戦略を立てるべき。ストレッチ戦略、レバレッジ戦略などを紹介しながら、客の価値を高めるコア・コンピタンス(他社に
は真似できない技術、スキル)に経営資源を集中せよ。当時としては斬新な考えですが、その後の現実では、寧ろコアコンピタ
ンスである本業を捨てて、富士フィルムのように事業の目的からして再構築した企業が生き残っているように思います。
●「ノードストロームウェイ 絶対にノーと言わない百貨店」
顧客が望めば、よそで買ってでも商品を提供する。個人の創造性は自由の産物であり、従業員に対し、顧客がハッピーになるな
ら法律違反にならなければ何をしてもよい自由が与えられている。命令への服従ではなく業績で評価される。そもそもルールが
少なく、ルールをやぶる恐れはない。などノードストロームの経営方針をわざわざ一冊の本としてます。
>>> Column07 ノードストロームの権限委譲
●「千円札は拾うな」
落ちている千円札に目を奪われているようでは成功はおぼつかない。タイトルがインパクトを与えたものの、それ以上の中身は
ない本。3年後の100億の為に今の40億を捨てる。大成する男はお金と時間の使い方が違う。などお金は貯めるものではな
く、効果的に使うものという思想が根底に見られます。既存の価値観を変えるにはよいかも。
>>> Column169 千円札は拾うな、って何故?
●「99.9%は仮説」
○○に違いない。皆そう思ってる。それってほぼ想像です。世の中のほとんどの発言は決めつけと仮説に支配されている。例え
ば皆って一体、何人中何人のことかときちんと考えること。仮説に頼る危険、探求の必要性を訴える書。
>>> Column222 99.9%
●「図解、わかるナレッジマネジメント」
今では一般化したナレッジマネジメントの基本と実例を丁寧に解説。暗黙知をどのように見つけるか、いかに社員の共通の知見
として企業に残すかのノウハウ集。
●「グループ連結経営」
象にダイヤ磨けない。だからこそグループ制の経営には意味がある。多くの実例を元にグループ経営のノウハウを解説。ソニー
のカンパニー制、コマツの人材流動化、社内ベンチャー、フリーキャッシュフローによる企業評価などを解説。
●「業績倍々ゲームの会社を作る 算数とハートの経営」
機械レンタル会社アクティオの創業者小沼光雄さんの本。時代のニーズを的確に理解し、危機をチャンスに変えながら、急速に
成長し続ける企業経営者の哲学の紹介。実は小沼さんご本人からいただきました。
■ 国際政治とインテリジェンスの第一人者佐藤優さん他の本。自己啓発のジャンルに入れるのは変かもしれないけど、
色々読んだ中で自己啓発にもなるものは取りあえず、ご紹介します。かつてロシア通の外交官であり、鈴木宗男氏と
ともに逮捕(嵌められた?)佐藤さんの他の本や東京新聞の執筆記事などは色々読んでますが、今の複雑な世界情勢
の中でどう行動すれば日本が生き残れるのかを、深層を理解し、的を射た解説で教えてくれる内容が多いです。
もっともっとマニアックな池上彰さんという感じで、はまります。
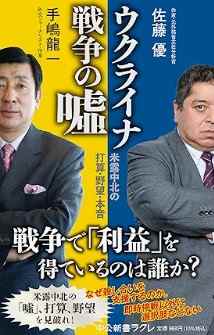

●「人に強くなる極意」
世界はびびらせることで成り立っている。時代の変化の中で生き延びていく為に、「怒らない」「びびらない」「飾らない」
「侮らない」「断わらない」「お金に振り回されない」「あきらめない」「先送りしない」という8つのテーマで解説。
自分は何にびびっているのかを知る。自分を大きく見せたいという意識を利用する。シンプルさを追求すると人間関係も楽に
なる。事務作業のイージーミスほど致命的。借金の仕方ひとつで人生を棒に振る。佐藤氏ならではの知見が面白い。例えば、
経理・庶務・人事において、例えば経費削減の貼り紙が急に増えたなど、突然社内の流れが変わった変化には、会社の危機が
隠されてこともあるので要注意、潮目の変化に注意せよと。そうそう「怒らない」の項に平気でうそをつく相手には大声で怒
鳴れとありますが、実践しています。
●「ズルさのすすめ いまを生き抜く極意」
大切なのはいかに負けるか。生き残る人の上手な逃げ方。・・人と比べない。問題から目をそむけない。酒に飲まれない。失
言しない。恩をあだで返さない。嫌われることを恐れない。約束を超えた信頼関係を築く。人を見た眼で判断しない。などな
どこれも元外交官佐藤氏ならではのすごみのある解説が読めます。
●「日本でテロが起きる日」
佐藤優さん著。昨今の世界的なテロ多発は決して他人事ではない。その背景、日本が狙われないわけがない事情の解説。何で
我々は他人事のようにニュースを見ているのでしょうね。ちょっと怖いですよ。人が多い所にいくのに身構えちゃいます。
●「知性とは何か」
2015年佐藤優さん著。日本には反知性主義が蔓延している。実証性や客観性を軽視する反知性主義は自分が欲する方向で
世界を理解しようとする。つまり、元々何が正しいかどうかが解りづらい国内情勢、世界情勢の中で、我が国をはじめ各国の
指導者たちは、政治力、時には武力を背景に自分がやりたいようにやりはじめている。沖縄問題に対する阿部政権に対する警
鐘の書です。確かに当時の麻生副総理のナチスに学べ発言は最たるものですね。
以下、2025年の私の補足ですが、今や、「反知性主義」の概念は巾広く、かつ難しく、権力と知的エリート(つまり特権
階級)との結びつきを非難・否定するという本来の解釈ではなく、逆説的側面である大衆の知性を肯定するという部分を拡大
解釈し、ポピュリズム的に大衆受けする政策・行動、例えばアメリカファースト、移民や外国人の否定で票を集める政治家の
活動も指しており、民主主義への悪影響や社会の分断にもつながりかねない動きが見られています。このような社会では現に
起きている陰謀論の流布、フェイクニュースの拡散などの情報操作により、真実と嘘の区別がつかない手段での指示集めも起
きがちであり、特に情報化が進んだ昨今その傾向が強く、我々市民には真実を自分自身の知見で見極める為の知識が必要です。
●「ウクライナ戦争の嘘 米露中北の打算・野望・本音」 解説長過ぎですが、今こそ知っておきたい内容
日本のインテリジェンス(安全保障情報の分析、諜報)の大家のお二人、佐藤優さん、手島龍一さん共著。この2人の共著に
は「賢者の戦略 生き残るためのインテリジェンス」「知の武装 救国のインテリジェンス」「動乱のインテリジェンス」など
がありますが、どの本も、世界情勢をどう読み解くか、IS、ウクライナ危機(ポロシェンコ政権時代の)、反知性主義、新
帝国主義(中露)、尖閣、プーチン、イラン、北朝鮮など、ここ10数年の日本を、そして世界を取り巻く情勢の深層を深読
みし、如何に日本が、そして我々日本人が生き残るべきかを考えさせられる本でした。そして「ウクライナ戦争の嘘」では、
2022年のロシアに侵攻されたウクライナについて、何故、言語道断の武力侵攻が起きたのか、戦争により得をしているの
は誰か、この戦争にはどんな虚実・真実があるのか、世界は核戦争を避けることができるのかなど、著者二人の対話形式で探
っていきます。どの本も読みながら、その内容に引き込まれます。私がこの手の本に興味を持つのは、日本の、世界の行く末、
ひいては我々の社会や経済の情勢を占う書でもあり、「インテリジェンス」の名の通り、見聞きする情報を、背景も理解した
上でいかに解釈するのかというヒントを得られる書のように思うからです。
2014年にロシアは何故クリミア、セバストポリを併合したのか、2022年に何故ウクライナに侵攻したのか、もう少し
解説すると、クリミアは帝政ロシアのエカテリーナ2世の頃からロシア貴族の保養地であり、セバストポリは地中海に出るた
めの要衛であり、またウクライナ自体もは旧ソ連の武器廠であったことによりロシアにとっては元々自国領意識が強いこと。
では何故、東部のルハンスク州、ドネツク州の割譲に何故プーチンがこだわるのか。どちらにもロシア系住民が多いこと。そ
もそもは、ウクライナには古都リヴィウを中心とする西部の反ロシア民族主義地域ガリツィア(ナチス親衛隊ガリツィア師団
を生んだあの地域)と親ロシア住民が多い東部のルハンス州、ドネツク州などのノバロシア地域、中央の反ロシア、親ロシア
が混在する地域があり、東西では宗教はもちろん文化が異なること。ウクライナが親ロシアのヤヌコヴィッチ大統領を見限っ
た2014年のマイダン革命後にどんどん右傾化していたこと。ロシアから見れば、西側諸国が自分達が東西冷戦の勝者にな
った気になり、ついには越えてはいけない最後の一線であるバルト三国をNATO化したこと。ウクライナには正規軍、内務
省軍、アゾフ大隊のような民兵組織の3つがあり、何れもゼレンスキー大統領の意のままには動かず、東部地域では親ロシア
武装勢力と反ロシア民族主義勢力の小競り合いが続く中で、ウクライナ軍が親ロシア武装勢力側をドローンで本格的に攻撃し
たことがプーチンに侵攻を決意させたこと。親ロシア住民にロシア国籍を認め、彼らを守るという名目でロシアが旧ソ連の国
に侵攻するのは、ジョージアの南オセチア地方でも行われており、ロシアの常とう手段であるのに、また、冷静に観察すれば、
ウクライナおよび西側はプーチンの尾を踏んでいることに気づいたはずであるのに、ウクライナも西側も警戒を緩めており、
2022年2月の侵攻前に、バイデンはその兆候を掴み、あろうことか公表(情報源がばれる)し、しかも侵攻すれば経済制
裁をする(つまり軍事介入はしない)と公言し、プーチンを勢いずかせてしまったこと。(わざとかも)バイデンは戦争には
参加せず、武器の提供だけで、ロシアの勢力を削ぎたかった。またそもそもバイデン政権はネオコン(軍産複合体)であるケ
ーガン一族のビクトリア・ヌーランドを国防次官としたずぶずぶのネオコン政権であり、在庫兵器を売りつけ国内の兵器を在
庫処分し更新する思惑もあったこと。バイデンはウクライナに核の放棄と引き換えに勝手にNATO加盟を約束したこと(本
来は加盟国全ての合意が必要かつ紛争を抱えている国は加盟できない)。プーチンは脅しではなく、核使用に踏み切る覚悟が
あること。などなど、「ウクライナ戦争の嘘」に書かれた分析は、TVでも新聞でも背景までは報道はされませんが、客観的
な事実ばかりです。・・・どちらか一方は悪、一方は正義という考え方で相手の立場を顧りみないのであれば、実際に核戦争
が起きる可能性が高い。さあどうする。そんな内容です。ちなみに第二次トランプ政権になる前の出版です。
●「新軍事学入門」
小峰隆生さん編集。小峯さんがインタビューで飯柴智亮, 佐藤優, 内山進, 北村淳, 佐藤正久ら名だたる方々に世界の軍事事
情に関する教えを請う形式で、日本の置かれた状況を明らかにしていく書。読むと夢も希望もなくなりますが、日本の置かれ
た政治、国民性などの制約の中で出来ることは何かと教えてくれています。佐藤優さんお勧めの本。ちなみに飯柴さんは米国
に渡り、米軍82空挺師団の将校として、アフガンにも従軍した経験がある軍事コンサルタントで、その界隈?では超有名人
なのですでが、自衛隊に当時は禁輸品だが、米国内では購入可能な軍用品(暗視スコープ)を提供し、FBIに逮捕され、軍
籍を失った方です。
●「グローバルジハード」
松本義弘さん著。これも佐藤優さんが解りやすいとして勧める書。世界情勢把握の為の鍵となるイスラム過激派の動向を知る
為の書。アルカイダは本部が倒産しても活動が継続されるフランチャイズのようなもの。組織ではなくグローバルな反乱。身
の回りの者が感化されることが危険。今後の世界的なテロ活動がどうなるかが予測できる本。日本人にとっても他人事ではあ
りませんよ。
●「地政学で考える日本の未来 ― 中国の覇権戦略に立ち向かう」
櫻井よしこさんが、虎視眈々と領土拡大を狙う中国の企みを解説します。そもそもルールや正義を重んじる日本人は、裏切り
や嘘・ねつ造を賢い知恵と考える中国人の怖さを全く理解出来ていないと櫻井さんは考えています。
チベットそしてウイグルを自国領と主張して、援助、解放と嘘をつき、結果乗っ取ってしまい、チベット人、ウイグル人の人
権はおろか、言葉も生活も、そして命までもを奪った中国の次なる野望は、台湾を、南シナ海を、尖閣諸島を、そして沖縄ま
でもを奪うことであると。また中国は尖閣に資源があるからという理由だけで狙っているのでは決してありません。中国はし
っかり計画を立て、長い時間をかけて大きな野望を実行しつつあるのです。地政学から考えると、南シナ海、尖閣(東シナ海)
を押えることは台湾を封じ込めるとともに、小笠原、サイパン、グアム、パラオ、ニューギニアとつながるいわゆる第2列島
線に進出し、太平洋に勢力を伸ばす礎となります。それに対して日本政府は一体何をやっているのか。この本を読むと、日本
の将来は極めて暗澹たるものだと確信します。国際情勢に不安があるとか、心配だというレベルなどではないのです。普段、
朝日新聞を国賊と非難している櫻井さんは、沖縄地元紙が「沖縄県民は日本は友人だが、中国は親戚と考えている。また75
%の沖縄県民が日本からの独立を望んでいる。」と偏向的な報道を行い、民意を曲げて伝えていることを非難し、中国大使で
あった丹羽氏が大使時代に日本は中国の属国となっても良いという意味合いの発言(※やくみつるも同様の発言をしています)
をしたこと、そしてそんな人物に中国外交を委ねるようなレベルの政府であることに大きな危機感が感じられるとしています。
我々はどうすればいいのかと切実に考えさせられる本です。
ちなみに、日本国内に居住・就業する中国人が増えれば、ロシアがジョージアやウクライナにしたように、国民の保護という
名目での武力行使が起きかねません。だいたい米国内に秘密裏に警察署を設置するような国ですからね。中国に口実を与える
ようなことは決して避けなければならないのです。と皆さんそろそろ気づいた方が良いのでは。別に桜井さんのファンではな
くても冷静に考えればそうなります。
■ OPEN AI社がChatGPTを世に出す数年前に、AIやメタバースの将来性に興味を持った私が読んだ本
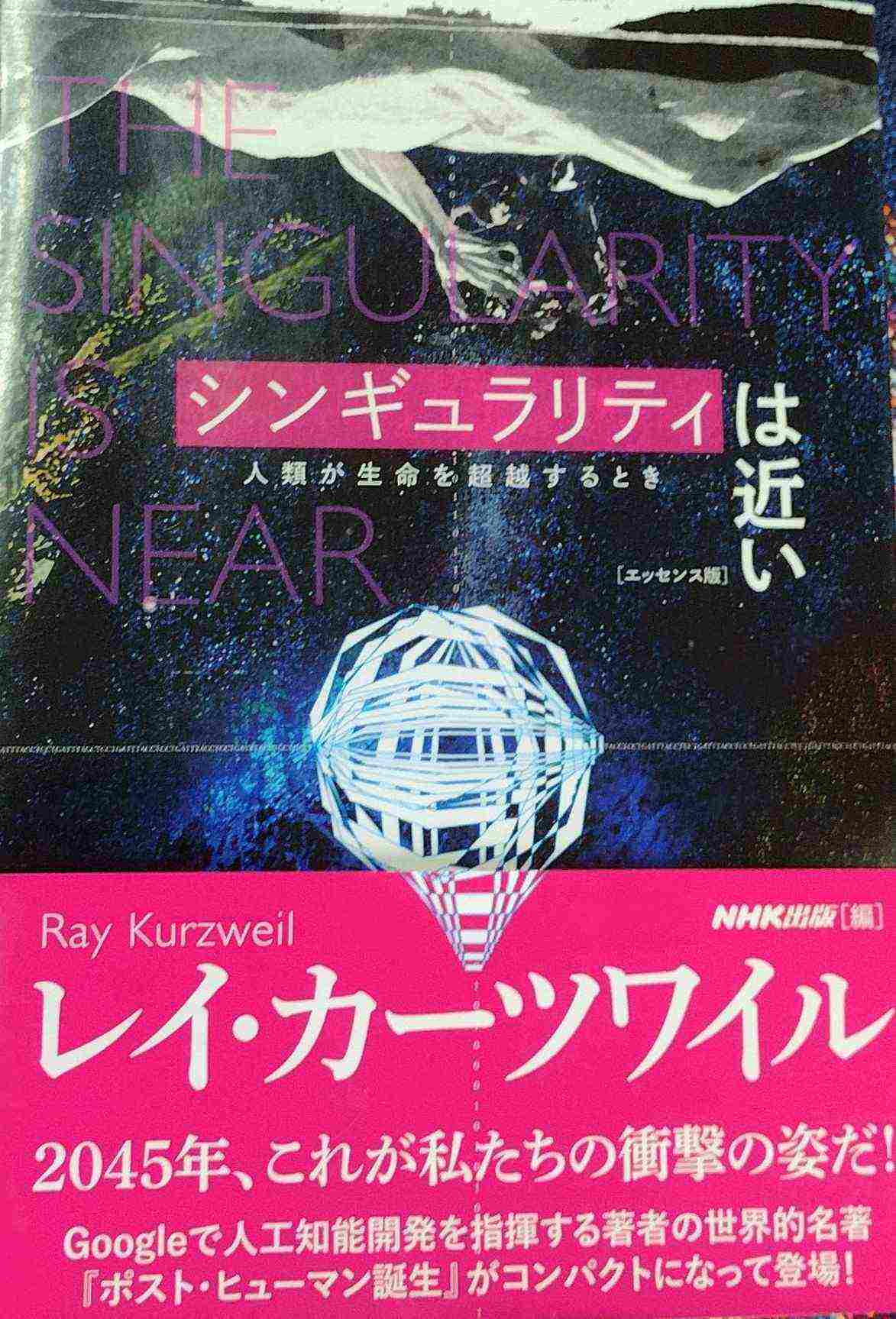
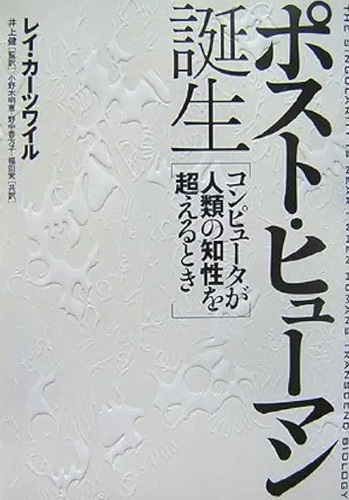
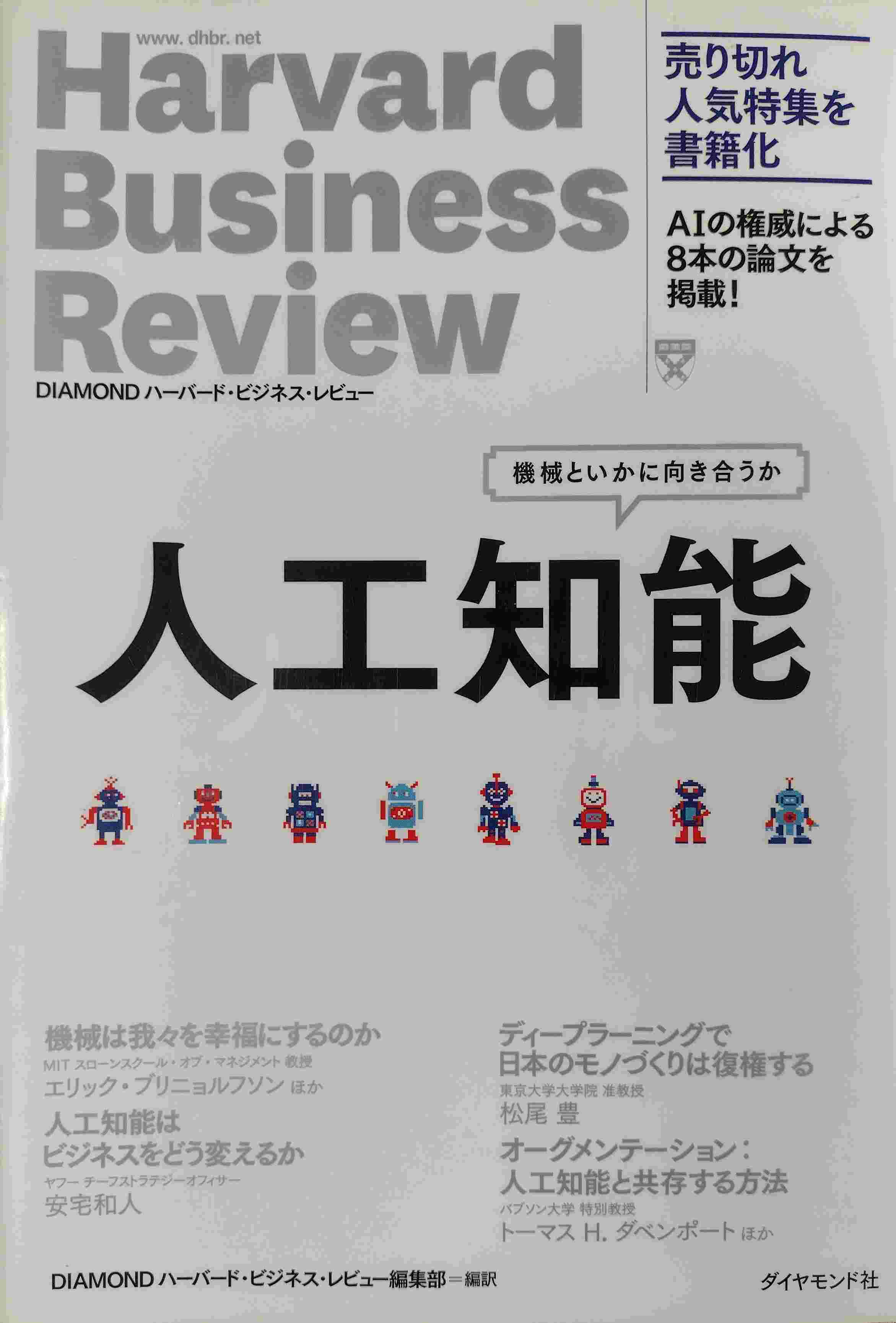
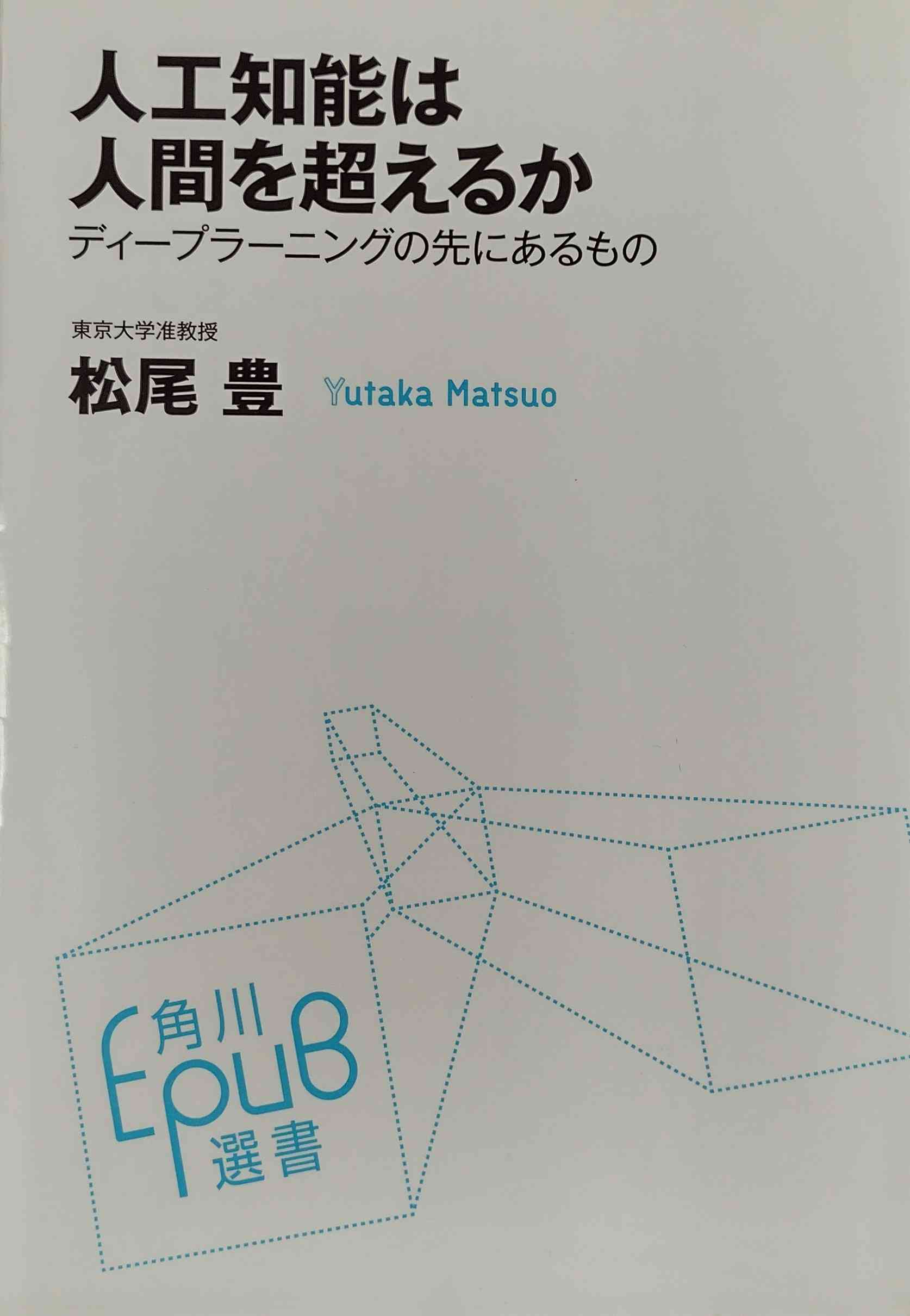
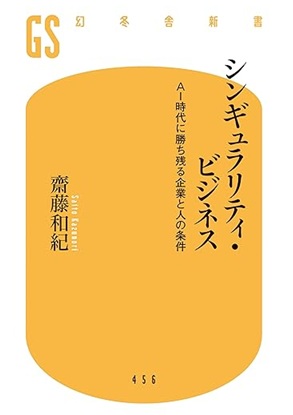
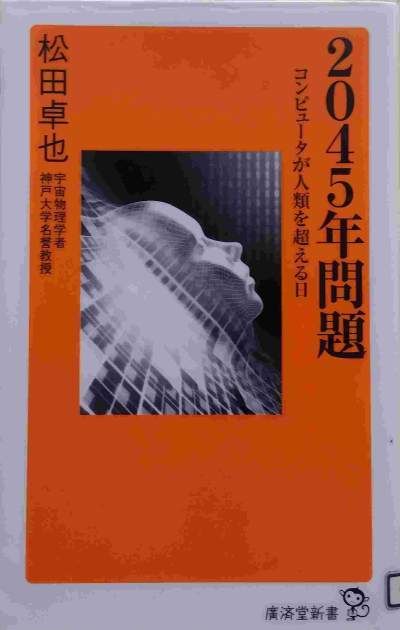
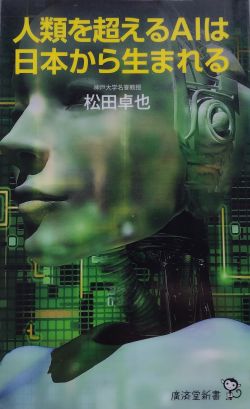
●「シンギュラリティ 人類が生命を超越するとき は近い」
シンギュラリティのバイブルとも言える書、これを読まずにAIやシンギュラリティを語るな。神戸大学の松田卓也教授の
講演で私も知ったレイ・カーツワイル博士は2030年代には機械への精神転送(マインドアップロード)が可能となり、
2045年には1000ドルのコンピュータが人類すべての知能を合わせたより知的になると予測しました。これはSFの
夢物語などではなく、ちょっと先の我々の未来予測です。我々はAIとどう向き合っていくのか、なんて考えていたらある
日突然、身近なAI、ChatGPTが世に出ましたね。ちなみに、AIの教育手段として、ディープラーニング(深層学習)
以外の手法も、決定木、SVM、ロジスティック回帰など色々出てきているようで、確実にAI技術は進化しています。
●「ポスト・ヒューマン誕生、コンピュータが人間の知性を超える時」
レイ・カーツワイル博士の書。シンギュラリティの先にあるのは、我々ホモサピエンスが機械と同化し、ポスト・ヒューマ
ンとして、生まれかわる未來。ナノテクノロジーにより病気も死も超越し、機械(アンドロイド)なのか、人間(サイボー
グ)なのかも区別がなくなる未来。結構、難しい本ですよ。だって、この本に書かれているのはSFの世界ではなく、我々
の現実の未来なのですから。
健康とは、幸福とは、現在とは全く違う次元で考えることができないと、読み進めることはできません。理窟っぽいSFよ
り遥かに重いですよこの本。このテーマについて語り合える友人が欲しいなと思うこの頃です。
●「Harverd Bisiness Review 人工知能」
月刊のハーバードビジネスレビューの人工知能に関するまとめ本が単行本となりました。MITのブリニョルフソン教授、
東大 松尾 豊準教授(当時)、ヤフー安宅和人氏、アリババの曽鳴CSO(当時)、バブソン大学ダベンポート教授などそ
うそうたる皆さんが執筆したハーバードビジネスレビュー各号のエッセンスである8本のAI関連の論文が詰まっています。
読むべし。
●「人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」
この本ではAIではなく、人工知能と呼びます。人工知能の未来を考える上での必須のテーマ、つまりシンギュラリティは
来るのか、です。最近TVでもよく見かける松尾さんは、日本の人工知能の第一人者ですからね。表面的な初心者向けの話
ではなく、人工知能の仕組みを細かく解説してくれますよ。この本では。ちなみに人工知能の定義は専門家ごとに違うよう
です。心を持つメカ。そう考える方もいるようです。今は、第三次AIブームと呼ばれるそうですが、過去2回のブームで
人工知能が世に出なかったのは、それほど技術が進展しなかったからであり、今回は、50年ぶりのブレークスルーをもた
らすかもしれない新技術ディープラーニングにかかっているそうです。さて、この書は2015年の出版ですけど、ブレイ
クスルーは実現されたと言えるのではないでしょうか。
●「シンギュラリティ・ビジネス AI時代の勝ち残る企業と人の条件」
シンギュラリティ大学で学んだ齋藤和紀さんの書。高度なAIが人に変わって仕事をする時代に、職を失わないのどのよう
な仕事か。そんな分析が近年色々と公表されていますが、この本は更に深く、生き残る企業と人を分析しています。例えば
Uberが急成長したのは、単に配達やタクシーからUberへの乗り換えを狙った限られたパイの中の奪い合いのビジネ
スではなく、今迄、自家用車を利用していた方もUberに乗り換えるという新たなビジネスだということです。アイデア
でビジネスを考えることが出来なければ、AI時代にあなたの居場所はなくなります。
また、カーツワイル博士も発起人となったシンギュラリティ大学についても解説が掲載されています。
●「2045年問題-コンピュータが人類を超える日-
宇宙物理学者である神戸大学松田名誉教授の著書。1年で倍になる指数関数的進歩の場合、30年後には10億倍になる。
スーパーコンピューターの初期からの進歩でもそれは裏付けられており、レイ・カーツワイル博士の2045年にはコンピ
ューターが人間を超える技術的特異点を迎えるという学説を指示しています。しかし2013年上筆のこの本ではシンギュ
ラリティという言葉は一切使用されていません。技術的特異点の説明として、「2001年宇宙の旅」の超人類や人工知能
HALや「攻殻機動隊」における人間の義体化、「ターミネーター」におけるコンピューターの反乱、「マトリックス」に
おけるシミュレーション現実(仮想現実)などを引き合いに出し、分かり易く解説してくれます。また、アップル社が開発
音声で入力できる人工知能Siriやアバターであるデニスの登場とそこに声や表情が加味されている点などの発展から人
間とコンピューターのインターフェイスの進化の予測。ナノテクノロジーの進化により赤血球サイズのロボットの登場を予
測。ウイリアム・ギブソンがインターネットがない80年代に書いたインターネット空間を想像させる小説「ニューロマン
サー」で登場した脳へのジャックイン接続から、ナノボットが脳血管に挿入されることによる脳とコンピュータや疑似世界
との一体化の予測。全宇宙がコンピューターになり、人類はコンピューターを通じて全知全能ならぬ、半知半能な神になる
など、カーツワイル博士予測を裏付けてくれます。そしてコンピューターの進化について4つのシナリオを紹介。また人工
知能に奪われてしまう仕事・職業を予測しています。2013年の予測ですよ。ちなみにこの本では松田先生はAIではな
く、人工知能と表現しています。
●「人類を超えるAIは日本から生まれる」
これも松田先生の本。2016年に書かれています。この本ではタイトルからしてAIと呼んでいます。人工知能への期待
が高まった1980年代、第2次人工知能ブームで主導的役割を果たしたのは当時の通商産業省が「第五世代コンピュータ
ー計画」の研究開発費を投入した日本だそうです。第2次人工知能ブームは結果として失敗でしたが、21世紀になってか
らの第3次人工知能ブームはディープラーニングの手法が開発されたことにより始まりました。2012年にはコンピュー
ターがディープラーニングにより、自分自身で「猫」という概念を獲得した「グーグルの猫」と呼ばれる有名な実験の他、
IBMやマイクロソフト、百度など企業の動き、EUのヒューマンブレインプロジェクトなどの動きの中でトップランナー
になるのは誰か。その中でモノづくり大国日本がどういう役割を果たすべきか。何故そうしなければならないのかを解説し
てくれます。OPENAI社は2015年設立ですが、まだ名前は出てきません。
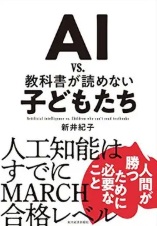
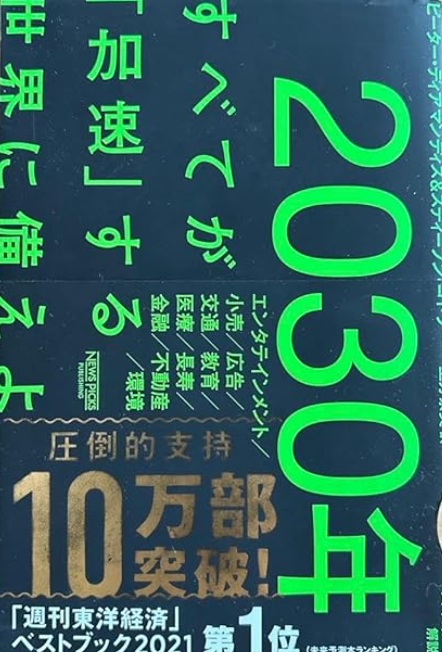
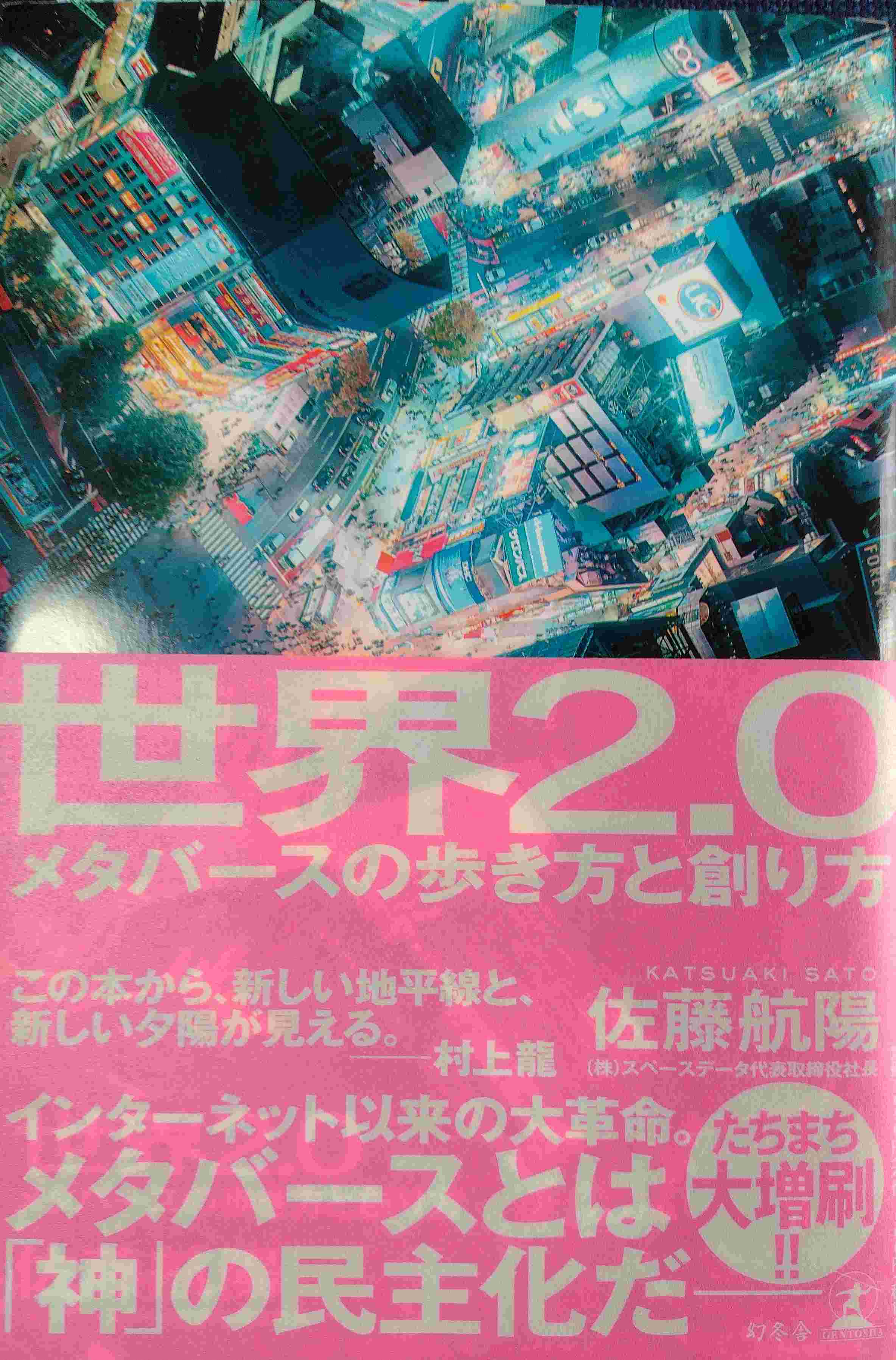
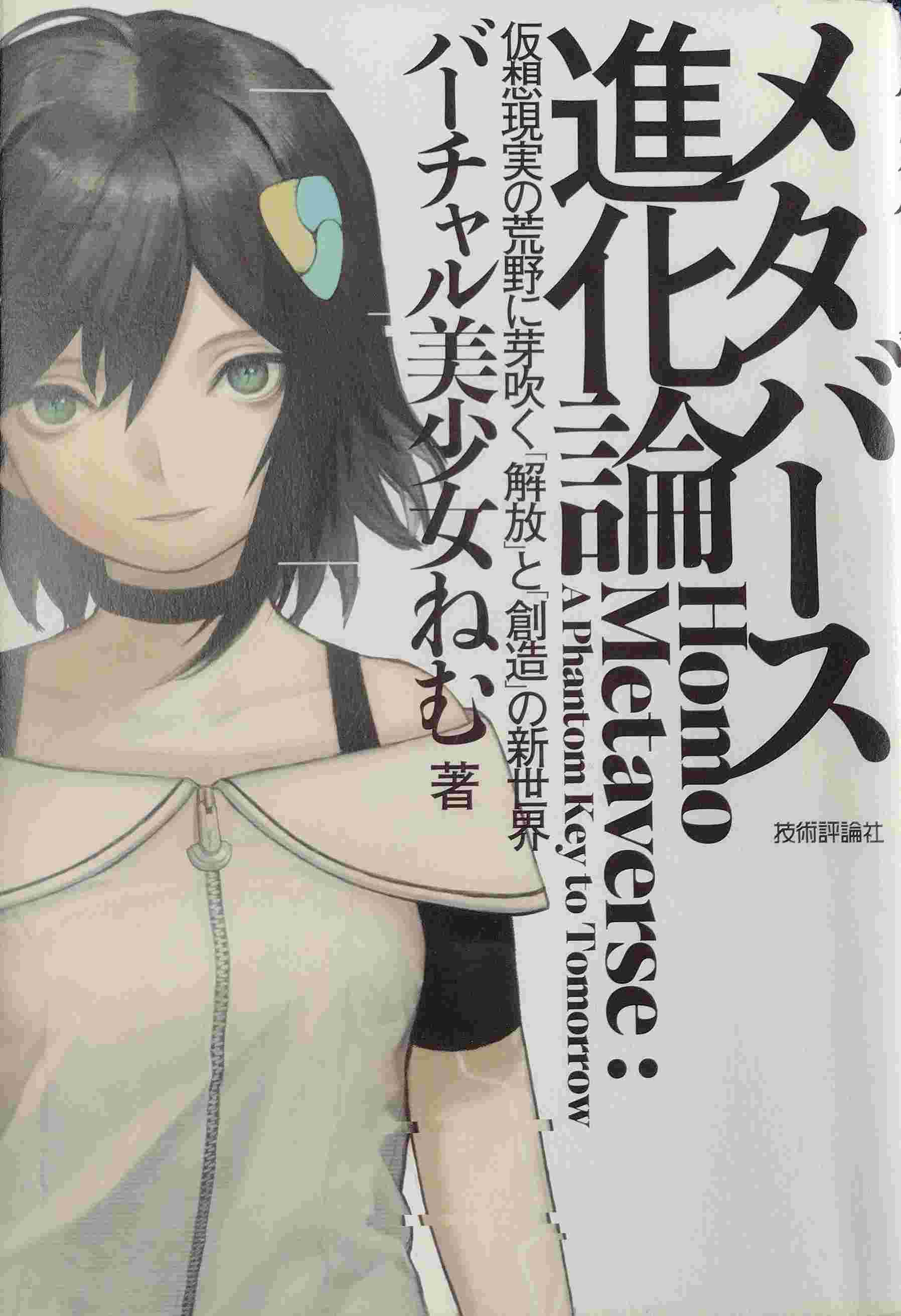
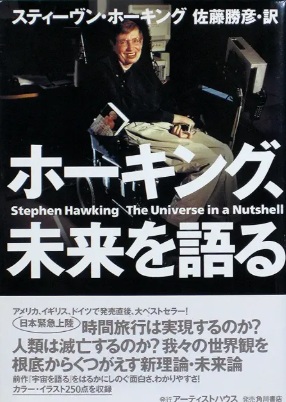
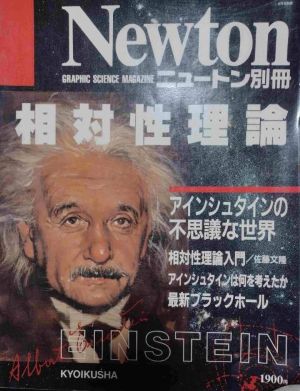
●「AIVS.教科書が読めないこどもたち」
ロボットは東大入試に合格できるかという実験で有名な数学者、AI研究家の新井紀子さんの書。ChatGPTすらまだ
世に出ない2018年の本ですが、今はまだ真のAIはまだ存在しない(AI的な技術でしかないの意)で、シンギュラリ
ティなど起きるわけがない。子供たちは受験勉強を基本とした暗記中心の学習しかしていないので、読解力も想像力も育ま
れていないまま大人になってしまうが、将来AIによって、仕事を奪われてしまう。教育を改革する必要がある。というよ
うな内容。私もかなり前に読みましたが、新井さんがシンギュラリテ否定論者というより、この数年の変化を予測できる方
は実際にグーグルでAIの研究に関わっていたカーツワイル博士や神戸大の松田卓先生くらいだということです。
●「2030年すべてが加速する世界に備えよ」
この手の本は最新でないと意味がないのですが、敢えて5年前のこの本をご紹介します。
あの(マーケッティング理論の)フィリップス・コトラーではなく、別のコトラーさんの未来予測本。でも、科学の未来の
予測がほぼ的中している前述カーツワイル博士は2020年代中にパソコン上に、人間の意識の再現・模倣が可能となると
考えています。それってつまりは、2030年にまでにということです。で、佐藤優さんも推薦するこの本の第3章エクス
ポネンシャル・テクノロジーPart2に仮想現実(VR)を裁判で使用した事例があり、裁判官がVRの世界を正に現実と誤
認したと。また拡張現実(AR)の進歩や実際の活用についても記載があり、3Dプリンターの進化や医療や建築での活用
例が記載されていますが、そんな感じで色々なジャンルにおける2030年を予測した書です。私のこのジャンルの学びと
方向性が一致するような印象がを受けました。この本の多くの予測にはAI、AR、ロボット技術などが絡んでいるのです。
医療、寿命延長、バーチャル世界への移住などなど。目新しいことはないのですが、カーツワイル博士の研究であるAIや
シンギュラリティに興味があれば、目を通しても良いかもしれません。AI時代初期にはまだ生き残っている仕事という観
点で読んでも良いかも。カーツワイル博士よりはずっと近未来(今よりほんのちょっと先)の予測でしかないのですけどね。
●「世界2.0 メタバースの歩き方と創り方」
WEB3.0と言われる現在、メタバースは急速に進化し、一般化しつつあります。しかし、今のメタバースは法治国家で
はない。AI技術ではなく、3D技術、アルゴリズムの進化により、例えば、○○っぽいメタバースを自動生成することも
可能となったようです。ポストメタバースにまで言及するメタバースの総まとめ本です。
●「メタバース進化論 仮想現実の荒野に芽吹く解放と創造の新世界」
この世界、つまりメタバース内では超有名人であり、自らをメタバースの原住民だというバーチャル美少女ねむ氏が体験す
るメタバースの真実。ソーシャルVRとしてのメタバースと、ゲームやSNS、ARやVRとの違い。NFT、ブロックチ
ェーンとの違い、現存する各メタバースの特徴・性格の総括的な分析結果の内容。利用上の注意事項、メタバースの将来像
にまで踏みこんだ本格的な内容です。ここまで今のメタバースを細かく分析したものはないとまで言われており、メタバー
スの全体像を正しく理解したいなら、読むべき書です。
●「ホーキング、未来を語る」
今は亡き天才、スティーブン・ホーキング先生が「宇宙を語る」の次に書いた本、発売されてすぐ読みました。アインシュ
タインの相対論、双子のパラドックス、ブラックホール、時間とは、空間とは、ワームホールとは、図解で分かりやすく紹
介してくれる本、十分の一も理解できなくても、多少のイメージは持てるようになります。読んでおいて損はないです。
●「ニュートン1991年4月号別冊 相対性理論-アインシュタインの不思議な世界-」
書店で最新号として並んでいたのを購入したので、34年前に読んだことになります。ガリレオガリレイとアインシュタイン
の相対性理論の違いから始まり、電車を例にした同時刻の相対性、時間の長さは一定ではないことを説明する双子のパラド
ックス、光速で送れる時間、重力によって光は曲がる、など時間と空間の概念、宇宙の膨張、ワームホールとタイムトラベ
ルなどを細かく解説。「未来を語る」より発行からすると10年前の本ですが、こちらも図解満載で分かりやすいです。
■ 我々ホモサピエンスは何故、他の人類を駆逐し、唯一の人類となったのか ハラリ教授から学ぼう
そして、いつか我々に取って変わるホモデウス、ポストヒューマンにつながる書

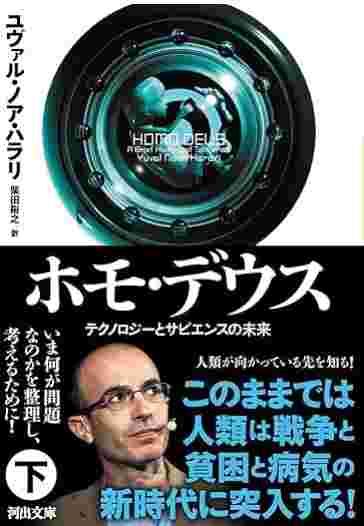
この2冊は、かなり掘り下げましたので、お時間があればお読みください。
●サピエンス全史-文明の構造と人類の幸福-
著者ユヴァル・ノア・ハラリはイスラエル・ヘブライ大学歴史学教授です。かつて流行ったような人類の創成期の謎を遺構や
神話を元に解き明かそうとした類の結果として想像の域を出ない書物(神々の・・とか)とは一線を画します。もちろん人類が
登場した250万年前から数千年前くらいまでの話は想像の域を出ることはないのですが、「サピエンス全史」は可能な限り
学術的な検証を踏まえた記述となっています。また、この本を読み進めながら思ったことは「前評判とは全く違い、読み応え
があり、かなり手ごわい書物」です。
「我々、ホモサピエンスは神話や宗教という架空のものを信じる能力によって結集し、ネアンデルタール人など他の人類を滅
ぼして地球上唯一の人類となった。」まあそんな太古の話が面白く書かれているのだろうと思っていたのですが、実のところ
タイトル通り、我々ホモサピエンスの現代までに至る「全史」が書かれているのです。
そもそも、この本の存在は知っていましたが、じゃあ大枚4000円以上払って読もうかと思った切掛けは、コンピュータの
能力が人類を超えるという「シンギュラリティ」の話で著名な神戸大の松田卓也教授の講演を聞いた際、認知革命(7万年前)、
農業革命(1万2千年前)、産業革命(2百年前)からシンギュラリティ(2045年)に至る話の引き合いに出していたからです。
ハラリ教授はこの本の中で、度々レイ・カーツワイル博士のシンギュラリティに関する話に触れています。
我々人類、つまりホモサピエンスの過去から未来に至る進化は、「サピエンス全史」、「ホモ・デウス」の内容をたどって、
理解・想像ができ、未来に関する部分の科学的見地は、カーツワイル博士の「シンギュラリティは近い」「ポストヒューマン」
によって現実味を帯びてくる。という感じでしょうか。
●ホモ・デウス-テクノロジーとサイエンスの未來-
ホモサピエンスが神話や宗教という虚構、つまり架空を信じて集団としての協力を可能とした認知革命、狩猟採集民からの農
耕民への脱却を生んだ農業革命、集団となることでヒエラルキーを生み、社会的・文化的な差別が発生。統一に向けた帝国主
義、貨幣経済、グローバル化、そして、科学革命、産業革命を経て発展する産業。その発展の中でホモサピエンスは飢餓や疾
病、戦争による大量死の時代を乗り越えつつあるようには一見、思えるが、我々のホモサピエンスの文明は本当に我々を幸福
にしたと言えるのか、否か。そもそもホモサピエンス、つまり我々にとっての幸福とは何か。
マンモスの復活や遺伝子操作を可能とする生物工学、サイボーグ化による長寿命、その先に来るかもしれない不死の時代を前
にして、機械上の脳の情報をアップロードすることによる不死を実現することを目指すギルガメシュプロジェクトによる人間
強化。つまり、非有機的人間工学による脳の再現が可能となる近未来でのコンピュータと人間の境目はどうなるのか。フラン
ケンシュタインの怖ろしい物語は単なる予言だったのか、ホモサピエンスを超える存在などは生まれはしないという警告だっ
たのか。脳とAIを融合させた超ホモサピエンスとして我々は、これからどのように進化し、どこへ向かうのか。
というようなことが、かなり回りくどく、この手の話が好きな私でも理解が難しいレベルで書かれています。実は「ホモ・デ
ウス」は日本での発刊時に書店店頭でペラペラめくっていると、おそらく私には理解できない難しい内容と思い、購入せず、
図書館で借りて、メモを取ったのですが、それをWORD化する気力が、長すぎて最後まで続かない状態でした。
最近(2025年)になって、武力による帝国主義はまだ続き、戦争が決してなくならない=つまり、大量死の時代は、この本の
記述とは異なりまだ続くのだと思い、途中までしかないメモを読み直した次第です。
知見を広める本ではありますが、詳細かつ長いので、決してお勧め本ではありません。
もう少し、この2冊の中身を知りたければ、以下をお読みください。
>>> 「サピエンス全史」、「ホモ・デウス」の詳細な解説(要約)はこちら
ちなみに、ハラリ教授は、この2冊の後、「NEXUS 情報の人類史」「21Lessons 21世紀の人類のための21の
思考」を上筆していますが、残念ながらまだ読んでおりません。