�Z���t�R�[�`���O���ĉ��H
�@�@�Z���t�R�[�`���O���ĉ��ł��傤�H
�@�@�ʂɓ�����̂ł͂���܂���B
�@�@�R�[�`���O���Č����ƁA�R�[�`���鑊�肪������̂Ǝv���Ă��܂��܂����A�����ɃR�[�`���������Ă����̂ł��B
�@�@���ꂪ�A�Z���t�R�[�`���O�B
�@�@�u�����h�}�l�[�W���O���Č��t������܂���ˁB��Ƃ̃u�����h�͂����߂āA�����͂𑝂��Ƃ�����@�ł��B
�@�@�u�����h�ƂȂ肤�閾�m�ȉ��l�ς�i�����ێ�����B �����ɑ��Ă���Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤�B
�@�@�����̉��l�m�ɂ��A�������g���u�����h�Ƃ��č��グ�Ă����B���ꂪ���ɂ̃Z���t�R�[�`���O�B
�@�@
�@�@�ł��A�����܂ł��Ȃ������āA���ׂ����Ƃ͂��낢�날��܂��B ������ƑO�����ɐ����Ă������߂��A�����オ����
�@�@�݂܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill01�@ �����u�����h
�@�@�p�[�\�i���u�����h�@����Ȍ��t���J�Ŏ��ɂ���悤�ɂȂ�܂����B�����̔\�͂��������ƌ��ɂ߁A�����̉��l���u
�@�@�����h�Ƃ��Ĕ��荞��ł����A���������́A����ȈӖ������ł��B
�@ ���荞�ނ��ǂ����͕ʂƂ��āA�����̔\�͂��������̂͗ǂ����Ƃł��傤�B�������g���u�����h�����邱�Ƃɂ���
�@�@�l���Ă݂܂��B�肵�āA�����u�����h�B
�@�� �u�����h���ĉ��ł��傤�H
�@�@��u�����h�A�D����A������Σ�@�o�X�Ō��������گ�Ӱق̒ݍL���ł��B�t�@�b�V�����Ɍ����Č����A�u�����h
�@�@�@�ɂ͍�����ɓ���ɂ����C���[�W������܂��B
�@ �܂��A��Ƃɂ���ẮA��Ђ̃u�����h�����l���A
�@�@�u�i���ɗ��t�����A�ڋq���i���厖�ɂ��Ă���������B���̉��l�ς��ڋq�̖ڐ��Œ��邱�Ɓv�Ɩ��m�ɒ�`
�@�@���Ă����Ƃ�����܂��B
�@ �i����M�p��ʂ��Ė�������ɗ^������́A���A�N�ɂł���ɓ���������̂ł͂Ȃ��@���ꂪ�u�����h��
�@�@�悤�ł��B
�@ �������A�n�[���[�_�r�b�h�\���B�o�C�N�ł����A�����ĕi���͗ǂ��Ȃ��A��Ђ��|�Y�����������Ƃ�����B
�@�@�ł��N���ǂ��݂Ă��u�����h�ł��B�ʎY�ł��Ȃ����̕����A�������͉��l�ς̒B�u�����h�ɂ͂���ȑ��ʂ���
�@�@��悤�ł��B
�@ ���낢��l����ƁA�u�����h�ƌ�������̂̋��ʓ_���R�����т܂����B
�@�@�@ �ۗ����Ă���i�� ���ƍ��ʉ��ł�����蕪��ł̔\�́j
�@�@�A ��т��Ă���i�� ���m�ȉ��l�ρA��ň�O�j
�@�@�B �蔲�����Ȃ��i�� ���������́A�K�ȍs���A�����j
�@�� �l�ɔF�߂�ꂽ���H
�@�@���̐l�́A���͂̐l�ɑ��݂�F�߂�ꂽ���A���Ԃł������Ǝv���Ă���B����̓q�g�Ƃ����������̏K���̂�
�@�@���ł��B�ł��A�����̔\�͂��ˏo�����l�ȊO�́A ��i�A�����A�����A�F�l�A���̑����͂̕��X�������̔\�͂�
�@�@�\���ɂ͔F�߂Ă���Ă��Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�����ɂ͔\�͂�����B����ɂ���ȂɊ撣���Ă�̂ɓK�ȕ]�����Ă��Ȃ��B�قƂ�ǂ̕��͂����v������
�@�@����x���x�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@�@�ł��A�厖�Ȃ��Ƃ�Y��Ă͂����܂���B�@�ڋq�̖ڐ��ł��B�u�����h�Ƃ����ϓ_�ōl����Ȃ�A���肪�ǂ��v����
�@�@���S�Ăł��B�\�͂����邾���łȂ��A���肪���҂��鐬�ʂ������B�@��������x�����łȂ��A�K�v�ȂƂ��ɂ͂���
�@�@�ł����ʂ��グ���邱�Ƃ��ؖ����ď��߂āA���ʂȐl�ԂƂ��Ă̑��݈Ӌ`��F�߂���̂ł��B
�@�@�l���ǂ��v�����Ȃ�ĊW�Ȃ��B��������ɂP�[�B�@�����Ō����u�����h�͏��F���b�e���ł��B�R�[�`���O�ł̓��b
�@�@�e���������Ƃ����サ�Ă��܂��B
�@�@�����ς��̃u�����h��z���Ă������X���A�����ƁA�l�̖ڂ��C�ɂ����̂ł͂Ȃ��A��肽�����Ƃ���ň�O�ɂ����
�@�@���������ł��傤�B
�@�@�ł��A���b�e�����t��ɂƂ��āA�f���炵�����b�e����\�点��B������R�U��̂Ȃ����g�̂��郌�b�e���B
�@�@�Z���t�R�[�`���O�Ƃ��Ă͖ʔ����C�����܂��B���q�l(�����ȊO)���ǂ��v�����́A���ꂩ��̐��̒��ł͏d�v��
�@�@����B
�@�� STEP�P�@�����̗�����
�@�@�l�́A���������Ă���B���̈Ӗ��ŁA���ׂĂ̐l�Ԃ̓u�����h�ɂȂ��\���������Ă��܂��B�ł����͂̓u
�@�@�����h�Ǝv���Ă����ł��傤���B
�@�@�����Ƃ��Ƀu�����h�ƔF�߂��邽�߂̑�1���́A�����̍˔\���m�F���邱�Ƃł��B
�@�@���L���ڂ������̗������Ƃ��ď����o���Ă݂܂��傤�B
�@�@�@ ���Z�ƌ�������̂����邩�A����͎����ɂǂ��𗧂��B
�@�@�A �ǂ�Ȕ\�͂����邩�A���̔\�͂͂��ł������ł��邩�B�ˏo���Ă邩�B
�@�@�@�B �ߋ��ɂǂ�Ȑ������������A�����������Ƃ��o���邩�B
�@�@�@�C �ߋ��ɂǂ�Ȏ��s���������A�Q�x�ƌJ��Ԃ��Ȃ����A�����w���B
�@�@�@�D �ǂ�Ȏ��i�����邩�A���i�Ɍ��������͂��ێ����Ă��邩�B
�@�@�@�E �ǂ�ȋƖ����o���������Ƃ����邩�A�������̌o������������Ă邩�B
�@�@�@�F �ǂ�Ȓ��������邩�A���̒����������ƐL���A���ʓI�Ɋ��p�ł��邩�B
�@�@�@�G �ǂ�ȒZ�������邩�A���̒Z���͕���ł��邩�B�t�ɕ���ɏo���Ȃ����B
�@�@�@�H ���Ȗ����ł͂Ȃ����A���Ȃ��̒�������Z�͑���ɂ͂ǂ������邩�B
�@�@�ł������ӏ������ɏ����o���ă��X�g�����ĉ������B
�@�@�������߂邱�Ƃ́A����F���̍ł����ʓI�ȕ��@�ł��B�܂��̓y�����������������ĉ������B
�@�� STEP�Q�@���݂����o��
�@�@�ǂ��ł����A���Ȃ��ɂ́A���蕨�ɂł��餖��͂�����܂������B�����������͖̂����B����ł��\���ł��B
�@�@STEP�P�̗�����(���X�g)���������ĉ������B���s�����āA�Z�������āA�������Ǝ��o���čĔ��h�~���o����A
�@�@�Q�x�Ɠ������s�����Ȃ����Ƃ��A���łɂ��Ȃ��̋��݂Ȃ̂ł��B
�@�@���M�������ƁA��������Ŏ����u�����h�ւ̑�1�������ݏo���Ă��܂��B���ӂ��Ǝv�����Ƃ͓O��I�ɁA������
�@�@���傤�B
�@�@�����āA�ǂ������A�����̂��ƂŁA���̔\�͂����ʓI�ɔ����ł���̂��A�Ċm�F���A��قǂ̗������ɉ��M
�@�@���Ă����܂��傤�B
�@�@�����܂�����ˁB�\�͂́A�����ł��ď��߂ĔF�߂���̂ł��B
�@�� STEP�R�@�����u�����h�����
�@�@�ǂ����A�����u�����h�̓y���
�@�@�@�ۗ���(�\��)�@�A��ѐ�(����ް��)�@�B������(����)
�@�@�̂R�v�f���ł߂邱�Ƃō�ꂻ���ł��B
�@�@�@�@ �d���ɂ����鎩���̋��݂ɓO��I�ɖ�����������B�@
�@�@�@�A �����̉��l�ρA���̂��Ƃ̔��f��m�ɂ��A����Ɋ�Â�����т����ԓx(����ް��)����ɕۂ��ƁA
�@�@�@�@�@�܂�s���̎��������ƁB
�@�@�@�@�@�T�b�J�[���c�I��̌��t���킩��₷���ł��B
�@�@�@�@�@�� �� �w��������A��ׂ��ꏊ�A���_�ƂȂ郋�[���x�ł��B
�@�@�@�B �A���Ȃ������A���������ƁA�����Ȃ��ƂɓO����B�@
�@�@�܂�A���s�i���A������v�A������M�`�@�قƂ�ǎА��ł��B
�@�@�ł́A�����̂��낢��Ȓ�������Z�̂ǂ��ɖ���������������̂ł��傤�H
�@�@�܂��́A���Ȃ����A�����u�����h�����ړI�͉����H�@�l���Ă݂ĉ������B
�@�@�d���ŔF�߂��邱�ƁB���h����邱�ƁB�d���ɂ�肪�������o�����ƁB
�@�@���ł����\�ł����A�������g�̓���������͂��ł��B���̖ړI���ʂ����̂ɍł��ߓ��ƂȂ�\�͂ɖ�������
�@�@���Ă݂܂��傤�B
�@ �����@��Ђ̃u�����h�ƌl�̃u�����h����v����@����
�@�@�����������������u�����h�Ɗ�ƂƂ��Ẵu�����h�̕���������v����B�ƂĂ��ǂ����Ƃł��B����̏ꂪ�^��
�@�@���邩���m��܂���B���҂���v���Ȃ��ꍇ�A�l�u�����h�͐�(�Ƃ�)���Ă�Ƃ��A�G�b�W(�ɒ[)�Ƃ��ŕЕt
�@�@����ꂩ�˂܂���B
�@�@��N�͎��������s���Ă���B� ���������Ă͐g���t�^���Ȃ��B
�@�@����Ȑ�含���t�����l������ɔF�߂��Ȃ���u�����h�Ƃ͌����܂���B
�@�@���b�L�ł͂Ȃ��{���̉��l�B���Ȃ����T���Ă݂ĉ������B
�@�� STEP�S�@��_����������
�@�@�Z���A��_�̂Ȃ��l�͂��Ȃ��ł��傤�B��_�͕����Ēu���āA���ӂȕ�����L���Ă������ƂɏW������A����
�@�@����̎�ł��B�ł��A�Z�����_��\�Ɍ����Ȃ��悤�R���g���[���ł���Ȃ�A����ɂ͕���ɕς��邱�Ƃ���
�@�@�����Ȃ�S�ɋ��_�ł��B
�@�@�������g�ɂƂ��ẮA�C�Â��Ă��Ȃ����ƁA�������Ȃ��Ƃł��A���͂̐l�ɂƂ��Ă͂��̐l�f���錈��I��
�@�@�v���ƂȂ�A�Z���Ƃ͂���Ȃ��̂ł��B�܂���Ȃ̂́A�����ł͂ǂ����Z�����킩��Ȃ����Ƃł��B
�@�@���͂̐l�ɕ����B����͓���ł��傤�B�����A�����╔���Ƃ����܂Ŗ{���Ō���W��z���Ă��܂����B
�@�@�R�[�`���O�ɂ͗ǂ��肪����܂��B
�@�@�ӌ��⊴�z�͋��܂��A�����Ƃ��Č��ꂽ�s���Ƃ��̉e���݂̂��w�E���܂��B
�@�@�Ⴆ�A���Ȃ��̕��������Ȏ咣�������A���͂Ƌ����ł��Ȃ��ꍇ�B
�@�@����̌��������ƁA�P�ɍU�����Ă���悤�ɕ������邼�B��Ƃ�
�@�@��ނ�̌������������Ȃ��Ɩl�ɂ͖��̔w�i���\���킩��Ȃ��ȁB�ނ���[�����Ă�悤�ɂ͌����Ȃ���B�
�@�@�Ƃ�
�@�@����ɒ�����������f�n������ꍇ��������u�N�͎��Ȏ咣�������B���ꂶ��_�����B�v�ȂǂƐ��i���
�@�@�Ă����P�ɂ͎���܂���B�s���͋����ł��Ă��A���i�͒����Ȃ��B�{�l�����Ă����v���Ă܂��B
�@�@�����ł͂Ȃ��A���Ȃ����g�̎�_�͂ǂ�����Ε�����̂��B �Z���t�R�[�`���O�Ƃ��Ă͓���̈�ł��B
�@�@���Ȃ��̏�i���ǂ��R�[�`�ł��邱�ƂɊ��҂��܂��傤�B�@�@
�@�@��_�������Ă����悤�Ȑ^�̗F�l���d���̏�ł���邱�ƁB �K�v�ł��ˁB
�@�� STEP�T�@�����̋��݁A��݂���
�@�@�@�b���A���Ȃ����g�̂��Ƃ��畔���w���ɔ��ł��܂������łł����B
�@�@���������u�����h������K�v�͑S������܂���B
�@�@�ł��A�Ⴆ�A�����̎d�����F�߂�ꂸ�ɂ�肪���������Ă��镔��������A���C�����߂��̂͏�i
�@�@�̖�ڂł��B
�@�@����Ȏ��A�����u�����h�̎�@�͖𗧂��܂��B�����̗������̏o�Ԃł��B ���ɁA�ߋ��̐����̌��A���s����
�@�@�z�����o���A���̕����ɂ͂Ȃ��\�͂ɏœ_�����āA�{�l�Ɏv���o�����ĉ������B
�@�@��N�Ȃ�ł���B��ł������̂ł����A�����ł� ��N�͂��̂Ƃ��o�����B� �Ȃ̂ł��B
�@�@��ꂽ�����ɂ́A���҂͏d�ׂł��B���҂̕\���ł͂Ȃ��A�����̊m�F�B�ߋ��̐����̌��ɂ�����̂ł͂Ȃ��A
�@�@�ߋ��̍Ċm�F�A�ǂ����ʂ��o�������Ɠ����p�t�H�[�}���X�����ł��Č��ł��邱�Ƃ̑厖���������܂��傤�B
�@�@���ׂ̈ɁA��������B
�@�@�u���x�������Ə�肭������B�v�@�i������āA����������Ă���B��Ƃ����v�������߂āB�j
�@�@�����̐S�ɗ]�T�̖������ɁA��݂܂ōĊm�F���邱�Ƃ͂���܂��A���M�����߂����镔���ɂ́A��
�@�@�݂��������A���݂��ς��邱�Ƃ������܂��傤�B�����炸�A�������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
Skill02�@ �N���[����M���ɕς���
�@�@�ӂ��Ă��߂A�x�@�͂���Ȃ��B���̂Ƃ���ł��B
�@�@��Ɗ����ɂ����ẮA��U���������N���[���A�g���u�����������Ɖ������A���q�l�̐M�������Ă����A����
�@�@�d���ɂȂ����Ă����܂��B
�@�@������O�̂��Ƃł����A�������M���͓̉���A�i�v�ɐM�����ڋq����������Ƃ͑������̂ł��B
�@�@�N���[���������Ă��炢�A�ꍇ�ɂ���Ă͂���Ȃ�M���ɂȂ�����@���l���Ă݂܂��傤�B
�@�@�����̍l����A�z�������ʓI�ɓ`������@�́A�R�[�`���O�X�L���Ƃ��Ăł悭���グ���܂��B
�@�@�֒�������A�x���킯�ł͂Ȃ��A�����̎Ӎ߂̋C���������ʓI�ɓ`���邽�߂ɂǂ������s�����Ƃ邩�Ƃ����ϓ_
�@�@�ōl���Ă݂܂��B
�@�� STEP�P�@�����̎��s�̂����ł��q�l���{���Ă���
�@�@���R�͉��ł��ꐽ���ɂ���܂�̂���{�ł��B
�@�@�܂��́A���q�l�̓{��͑S�Ď����ɂԂ��Ă��������܂��B�@�������A����̌��t�ɔ[�����ĂȂ��悤�Ȋ��
�@�@���Ĉ�{���q�̑��Ƃ����ł́A���ӂ��S�������悤�Ɏ���܂��B
�@�@�u���{��͂����Ƃ��ł������܂��B�v�@����������ʂ�ł��B��Ɠ��ӂ��錾�t���͂��݂Ȃ��玨���X���܂��傤�B
�@�@���ɁA���q�l���������������߂��̂�҂��āA���s�̓��e���Ċm�F���A���炽�߂Ĕ��F�߂܂��B
�@�@�u�{���ɂ������킯�������܂���B���������O���Ă���܂����B����Ȃ����f�������������l�т̌��t��������
�@�@�܂���B�v
�@�@�Ō�́A���q�l�̔[������A�̒ʂ������@�Ŏ��Ԃ����E���A���q�l���������邱�Ƃ�S�����܂��B
�@�@�����Ă݂�ƁA������O�̂��Ƃ���Ȃ̂ł����A�������������̗��ꂾ�����Ƃ��ɁA���s����������܂��
�@�@�������ǂ������ԓx�����������v���o���Ă��������B�����Ɏӂ��Ă��ꂽ��ɁA�����炪�[������Ή������Ă���
�@�@���ł��傤���B
�@�@�����g�͂��������L���͂قƂ�ǂ���܂���B
�@�@�o�����炷��ƁA���s�����������́A
�@�@�����ɂ́A�����̔ۂ�F�߂Ȃ��B�@�����炩�Ɏ����̑��ɔۂ�����Ƃ킩��ƁA�����Ă��̏ꍇ�A������ɏI
�@�@�n����B���������͂���Ȋ����ł��B
�@�@�Ñ��ł����Ȃ������ԑ厖�ȕ����A�ӂ邱�ƁA�����邱�Ƃ͂܂�����܂���B�������ȏ�Ԃł��B
�@�@�����炱���������Ƃ����Ή�������̂ł��B���ꂪ�N���[����M���ɕς����1���Ȃ̂ł�����B
�@�� STEP�Q �����̎��s�̂����ł��q�l���{���Ă���
�@�@�����̎��s�͏�i�̐ӔC�B���O��ЊO�ւ��Ȃ����\������ԓx�͖��m�ɂ��܂��傤�B
�@�@�����ďd�v�Ȃ��ƁB���q�l����Ђǂ������Ă��Ȃ��������Ă��A�����d�ł����ɂ��Ă͂����܂���B
�@�@�l�ɂ���Ă���Ȃ��Ƃ�l�ɂ��Ȃ��B��i�ƕ����̊W�ł����������B���Ȃ����{���Ă���Ȃ�A��ÂɂȂ��
�@�@�̂�҂��Ă���A�����Ǝ��s�̌����A���������Ƙb�����܂��傤�B
�@�@���ɁA�����Ɏ��]�����������������Ƃ��Ă��A�\���ڂ��s���͂��Ȃ��������ƂƁA�����̔\�͂��悭�c�����Ă�
�@�@�Ȃ������ӔC�͏�i�ɂ���܂��B�@�d���̎��s�͎d���ŕԂ��Ă��炤�B��������Ȃ��ł�������ŁB
�@�@�����̎��s�͕����̐����ɂȂ���B�����v���A�q��ɓ{���邱�Ƃ��ɂ߂đO�����ňӖ��̂���s�ׂ�
�@�@�v���Ă��܂��B�@
�@�@�@�i�������A�������O�����ł��邱�Ƃ��O��ł����B�j
�@�� STEP�R�@���q�l�Ƃ̖����Ȃ����Ƃ����������B
�@�@����ɂ͐F�X�ȃP�[�X������܂��B
�@�@ �����[�i�ɐ��Y���Ԃɍ���Ȃ��B�������z���Г��Ŕی����ꂽ�B���X�B
�@�@�������A�ł��Ȃ����̂͂ł��Ȃ��B�܂��A�̓��e�𐳊m�Ɋm�F���܂��傤�B
�@�@���ʂŖ����̂��B�@�����Ȃ��\���m�ɓ`���Ĕ[�����Ă�����Ă����̂��B
�@�@�{����ςނ��ƂȂ̂��A�������̂����r�W�l�X�Ƃ��Ă͏d�v�ł���܂����A����͌_���o�c�I
�@�@���f�ɂ��̂ŁA�����ł͐G��܂���B
�@�@�M���Ƃ����_�ł́A�������ǂ��v�������ł͂Ȃ����肪�ǂ���~�߂��̂����d�v�ł���A����̓R�[�`���O��
�@�@��{�ł��B�����ň��������������ꍇ�ł��A���肪�m���ɂn�j���Ɖ��߂��Ă��܂����̂Ȃ�A���ʂł̖�
�@�@���̂Ɠ����ł��B
�@�@���q�l�̑��Q���Œ���ɗ}����ׁA�o������͉\�Ȍ���A�������v���ɒ��A���ӂ�s�����܂��B
�@�@����́ASTEP�P�@�Ɠ����ł��B
�@�@�܂�����ߍ��킹�����邽�߂ɂł����Ă�p�ӂ��铙�A��ЂƂ���GO�T�C�����o��Ώo���邱�Ƃ͌�������
�@�@�������Ƃ��K�v�ł��傤�B
�@ �ǂꂾ���e�g�ɑ���̗���A�C�����ɂȂ��čl�����������A���̌�̑���Ƃ̊W�����肵�܂��B
�@�� STEP�S�@�������Ȃ���Α��ЂƎ������Ɣ���ꂽ
�@�@�Ⴆ�A�����Ȓl�����v���B���ǂ����{�����͕ʂƂ��āA�N���[���̈�ł͂���܂���B
�@�@�����ł��邩�f�邩�͌o�c���f�Ȃ̂ŁA�������܂����A���ӂ������āA���\�ȑË��āA�D�����͍���
�@�@��p���͕K�v�ł��B���̏�ŁA�s���ł���ǂ����邩�ł��B
�@�@���ӂł��Ȃ��Ă��A�����ăP���J�����B�F�D�I�ȊW���c�����܂�����������܂��B���肪��芷�������
�@�@���]���邱�Ƃ����Ă��邵�A����������������邱�Ƃ����ď\���L�蓾�܂��B
�@�@��������������Ȃ��B����̒S���҂ɂ����v�����Ƃ��Ă��B�����܂���������������ł��ˁB�ƌ����Đa�m�I
�@�@�ɕʂꂽ�����̂ł��B�M�������͎c���܂��傤�B
�@�� STEP�T�@���q�l�̃N���[���������łȂ�
�@�@�Ⴆ�A���q�l���g�̔����R��ⓖ�Ђւ̓`���Y��B
�@�@�����ȃN���[���̏ꍇ�Ɠ������A���ӂ���Ή������邱�ƁA����̗���A�C�������l���邱�Ƃ͓����ł��B
�@�@�@�@�u����͂�����ł��傤�B�v
�@�@�@�@�u���͂ł��邱�Ƃ͂����Ă��������܂��B�v
�@�@�ł��A�ŏ�����Ȃ����݂��Ȃ���͐�ɔF�߂Ă͂����܂���B���݂��Ȃ����F�߂邱�Ƃ́A�M����
�@�@�邱�Ƃɂ͂Ȃ���܂���B
�@�@���Ȃ��������Ȃ����Ƃ������������Ƃɂ���A���ꂩ����������Ƃ������ł��傤�B�܂��A�W���������̃v
�@�@���C�h�͊m���ɏ����܂��B
�@�@���̌���������ɂ��邱�Ƃ��������ꍇ�A�u�~�X�v�Ƃ������t��A�u�������Ă���������Ηǂ������̂�
�@�@�����~�X�v�ƌ����đ��肪�����ł���悤�ȕ\���͂��Ă͂����܂���B
�@�@�u���ʂ͂����ł��B�v �u���x���\���グ���悤�ɁE�E�v�@�Ƃ��������������肪�����A�������Ă���Ȃ��ƌ��ߕt
�@�@���Ă���悤�Ŋ�����t�Ȃł��܂��B
�@�@�v�͑���̊���̓��������c�����Ƃ��̐S�Ȃ̂ł��B
�@�� STEP�U�@�Г��̃N���[��
�@�@����悩��̃N���[����O��ɘb�����Ă��܂������A�Г��̃N���[���ł��A�l�����͑S�������ł��B
�@�@���܂Ő����������Ƃ̊�{���Ċm�F���܂��傤�B
�@�@�E�s���Ȏv�����������s��ۂ͂�����Ƃ�т�B
�@�@�E����̌������͂������蕷���B�������A����̃y�[�X�Ɋ������܂ꂸ�A����̑i���̒��g�ɗ�ÂɎ���
�@�@�@�X����B
�@�@�E����̋C�����ɂȂ��čl����B���͂ł��邱�Ƃ͋��͂���B
�@�@�E��̓I�ȉ�������Ă���B
�@�@�E�B���ȕ\���͂��Ȃ��B�@�@�@�~�u���Ԃ�v�@�~�u�ꉞ�v
�@�@�E�Ȃ����Ƃ̔��F�߂Ȃ��B����ł�����̍����Ă��镔���𗝉�����B
�@�@�E���}�ȑΉ��A����Ɍq����Ή����ӎv�\������B
�@�@�@�u�����������ׂĂ����܂��v�@�u����\�����Ӓv���܂��v
�@�@�������M�����K�v�Ȃ��Ȃ�A����Ȃ��Ƃ�����K�v�͂Ȃ��ł����A�M���W������A���肪������
�@�@�����Ă���邱�Ƃ�����ł��傤�B�M���́A�l�ԊW�̊�{�ł��B���q�l�Ƃ̊W�ł��A�������Ƃ̊W��
�@�@�������ł��B���������i�ƕ����̊Ԃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill03�@ ��肽�����Ƃ�����Ă݂悤
�@�@������͕������M�������Ă��� ����ȃt���[�Y���ߋ����x���o�Ă܂���܂����A����́u�����v�ɏœ_��
�@�@���āA�����̒��ɂ��铚�������o���A�����̃S�[�����ǂ��B�����Ă������ɂ��ĒT���Ă����܂��B
�@�@�N�ł��A�m�M�I�ɂ���Ă݂������Ƃɂ��ẮA���ꂪ���i�擾�ł���A���s�ł���Ԃ̍w���ł���A��
�@�@�p����@�Ɋւ��ăz�[���y�[�W�Œ��ׂĂ݂���A��������Č���ׂĂ݂��肵�āA���Ȃ�ϋɓI�ɍs
�@�@������Ǝv���܂��B
�@�@�ł��A���ڂ낰�ɂ�肽���Ƃ͎v�����Ƃł͂����Ă��A�ǂ����Ă���肩����Ȃ����ƁB�����Ƃ͂Ȃ��炠����
�@�@�߂Ă��܂��Ă��邱�Ƃ͗L��܂��B
�@�@�P���ɍl����A���Ȃ����R�������āA�ׂ��Ă����A�����ɂȂ���͂��ł��B
�@�@�ł��A�ǂ����Ă���菜���Ȃ���Q�͂���������܂��B�����Ŕ[�����Ă��܂��A���͖��ŏI���܂��B
�@�@����ł́A�P�O�̃N�G�X�V�����B�����ɕ����Ă݂Ă��������B
�@�P��t Question�@ ��肽�����Ƃ��ĉ��H �@����A�{���ɂ�肽���́H�@�@�@
�@�@�@�d���ł��V�тł��A�قƂ�ǂ�����߂Ă��邱�Ƃ��v�������ׂĉ������B
�@ �A�l�͌��t�ɏo�����莆�ɏ������肷�邱�ƂŁA���ڂ낰�Ɏv���Ă��邱������������F���ł��܂��B�v��
�@�@�@�@�����ׂ����Ƃ�S�Ď��ɏ����Ă݂ĉ������B
�@�@�B������������߂Ă���i�������͎��|����Ȃ��j���X�g���������茩���������B�{���ɂ�肽�����Ƃ͂���
�@�@�@ �܂����B�ǂ̈ʂ���Ă݂����ł����B
�@�@��Ԃ�肽���Ǝv�������ƂɃ^�[�Q�b�g���i��܂��傤�B
�@�Qnd Question ���ꂪ��ꂽ��Ԃ��Ăǂ�������ԁH�@��̓I�ɂ́H
�@�@�p�Q��p�R�́A�����ǂ�ȃ��x���܂Ŏ����������̂��o���邾���@�艺���āA�����̂�肽�����Ƃ���̉�
�@�@���A�C���[�W�Ƃ��Ė��m�ɂ���X�e�b�v�ł��B
�@ �Ⴆ�A�p�P �̓������w�p��b���K�������x�ł���A
�@�@�@�����ɂƂ��āw�p��b���K�������x������������Ԃ��Ăǂ�ȏ�Ԃ��A��̓I�Ɏv�������ׂĂ��������B
�@�@�@�@���@�p��b�����ɒʂ��Ă�����
�@�@�A�p��b�����ɍs�����Ƃ��ŏI�ڕW�H
�@�@�@ �������ł���A�{���ɂ�肽�������͉��H
�@�@�@ �Ƃ����悤�ɤ��肽�����Ƃ��������̉����Ă��������B
�@�@�@�@���@�O���l�Ɖp��œ����b���ł�����
�@�@�B�����Ƃ����Ƌ�̉�
�@�@�@�@�� ��̓I�Ȃǂ����̍��̊X�p�ŁA���Ȃ������n�̕��Ɨ����ɉ�b���Ă��������A�X�̗l�q���b
�@�@�@�@�@�@�̑��肪��̓I�f���Ƃ��āA�F��A����Ă��鉹�y�A�ꍇ�ɂ���Ă͓������̒g������A�X�̓���
�@�@�@�@�@�@�܂Ŏv�������Ԃ悤�ȃC���[�W�ƂȂ�܂ŋ�̉����A�]���ɏĂ��t���ĉ������B
�@�@�@�@�@�@���r�W�l�X�̕��䂪�^�[�Q�b�g�łऑS�������ł��B�O��I�ɋ�̉����Ă��������B
�@�Rth Question ���ꂪ�o�����牽���y�����́B
�ǂ�ȋC�����H
�@�@�@�@�p�Q�́w�ǂ����̍��ŁA��̓I�ȒN���Ƙb���Ă���x�C���[�W���v�������ׁ@�����͂��̎������y����
�@�@�@�@ ���A���ɖ������Ă���̂����l���ĉ������B
�@�@�@�A�C�O�Ŋ�����A���n�ɗn�����ށA�l�Ƃ̌𗬁A�y�������ԁA���ł����\�ł��B���̂��Ȃ��̐���
�@�@�@�@ �ɂ͂Ȃ��A�o ���邾���V�N�ŁA��̓I�Ȗ����A��т��l���ĉ������B
�@�@�@�B���̖����E��� �� �p�Q�ł̃C���[�W�ƂƂ��ɂ��ł��v���o����悤�ɉ��x�����x���z�����Ă݂ĉ���
�@�@�@�@ ���B
�@�Sth Question ���ł��܂܂ł��Ȃ������́H�@��Q�͉��H
�@�@�@�@����Ȃɖ����ł��邱�ƂȂ�A���܂ł��Ȃ������͉̂��̂Ȃ̂��H
�@�@�@�@�@���s�Ɉڂ��Ȃ����������̏A�C���͂��Ă݂ĉ������B
�@�@�@�@�y�����I�ȏ�Q�z
�@�@�@�@�@ �� �]�T���Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�E���Ԃɗ]�T���Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���K�I�ɗ]�T���Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�E��̓I�ɍl����]�T���Ȃ��i���ԁA�S�̗]�T�j
�@�@�@�@�@�� ��̓I�ȏ�Q������
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�������]���ɂȂ�i�d���A�Ƒ��j
�@�@�@�@�y�S�̒��̏�Q�z
�@�@�@�@�@ �� ����������ݏo���Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�E������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���̂܂܂ł������A���S�n������
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���܂������킯�Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�E��l�ł��̂͂�����ƋC�p��������
�@�@ �A��Q����z���邽�߃q���g�@�i�ł��A�����͎����̒��ɂ���܂���j
�@�@�@ �d������� �� �@�E�{���ɂ�肽�����ƂɎg�����Ԃm�ɂ��餂łख{���̎d���͂�����Ƃ�邽��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ɃX�P�W���[���Ǘ�����
�@�@�@ �S�@ �@�@ �@ �� �@�E���܂������Ă��鎩����z������
�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@ �E���߂Ă��錋�ʂ̃C���[�W����Ɏv���o���A�S�[���Ɍ������Ĉ�����O�i����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �E�M���ł���F�l��A�h�o�C�X�����炦��l�ɘb��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�E�����ɐ錾����A�Ƒ��ɐ錾����
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�E��������̂�x�点��
�@�@�@ �S�ʁ@�@ �@ �� �@�E��肽�����Ƃ��A�����̐����E�L�����A�A�b�v�ƌ��т��āA���̂��߂̎��ԁA����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���߂̓����ƍl����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ��肽�����Ɓ@���@�����̂��߁A�����ׂ����Ƃł�
�@�Tth Question�@ ��̓I�Ȏ菇�́H�@�@�l���Ă݂悤
�@ �@���C���[�W����S�[�����N�_�ɁA��������S�[���ɓ��B�ł��邩�t�߂肵�Ȃ���l���Ă݂܂��傤�B
�@�@�@�@ �p�b�ł����n���}�@�ł��B
�@�@�@�@�@�i�Ⴆ�j
�@�@�@�@�@�p��b�𗬒��ɂ���ׂ��悤�ɂȂ�
�@�@�@�@�@�@ �� �O�l�̗F�l������b����@�@�@ �� �����ɏЉ�Ă��炤
�@�@�@�@�@ �� �p��b��ԋ����ɂU�����Ԓʂ��@�� �T�Q�����̎��Ԃ��m�ۂ���@�� �����P���ԑ��o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����m��
�@�@���ł��邾����̓I�ɁA�菇(����)���l���Ă݂ĉ������B
�@�Uth Question�@�@�����łł��邱�Ƃ͉��H�@�l�ɗ��ނ��Ƃ͉��H�@�@�������Ă݂悤
�@�@�@�@���ɁA�d���Ɋւ��Ă�肽�����Ƃ���������Ȃ�A�����̗͂����ł͂ł��Ȃ����Ƃ͑����͂��ł��B
�@�@�@�@��肽�����Ƃ̎����ɁA�ǂ�Ȑl���A���A����̃��\�[�X���K�v�ƂȂ�̂��A�Ċm�F���Ă݂ĉ�
�@�@�@�@�����B
�@�@�@�A�l�ɗ��ނ��Ƃ��A������Ǝ��ɏ����o���ă��X�g�����邱�ƂŁA���m�ɔF���ł��܂��B
�@�Vth Question �@ ���߂�l�͒N�H�@����͂ǂ��ɂ���H
�@�@�@�p�U�ŏ����o�������ڂ́A��ɓ���ł��傤���B��Âm���ɂԂ��Ă����ĉ������B
�@�@�@�����\�[�X�͐F�X�Ȍ`�ł���܂��B
�@�@�@ �@�������g�̉ߋ��̐����̌���A�Г��̐������Ă���҂̎��Ⴉ��A���܂��������v���Z�X�����o��
�@�@�@�@�@���Ƃ��ł��܂��B
�@�@�@�������̎d���▲�ɐl����������Ő�͂Ƃ���ׂɂ́A����ɂ������S�[�����C���[�W���Ă��炤��
�@�@�@�@ �����z�ł��B
�@�@�@���ꂪ�����ł��A�������S�[����B���������Ƃ����M�ӂ𗝉����Ă��炤���Ƃ͍Œ���K�v�ł��B
�@�Wth Question �@�������ɕ��@�͂���́H�@
�@�@�S�[���ɓ��B���邽�߂̕��@���v�����Ȃ��ꍇ�����邩���m��܂���B
�@�@�@���C���[�W����S�[�����@���Ɂw�ǂ����̍��̊X�p�ŁA���n�̕��Ɨ����ɉ�b���邱�Ɓx�ł���A
�@�@�@�@ �����B������v���Z�X�́A�p��b�����ɍs�����Ƃ����ł͂Ȃ��͂��ł��B�@���̎�i�ɂ��Ă�
�@�@�@�@ �l���Ă݂ĉ������B
�@�@�@���d���̏ꍇ�������ł��A�ł��邾�����_��ς��āA�S�[���֓��B������@���l���Ă݂ĉ������B
�@�@�@���������ʂ�����ʂȃS�[����ڎw�����Ƃ��\��������܂���B
�@�Xth Question �@���܂łɉ�������́H
�@�@�����������A�S�[���܂ł̓��������Ă�����A���́A�ǂ̃X�e�b�v�������܂łɒB�����邩�A�^�C
�@�@�@�@ �����~�b�g�����߂܂��B
�@�@�@�����ۂɊ������J�n������A�X�P�W���[���ʂ�i�����Ă��邩�A�����m�F���ĉ������B
�@�@�@���v���ʂ�ɐi�܂Ȃ��ꍇ�ł��A�S�[���̃C���[�W���v���o���Ȃ���A�P�����O�ɐi�݂܂��傤�B
�@Last Question �ǂ��܂łł������ȁH
�@�@�@���P�T�Ԍ�̎����A�P������̎����A�R������̎������������݂̎����Ɣ�ׂāA�ǂꂭ�炢�O�i��
�@�@�@�@ �����i�����������j���m�F���Ȃ���A��肽�����Ƃ��i�߂Ă��������B
�@�@�@�����������y���݂ɂȂ�B�S�[���ɓ��B��������Ɗy�������Ƃ��҂��Ă���B�����Ă�肽����
�@�@�@�@ ���ɕς����̂ł�����B
�@�@�ǂ��ł����A�z���͎����������ł����B
�@�@�����Ă��č��X�Ȃ���v�����̂ł����A�R�[�`���O�́A���_�̕����ɗ��������镔�������Ȃ葽��
�@�@�ł��ˁB
�@�@�����ƃv���̃R�[�`�́A���R�Șb�p�̒��ŁA����ɂ����[����������A�E�C�t�����肵�Ď��s����
�@�@����B
�@�@�����͗�������Ɣ��_���鑊��Ȃ�A�O�ɂ͐i�݂ɂ����ł��ˁB
�@�@�@���������������킯����Ȃ���B������b����������������B�
�@�@�@�@�@�E�E�E����Ȃ����炩���ƕ�e�͂���i�ɂ͕K�v�Ȃ̂����m��܂���ˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill04�@ ��c��߂܂����A���܂���
�@�@�ȑO�A���Ԃ̌����I���p��������钆�ŁA��c������������v�_������グ�܂������A����͂���
�@�@�Ɖ�c�̒��g�A�^�c�ɓ˂�����ŁA��c�̕K�v�����l���Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�� ��c��肽���ł����H
�@�@�̂������玿��A ���Ȃ��́A��c���čD���ł����H
�@�@�قƂ�ǂ̕��́A���܂�D���ł͂Ȃ��Ɖ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�F����̃C���[�W�̒��̉�c�́A�Ⴆ�A���Ԓׂ��A�E�ϗ͂̃e�X�g�A����I�`�B����A������
�@�@�ے肳����A�c�_���Ȃ��Ȃ��܂Ƃ܂�Ȃ���@���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����B
�@�@�������A�����C���[�W�قNj����c���Ă���B�@
�@�@�ł͂Q�߂̎���B ���Ȃ��́A��c����肽���ł����H
�@�@��������߂̎���̑����ł�����A�قƂ�ǂ̕��͂m�n�ł��傤�B
�@�@����ł́A�R�߂̎���B ���Ȃ��́A��c���K�v���Ǝv���܂����H
�@�@���������A��c��������Ђ́A��݂ȉ�Ё@�Ƃ����C���[�W�������̂ł́H
�@�@�������A���͂����͎v���܂���B�m���Ɍ��_���o�Ȃ���c����ӂ܂ŔN����N������Ă����Ђ�
�@�@��قƂ�ǏI����Ă��܂��B���A�Ӗ��̂����c�������I�ɂ���Ă���Ȃ�A�b�͈Ⴂ�܂��B
�@�@�ł́A�Ӗ��̂����c�������I�ɂ�邱�Ƃ��l���Ă݂܂��傤�B
�@��STEP�P�@�@��c�̖ړI�m�ɂ���
�@�@���`�B�A��L�A�ӎv����B��c�̖ړI�͂��낢�날��܂��B
�@�@���`�B�������ړI�Ȃ��c�͕s�v�����m��܂���B��炾���Ď�i�͂�������B�����A�g�b�v�̈ӎu��
�@�@�M�ӂƂƂ��ɖ��m�ɓ`����B���ꂪ�ړI�Ȃ�Z�������A�Ј����W�܂�Ӗ������邩���m��܂���B����^
�@�@��c�͂��̂�����ł��B�����ċc�_�̏�ł͂���܂���B
�@�@�ӎv����̏�Ƃ��ĉ�c���g���Ȃ�A���_���o�����Ƃ��K�v�ł��B�����āA����ꂽ���ԓ��ɋc�_��s�����A
�@�@���_���o���Ȃ�A�����I�ɉ�c��i�߂邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�@������ɂ����Î҂́A��c�̖ړI�m�ɂ��A�ړI�ɉ������o�Ȏ҂����W���A�ړI��B�����邽�߂�
�@�@�i�s�A���Ԋ������O�Ɋ�悷�邱�Ƃ��K�v�ł��B�ړI�����m�ŁA�o�Ȏ҂�����𗝉����Ă���A�c����
�@�@�E�����Ă��A�����߂��̂����͂��₷���͂��ł��B
�@�@�i���W���A�悭�������̌��t�́A�܂��ɉ�c�ɂ҂�����̌��t�ł��B
�@��STEP�Q�@�@��c���Ǘ�����
�@�@��c�̖ړI��j�ޓG�͉��ł��傤�B�ړI�̕s�������炭�鉡���ւ̒E���B�@�o�Ȏ҂̏����s�����炭���
�@�@���̕s�o�B
�@�@�Ⴆ�A�o�Ȏ҂����̏�ōl���Ȃ���ӌ���������c�́A�c�_�����Ă���悤�ł͂����Ă��A�ł����Ԃ��
�@�@�₵�A�{ ���ł͂Ȃ��c�_�ɉ�c�����˂܂���B
�@�@�܂��A����̏o�Ȏғ��m�ŁA�ׂ��ȋc�_�����Č��_���o���Ȃ��Ă͐�i�߂����ɂ��Ȃ肩�˂܂���B
�@�@�ǂ�����悭������i�ł��B���������ƁA��c�ŏo�����_����ɂȂ��ĕ����������܂��B���̎��͎v����
�@�@���Ȃ������Ƃ������R�ł��B�܂菀���s���B
�@�� Work�P ��c�̖ړI�����O�ɒʒm����
��
�@�@�ړI�̕s����������Ȃ�ړI�𗝉����Ă��炢�܂��傤�B
�@�@�P�j��c�̏��W�ʒm�ɂ́A��c�̑�̖ړI�A���߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ڂ����������ŋL�ڂ��܂��B��c
�@�@�@�@�̖ړI�́A���W�ʒm�݂̂łȂ��A�����̖`���ł����m�ɂ��܂��B
�@�@�Q�j���ɁA���O�ɍl���A�������Ă������ڂm�ɋL���A�e���傪�p�ӂł����E�I���}�����������Ă�
�@�@�@�@�炢�܂��B
�@�@�R�j����̕���Ԃł̎��O�������K�v�Ȃ�A�������s���Ă����悤�ʒm���܂��B��c���ɓ���̏o�Ȏғ�
�@�@�@�@�m�݂̂̋c�_�Ɏ��Ԃ��₷���Ƃ��h���܂��B�ꍇ�ɂ���ẮA���O�̏���c���J�Â��Ă������ł�
�@�@�@�@�傤�B
�@�@�S�j����
�@�@�@�@�P�j�`�R�j�ɂ��āA�P�ɊJ�Òʒm�ɋL�ڂ��邾���ł́A�\���ɈӐ}���`���Ȃ��Ȃ�A������x�̍�
�@�@�@�@���s���܂��B����������������ł��傤���A���[���⎆�ł͓`���Ȃ��^�ӂ�a�����A��Î�
�@�@�@�@�̂��Ȃ��̍s���Ŗ��߂�A
�@�@�@�@���ꂪ���ł��B
�@�@�@�@�������_�����\�z�����Ȃ�A�z�肷�錋�_�����A����ɑ����ӌ��A���ɁA�{�|�̃|�C��
�@�@�@�@�g�����O�Ɋm�F������A�����܂łɗp�ӂ��Ă��炤���Ƃ��\�ł��B
�@�� Work�Q ���Ԃ��Ǘ����遚
�@�@�P�j�{�Ԃ̉�c�ł́A����ꂽ���Ԃ��ǂ��g�����m�ɂ��܂��傤�B
�@�@ �@���Ԋ����L�ڂ������W����z�t���邱�Ƃ��A���ɂ͌��ʓI�ł��傤�B
�@�@ �@�i�i�Ɂu���낻��A���̋c��Ɉڂ�܂��B�v��u���_���o���܂��傤�B�v�@�������Ղ��Ȃ�܂��B
�@�@�Q�j�l�́A����̂��Ƃ��������Ă��A�o���Ă���̂̓C���p�N�g�̂������P�A�Q�_�݂̂ł��B
�@�@�@�@�����͗v�_�݂̂ɍi�邱�Ƃ��o�Ȏ҂ɓO�ꂵ�܂��傤�B
�@�@�@�@�@(�����z�t�ŏ\���Ȃ��Ƃ������̂ł�)
�@�@�R�j������O�̂��Ƃł����A�����Ԃ̉�c�͏W���͂����܂��B��c�̓��e�ɂ���Ă��Ⴂ�܂����A
�@�@�@ �����Ă��P�`�Q���Ԃ������Ƃ���ł��傤�B���ɏ��`�B�����łR���Ԃ��������c�̏��W�ʒm������
�@�@�@ ��A���Ȃ疳���ɗ��R�������Ăł����Ȃ��܂��B
�@�@�@ �\���Ȕ������ł��Ȃ���A�c���^�����炦�Ώ\���ł��傤�B�Ⴂ�܂����H
�@ �S�j��c���Ǘ����邱�Ƃ́A�v���W�F�N�g���Ǘ����邱�Ƃɂ��q����܂��B
�@�@�@�@����̌��_�͉����i�x��͉����j
�@�@�@�A���̉�c�͂���
�@�@�@�B���̎��܂��ɂǂ�ȍ�Ƃ��s��
�@�@�@�C�����������Ď��̉�c�ɗՂނ�
�@�@�@��c�̏I�����ɖ��m�Ɋm�F���邱�Ƃ���v���W�F�N�g�̎���(���ޭ��)�Ǘ��ɂ��Ȃ�܂��B
�@��STEP�R�@�@��c�̌㖡���l����
�@�@�ӎv���肪�ړI�̉�c���������ƏI��点���͉����B
�@�@�@���m�Ȍ��_���o�����ƁB����ɂ��܂��B
�@�@�������A
�@�@�A�o�ȎґS�����ӎv����ɎQ�������Ǝv����A��c���X�ɈӖ��̂�����̂ɂȂ�܂��B
�@�@�S���Q���Ƃ悭�����܂����A�Ј��̈ӎu����ւ̎Q���ӎ������̒��ŏ�������͓̂�����Ƃł��B
�@�@��c�̏o��
�@�@�ґS�������O�ɑō������e�𗝉����A�����̈ӌ��������ĉ�c�ɖ]�݁A�c�_�����A���_���o���B���ꂳ
�@�@���ł���A��c�����̖������ʂ����܂��B
�@�@�@�A�A���B���ł���Ή�c�̌㖡�͂��Ȃ肢�����̂ɂȂ�ł��傤�B
�@�@���̂��߂ɂ��A�J�ÖړI�̎��O�ʒm�iWork�P��1�j�2)�j�͏d�v�Ȃ̂ł��B
�@�@��c�̓x�Ɉ݂��ɂ��Ȃ�B����ȕ��͐��̒��ɑ����悤�ł��B��c�����₪�鑽���̕������ɂ��闝�R
�@�@�́A��c�������̍s���┭���������ɂȂ��Ă��邱�ƁA���O�����ȃA�h�o�C�X�����炦����
�@�@�͂Ȃ����Ƃ��グ�Ă���悤�ł��B
�@�@�����ŁA�Ɩ��̕�̉�c�Ȃ�A
�@�@�B�u���[���X�g�[�~���O�Ɠ����悤�ɐl�̔�����ے肵�Ȃ����ƁA
�@�@�C�}�C�i�X���v���X�ɕς�����悤�ȃA�h�o�C�X��^���邱�Ƃ���c�i�s��̃��[���Ƃ���A��
�@�@�ɂƂ��āA���̉�c�͗L�Ӌ`�Ȃ��̂ƂȂ�܂��B
�@�@��c�͔ے肳����ł͂Ȃ��B����Ȍ㖡����ł��B
�@��STEP�S�@�@��c�ňӌ����q�ׂ�ɂ�
�@�@�o�Ȏ҂̗���ōl���Ă݂܂��傤�B�o�Ȏ҂Ƃ��ĉ�c���Ӗ�������̂ɂ���ɂ́A�O�q�̒ʂ�A�c��Ɋ�
�@�@���Ė��m�Ȉӌ��A�ꍇ�ɂ���Ă͕�����\����ӌ��m�ɓ`���邱�Ƃł��B
�@�@���̂��߂ɂ́A���W�ʒm�ɋ�̓I�L�ڂ��Ȃ������Ƃ��Ă��A��Î҂ɉ�c�̎�|���m�F���邱�Ƃ��K�v
�@�@�ł��B��肠�����o�Ȃ��Ă݂悤�Ȃ�čl���ł́A���Ԃ����ʂɂȂ邾���ł��B
�@ �@�����ďd�v�ȃ|�C���g�B���������Ȃ���Ώ��Ȃ��قǁA���m�Ș_�|�̔����ɏd�݂��o�܂��B�Ӗ��̂Ȃ�����
�@�@ ��A�E���ɂ͒��ӂ��܂��傤�B
�@��STEP�T�@�@��c��킢�̏�ɕς��Ȃ�
�@�@��c��ō����Ŕ��Έӌ������邱�Ƃ́A����I�ɉ�c���I�����A�n���I�ł��芽�}���ׂ����Ƃł��B
�@�@�������A���ɂ͊���I�ɔ��Έӌ�����������A����I�Ɏ����̌��_���咣����҂������肵�܂��B
�@�@�厖�Ȃ̂́A����ł͂Ȃ��A�����Ƃ��ĒN�����[���ł��錋�_���o�����Ƃł��B
�@�@���̂��߂ɂ́A
�@�@�P�j����U������
�@�@�@�i��҂́A�u�܂��́A�v���Ă��邱�Ƃ�S�������Ă݂ĉ������B�v���A���������p���������܂��B
�@ �@�@�o�Ȏ҂���ÂɎ����̘b�Ɏ����X���Ă���Ǝv���A�����͊�����U�����������₷���Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���l���̑ō��������l���̉�c���ɂ����܂����j
�@�@�Q�j�ӌ����܂��Ȃ�����Ƃ����Ĕ��Ȃ��B
�@ �@�@�l�U���ł͂Ȃ��A�����̈ӌ����q�ׂĂ������́A�ǂ��炩������肹���A�������e�̎�����
�@�@�@ �����ڂ�������B
�@�@���ɂ́A�����ے肵�A������D�ʂɌ����邱�Ƃɏd���������҂����܂��B�ނ�́A��c��킢�̏�Ƃ�
�@�@����ɏ����ƂŎ��Ȏ咣���s�����i�Ȃ̂ł��B
�@�@���̗�ő厖�Ȃ̂́A�ǂ���̈ӌ����S�̍œK�Ȃ̂��ł��B���Ȃ��̈ӌ����ے肳��Ă���Ȃ�A
�@�@�R�j����̎咣�̐����������́A�K�ɕ]������B���̏�ŁA�Ⴂ�m�Ɏ咣����B�����ے肷��
�@�@�@ �̂ł͂Ȃ��A����̈ӌ��Ǝ����̈ӌ��̈Ⴂ�m�ɂ��A�ǂ��炪�S�̍œK���̔��f�ޗ��𑼂̏o
�@�@�@ �Ȏ҂ɗ^���܂��B
�@�@�S�j���Ȃ��ɂƂ��ď������������Ȃ̂ł͂Ȃ��B��ɏ���Ȃ������ȊO�͉\�Ȍ���������A����
�@�@�@ �ɏ������Ǝv�킹�Ă����B���Ȃ����������D�ނȂ�ʂł����A������ЁA�]�ƈ��ɂƂ��čœK�Ȍ�
�@�@�@ �_���l���Ă݂܂��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill05�@ ���Ԃ̖��ʂ�r������
�@�� ������Q�T���Ԃ�������
�@�@�P���͂Q�S���Ԃł��B���̒��Ő������Ƃ褐H��������ʋ�����d��������B�d���D��Ŏ��Ԃ��l���Ȃ�
�@�@�Ƃ����Ȃ��̂��A��X�̌����ł����A�����Ǝ��Ԃɗ]�T�������ĕ�炵�����ƒN�����v���Ă���̂ł�
�@�@�Ȃ����傤���B���Ƃ����P���Ԃł�������A������Q�T���Ԃ�������Ǝv���܂��B
�@�@�d���ɗ]�T�����A�������鎞�Ԃ��~�����B�ړI�͂Ȃ�ł��ǂ��ł����A��x�A�����̂Q�S���Ԃ�
�@�@�������Ă݂āA���Ԃ������I�Ɏg���Ă��邩�`�F�b�N���Ă݂Ă͂������ł��傤�B
�@�� STEP�P�@�@���Ԃ���肭�肷��
�@�@���Ԃ�Q��錴����r��������@���l���Ă݂܂��傤�B
�@�@�P�j�W�������@
�@�@�@ ��Ƃ����Ă��鎞�Ɋ��肱�܂�A��Ƃ��i�܂Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͑������̂����B
�@�@ �@�ł������ɏo���Ȃ�������������̂ł��B
�@�@�@�@���@�{���ɏW�����������ɂ́A�R�O���ł��ꎞ�Ԃł�������������m�ۂ��Ă�����B
�@�@�@�@���@�ً}�ȊO�̓d�b�����p���Ȃ��ł��炤�B
�@�@�Q�j�v��𗧂Ă�
�@�@�@�������Ă���v���W�F�N�g���ǂ��i�߂邩�A��������̍�Ƃ��������n�߂邩�B�X�P�W���[����D��
�@�@�@���ʂ����m�łȂ��ƁA��Ƃ͂����݂��������̂ł��B
�@�@�@�@���@�X�P�W���[���A�z�肷��S�[�� ���o���邾�����m�ɂ���B
�@�@�@�@���@�P�O�O���S���ɗ͂𒍂��̂ł͂Ȃ��A�D�揇�ʂ̍�����Ƃ�����|����B
�@�@�@�@���@��z�͂X���܂łɍs���Ƃ��A��ƂɊւ���Œ���̃X�P�W���[�������[���Ƃ��Ď��ɏ����Đ�
�@�@�@�@�@�@ �����邾���ł��Q�x��Ԃ�����܂��B
�@�@�R�j���肬��ɂȂ�Ȃ��Ă�����
�@�@�@�u�����v �� �u�̂ё��v �łȂ��Ă��ċx�݂̍Ō�ɏh��������͌��\�������̂ł��B�l������o
�@�@�@���ƌ���ꂽ���ނ���ߐ�ԍۂɍ���Ă��܂��B
�@�@�@�ŏ��ɂ�邩�A�Ō�ɂ�邩�A�v��I�ɐi�߂Ă����̂��A�w�Z�̏h��Ȃ�ΐV�w���ɏh�肪�o����
�@�@�@��������Ηǂ��̂ł����A�d���͂����͂����܂���B
�@�@�@����I������O�ɁA���X�ɐV�����d�����킢�Ă��܂��B
�@�@�@���@�X�^�[�g����ł͂Ȃ��A�S�[��������v��𗧂Ă܂��B���̂��߂ɂ́A�B�����ׂ��S�[���m
�@�@�@�@�@ �Ɉӎ����ĉ������B�S�[���Ɍ����Ăǂ������X�P�W���[����g�ނ����t�ɍl���Ă����B
�@�@�@�@�@ ��ɁA�������v��r��̂ǂ��ɂ���̂����ӎ����čs�����܂��傤�B
�@�@�S�j������`�͂�߂�
�@�@ ����ꂽ���Ԃ̒��ŁA�S�Ă����Ȃ��̂͒N�ɂ����ĕs�\�ł��B�ł�������`�͐��i�E�K���Ȃ̂�
�@�@ �ȒP�ɂ͕ς����܂���B
�@�@���@������ �ł͂Ȃ� ��i�ࣂ��߂����悤�ɂ��܂��傤�B��������Ȃ��ł����A�����͈�i������
�@�@�@�@�@�� �����Ɉ���߂Â����؋��ł��B�@�i�����d�˂Ă���A�����Ƃ����͊����ɂȂ�܂���B
�@�@�T�j�����őS�Ă�낤�Ƃ��Ȃ�
�@�@�@������`�ɒʂ��܂��B�����ł��ׂĂ��Ȃ��ƁA�����̎v���ʂ�̌��ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��B������܂�
�@�@�@�ł��B�`�[���ŕ��S���邱�ƁA�����ɔC���邱�Ƃ���ɂȕ�������̂ł��B
�@�@�@���@�S�ɗ]�T�������܂��傤�B�����̈Ⴂ�͋C�ɂ��Ȃ��B�ړI���B���ł�������̂ł�����B
�@�@�@���@���Ȃ��̕������y��M���Ďd����C���܂��傤�B�����̃~�X�����s�͋���̋@��Ǝv����
�@�@�@�@�@ �����̂ł�����B�@�u���������ˁv �ƌ���@���Ă�������������Ȃ��ł����B
�@�@�U�j����������������Ȃ�
�@�@�@�m���ƌ����Ȃ��l�͎d���ɖ�����Ă��܂��܂��B
�@�@�@���ł��Ă��܂����́A���ʂƂ��āA�S�Ē��r���[�ɂȂ邩������܂���B
�@�@�@���@���̒��̃X�P�W���[���\�ɂ͎d�������ł��l�ߍ��߂܂��B�������Ă���d���̎菇�A�X�P
�@�@�@�@�@ �W���[�������ɏ����o���Đ������A�������Ǝ������[�����Ă�m���ƌ������ł��傤�B
�@�@�@���@�����A���Ȃ��̕��������܂�m�n�ƌ���Ȃ����i�Ȃ�A�m�[�ƌ����Ă������̂��Ɩ��m�ɓ`����
�@�@�@�@�@ ���傤�B��łł��܂���ł����ƌ����Ă����邵�A�撣��߂��ăm�C���[�[�ɂȂ��Ă�����ł�
�@�@�@�@�@ �傤�B
�@ �V) ���Ԃ��ɂ���
�@�@�@��c��ō����A������Ƃ����Ȃ͂����̎��Ԃ����������Ƃ͂���܂��B�ꕪ��b���ɂ���
�@�@�@���傤�B
�@�@�@���@�u�R�O�������ō������悤�v �u�����܂łɂ��̎���������āv���@���Ԃ����K�������܂��傤�B
�@�@�������g�̎��Ԃ̎g�����ɂ��āA�`�F�b�N���I��������A�����̕��X�ɂ��Ă��ώ@���Ă݂Ă���
�@�@�����B�N�������Ԃɒǂ��Ă��炢�炵���肵�Ă��܂��B
�@�@���Ȃ��̕��������Ԃɒǂ��č����Ă���悤�ł���A��L���Q�l�ɃA�h�o�C�X�ł��邩�������
�@�@����B
�@�� STEP�Q�@�@�A�C�f�A�Ŏ��Ԃ���肭�肷��
�@�@���Ԃ���肭�肷�邽�߂̍H�v�����������A���Љ�܂��B
�@�@�P�j�����������邩�A���T�������邩�����߂�
�@�@�@�����P�ɁA��ƍ��ڂ��X�P�W���[���ɑg�ݍ��ނ̂ł͂Ȃ��B���������Ƃ��邱�ƁA���T�Ȃ��Ƃ��邱
�@�@�@�ƂƂ��āA�������g�ɑ��Đ錾���Ă݂Ă��������B�������I�ɍ�Ƃ�i�߂铮�@�t���ł��B
�@�@�Q�j�ړI�ӎ��m�ɂ���
�@�@�@��������@�t���ł����A���������ԁA�����Ԃ��ǂ��g�����A�ړI�ӎ��������Ď��Ԃݏo��
�@�@�@�Ă����B�q�����~�������̂����߂ɂ��َq�̊ʂɕS�~�ʂ����߂�C���[�W�ł��B
�@�@�R�j�s����������
�@�@�@�Ⴆ�A���N���B�ł��������Ă��ƌ���ꂻ���ł����A���N���ɂ͎O���ȏ�̓�������܂��B
�@�@�@�R�O�����N����1���ԕ��͌��ʂ�����܂��B���Ƃ��Ɖ����ɏo�Ђ��Ă����ɂ����܂����A��
�@�@�@�d�Ԃɍ����ĕ����A��Ђɒ�������l�ɂ���܂��ꂸ��d���Еt���āA�莞����͌����ǂ��d
�@�@�@��������B���ɂ���Ă���͑����ł��B
�@�@�@���x�݁A�T������P���ԁ@�����ł������̂ł����A�s�����������Ă݂�B
�@�@�@�����Ƃ�����ƕς��Ă݂�B�@���ꂾ���ł����Ԃ����܂��g���q���g�����邩������܂���B
�@���܂��ł����A
�@�� STEP�R �d�����łɂȂ�Ȃ����߂��@
�@�@���Ԃ�����Ȃ��č����Ă��邠�Ȃ��͎d�����łɂȂ��Ă��܂��B
�@�@�ȉ��̎���ŁA�����̎d�����œx���`�F�b�N���Ă݂ĉ������B
�@�@�P�j �c�Ƃ��Ȃ��ŋA�邱�Ƃɍ߈���������
�@�@�Q�j �����ŊԂɍ���������Ƃ��A�������ɂ��Ȃ��ƕs����
�@�@�R�j �y���x���ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��Ɖ�Ђɍs�����Ƃ�����
�@�@�S�j �������Ԃɒǂ��A ��������l���Ďd�������邱�Ƃ��Ȃ�
�@�@�T�j �c�Ƃ��Ȃ���d�������Ă���Ƃ���s���o��
�@�@�U�j �ŋ߂̋C���炵�Ƃ����A��i�⓯���ƈ��݂ɍs�������Ƃ����v���o���Ȃ�
�@�@�V�j �Ƒ��Ƃ��鎞��A�A�Q���ɂӂƎd�����v���o�����Ƃ�����
�@�@�W�j �ō�����҂����킹�ɒx�����邱�Ƃ�����
�@�@�X�j �ŋ߃X�J�b�Ƃ������Ƃ��Ȃ�
�@ 10�j ����Ȏd�������Ƃ����������ւ炵��
�@�@�P�O���ڂ̂��������ȏオ�Y������Ȃ炠�Ȃ��͗��h�Ȏd�����łł��B
�@�@�X�g���X�����܂��Ă���ɈႢ����܂���B
�@ ���Ԃ��Ƃ��ă����b�N�X����ƌ����Ă����X����ł��傤���A������������ł��d���̃y�[�X�𗎂�
�@�@���Ă݂���A���x�݂ɂ�����Ƃ����U��������A�T�������ł��̂�������A������Ƃ����C����
�@�@�݂Ă��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill06�@ �v���Ƃ��ẴR�~�b�g�����g
�@�� STEP�P�@ �R�~�b�g�����g�@�E�E�E�E�m���}�ł͂Ȃ�����̕\��
�@�@���Y�̃J�����X�S�[���b�n�n�̓o��ȗ��A�悭���ɂ��錾�t������܂��B
�@�@�R�~�b�g�����g���ւ��A����A�ӔC�Ƃ����Ӗ��ł����A
�@�@�J�����X�S�[�����ɂ�����R�~�b�g�����g�ͤ�u�����͂�����Ȃ��Ƃ���l�ł���Ƃ̐錾�v
�@�@�܂�A��m���}��ł͂Ȃ�����ꣂ̕\���ɂȂ��Ă���܂��B
�@�@�����܂ŋ����ӎv�\�������邩�ǂ����͕ʂƂ��āA�R�~�b�g�����g�����邱�Ƃɂ��A����̖ڕW�̒B��
�@�@ �E���B����^���ɍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�i�Ⴆ�j
�@�@�@���@�S�[������̓I�ȃC���[�W�Ƃ��đ�����B
�@�@�@���@��ɃS�[���ƃS�[���܂ł̋���(�M���b�v)���m�F����B
�@�@�@���@�s���Ɛ��ʂ̊W���������Ɣc������B�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�S�[���������ӎ����čs�����Ă���A�ǂ�Ȍ��ʂł����Ă��A������x�̒B�������c��ł��傤�B
�@�@�����ɂ���̂́A���̊����ւ̃R�~�b�g�����g�ł��B
�@�@�@�R�~�b�g�����g�@�� �@�u�S�ĂɊւ��ӔC�������Ɓv �ł�����̂ł��B
�@�@�܂��́A�������g�ɑ��ăR�~�b�g�����g���Ă݂܂��傤�B
�@�� STEP�Q�@ ����������
�@�@�R�[�`���O�ł́A���������邱�Ƃ̏d�v�����悭�b��ɂ̂ڂ�܂��B
�@�@��b��s���𒆓r���[�ɂ���Ǝ������g�ɁA����ɂ�����Ƃ����s�������c��܂��B
�@�@�����ł̕s���́A�Ⴆ�Έȉ��̂悤�ȏ̂��Ƃł��B
�@�@�@����b����������I�ȓ��������ŏI���A�������Ȃ��B
�@�@�@���b�̓r���ő��肪�ǂ����ɍs���Ă��܂��A���r���[�ɂȂ�B
�@�@�@���������ڕW���ݒ肳��Ă��āA�������B���Ȃ̂���ԉ����Ă���B
�@�@�@���g�D�ڕW�B���Ɍ��������������[�`�������A�ڕW���Â��B�������Ȃ��B
�@�@�R�~���j�P�[�V�����Ȃ�A�������Ă��炦�Ȃ��s���B�E�E����ȑO�ɁA������ƕ����Ă��炦�Ȃ��s���B
�@ �� ��b���Ȃ肽���Ă��Ȃ������������B�ł��傤���B
�@�@���̐l�ɘb���Ă����ʂ��@�Ǝv���Ă��܂��A���̉�b�̃`�����X�������Ă��܂��܂��B��i�ƕ�
�@�@���̊W�ł���ΐM���������Ȃ�ł��傤�B�@�X�g���X�����Ă����ς����܂�܂��B
�@�@�ƂȂ�A�R�[�`���O�̊�{�I�X�L����ϋɓI�ɒ���� ����ʓI�Ȏ�������飂̏o�Ԃł��B
�@�@��b����b�Ƃ��Đ�������悤�ɂȂ�X�g���X������ł��傤�B
�@�@�܂��A�u�r�W�����v�m�ɂ��āA�ڕW�Ɍ����Čv��𗧂ĂĂ������ƁA�J�����X�S�[���В��̂悤�ɁA�R�~�b
�@�@�g�����g���A�����̍s�����m���Ɋ��������Ă������Ƃɂ���Ă������͂Ȃ��Ȃ�ł��傤�B
�@�� STEP�R�@�@�v���t�F�b�V���i���͌p���I�Ɍ��ʂ��o��
�@�@�R�[�`���O�{���ł͂悭�A�p�����邱�Ƃ̑厖�����Љ�Ă��܂��B
�@�@���̃T�C�g�ł��Љ���S���t�̃X�C���O�̃C���[�W�B���K�𑱂��Ă��Ȃ��ƁA�����X�C���O�̃C���[�W��
�@�@����Ă��܂��܂��B
�@�@�����̃R�~�b�g�����g�����������邽�߂ɂ́A�p���I�ɍs�����Ă������Ƃ��s���ł��B
�@�@�p���͗͂Ȃ�A�N�ł��m���Ă��邢�����t�ł��傤�B
�@�@��鎞�͂��@�Ƃ������t�͗�܂��Ɏg�����Ƃ͂����Ă��A�����Ɏg���Ă͂����܂���B
�@�@��ɂ��B�����Č��ʂɂȂ���B�v���Ƃ��đ厖�Ȃ��Ƃł��B
�@�@�v���t�F�b�V���i���B�������t�ł��B�@�@���Ȃ��̒��́u�v���v�̃C���[�W�͂ǂ�Ȃ��̂ł����B
�@�@���b�X���v���A�c�A�[�v���A�v���싅�I��Ƃ����낢�날��܂����A�����A�E�ƂƂ��ĉ���������҂Ǝv����
�@�@���܂��B
�@�@������������Ӗ�������ł��傤�B��V��������ē����Ă��邠�Ȃ����A�v���T�����[�}���ł��B
�@�@�ł��A���̒��̃C���[�W�ł́A��Ɍ��ʂ��o���A���ʂɑ��ĕ�V��ҁB���ꂪ�v���ł��B
�@�@NBA�̃v���o�X�P�I��̓c���̃C���[�W������ɂ����܂��B�_��������Ȃ���A�����فB�p���I��
�@�@���ʂ��o���I�肾����NBA�ɂƂ��Ẵv���_��I��Ȃ̂ł��B
�@�@�v���ł��葱���邱�Ƃ͂ƂĂ���ςł炢���ƁA���̂��߂ɂ́A��ɑË����Ȃ����ƁB
�@�@�T�����[�}���́A�Ë��Ƃ̐킢�B�Ë��Ƃ̒��a�B����ȋC�����܂����A
�@�@���ʂ��o���Ȃ��T�����[�}���̓v���ƌĂ�Ȃ����オ�A���������܂ŋ߂Â��Ă���悤�ȋC�����܂��B
�@�@���T�A����Ë����܂����H�@���ʂ��o���܂����H�@�������g�ɕ����Ă݂Ă��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
Skill07�@ �p���g�̂Q���Ő��ʂ��グ��
�@��STEP1�@�@�Q�O�F�W�O�̖@��
�@�@�R�[�`���O�̖{���݂Ă���A�Q�O�F�W�O�̖@���Ƃ������t���o�Ă��܂����B�ǂ������Ӗ����ƒ��ׂĂ����Ƃ�
�@�@��A�Ȃ�ƁA���X���ȒʐM�����������̂g�o�Ƀ��|�[�g������܂����B�@
�@�@�v��ƁA
�@�@�19�`20���I�����Ɋ����C�^���A�̎Љ�o�ϊw�҃p���g�́A�w�v���x�̍���20���̐l���A�S�̂�80
�@�@���̊�^�����Ă���x �Ƃ����@���\�����B��X�̎Љ�ɓ��Ă͂߂�Ȃ礁w�g�D�̋Ɛт́A�D�G�Ȑl
�@�@�Q�O������S�̂̂W�O���̊�^�����Ă���x �Ƃ���@�w��c�ł́A�o�Ȏ҂̂Q�O������S�̂̂W�O���̔�������
�@�@�Ă���x�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���B�܂�A�������ׂ��d���̂����̂Q������������A�S�̂̂W����������
�@�@���̂Ɠ����ʂ̌��ʂ��o����B���퐶���̓K�p����Ȃ�A���̓��̂����ɂ�肽�������ӏ������ɂ��A��
�@�@�ʂQ���ɑ������镔����K�����s���邱�Ƃł���B�v
�@�@�Ƃ܂ŏ����Ă���܂����B
�@�@���X���Ȃ��ăR�[�`���O�I�ȍl������������Ă�����ł��ˁB
�@�@���́A�p���g�Ƃ͂p�b�ł����Ƃ���́A�p���[�g�}���l���o�����p���[�g�̂��Ƃł��B
�@�@�����A����Ȃ�m���Ă����B�Ƃ������������Ǝv���܂����A�p���[�g�}�������������̑傫�ȕ�����
�@�@�Q�`�R���̌����ɏW�����Ă���Ƃ������ƌ����o���A���̖��ɑΏ����悤�Ƃ����p�b�X�g�[���[�̑g��
�@�@���ĂɎg����̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
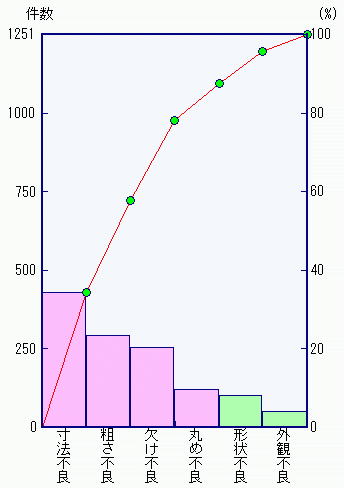
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꂪ�p���[�g�}�ł��B
�@�@���Ȃ��̕��������Ԃɒǂ��č����Ă���悤�ł���A��L���Q�l�ɃA�h�o�C�X�ł��邩������܂�
�@�@��B
�@��STEP�Q�@�@�^�[�Q�b�g�ƂȂ�Q�O����T��
�@�@���B�̓��X�̍s����G�l���M�[�ɂ͌��E������܂��B�@�R�[�`���O�I�ɍl����ƁA�������g�╔���A
�@�@�`�[���������p�t�H�[�}���X�����邱�Ƃ�]�ނȂ�A�K��@���ĂP�O�O�����ς��Ɋ撣�点��̂ł�
�@�@�Ȃ��A����̎d����v���W�F�N�g�̒��Ń^�[�Q�b�g�ƂȂ�Q�O���̎d���������A�����ɒ��͂��Ă������Ƃ�
�@�@�w������̂����ʓI���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�@�Q�O���̃^�[�Q�b�g�������邽�߂ɂ́A
�@�@�P����A�P�T�ԁA�P�����A������ŁA���Ȃ����Ɩ��シ��ׂ���ƁA���Ȃ�����肽����Ƃ����X�g�A�b�v
�@�@���邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�@���X�g�̒��ŁA
�@�@�@��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����
�@�@�A���ׂ�����
�@�@�B������ق���������������Ȃ�����
�@�@�C���̑�
�@�@�Ɋe��Ƃ�D�揇�ʕt�����ĕ��ނ���B��ςő�G�c�ɕ����āA���Ȃ��̃S�[���B����ɉ����Č�
�@�@����B
�@�@�@���P�O�`�Q�O�����炢�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�R�O���ɂȂ������č\���܂���B
�@�@�@���珇�Ɏ�����Ă݂܂��傤�B
�@�@
�@�@���ۂɂ͂Q�T���Ƃ��R�O���̕��������s�ł������_�ŁA�S�̖̂ڕW���B�������̂����m��܂���B
�@�@�@�@�@�i�Q�O���ƂƂ����������̂��̂ɂ������K�v�͂���܂���B
�@��STEP�R�@�@�S�[���������̂��̂Ƃ���
�@�@
�@�@���ʁi�p�t�H�[�}���X�j���グ��Ō�̂��Ȃ߂́A�������g�ł��B��Ђ�`�[���A�܂��Ă͏�i�̃S�[
�@�@���ł͂Ȃ��A�������g�̃S�[���Ƃ��ĖڕW���������Ă������Ƃ��A�p�t�H�[�}���X���ō��ɔ��������
�@�@���ł��B
�@�@�Q���̍s���ŁA�S�[�����B���ł��Ă���̂��A����m�ɂ��邽�߂ɂ́A�S�[���̒B��������m
�@�@�ł��邱�Ƃ��K�v�ł��B����Ɍ����Ȃ�A�������g�̃S�[�������邱�Ƃ��K�v�B
�@�@�S�[�����������g�̂��̂Ƃ����@���̂��߂ɂ́A�����Ŕ[�����A�����ŃS�[����ݒ肷�邱�Ƃ��O��
�@�@�ł��B
�@�@�@�@ �����A���Ȃ�����i�Ȃ�A�@�u�����͑���̒��ɂ���v
�@�@ �A ���Ȃ����g���ƂȂ�A �@�@�@�u�����͎����̒��ɂ���v �ł��B
�@�@��������̃S�[���A�������Ă���v���W�F�N�g�̃S�[�� �����Ȃ����g��������g���[������܂ŁA�O
�@�@��I�ɍl���Ă݂Ă͂������ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill08�@ NO�ɂ�������������
�@�@���̒��ɂ́A���ł��m�n�ƌ����Ă��܂����i�܂�X�^�[�g���C�����m�n�j�Ɖ��Ƃ��x�d�r��T�����Ƃ����
�@�@�i�X�^�[�g���C�����x�d�r�j�����܂��B�o�����X���Ƃꂽ�x�d�r�A�m�n��������̂���ԗǂ��̂ł����A��
�@�@�X�������������A���i�ɍ��E����镔���������悤�ȋC�����܂��B
�@�@�Ⴆ�A��i�ɂm�n���Č����܂����B�m�n�ƌ����Ȃ����ɂ͎d�������܂�C���A�c�Ƃ���������
�@�@�����j�o���Ă�邩���A�Ȃ�Ƃ���肭�肵�Ă�������Ă��Ȃ��̎���ɂ�����ł��傤�B
�@�� STEP�P�@�m�n�ƌ����Ȃ����R
�@�@���́A�m�n�ƌ����Ȃ��̂ł��傤�B
�@�@�@�� �e�������@�@�@�@�@�@�� �@���i�I�ɐl���T�|�[�g����̂��D��
�@�@�@�� �l�ɂ����炵�����@�@���@ �����I�Ȑ��i
�@�@�@�� ��i�ɋt�炦�Ȃ�
�@�@�@�� �����ȊO�ɂ͂ł��Ȃ��Ǝv���Ă���@�@�� �@���M�ߏ�
�@�@�@�� �m�n�ƌ����Ƒ��肪����Ǝv���Ă���
�@�@�@�� �m�n�������������Ǝv���Ă���
�@�@���ɂ����R�͂��邩������܂���B�ł��A���Ȃ������l���̕������y�����܂Ƃ߂Ďd���̎w��
�@�@�����闧��ɂȂ�����́A�d�������܂��Ă��܂��A���ɂ͔[�����肬��ŏ[���`�F�b�N�ł��Ă��Ȃ�
�@�@���ʕ����o�Ă��邩������܂���B�d���̎��̒ቺ�ł��B
�@�@���̈����d���ł́A���ʂƂ��đ���̈˗���B���ł��Ă��܂���B�������A���Ȃ��̐��_�q����
�@�@�ǂ��Ȃ��B
�@�� STEP�Q�@������ɂm�n�ƌ���
�@�@���Ȃ��̕���ł����o���Ȃ���Ƃ͕ʂƂ��āA������łł��邱�Ƃ𗊂�ł���������\��������
�@�@�ł��B
�@�@����ɑΏ�����ɂ́A�d�����������m�ɂ��邱�Ƃł��B������m�łȂ��Ɓu�O���
�@�@����Ă��ꂽ����Ȃ����B�v�ƌ���ꂩ�˂܂���B
�@�@���ɊǗ�����̏ꍇ�A�����傩��̓T�[�r�X����Ǝv��ꂪ���ł��B
�@�@�Ⴆ�Έȉ��̂悤�Ȋ��݂��Ă݂Ă͂������ł��傤���B
�@�@�@������ɂx�d�r�Ƃ�����i��j
�@�@�@�@�� �����Ɓ����͂��ł�������B�ł��[���͂R����B
�@�@�@�@�� �����ɂ��ẮA�]�͂̂��鎞�����B
�@�@�@�@�� �~�~�͊e���傪�����ł�邱�ƁB
�@�� STEP�R�@�����ɂm�n�ƌ���
�@�@��G�b�W�ȕ��������v�̍��̒��ŁA�����ւ̂m�n�̌�������������܂����B
�@�@�v�_�̂݁A�����炢���Ă݂܂��傤�B
�@�@�����ɂm�n�ƌ����Ƃ��̃|�C���g
�@�@�@�� �͂�����m�n�ƌ����i�m�n�ƌ��߂���B���ɂ��Ȃ��j
�@�@�@�� �m�n�̗��R�m�ɂ���i��̓I�����Ŕ[���������߂�j
�@�@�@�� ����̌��������������蕷���i�m�n�ɖ��������c���j
�@�@�@�� ��ɂm�n�ł͂Ȃ��i�����ӌ��͎�����j�@
�@�@�@�� �x�d�r�̉\����������ƒNj�����i�{���ɂm�n�ł����̂��j
�@�� STEP�S�@��i�ɂm�n�ƌ���
�@�@�N�ł���i�ɂm�n�͌����ɂ������̂ł��B�ł��A�O�q�̒ʂ�A���������Ĉ������d���̌��ʂ��s�\
�@�@���Ȃ�A�������Ė��f�������邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B
�@�@�� �o���Ȃ�������`���� ��
�@�@�����I�ɕs�\�Ȃ�A����̂܂܂����������Ȃ��ł��傤�B���Ȃ��̏�i�ɂ͂��Ȃ����܂߂������̋�
�@�@���z�����R���g���[������`��������̂ł��B��������A��i�ƃR�~���j�P�[�V���������Ă���A
�@�@���Ȃ��₠�Ȃ��̃`�[���̖Z������m������Ŗ����������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�@�@�������A���p�Ƃ̃o�b�e�B���O�ł�������������܂���B�܂��A��i�̈˗����Ɩ����̂��̂ł͂Ȃ��A
�@�@�q��̐ڑ҂ւ̓��Ȃ������肷�邩������܂���B
�@�@��i�̈˗����A�Ɩ����߂��A�P�Ȃ�v�]�Ȃ̂��͊W����܂���B�T�����[�}���ł���ȏ�͎d��
�@�@�͏�ɗD�掖���ł��B
�@�@�厖�Ȃ��Ƃ͂R�B
�@�@�P�j���Ȃ��̎��p�͍ŗD�掖�����H�i�ً}���Ԃ��H�j
�@�@�Q�j���Ȃ��̏�i�̈˗��͋Ɩ��ɒʂ��邱�ƁA�������́A���Ȃ����̌�����~���j�P�[�V������[�߂�
�@�@�@ �̂ɖ𗧂��Ƃ��H
�@�@�R�j�����Ă��Ȃ��̉��l�ρi�s����j�͉����H
�@�@������ꗧ��ōl���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��A�@�����́A���Ȃ��̒��ɂ���܂��B
�@�@�q��Ή��������̎ɂȂ���d�v�Ȏd���ł��B
�@�@�f�킴��Ȃ��ꍇ���A��֕��@���Ă���B�[���������߂�iSTEP�T�Q�Ɓj���̐��ӂ͕K�v�ł��B
�@�@�ł������ŁA���Ȃ�����i�ŁA�������m�n�ƌ����̂�Y��ł���Ƃ�����ǂ��ł��傤�B�@�@���Ȃ���
�@�@����������������Ɣ\�͂����Ă���邱�Ƃ����҂���Ȃ�A�������g���ŗD��ƍl���邱�Ƃ�����
�@�@�����D�悵�Ă����܂��傤�B
�@�@�����܂ŁA�Ɩ��Ɏx��̂Ȃ�����ł����B�d���̎�͎d���ŕԂ��Ă��炤�B
�@�@��������Ȃ��ł�������ŁB
�@�� STEP�T�@�q��ɂm�n�ƌ���
�@�@���肪�q��Ȃ�A�ʂƌ������āu�o���܂���v�Ƃ��������Ă��A�[�����Ȃ��ł��傤���A�Q�x�Ǝd��������
�@�@�������m��܂���B
�@�@��{�I�ȍl�����́A�����ɂm�n�ƌ����ꍇ�Ɠ������m�n�ƌ���ꂽ���̔[���������߂邱�Ƃɂ���܂��B
�@�@�� �m�n�ɂ������������� ��
�@�@�܂��́A�˗����Ă����������A���ɕ����I�ɖ����ȗ��R�Ƃ����悤�ɑ���𗧂Ă������������邱
�@�@�Ƃ͍Œ���K�v�ł��B
�@�@�Ⴆ�A
�@�@�u���˗������������Č��h�ł��B���A��Ǝ������d�Ȃ�d�������Ɉ����Ă���܂��āA�ӔC������
�@�@�đΉ������Ă��������Ȃ����Ԃ��l�����܂��B�v
�@�@�����A�Г������ł���\��������̂Ȃ�A���ۂɒ������Ă݂邱�Ƃ��K�v�ł��B���������肾���āA
�@�@���ɗ��ޏꍇ�̎��Ԃ̗]�T�͗~�����͂��B
�@�@�u�P�����������Ԃ����������Ȃ��ł��傤���B�v
�@�@�Q���ł��A�R���ł������ł����A���炭�Ƃ���Q��R�����Ȃ�ĞB���Ȃ��Ƃ������Ă͂����܂���B����
�@�@�͖��m�ɂ��܂��傤�B���ӂ͎����Ȃ���Ȃ�܂��A���ӂƞB�����͕ʂł��B
�@�@�����Ċ��҂��������߂�����m�n�Ƃ����^�C�~���O�͑��߂ɍ�褂m�n�Ȃ�m�n�Ɩ��m�ɓ`���܂��B
�@�@�ŋ߂ł́A��ЋA��ɓۂ݂ɂ������Ă��A�t������������Ȃ���҂������Ȃ��Ă���悤�ł��B
�@�@�ۂ݂ɃP�[�V�����ɉ��l�������o�����A�T���܂łɎd�����撣��Ƃ����l�����̕��������Ă��܂��B
�@�@��Ƃ̏������s�����Ȍ��݂ł͂������̍l�����ł͂���܂����B������Ǝ₵���ł��ˁB
�@�@�������A����A�������̃��`�x�[�V�����[�֖{�i���҂͏����j�����Ă����Ƃ���B�ȉ��̂����肪�A
�@�@�u�ۂ݂ɃP�[�V�����̗ǂ������ł͂Ȃ��B���͂ƃR�~���j�P�[�V������[�߂�`�����X�͑O�����Ȑl�Ԃ�
�@�@���čő���ɗ��p���ׂ��B�v�ƁB
�@ �O�����ȕ��X�ւ̃`�����X�͗p�ӂ��Ă����܂��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill09�@ �������ɂȂ�
�@�@�܂��́A�����炢�B
�@�@�R�~���j�P�[�V�����̌��_�͑o�����̉�b�ł��B
�@�@��i�̑�����̉�b�ƕ����̑�����̉�b�B��y�ƌ�y�A�e�q�A�j�������ē����B
�@�@�o������̉�b�������ď��߂ăR�~���j�P�[�V�����ƌ�����̂ł��B�@����I�ɒ��邾���ŃR�~���j�P
�@�@�[�V���������Ă���Ǝv���̂͊ԈႢ�ł��B
�@�@�R�[�`���O�ŃR�~���j�P�[�V�����ɂ��ĉ������ۂɁA�悭�L���b�`�{�[�����o�����̉�b�̗�Ƃ�
�@�@�Ď��グ���܂��B�@�����Ă͕Ԃ��A�����Ă͕Ԃ��B
�@�@���肪�Ԃ��O�ɂQ���߁A�R���߂𓊂��Ă͂����܂���B�@����͎~�߂��ꂸ�ɑގU����ł��傤�B
�@�@���܂��L���b�`�{�[���ɂȂ�Ȃ��Ȃ�A����ɉ��������������āA�܂�������y���݂𗝉�������B
�@�@���ꂪ�������蒮���Ƃ������Ƃł��B
�@�@����́A���Ȃ����g���������ɂȂ��āA����̉�b��m�E�n�E�������o�����Ƃ��l���Ă݂܂��B
�@�� ���Ȃ����b�������Ȃ邱�Ƃ��ĉ��ł����H�@�@ �@������̓��ӕ��쁄
�@�@��������̂���b���U����Ή�b�ɎQ���������Ȃ�܂����A����Ɉ���i��ŁA���ӂȂ���
�@�@�ɂ��ĕ������A�b�������Ȃ�܂��B
�@�@�������Ǝv��ꂽ��A���h����Ă���ȂƎv�����肷��A�����S�����������ĕK�v�ȏ�ɘb����
�@�@���͂Ȃ�܂��B
�@�@�N�����ē����ł��B�@�@����̓��ӂȂ��Ƃ��������蒮�����Ƃ���b�ݏo���܂��B
�@�@���肪���ӂȂ��Ƃ��ώ@���܂��傤�B���ꂪ�A���Ȃ����w�Ԃׂ��_�Ȃ̂ł�����B
�@�@�厖�Ȃ̂͌����ɂȂ邱�ƁB���͂̐F�X�Ȑl����A�������w�Ԃ��Ƃ�����Ǝv�����Ƃł��B
�@�@��i�ł��A��y�ł��A�����ł��B�������������y���炾���Ċw�Ԃׂ����Ƃ͂�������͂��ł��B
�@�@�Ⴆ�A���s���肵�Ă���҂��炾���Ď��s�����������w�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B
�@�@����͕K���A���Ȃ��ɂƂ��ăv���X�ɂȂ锤�ł��B
�@�� ���Ƃɂ��ł���������@�@�@�������̑��Ɓ�
�@�@���Ƃ́A����̌������Ƃ��Ă���A�����ł��Ă��邱�Ƃ̕\���ł��B
�@�@����Ɉ��S��^���A��b�������o���܂��B
�@�@�ł�����������낤�Ǝv���Ȃ�A�����������Ƃ̋������k�߂邱�Ƃ��K�v�ł��B�@����̌������Ƃ�
�@�@�����̑̌��̂悤�Ɏ~�߂�B�@�܂苤���̂��鑊�ƁB
�@�@�Ⴆ�A�������ɂȂ��ė��Ђ��Ă��ꂽ�����A�u�O�͏�����B�v�@�ƌ����A
�@�@�u���������ł����B�v�@�ł͂Ȃ��@�u���������ł��ˁB�v�@�Ȃ̂ł��B
�@�@�������A����Ō����̂ł͂Ȃ��A�ꏏ�ɂ炳�������邱�ƁB���ꂪ�����ł��B
�@�� �Ƃ����ɂ������肩��̋�����
�@�@���̒��ɂ͂Ƃ����ɂ��������������̂ł��B
�@�@���ɂ͑���ɂ���Đڂ�����ς��邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�@�� ���M�ƂŤ��ɑ����ے肷�鑊��ɑ��ẮA
�@�@�@�@�u���Ȃ��̒m�b��݂��ė~�����v���A��������ԓx�Őڂ���B
�@�@�� �����Ť��������l���鑊��ɑ��ẮA
�@�@�@�@�e�[�}�m�ɂ�����ŁA�l���鎞�Ԃ�^���Ȃ��畷���B
�@�@�� ���ƂȂ���������ɕ������ɉ���Ă��܂�����ɑ��ẮA
�@�@�@�@�ے肹���ɑ��Ƃ�ł��Ȃ���A���ł��b���Ă��炤�B
�@�@�� �b���D���̑���ɂ́A�E�E�E�E�E����ɘb�����Ă����܂��傤�B
�@�� �����ė�߁@�@�i�����p���j�@
�@�@�N�ɑ��Ă��ʂ��邱�Ƃ́A��߂ł��B
�@�@��������̂Ȃ�A����������܂��傤�B�@��������т�����������̌��t�ł��B
�@�@�u����ǂ̎d���ɖ𗧂������ł��B�v �Ƃ� �u�������Ɉ���߂Â��܂����v �Ƃ�
�@�@�ȒP�Ȋ�т̌��t��t�������邱�ƂŁA�܂������Ă��������ȂƎv���Ă��炦����K���Ȃ̂ł��B
�@�@�ł��A������o�C���̓_���ł���B���̒��͏��������ł��B���݂��̂�����Ƃ����T�|�[�g�Ɏd�����x
�@�@�����Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��̂ł��B�S���炨��������܂��傤�B
�@�@�܂����A�ӂ�Ԃ��Đl�ɋ���������͂��Ȃ��Ǝv���܂����A�l�ɂ��̂𗊂ނƂ��͐S����������
�@�@���グ�鎋�������̋C������\�����܂��B
�@�@���肾���āA�����ė~�����Ƃ����ԓx���ɂ��ݏo�Ă����Ƃ͌���Ȃ��͂��B
�@�@�A���A�ڋ��Ɍ����邱�Ƃ�����̂ł����ӂ��������B
�@�� �R�~���j�P�[�V�����p��𗧂Ă�
�@�@�R�~���j�P�[�V�������͋������ł��B
�@�@�R�~���j�P�[�V�����X�L�������p���ċ������ɂȂ���@���l���Ă݂܂��傤�B
�@�@�� ���b�e����\��Ȃ� ��
�@�@�R�[�`���O�̊�{�̈�ł��B�@���̐l�͂��������l���������ł��Ȃ��B�������ߕt�����u�Ԃ��Ȃ���
�@�@�����͎����܂��B�@�b�����Ă��Ă������Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@����̉\����M���܂��傤�B
�@�@�� �����̍l���ƈႤ�Ǝv��������Ƃ����Ĕے肵�Ȃ� ��
�@�@�l�����͐l���ꂼ��ł��B�����̍l���ƈႤ����Ƃ����Ă����ے肵����A�������肷��̂͊�
�@�@�Ⴂ�ł��B
�@�@����ȕ����R�~���j�P�[�V�������ɂȂ邱�Ƃ͗L�蓾�܂��A����̖��m�Ȋ��Ⴂ�ł��Ȃ�����A
�@�@ �ے肷�邱�Ƃɂ͈Ӗ�������܂���B
�@�@�Ƃ͌����Ă�����ȕ��͂������ے肵�Ă��܂��܂��B�@�ł��A������͂���܂��B
�@�@�ے肵�����Ȃ�����A���̂悤�ȍl���Ɏ���������̋C�����◧����l���邭��������̂ł��B
�@�@�����ƒP���ɁA�ے肵�����Ȃ�����T������ł������̂ł��B
�@�@��荇�����P�O���ԁA�ے����߂Ă݂āA���͂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������D�]���邩�ǂ����ώ@���Ă�
�@�@�ĉ������B
�@�@�� �咣���������Ƃ����k�Ƃ��Ď��������� ��
�@�@�咣�Ƃ����ƈ���I�ɂȂ肪���ł��B
�@�@���k�Ƃ��Ď��������ӌ����Ȃ��璲������B���������˂Ȃ����e�ł����k�����������f��
�@�@��������ƂȂ�Ύ~�ߕ����Ⴂ�܂��B
�@�@����͕����ɑ��Ă������ł��B����I�Ɏw�����߂���̂ł͂Ȃ��ꏏ�ɍl�������Ƃ�C���ꂽ�Ƃ�
�@�@����`�x�[�V�������A�b�v���܂��B
�@�@�� ����������Ȃ� ��
�@�@�ȑO�V���[�g�R�����Ƃ��ĉ���������e�ł��B
�@�@�����A�^���ʂŌ����������č���͓̂G������A����̊ԈႢ�𐳂����Ƃ��鎞�����ɂ��܂��傤�B
�@�@����̉E�ߑO���ꂪ�x�X�g�ł��B
�@�@�����w���ƌ������̓Z���t�R�[�`���O�ȓ��e�ł����A�m�E�n�E������邾���łȂ��A������Ƃ���
�@�@��ۂɂ������l�����ōs������X���[�Y�ɂȂ�Ǝv���܂��B�@�@�Q�l�ɂ��Ă݂ĉ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill10�@ ����ۂ����Ȃ���ς���
�@�� �v�����[�O�@���ΖʂōD�������A�������
�@�@�d�����A���ΖʂŃZ�[���X�ɗ��������A�E���������Ă���w������ɂ�����邱�Ƃ��悭
�@�@����܂��B
�@�@�Z�[���X�ƌ����Ă��A�S���̔�э��݂ł͂Ȃ��A�����̎����̐V�S���҂ł�������A�b����
�@�@�����Ǝ�̕��̃A�|�ɉ������肵�Ă���킯�ŁA���Ȃ��Ƃ����̂ق��ɂ͎��Ԃ������Ęb�����f��
�@�@���Ƃ����ӎu�͂���킯�ł��B
�@�@�w���ɂ��Ă������B�������Ȃ�̗p�ɂȂ������Ǝv���ĉ���Ă���̂ł��B
�@�@�Ƃ��낪�قƂ�ǂ̏ꍇ�A����������̏u�ԁA���̓��̒��Ɂ~�i���_�j�⁛�̕����������т�
�@�@���B
�@�@���_��������ł��܂��ƁA�b�����Ă��Ă����̂��}�C�i�X�ȕ������ڂ����Ă��܂��܂��B
�@�@�܂��A���A���������x�Ȃ̂ɁA����Ƀ}�C�i�X�C���[�W������Ă��܂��A����ۂ������Ƀ}�C�i
�@�@�X�����炱�����Ǝv���܂��B
�@�@����ۂ��^�������ςɂ����Ȃ��̂����m��܂��A�l�̐S�͂��̐���ςɍ��E����Ă�
�@�@�܂��܂��B
�@�@���ɂ́A����̕����킴�킴�}�C�i�X�̃C���[�W�������邽�߂ɗ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���
�@�@�������ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�@�@�t�ɁA����ۂ��v���X�C���[�W�ł���A������M�S�ɘb���Ă���邩������܂��A�R
�@�@�~���j�P�[�V�����̉��s�����[�܂邩���m��܂���B
�@�@����́A����ۂ��t��ɂƂ��ăR�~���j�P�[������[�߂���@���l���Ă݂܂��B
�@�� STEP�P ����ۂ��ĉ��H
�@�@�ł́A����ۂ��ĉ��ł��傤�B
�@�@���炭�́A����̊O���i�����A����A���^�A�������܂��j�{���A�̎d�� ����ȂƂ���ł��傤���B
�@�@���Ȃ��́A�������l�ɗ^�������ۂ𗝉����Ă��܂����B
�@�@���͒��g�ŏ����B
�@�@�����v���Ă�����́A����̂��Ƃ��l���Ă��Ȃ��̂ł��B�@�d�����̑��Œ����t�������ɂȂ邩��
�@�@�m��Ȃ����肪���T�����A�u�₩�ł����������C���������ł��傤�B
�@�@�܂��͎��������߂ĒN���ɉ���ɁA�ǂ�ȕ�����ԓx�Ȃ̂�������̎�����U��Ԃ��Ďv��
�@�@�o���Ă݂ĉ������B
�@�@�������ς肵�Ă܂����H�@��ꂪ����������Ă��܂��H
�@�� STEP�Q�@�g�����Ȃ݂𐮂���
�@�@�V���L���ɗD�G�ȉc�ƃ}���̐S�|�����ڂ��Ă܂����B
�@�@���킭�A�������߂ɖʉ�ꏊ�ɓ������A���Ńl�N�^�C�┯�̗�����`�F�b�N���A���������̂�҂��A
�@�@���ԋ߂��ɂȂ��Ă������Ɋ���o���Ƃ̂��Ƃł��B
�@�@�������P�[�X�ɂ����܂����g�����Ȃ݂͑���ۂ̏d�v�ȃ|�C���g�ł��B
�@�@�u�h�o�Ƃ̖ʉ�̍ۂ͑���̊�Ƃ̐��i��Е��ɍ��킹�āA���Ă����X�[�c��C�V���c�A�g�ɕt
�@�@���鏬���܂ŋC���g���Ƃ����������邻���ł��B
�@�@�����ő厖�Ȃ̂́A��͂葊��̂��Ƃ��l����Ƃ������Ƃł��B
�@�@�����������Е��̊�ƂɃL���L���L���̊i�D�͂��Ă����Ȃ��ł��傤�B
�@�@����̋C�ɂ����O�����o����̂́A�s�o�n�ւ̔z���⑊��̎Е��̉����ד����Ȃ��؋��ł��B
�@�@�d���̃p�[�g�i�[�Ƃ��đ��������Ƃ͎v���ɂ����ł��傤�B
�@�@��قǗD�G�Ȏd����T�[�r�X���o���邱�Ƃ��ŏ����画���Ă���C�ɂȂ�Ȃ���������܂�
�@�@�B
�@�@���ɋC�������ق��������̂́A�Ⴂ���̔��^�╞���B
�@�@������̒��Ԃ⏗���ɂ͎�悤�ȃt�@�b�V�����B�Ⴆ�h���}�ɏo�Ă������ȃt�@�b�V���i�u����
�@�@�ڂ��ڂ����͗v���ӁB�N�z����Ƃ̕t�������������؋��ł�����܂��B
�@�@�������Ȃ����f�U�C�i�[��A�[�e�B�X�g�ł͂Ȃ��Ȃ�A�N�z���オ�ǂ��~�߂�̂��l���Ă݂�
�@�@�ق�������ł��B
�@�� STEP�R�@�����Ɏ������F�A���邭������F���Ēm���Ă܂����H
�@�@�w���͏A��(�A�E����)�{�����ĂȂ��̂��ȂƎv���Ė{���̏A���{����ɂ��Ă݂܂����B
�@�@����ƁA�ڂ��Ă��邶��Ȃ��ł����A���̂��ƁB
�@�@�ƊE�ɉ�킹���X�[�c�A���C�V���c�A�l�N�^�C�̐F�B�����𖾂邭�݂���F�B��
�@�@�F����{���ɍs���Ȃ���ł����ˁB�����Ȃ���Ύ����Ɏ��M������̂����Ԓm�炸�Ȃ̂��B
�@�@1000�~������ƂŎ�ɓ�����Ȃ�ł����ǂˁB
�@�@�{���ɂ́A���i�ʂɎ������F�A�����̐��i�𖾂邭������F�A�����̋C������\������F�����
�@�@�������̂܂ł���܂����B�ʔ����̂Ŗ{���Ńp���p���Ƃ߂��邭�炢���Ă����������m��܂���B
�@�@�@�@�i�ւ��[�A����Ȃ̂���̂Ƃ��������ł��B�j
�@�� STEP�S�@���������ĉ��H�@�u�₩�����ĉ��H
�@�@�Ⴆ�A�Ăɂ������ꍇ�A���������ȕ��Ȃ�㒅�𒅂ĂȂ��Ă��C�ɂȂ�Ȃ��̂ɁA�����Ă�
�@�@�炻���Ȋ�̕��ɑ��ẮA�t�ɉ��̏㒅�𒅂Ȃ��̂��ƋC�ɂȂ�܂��B�@
�@�@�@�i������͑������Ə㒅�𒅂Ă�̂ł����B�j
�@�@�������͊O���痈�Ă���̂ŁA�������Ȃ�A�㒅��E���悤�Ɋ��߂܂��B
�@�@�������A�r�W�l�X�Ől�ɉ�ړI�́A�����Ă炢�Ɛ������邽�߂ł͂���܂���B
�@�@�����͑f���炵���T�[�r�X�⏤�i�A���ɂȂ����l�ς���邱�Ƃ��\�Ȃ̂��Ɛ������邽��
�@�@�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@����������\������ɂ���������A�����̐������Ă���鑊��ɉ�����Ƃ̊�т�A������
�@�@���炵�����i�̊J���E�̔��Ɋւ���Ă����т�\�������ق��������Ɨǂ��͂��ł��B
�@�@�ł́A�ǂ�����āB�E�E�E�債�����Ƃł͂���܂���B
�@�@��������������A������Ƃ����y�������Ȋ����������̂ł��B���̂��߂ɂ����i�A�d���ւ̂��
�@�@��������ɐ��������������邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�@����ȂɊȒP����Ȃ��B�E�E�������A�͂��߂Ă��̃T�C�g��ǂޕ��ɂ͓�������m��܂���B
�@�@�ł��q���g�͉��x��������Ă��܂��B
�@�@�d���̐��ʂ������̐����Ƃ��čl���A���̂��߂̖ڕW��ݒ肵�Ă����@���X�B
�@�@�悤���v���X�v�l�������Ƃł��B
�@�� STEP�T�@�����čŏ��̈��A
�@�@����ۂ��v���X�ɂ���b�����Ƃ������̂�����܂��B
�@�@�� �܂��͈��A ��
�@�@�u����ɂ��́vor�u�͂��߂܂��āv���̌�ɂ����ꌾ�����܂��B���Ԃ�����Ă��ꂽ����B��������
�@�@�̒����Ă��ꂽ����ȂǁB
�@�@���}������ꍇ���A�u�Z�������ς݂܂���B�v�u���������ł��傤�B�ǂ����㒅��E���ʼn������B�v��
�@�@�������Ƌ��������߂Č������Ƃ��K�v�ł��B
�@�@������O����Ǝv�����B�@�S���猾���Ă܂����B
�@�@�����A�|����鎞�������ۂ͎n�܂��Ă��܂��B
�@�@�u����ł���̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B�v�������A���i���X�b�Ƃ��ĂĂ͌����܂���B
�@�@�厖�Ȃ͓̂����̐l�Ƃ̐ڂ����ł��B
�@�@�� �����Ė��O���Ă� ��
�@�@
�@�@���ΖʁA�������͖ʎ��̔�����������Ƃ̋������߂Â�����@����͖��O���������ƌĂԂ���
�@�@�ł��B
�@
�@�@�u�ے��v�ł͂Ȃ��A�u�����ے��v
�@�@���O���ĂԂ̂́A���݂����A���̑��吨����A����̂P�l�ɕς���Z�ł��B����͍��R���Ŏ���
�@�@�f�[�g�ɂȂ���Z�Ƃ��Ă��悭�Љ��Ă��܂��B
�@�@�� ��b���n�܂����� ��
�@�@���ӓ_������������܂��B
�@�@�@�E�F�B���t���g������A�����̃y�[�X�ň���I�ɘb�����肵�Ȃ��B
�@�@�@�E�b���̗���m�ɂ��A�ł���Ό��_�����ɘb��������B
�@�@�@�E����̘b�ɂ͓K�x�ɑ��Ƃ�ł��A�������Ă��邱�Ƃ��ӎv�\������B
�@�@�@�E����̘b�ɊS�����痦���ɕ\������B
�@�@�@�@�u�w�͂���Ă���̂ł��ˁv�u�����ł����A������J���ꂽ�ł��傤�B�v
�@�@�@����A�R�[�`���O�X�L���ŏЉ����@�������炢���Ă݂ĉ������B
�@�� STEP�U�@�厖�Ȃ̂́A����
�@�@�ڂ͌��قǂɂ��̂������B�N�ł��m���Ă��錾�t�ł��B
�@�@�Ȃ̂ɁA�ڂ������j���ł�������悭��������Ⴂ�܂��B �l���������鎞�ɖڂ���ɂ��炷�̂��K��
�@�@�ɂȂ��Ă�����͑����悤�ł����A������l����邱�Ƃł͂���܂���B
�@�@��������Ƒ���̖ڂ��݂�B�ɂ�߂����炾�߂ł���B
�@�@�R�[�`���O�̓���Z�~�i�[�ɍs���ƁA�ڂ��܂߁A�����̕\�����ɂǂ�Ȉ�ۂ�^���邩�Q�l��g
�@�@�Ŏ������肵�܂��B
�@�@���邢�\��A�Â��\��A��т̕\��B
�@�@�ʂɉ��Z�����v����킯�ł͂���܂���B���Ζʂ̑���ɊԈ������ۂ�^���Ȃ����߂ɁA��x��
�@�@���̕\����Ċm�F���Ă݂ĉ������B
�@�@�Г��ŃR�[�`���O��@��������Ă���ƁA
�@�@�@�u�R�[�`���O�Ƃ͑���ɛZ�т邱�Ƃ��H�v�Ƃ��u�R�[�`���O�͉��Z���H�v�Ƃ�
�@�@�@�u����ɍ��킹��C�͂Ȃ��B�����͑f�̂܂܂ł����B�v
�@�@�Ƃ��������������Ȃ�̊����ł�������Ⴂ�܂��B
�@�@���́A
�@�@�u�R�[�`���O�Ƃ͑O�����ɐ����邽�߂ɖ{���̎����ɋC�t���A���������܂��\�����邽�߂̋Z�ł��B�v
�@�@�Ɛ������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill11�@ �v���X�v�l�Ŋ����
�@�@�����Ƃ������t�ɂ͉��ƂȂ����r���[�ȃC���[�W������܂��B�����Ă��܂��u�Ë��v�B
�@�@�ł����̐��̒��A�����̂��Ƃ������Ȃ���ΐ����Ă����܂���B
�@�@�u�Ë��v�ł͂Ȃ��A�u���a�v�Ƃł��������ق����K�����m��܂���B�����̈ӌ����ő���I�ɔ�
�@�@�f���ꂽ���a�ł��B
�@�@�ł��A�����͉䖝�����̂ł͂Ȃ����a�����̂��Ɩ��������Ɍ����������Ă���ƁA�����~���s��
�@�@���������邩���m��܂���B
�@�@����́A�v���X�v�l�́u�����v�ł��܂��������R���g���[�����Ă������Ƃɂ��čl���Ă݂܂��B
�@�@�� �l�K�e�B�u�Ȋ����͂�߂悤
�@�@������O�ł����A�}�C�i�X�v�l�̊����͍ň��ł��B���͂ɑ��Ă����e��������܂��B
�@�@�u����������ĉ�Ђ͕ς��Ȃ���v
�@�@�u�撣�������ċ�����������킯����Ȃ��v�I�ȃZ���t�͐E��̕��͋C�� �i�i�Ɉ��������܂��B
�@�@����ȃZ���t����������������A���̏�Ŕے肵�܂��傤�B
�@�@�u����Ă݂Ȃ�����킩��Ȃ��v�@�u�������g�̐����ɂȂ����������Ȃ����v���B
�@�@���]�є��N���@�����i���ł��B
�@�@�������A���Ȃ����g���Ɩ��A�����̐����E�L�����A�J���ɂ��Ă�������Ƃ����l���������Ƃ�
�@�@�O��ł��B
�@�@�� �����Ȃ����R
�@�@�d���ō� (����) ���l�߂Ă��܂����A�l�ƂƂ��Ƃ�c�_���Ă��܂����B �������Ȃ�����藧�ĂĂ����
�@�@�ł��傤�B
�@�@�d�����y�����B�@�c�_���y�����B
�@�@�ł��A���͂̕��X�̖��f�ɂȂ��Ă��Ȃ����A�悭�l���Ă݂ĉ������B
�@�@�����A������`��A�������A�v���C�h�����Ȃ�����藧�ĂĂ���̂Ȃ�A���̂�������v���C�h�ɉ�
�@�@�̈Ӗ�������̂�����x�l���Ă݂ĉ������B
�@�@�{���K�v�Ȏ��ȏ� �i�I�[�o�[�X�y�b�N�j �̂��Ƃ����邱�Ƃ��A�����̎��Ȗ����ɂȂ��Ă�����A����
�@�@�d�����a���ɂȂ��Ă���\��������܂��B
�@�@�܂��A�����̍l������ɐ������Ǝv�����Ƃ͂ƂĂ��댯�ł��B�@�����ǂ�����œ����邱�ƂȂ�Ĥ
�@�@�قƂ�ǂ���܂���B
�@�@�u�l�̐��������[���͂���B�v�ƍl���Ă����ق����A�l�̋C�����◧��𗝉����悤�Ƃ����C�����ɂȂ�
�@�@��͂��ł��B
�@�@�� �v���X�v�l�Ƃ��Ă̊y�ώ�`
�@�@�v���X�v�l�̊y�ώ�`�ɂ�銄���͂��Ȃ����~���܂��B
�@�@�Ⴆ�A��i�ɓ{��ꂽ���A
�@�@�@�E�}�C�i�X�v�l�Ȃ�u�{���Ă܂ł���Ă��Ȃ��v�ł����A
�@�@�@�E�v���X�v�l�Ȃ�u���҂���Ă��邩��{��ꂽ�̂��v�Ɖ��߂��A�u���͊撣�邼�v�ƍl����芷����
�@�@�@�@���Ƃ��ł��܂��B
�@�@�܂��A���̎d������萋���Ĉ����������̂��Ƃ����悤�ɁA�ړI�ӎ������m�ł���A�����̍���
�@�@�ɂԂ����Ă��O�����ȋC�������ێ��ł��܂��B
�@�@�����Ƃ͂�����ƈႢ�܂����A
�@�@�u������ϊv�̃`�����X�v�Ƃ��u�N���[��������̎R�v�ƍl���邱�Ƃ��A���Ȃ��₠�Ȃ��̃`�[���̂�
�@�@��C���h���C�u���錴���͂ƂȂ�̂ł��B
�@�@�� �X�g���X�R���g���[���ɂ����銄���
�@�@�������邱�Ƃ͍������B�������x�X�g�ȍl���ł��B�@�����^���B
�@�@�ł��A���܂����ʂ̏o�Ȃ���Ƃ�����������������������ƂȂ�Θb�͕ʂł��B
�@�@�X�g���X�Ɏ�����ǂ����܂Ȃ��ׂɂ������͑�ł��B
�@�@�u�����̂Ƃ���͂����܂ŁA�C������芷���Ė����܂��g���C���悤�B�v����Ȋ���肪�A���_�q��
�@�@����K�v�Ȃ̂ł��B
�@�@�����đË��ł͂���܂���B
�@�@�� ���ł������킯����Ȃ�
�@�@��鎞�͂��B�K�v�Ȏ��ɂ͂Ƃ��Ƃ�d���ɑł����ށB���ӕ���ł͈��������Ȃ��m��������B
�@�@����ȃ����n���������Ă�������肪�����Ă��܂��B
�@�@�厖�Ȃ̂́A�����ɂ͔\�͂�����Ǝv���Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��A���ۂɕK�v�ȂƂ��ɂ��̔\�͂��o����
�@�@���Ƃł��B
�@�@���ꂪ�A���Ȃ��̊���肪�O�����ł��邱�Ƃ̏ؖ��ɂ��Ȃ�܂��B
�@�@�ǂ��ł��傤�B�@���Ȃ����g�₠�Ȃ��̃`�[�����v���X�v�l�ɕς���q���g�ɂȂ�܂��ł��傤���B
�@�@�������}�ɕς��Ƃ͎v���܂��A�ȒP�Ȃ��Ƃ��������ӎ����čs���Ɏ�����Ă����B
�@�@���ꂪ�R�[�`���O�̈�ʂł�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill12�@ �t�@�V���e�[�^�[�̃e�N�j�b�N
�@�@���肪�܂��b���Ă���̂ɁA�Ⴄ�ӌ������Ԃ��Ă���ׂ�B
�@�@�ŋ߁A�s�u�̓��_�ԑg���ł悭����������i�ł��B
�@�@���e�����������ǂ������A���̑傫���A�����������s���Ă��܂��B�ق��Ă��܂��Ă͕����Ƃ�
�@�@��ɂQ�l�A���ɂR�l������ׂ�܂���A�N�����������Ă���̂��킩��܂���B
�@�@�ł��A������ĉ�c�ł��悭��������i�ł��B�E�E�E�c�_�ł��ėǂ��B
�@�@�������A��X�ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́A���Έӌ��ɂ�����݂��A�c�_���������Ƃł��B ��Ƃł́A�㉺
�@�@�W�����m�ł�����A����̕��̈ӌ��ɍ��E���ꂩ�˂܂���B
�@�@���͂�����R���g���[������E�Ƃ�����܂��B�t�@�V���e�[�^�[�B
�@�@���������Ƃ͂���܂��H�E�E�x���E���i�Ƃ����Ӗ�������܂��B
�@�@�t�@�V���e�[�^�[�Ƃ̓v���W�F�N�g���c�̐i�s���������ʂ��o�����Ƃ����E�Ƃł��B
�@�@�����Ō��ʂ��o���̂ł͂Ȃ����ʂ��B�ǂ��ƂȂ��r�W�l�X�R�[�`�Ǝ��Ă��܂��B
�@�� ��c�̗v�_�ƃt�@�V���e�[�^�[�̗���
�@�@��c�����܂��i�߂邱�Ƃɏœ_�����Ă�Ȃ�ASkill�O�S�u��c��߂܂����A���܂����v�ɂāA
�@�@�@�@ �ړI�̖��m��
�@�@�@�A �o�Ȏ҂̎��O����
�@�@�@�B ���ԊǗ�
�@�@�@�C ���m�Ȍ��_
�@�@�@�D �ӎv����ւ̎Q���ӎ�
�@�@�@�@�@�@���̂T�_���d�v���Ɛ������܂����B
�@�@���O��������������s�����_���o���Ƃ����_�ł́A�t�@�V���e�[�^�[���d������_���S�������ł��B
�@�@�傫���Ⴄ�_�́A�t�@�V���e�[�^�[�͉�c�̎�Î҂�v���W�F�N�g�̃��[�_�[�ł͂Ȃ��A�����ȗ����
�@�@�̉�c�̌�ʐ����W�A�i�s���ł���Ƃ���ł��B
�@�@����̓v���W�F�N�g�ɂ����Ă������ŁA�Q���ґS���ɐ���������F���𑣂��A����̗��ĂɌ������S
�@�@���̈ӌ��������o���A�܂Ƃ߂Ă������߂̌�ʐ��������Ă䂫�܂��B
�@�� �t�@�V���e�[�^�[�P�O�̃e�N�j�b�N
�@�@Tec�P�D�ō����ꏊ�A���̔z�u
�@�@�@�t�@�V���e�[�^�[�͑ō����ꏊ��Ȃ̔z�u�ɂ��z�����܂��B
�@�@�@�@�@ �R�����݂����ȋC�ɂȂ�^���ʂ͔����܂��B
�@�@�@�@�A ���������߂������A�e���݂������鋗���ɍ����Ă��炢�܂��B
�@�@�@�@�B ���ł͌������Ȃ��Ȃ�����c�ł̃R�[�q�[���A�����b�N�X���邽�߂̍H�v������܂��B
�@�@Tec�Q�D���Ζʂ̃����o�[�͎��ȏЉ�
�@�@�@��c�̏o�Ȏ҂̖��O���킩��Ȃ��������Ă悭����܂��B���O�ł��ˁB�v���W�F�N�g�����o�[�̊�
�@�@�@�Ɩ��O����v����̂́A�e�ߊ��ȑO�̖��ł��B
�@�@�@���������A�����A����̖������̊ȒP�Ȏ��ȏЉ��͍ŏd�v�ł���B
�@�@Tec�R�D�v���W�F�N�g���c�̖ړI�A���Ԋ����ŏ��Ɋm�F
�@�@�@����ꂽ���ԂŌ��_���o�����߁A�v���W�F�N�g���c�̖ړI�A�X�P�W���[���͍ŏ��ɖ��m�ɂ��܂��B
�@�@Tec�S�D�n�ʂɂ�锭���E�U���ɂ͂�����
�@�@�C�Â��͒n�ʂɂ���Đ��܂��킯�ł͂���܂���B
�@�@�@���ɍŏI���茠�҂����m�ȏꍇ�ł��A���f�ޗ����o�����܂ł́A�������T���Ă����������Ƃ��L��
�@�@�@�ł��B
�@�@Tec�T�D���_�͑S�ė��Ă��炤
�@�@�@�u���[���X�g�[�~���O�B�N�ł��m���Ă錾�t�ł��B�l�̈ӌ���ے肹���A�v���W�F�N�g�i�s��̖��
�@�@�@�͏o�������܂��B
�@�@�@�u����Ȃ̖�肶��Ȃ���v�Ƃ����悤�Ȕے�I�������̂��̂����Ȃ̂ł��B
�@�@Tec�U�D����F���͎Q���ґS���ŋ��L���Ȃ���Ȃ�܂���
�@�@�@��������l�ł��A����F�����Ȃ���ԂŐ�ɐi��ł͂����܂���B
�@�@�@�����ł������m�F���A�Ԏ����Ȃ��ҁA���M�Ȃ��C�̎҂ɂ͌ʂɊm�F���܂��B
�@�@Tec�V�D�b�̒����l�ɂ͒Z�k���w��
�@�@�@�l�̘b���Ղ�Ȃ��Ƃ��������͑厖�ł͂���܂����A�吨�̕����������ׂ���c�ŁA�S���b������
�@�@�@�ł��Ă��Ȃ������A����ꂽ���Ԃ�1�l�Ŏ��Ԃ��g���Ă��܂����Ƃ͂�߂����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�@�@�b����������A�v�_�������Ă��������Ƃ����T�C�������m���Ă����A
�@�@�@�t�@�V���e�[�^�[���K�v�ɉ����č��}���܂��B
�@�@Tec�W�D�E���������Șb��̓|�P�b�g��
�@�@�@����̋c��ł͂Ȃ����A�d�v�Șb��͒E���������₷�����̂ł��B
�@�@�@�|�P�b�g�ɂ��܂����o�Ŗ��������ɋL�^�ɂ͗��߂܂����A�ʂ̋@��ł̘b��Ƃ��邱�Ƃ���
�@�@�@�܂��B
�@�@Tec�X�D���ӁA�s���ӁA�ꕔ���ӂ̏�S���ŔF��
�@�@�@�ŏI���茠�҂���l�ł��A�t�@�V���e�[�^�[�͑S���̈ӌ����m�F���܂��B
�@�@�@�Ⴆ�A�^���̕��͂n�j�w�}�[�N�A�ꕔ���ӂ͂P�{�w�A���͓��̂Ă����G�铙�S���ɋ��肵
�@�@�@�Ă��炢�A�S�̂̏��m�F�A�L�^������Ō���ɓ����܂��B
�@�@Tec10�D�c���^�A���s�X�P�W���[���͖��m��
�@�@�����A�ӌ��͂܂Ƃ܂����B�ł����̂���ɐi�܂Ȃ��B�悭����b�ł��B
�@�@�t�@�V���e�[�^�[�́A�N���A���܂łɁA�ǂ��܂ł�邩���m�F���Č��_�Ƃ��܂��B�������c���^��
�@�@���s�X�P�W���[���A�S���҂L�̏�A�o�ȎґS���ɔz�t���܂��B
�@�@�������ł��傤�A�t�@�V���e�[�^�[�̃e�N�j�b�N�B
�@�@����̋Ɩ����c�ɂ����p�ł��邱�Ƃ���ł��B������Ƃ����~�[�e�B���O�ɂ����Ďg���܂��B
�@�@�厖�Ȃ̂͂������āA�����o�[�̔[�����B�����I�ȗ��ꂳ���ێ��ł���A���Ȃ��ɂ��A�Г���
�@�@�t�@�V���e�[�^�[�Ƃ��Ẵv���W�F�N�g���i���\�ɂȂ�ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill13�@ ���̃e�N�j�b�N
�@�@�ŋ߁A���l�Ƃ��l�S�V�G�[�^�[�Ƃ������t���͂���Ă��܂��B
�@�@�������A���Ƃ����A�s�u��f��̂悤�Ȕƍߌ�������A�ނ���r�W�l�X�̐��E�����̕\����ł�
�@�@��ˁB�o���o���̉c�ƃ}���łȂ������āA�Г��O�Ƃ̌��͑�R����͂��ł��B
�@�@�Ⴆ�A�����Ɏw������B��������Ȃ̂��Ƃ������Ƃɂ��C�Â��ł��傤���B
�@�@���������Ȃ����������B���̊�{�𗝉�����A�������ł͂Ȃ��A�[�������ē��������Ƃ�
�@�@�\�ɂȂ�͂��ł��B
�@�@�R�~���j�P�[�V�����Ƃ��Ă̌��̃e�N�j�b�N���r�W�l�X�ɂ�����l�ԊW�ɐ��������Ƃ��l���Ă݂�
�@�@���傤�B
�@
�@�� �R�~���j�P�[�V������Win-Win
�@�@���̍ő�̊�{�́A�����Ƒ��肪���ɖ����ł��錋�ʂ邱�Ƃł��B
�@�@�܂�Win-Win�i�o���̏����j�B
�@�@����́A���肪�����ł��낤�ƁA��i�⓯���E�����A������ł��낤�Ɠ����ł��B
�@�@���̖ړI�͔s�҂��o�����Ƃł͂Ȃ��A�ő�������߂邱�Ƃł��B
�@�@���������āA����ɂƂ��Ă�Win��������m�邱�Ƃ���O��B
�@�@���ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A�����Win�ɂ��A�g�D�Ƃ��Ă�Win�ƁA�l�Ƃ��Ă�Win�����邱�Ƃł��B
�@�@�l�I�ɂ�OK�����lj�ЂƂ��Ă�NO�B�S�̍œK���l�����YES�����njl�Ƃ��Ă͔[����������
�@�@���B����ȑ���̔w�i��̋C�����ɂȂ��čl���Ă݂Ȃ��ƁA���ł�Win-Win�͒B���ł��܂�
�@�@��B
�@�@���̂��߂ɂ́A�l�Ƃ��Ă̑��肪�������ǂ��v���Ă��邩�H����̑g�D�̒��ł̃L�[�}���͒N���H
�@�@�����܂ŗ������Ă���K�v������܂��B�L�[�}���͌�����̃g�b�v�Ƃ͌���܂���B
�@
�@�� ����ɂƂ��Ẵ����b�g���l����
�@�@�Ⴆ�Ε����ւ̎w���E���߂ɂ����āA�u�[�������Ȃ���������Ȃ����A���߂�����Ă���B�v�ł͏\��
�@�@�Ɏd���̐��ʂ��オ�邱�Ƃ͊��҂ł��܂���B
�@�@�܂��A����̎咣��ʂ����Ƃ��Ă����c�� �v���[�ŒN���Ƌc�_���A�����̐�������i����Ƃ�����
�@�@���A����̔ے�ɂȂ���ꍇ�͌��ɂ����Ă͋t���ʂł��B
�@�@���̂Q�̗�ɂ����đ�Ȃ͎̂����̐������ł͂Ȃ��A����ɂƂ��Ẵ����b�g���킩��₷���`��
�@�@�邱�Ƃł��B
�@�@�傫�ȃ����b�g������̂�����A�����̂��Ƃ͉䖝���Ă�����Ă݂邩�Ƃ����C�ɂ�����ΐ����ł��B
�@�@���ɎГ���c�̏ꍇ�A��������������܂œǂ�ł������͂قƂ�ǂ��Ȃ����A�������炵���b����
�@�@�����Ė��C�������������ł��B
�@�@�v�_���i�肱�݁A����̃����b�g�m�ɂ��邱�Ƃ��őP�̌���i�Ȃ̂ł��B
�@�� ���������
�@�@���肪�g�D�̏ꍇ�A����̒��ɖ�������邱�Ƃ͌��p�̊�{�ł��B����͑Ε���̌��������B
�@�@�������g�������ł��݂��̗��v���l���Ă��邱�Ƃ𐳂����������Ă���閡���E�F�l���A��������W
�@�@���Г��̑�����ɑ��₵�Ă����̂ł��B
�@�@������ł����H
�@�@�ł��A���Ȃ����g�����ۂɐ����ł���A��������Ȃ��ɍ����Ă��鑊��͏����Ă�����悤�ȕt����
�@�@�������������S�|���Ă���Ώ\���ɉ\�ł��B
�@�@�܂�A�����Ƃ����������̂��߂ɕt�������̂ł͂Ȃ��A�M���Ō���Ă���A���������ɑ��k�ł���
�@�@�W�ł��B
�@�@���������āA�����܂ő���̉�Ёi����j�̂��߂ɂȂ邱�Ƃɂ��Ă̑��k�����܂��B
�@�@�u�N�̉�Ёi����j�ƒ�����������̂����ǁA�ǂ�Ȋ��G������ꂻ�����m�肽���B�v�Ƃ��B
�@�@�u�N�ɘb��ʂ��̂����ȁH�v�@�Ƃ��ł��B
�@�@�E�E�E�E���Ȃ����K�v�Ƃ��Ă��������邩���m��܂���B
�@�� �y�[�V���O�̊��p
�@�@�R�[�`���O�̃X�L���̈�Ƀy�[�V���O�Ƃ������̂�����܂��B
�@�@�y�[�V���O�ł́A����ɍ��킹�A�e�ߊ�����������̂���{�ł����A����i�߂��ł����ɗ���
�@�@�܂��B
�@�@�ȑO�ɂ����Љ�����o�Y�ƐV���̋L���ł́A�D�G�ȉc�ƃ}���͑���̎�̘b������ɂƂǂ܂�
�@�@���A�d�v�ȏ��k����̎Е��ɍ��킹������������Ƃ܂ŏ����Ă���܂����B
�@�@�܂������܂ł�炸�Ƃ��A����Ƃ̉�b�̒��ő���̌��t�����p�����褌J��Ԃ����肷�邾���ł��A
�@�@�e�ߊ��͓����܂��B
�@�@�u��������Ȃ����B�v�@�@�@�@�@�u�����Ȃ�ł��B�ł��O��̖��_�͉��P���Ă����ł��B�v
�@�@�u�����͑O���_���������B�v�@�u���������ʂ�ł��B�ł��O��̖��_�͉��P���Ă����ł��B�v
�@�@�u�N�̈ӌ��́������ȁB�v �@�u�����ł���ˁB�ł��ǂ��_������܂��āB�v
�@�@�u�����ɂ͔����ȁB�v�@�@�@�u�ł́A���̑��̕����͎^���Ǝv���Ă�낵���ł��ˁB�v
�@�@������܂����H
�@�@�y�[�V���O���g�����ƂŁA����̌��t��ے肹���ɁA�����̈ӌ����咣���邱�Ƃ��o����̂ł��B
�@�@�܂��A�e�ߊ��Ƃ��������Ȃ�A����̎咣����������ƍŌ�܂Œ������Ƃ����ł��e�ߊ��͓����܂��B
�@�@��������ƍŌ�܂Œ����B��������h�ȃR�[�`���O�X�L���ł����ˁB
�@�� �t�b�g�C���U�h�A
�@�@�����ʂ�A�h�A�ɑ����͂���ŕ߂��Ȃ�����̈ӂł��B
�@�@�����̎咣�̒��ő��肪�n�j�ł��鏬���Ȃ��Ƃ������O�j�����炢�A���ʂƂ��đS�̂�F�߂���
�@�@��̂ł��B
�@�@�Ⴆ�����Ȓ�Ăł����肪�����ł��A�[���ł����Ă�ςݏd�˂Ă����܂��B
�@�@�������Ă����̂������R�̂悤�ȐM����������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�@�@���t�ł����قǒn���ł���K�v�͂���܂���B���i���瑊��̋C�������ɂ��Ă���ΈӊO�Ƒ���
�@�@���R�ɂȂ�ł��傤�B
�@�� ���ʕ\��
�@�@�����ɂ͕K�������b�g�ƃf�����b�g������܂��B�������̃����b�g���l����̂����̑�������
�@�@�͂���܂����A���Əꍇ�ɂ���ẮA�����Ƀf�����b�g�m�ɂ��邱�Ƃ����ʂ�����܂��B
�@�@�������邪�A����ɏ��闘�_������B�����b�g�A�f�����b�g�̗��ʕ\��������킯�ł��B
�@�@�Ⴆ�A�u�ܖ������͒Z�����ƂĂ����������f�U�[�g�v�E�E�E�����Ŕ��ꂻ���ł���ˁB
�@�@�g��������ł́A�f�����b�g�������b�g���X�ɋ�������̂ł��B
�@�@�������A�v�����Ō����̂ł͂Ȃ��A���肪�ǂ��~�߂邩����������l���Ă��猾�����ق����ǂ�
�@�@�ł��傤�B
�@�� �����I�A�v���[�`
�@�@���̏�ʂł̕����I�A�v���[�`�B
�@�@���x���Љ�Ă���܂����A����ō����ł̍���ʒu���Č��\�厖�ł��B
�@�@�E���Г��ł���A�o���邾���g�����ꂽ��c���̒�ʒu�ɍ���܂��B���ꂾ���ŗ��������܂��B
�@�@�E����̃L�[�}���Ƃ̐��i�^���ʁj�͂ł��邾�������܂��B���Έʒu�͐S���I�ɔ��������Ȃ�X��
�@�@�@������̂ł��B
�@�@�E����̂T�O�����ȓ��i�p�[�\�i���X�y�[�X�j�ɂ͓���Ȃ��B
�@�@�E����Ƃ̋������߂��ꍇ�́A���肩�猩�ĉE���ɍ���܂��B�܂�S���Ƌt���B�����i�S�����j�Ɉ�
�@�@�@�u����Ɩ��ӎ��ɒ�R�������Ȃ�̂ł��B
�@�@������ƋC�����邾���ŁA����ւ̐S���I�������y���ł���̂ł��B
�@�� ���P�̍�
�@�@�قƂ�nj��������͂Ȃ��炠����߂Ă�����A������Ƃ����܂Â��ł�����߂���͌��\���܂��B
�@�@�ł��悭�l���Ă݂܂��傤�B�v���[�����ɂƂ�A���𗧂Ă邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A ����ʂ��Ă�
�@�@�݂��̃����b�g�������o�����Ƃ��ړI�Ȃ̂ł��B
�@�@�P��̃v���[���Œʂ�����ł����A����̗v�]�����Ȃ��Ȃ���őP�̊��ɂ��Ă����̂��Ɨ���
�@�@�ł��Ă���A������߂�K�v�Ȃǂ���܂���B
�@�@�I���}��p�ӂ���Ƃ��A���̓s�x���P�̍���l���Ȃ���A�������O�i���܂��傤�B
�@�@�������Ȃ��ɋ삯�������ł���̂Ȃ�A
�@�@���e�͗ǂ����A������ɒf��ꂻ���ȃv�����𐔈č���Ē�Ă��A�Ō�ɖ{���̒�Ă�����B
�@�@����ƁA������S���f��̂͐\����Ȃ��Ƃn�j���Ă���邱�Ƃ�����܂��B
�@�@�P���ł͂Ȃ��ł����A����������������̂ł��B
�@�@���̃e�N�j�b�N�B�������ł��傤���B
�@�@���̑��ɂ��A���̃g�[�������܂��g����������A�g�U���U��Řb������������Ȃǃe�N�j�b�N�͂���
�@�@���날��܂��B
�@�@�f��̌��l�̂悤�ɔh��ł͂���܂��A��l�̎v�����łł��邱�Ƃł͂���܂���B
�@�@�����ɍ���������g�ɕt���āA�r�W�l�X�ɂ����Ă��Ȃ��̎咣����������ʂ����߂ɖ𗧂ĂĂ�
�@�@�ĉ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill14�@ �ϋɓI���̎咣�E�A�T�[�e�B�u�l�X
�@�@��������ɐ�ɐ������Ƃ͎v���Ă�����͂قƂ�ǂ��Ȃ��ɂ�������炸�A�A�����ӌ��̒���
�@�@�ƍs�����钆�Ŏ����������h���Ǝv�����݁A�����̔����͐������ƐM���Ă���������Ȃ葽���A
�@�@�Ƃ������������܂����B
�@�@�������t�ɁA���̒��ɂ́A�����̈ӌ���������Ǝ咣�ł��Ȃ��������\����悤�ł��B
�@�@�����ŁA�G����A�V���̃��[�_�V�b�v�֘A�̃R�����ł悭��������A�T�[�e�B�u�l�X�i�ϋɓI����
�@�@�咣�j�Ƃ������t�ɂ��čl���Ă݂܂��B
�@�@�A�T�[�e�B���̖{���̈Ӗ��́A�f���I�Ƃ��ƒf�I�A���������܂�ǂ��Ӗ��͂���܂��A�R�~
�@�@���j�P�[�V�����p�Ƃ��ẴA�T�[�e�B�u�l�X�́A�u����Ƃ̊W���l������ŐϋɓI�������Ɏ�
�@�@�Ȏ咣����v�Ƃ����l�����̂悤�ł��B
�@�@�������X�Ǝv�������A�ϋɓI�Ɉӌ��������Ȃ��������y�ɃA�h�o�C�X����C�����ł��ǂ݉���
�@�@���B
�@��
�����̍l����`���Ȃ��Ƃǂ��Ȃ邩�H
�@�@ �� �o�����̃R�~���j�P�[�V�������n�܂�Ȃ�
�@�@�@�@�@�����̍l����ɓ`���Ȃ���R�~���j�P�[�V�����͎n�܂�܂���B
�@�@�@�@�@�ɘ_����A�v���Ă��邾���Ō���Ȃ��̂́A���͂̕��ɂƂ��Ă͂��Ȃ��������l���Ă���
�@�@�@�@�@���̂Ɠ������Ȃ̂ł��B
�@�@�� �C�t���������Ȃ�
�@�@�@�@�@�܂��A�R�~���j�P�[�V���������ޑ厖�Ȍ��ʂ̈�Ƃ��āA�{�l�̋C�t��������܂��B
�@�@�@�@�@�l�͎v������U�A������o������A���ɏ������肷�邱�ƂŁA�����̍l�������邱�Ƃ��o
�@�@�@�@�@���܂��B
�@�@�@�@�@�܂��A���͂���̃A�h�o�C�X������A���̎v�����m�M�ɕς�����A�ԈႢ�ɋC�t��������o
�@�@�@�@�@����̂ł��B
�@�@�@�� �~�X�W���b�W�ƌ��
�@�@�@�@�@���ɍl����ׂ��́A�`����ׂ����Ƃ�`���Ȃ������ꍇ�ɂǂ�Ȍ��ʂ��������ł��B
�@�@�@�@�@�����ׂ��ӌ��⎩���̎v����`�����Ȃ��ƁA�~�X�W���b�W�̌����ƂȂ�����A�������g����
�@�@�@�@�@������邱�Ƃɂ��Ȃ���܂��B
�@�@�@�@�@�P�j �Ⴆ�A�d����̏����Ɋւ��āA���肪�Ԉ���Ă���̂ɂ��ꂪ�`�����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@���̏�A���Ȃ��͊Ԉ���������͏o���Ȃ��̂ŁA�扄���B����ł͒P�ɂ��Ȃ�������
�@�@�@�@�@�@�@���Ǝv���邾���ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�܂����Ȃ��̐扄���̂����ŏ�������x��ɂȂ邱�Ƃ����ėL�蓾�܂��B
�@�@�@�@�@�Q�j �����ɗU��ꂽ���݉�B�����͂ǂ����Ă��C���i�܂Ȃ��̂ɂ��܂��f��Ȃ��B���邸��A
�@�@�@�@�@�@�@��Ă����ꂽ���A��b�ɂ�������Ȃ��B���ƂȂ����͂��S�z��B
�@�@�@���Ȃ����ԈႢ���Ǝv���̂Ȃ�A�Ԉ���Ă��鎖�����A
�@�@�@�ł��Ȃ��̂Ȃ�A�ł��Ȃ����R���A
�@�@�@��肽���Ȃ̂Ȃ�A��肽���Ȃ��C�������A
�@�@�@�s�������Ȃ��Ȃ�A�s�������Ȃ����R��
�@�@�@���m�ɓ`���邵���Ȃ��̂ł��B�m�ɓ`���܂��傤�B���ꂪ�A�T�[�e�B�u�l�X�ł��B
�@�@�@
�@�@�@�E�E�E�E�E�E�@�ł��`�����Ȃ��B����ȕ��͍Ō�܂ł��ǂ݉������B
�@�� ���́A�l����`�����Ȃ��̂��H
�@�@�������咣�ł��Ȃ������Ƒ���l���Ă݂܂����B
�@�@�@ ����Ɉ���
�@�@�@�@�����v�����Ȃ��͎��͂ɋC���g���߂��ł��B�ł��C���g�����Ǝ��̂͗ǂ����Ƃł��B
�@�@�@�@ �ˁ@�����ŁA���A����Ȃ��ƌ�X���������B�����v���Ă݂Ă͂������ł��傤���H
�@�@�A ����ꂽ���Ȃ�
�@�@�@�@���������Ƃ������Č�����̂Ȃ�~�ނȂ��B�����v�����͕ʂƂ��āA�قƂ�ǂ̕��́A
�@�@�@�@�l�ɂ͌���ꂽ���Ȃ����̂ł��B�ł��{���Ɍ�����̂ł��傤���H
�@�@�@�@�ˁ@���Ȃ����g���l���璉�����ꂽ��A���_���w�E����邱�Ƃ�z�����Ă݂ĉ������B
�@�@�@�@�@�@ �����ʓ|���݂Ă��炢�M�����Ă��鑊��Ɍ�����Ȃ炻��قǕ��������Ȃ��B
�@�@�@�@�@ �@�����v���܂��B�����A���Ȃ����g������ɐM����^����悤�ȃv���X�s�����������s��
�@�@�@�@�@�@ �Ă����悢�̂ł��B
�@�@�B ���͂̈ӌ��Ɋ������܂ꂪ��
�@�@�@�@�l�͂ǂ����Ă����͂̕��̈ӌ��ɗ����ꂪ���ł��B
�@�@�@�@�ˁ@����ȕ��͎����̍l�����Ċm�F���Ă݂�ׂ��ł��B�Ⴆ�A�����̊���ɐ����ɂȂ�A����
�@�@�@�@�@�@ ����̈Ӗ����l���Ă݂�B����Ȃ̂��A�����̂���ґ���ōl���Ă݂�ƍl�������m�ɂȂ�
�@�@�@�@�@�@ �܂��B
�@�@�C �b���Ă��`���Ȃ�
�@�@ �@ �b���Ă�����肪�b�������͂��B������Ɣ��_�����Ɠ������Ȃ��B����ȕ��́A�ӌ��E�l����
�@�@�@�@������Ɛ�������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�@�@�@�ˁ@�����̍l��������K���A�z���ł͂Ȃ��A������������Ɗm�F����K��������Ɨǂ��ł�
�@�@�@�@�@�@ �傤�B �]�T������̂Ȃ�A�b���̑g�ݗ��Ă����n�[�T�����Ă݂邱�Ƃ����ʓI�ł��B
�@�� �����A�����̍l����`���Ă݂悤
�@�@�����ł́A�����̎咣����̓I�ɂǂ�����ē`���邩���l���Ă݂܂��B
�@�@�@ �����ɓ`����
�@�@�@�@ �����ɓ`���邱�Ƃ��o���Ȃ����獢���Ă���B�E�E�E�킩��܂��B
�@�@�@�@ �X�g���[�g�Ɍ����̂ł͂Ȃ��A�l����`�������Ƃ������Ȃ��̋C�����A�`����ꂸ�ɍ����Ă����
�@�@�@�@ ���Ƃ������Ȃ��̑z����ɗ����Ɍ���Ă݂܂��傤�B�������ɂ��܂��B
�@�@�A �Ȍ�����̓I�ɓ`����
�@�@�@�@ �O�u��������������A���ǂ��nj����ƁA�b�͂������ē`���܂���B�Ȍ��ŕ�����₷�����t��
�@�@�@�@ �g���A�v�_�m����̓I�ɓ`���܂��傤�B
�@�@�B �J��Ԃ��`����
�@�@�@ �@���X�ӌ����ʂ�Ȃ��Ă��A�����炸�A�����������ԓx�ŌJ��Ԃ��`���܂��傤�B
�@�@�@ �@��Â���т������Ȃ��̑ԓx�����Ȃ��̎咣�m�ɂ��܂��B
�@�@�C �������߂��邠�Ȃ��̋����͑厖��
�@�@�@�@ �I�u���[�g�ɂ���ނƐ^�ӂ͓`���܂���B�ł��A����ɂ����Č���ꂽ���Ȃ����Ƃ͂��邾�낤
�@�@�@�@ ���A�ے肳�ꂽ�Ǝv���Ύ����ӂ����܂��B
�@�@�@�@ �X�g���[�g�Ȍ��t�Ɂu�\����Ȃ����ǁv �u�Z�����Ƃ��������ǁv�Ƒ�����v����錾�t�������ē`
�@�@�@�@ ���܂��傤�B
�@�Y�Y�Y�Y�Y�Y
�@�@��l�������̐g�ɂȂ��Đ������܂������A
�@�@���́A�����ׂ����Ƃ͂�����ƌ����Ă���Ƃ����������Č��\�����͂��ł��B
�@�@�ł��A���M�������Ă�����������͋t�ɁA�������y�ɍ����I�ȑԓx�Őڂ��Ă��Ȃ����_�����Ă�
�@�@�ĉ������B
�@�@�{���ɐ������Ǝv���Ă����Ȃ��̑O�ł͔����ł��Ȃ��Ƃ����������y�����l��������A�d���̌�
�@�@���͊m���ɉ������Ă���͂��ł��B
�@�@�������������Ǝv��������߂̂�����́A�������y�̔������A�Ƃ肠�����͍Ō�܂ʼn䖝���Ē�
�@�@���ƌ��߂Ă݂ĉ������B
�@�@�u�������N�G�X�g�͂���H�v�Ɛ����|�����āA�͂��߂Ĉӌ���������������Č��\���݂���̂ł��B
�@�@�����ƁA�����̔����������āA�O���[�v��`�[���̊��C���o�Ă���͂��ł��B
�@�@���݂������݊�邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B
�@�� �����Ƃ��܂��`�����͂Ȃ����H
�@�@�R�[�`���O��S���w�̃X�L�����g���A����̗�����l���Ȃ���ϋɓI���Ȏ咣���ł��Ȃ����ƍl
�@�@���Ă݂܂����B�A�T�[�e�B�u�l�X�̖{���̎�|����͊O��邩���m��܂��A���܂��ӌ���咣��ʂ���
�@�@�Ǝv���̂Ȃ��͐F�X����̂ł��B
�@�@�@ �x�d�r�A�a�t�s�Ŏ咣
�@�@�@�@�����Ȃ�ے肹���A�܂��͏���or���A���ꂩ�甽�_���Ă����ƁA����̊�����t�Ȃł��Ȃ��ł��݂܂��B
�@�@�@�@�u�����ł��˂��B�s�������ł��B�ł������͓s���������̂ł��B���݂܂���B�v
�@�@�@�@�q�悩��̖����ȗv���ɑ��Ă��A
�@�@�@�@�u���肪�Ƃ��������܂��B�������������̂ł����A�ł��A���낢��ƒ������Ă݂܂������A
�@�@�@�@�@�����Q�T�ԂقǓs�������Ȃ��̂ł��B�v
�@�@�A �咣�ł͂Ȃ��A�I���}�̈�Ƃ��ē`����
�@�@�@�@�_�u���o�C���h�ƌĂ��e�N�j�b�N�B
�@�@�@�@�Ⴆ�A�u�H���ɍs���܂����H�v �Ƃ͌��킸�ɁA�u�m�H�Ƙa�H�Ƃǂ����������H�v �Ƃ���������������ƁA
�@�@�@�@�u�m�n!�v�@�ƌ�����m���͌���܂��B
�@�@�@�@���Ƃ��f���Ă��@�u���Ⴀ�����ł�����H�v�@�ƌ�����Ɓ@�u�܂��������炢�Ȃ�B�v�@�Ƃ�������N����
�@�@�@�@�����̂ł��B
�@�@�B �ӌ��ł͂Ȃ��A�q�ϓI������X�N�Ƃ��ē`����
�@�@�@�@���R�Ȃ���A���͂��ꂽ���ʂƂ��Ă̎�����X�N�Ƃ��Ďw�E�����Ǝ���݂�����܂���B������
�@�@�@�@���Ă̏d�݂͒N�ɂł��������₷���A�܂������������̂ł��B
�@�@�C ���������
�@�@�@�@���p�̈�Ƃ��Ă��A����̃`�[�����ЂɁA�����̈ӌ��̑�َ҂���邱�Ƃ͈ӌ������܂��`����
�@�@�@�@��i�ł��B���R�Ȃ���A��������̃R�~���j�P�[�V���������������܂��B
�@�@�D ���ʕ\��
�@�@�@�@�O���iSkill13���̃e�N�j�b�N�j�ł��o�ꂵ�����ʕ\���B
�@�@�@�@�����b�g�݂̂�`���āA�ӌ���ʂ����Ƃ�����A�f�����b�g�A�����b�g�̗�����`�����ق����������
�@�@�@�@���Ƃ͎��Ƃ��Ă���܂��B
�@�@�@�@�E�E�E�E�E�@�Ⴆ�A���������Ȃ����ǔ��������B��J�������邩������Ȃ����K���ɂ���B�@���B
�@�@�E ���N�G�X�g
�@�@�@�@���N�G�X�g�͈���I�Ȉӎv�\���B�̗p�����Ƃ͌���܂���B�����炱���C�y�ɗv�]�ł���̂ł��B
�@�@�@�@�u���N�G�X�g�Ȃ�ł����ǁB�v�@�E�E�E�C�y�Ɍ����Ă݂܂��傤�B
�@�@�Y�Y�Y�Y�Y�Y
�@�@�ǂ��ł����A��l�������Ȃ��B�A�T�[�e�B���Ɏ咣���o�������ł����H
�@�@������ł�������O�ɐi��ł݂܂��H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
Skill15�@ �t�@�V���e�[�V��������P�E��b��
�@�@�t�@�V���e�[�V�����ɂ��Ă͈ȑO�ɁA��c�����̂P�O�̃e�N�j�b�N���Љ�܂������A����͂�������i��ŁA
�@�@����̋Ɩ��Ƀt�@�V���e�[�V�������������Ă������@�����Љ�܂��B
�@�@���́A���e����̃t�@�V���͉p��ł͂��������B�������~���ŊȒP�ɂ���X�L���Ɗo���ĉ������B�Ⴆ�A�p�b��
�@�@�u���̍��v�@���g���Ė��_�͂���̂��A�l���������@�Ƃ��Ẵt�@�V���e�[�V�����ł��B
�@�� Step1�@ �R�[�`���O�X�L�����g������b�p
�@�@�{���̃t�@�V���e�[�^�[�͎w���҂ł͂���܂���B�R�[�`���O�Ɠ���������ϖ����ɑ���̍l�����A�{��
�@�@�������o���܂��B
�@�@�����͑��� �i�����o�[�j �̒��ɂ���B����ȋC�����ʼn�b���R���g���[�����Ă������Ƃ����߂��܂��B
�@�@���@��u�������čl���������o���@�@�i�`�͎Ј��A�e�̓t�@�V���e�[�^�[�ł��邠�Ȃ��j
�@�@�@�`�@�u�Г��̊�������}�ꂽ���āA�s�n�o�_�E������Ȃ��Ⴄ�܂��s���Ȃ���B�v
�@�@�@�e�@�u���Ⴀ�A���Ȃ����В����Ƃ�����A�ǂ�Ȏ�i������܂����B�v
�@
�@�@�@�`�@�u�В���������A�N��ɊW�����ɗD�G�ȎЈ��咷�ɂ���Ƃ��E�E�E�B�v
�@�@�@�e�@�u�����{���Ɏ��s����Ƃ�����A�ǂ�Ȗ�肪����Ǝv���܂����H�v
�@
�@�@�@�`�@�u���[��B�s���������Ј������邩���m��Ȃ��ȁB�v
�@�@�@�e�@�u��̓I�ɂ́A�N���A�ǂ�ȕs���������̂ł����H�v
�@�@�@���@���Ƃ͑S���Ⴄ��Ԃɒu�������āA�l�����@�艺����̂ł��B
�@�@���@�y�[�V���O�ʼn�b�𑣂�
�@�@�@�`�@�u��̌��A���܂������ł��Ȃ��B���������̂��B�v
�@�@�@�e�@�u���܂������ł��Ȃ��̂��B����͍������ˁB��������l���Ȃ�����ˁB�v
�@�@�@�`�@�u�������̈ӌ��������ƕ����Ă���Ȃ���B�v
�@�@�@�e�@�u�ӌ��������ƕ����Ă���Ȃ��̂��A�����������˂��H�v
�@�@�@�`�@�u���Ԃ�A�������Ȃ̂��Ǝv�����ǁB�v
�@�@�@�e�@�u�������A�������Ȃ̂��B�ǂ��ɂ����ĕς�����@�͂Ȃ����˂��H�v
�@�@�@���@�ꌩ����̌��t�̌J��Ԃ��ł����A�������蒮���Ă��炦�Ă��邱�Ƃ��m�F�ł�������̉�b�͒e�݂�
�@�@�@�@�@ ���B���Ƃ����ł����ʂ�����܂��B���̗ǂ����l���m���Ďd��������ł���B���ꂪ�y�[�V���O�ł���B
�@�@���@�I�[�v���N�G�X�`�����A�N���[�Y�h�N�G�X�`�����Ŏv�l�𑣂�
�@�@�I�[�v���N�G�X�`�����j
�@�@����̂�₱���������ɑ��āA
�@�@�@������j�@�u�������������̂ł����H�v�@�@�@�@�@�@ ����ł͔�����ے肳��Ă����ۂ��܂��B
�@�@�@�ǂ���j�@�u�����̃|�C���g�͂ǂ̕ӂł����H�v�@����Ȃ�A�|�C���g���Ċm�F���Ă����ł��傤�B
�@�@�N���[�Y�h�N�G�X�`�����j
�@�@�D�_�s�f�ōl���m�ɂ��Ă���Ȃ�����ɑ��āA
�@�@�@������j�@�u�ǂ��l���Ă���̂ł����H�v�@�@�@�@�@�@����ł͍l���邾���Ō��_���o���Ă���܂���B
�@�@�@�ǂ���j�@�u�^���ł����A���ł����H�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�ǂ��炩�Ƃ����Ǝ^���Ȃ̂ł��ˁH�v�@�����͖��m�ł��傤�B
�@�@���@����̑傫����ς��āA�l���₷������
�@�@�Ⴆ�A�o��팸����F�ōl���Ă����ʂ�n�����Ă��������B
�@�@�ӌ����o�Ȃ��̂́A���z���d�����Ă���̂ł͂Ȃ����_���d�����Ă���̂ł��B����̑傫����ς���A
�@�@���_���ς��܂��B
�@�@�`�����N�A�b�v �i�傫�Ȏ���j
�@�@�ׂ��Ȃ��Ƃ���ŁA���ʓI�ȃA�C�f�A���o�Ȃ����ɁA
�@�@�@�u���̉�Ђ�ǂ����邽�߂ɁA��肽�����Ƃ��������牽�ł������Ă݂Ă�H�v
�@�@�`�����N�_�E�� �i�I���i��������j
�@�@��̓I�Ȉӌ����o�Ȃ��� or ���z���s���l�������ɁA
�@�@�@�u�N�́����̒S������ˁB�����̎d���Ł��������_�ɂȂ������Ƃ͖������ȁH�v�@
�@�@�Y�Y�Y�Y
�@�@�ȂA�R�[�`���O����Ȃ����B�����R�[�`���O���L�`�̃t�@�V���e�[�V�����Ȃ̂ł��B����A���s���Ă݂�
�@�@�������B
�@�� Step�Q �@�O�����ɂ����b�p
�@�@�v�l����~���ċc�_�̂Ȃ���c�A�s���l�����v���W�F�N�g�B
�@�@����Ȏ��ɂ̓t�@�V���e�[�^�[�̔��������̂������܂��B������O�̎v�l��������ƕς��āA�`�[���̃��`
�@�@�x�[�V�����t�o��}���Ă݂܂��傤�B
�@�@���@��b�������Ɍ���������ɕς��Ă݂�
�@�@�@�~�@�u���̎��s�����H�v�@�@�@�@�@�@�@�@�ӂߌ����́A���C��D���܂��B
�@�@�@���@�u���������Ŏ��s�����̂��ȁH�v�@�@����ݸ����݁B�Ĕ��h�~�Ɍ��ʂ���B
�@�@�@���@�u�ǂ��������A�����ł��邩�ȁH�v�@�v�l�𖢗��Ɍ����܂����B�O�����ł��B
�@�@���@����ł��O�ɐi�ނ��߂̎�������Ă݂�
�@�@�@�~�@�u�ǂ����Ă��_���ł����H�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_���ł��ƌ����Ă��d�����ł���B
�@�@�@���@�u�������ɏo���邱�Ƃ͉����ȁH�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ƑO�����ɂȂ鎿��ł��B
�@�@�@���@�u���������̐������Ȃ������牽���o����H�v�@�@������͂����Ďv�l���L���܂��B
�@�@�ᔻ���肷����Ɂj
�@�@ �u�ᔻ�͌�ɂ��āA�܂��S���̃A�C�f�A���܂��B�v��ڰݽİ�ݸނł��B
�@�@�����̏��Ȃ����Ɂj
�@�@�@��@�@�u�܂��A��������Ă��Ȃ����̈ӌ��������Ă݂����ł��ˁB�˂��F����B�v
�@�@�@��A�@�u���́������ӌ��������Ԃł�����A�l���Ă����ĉ������B�v
�@�@�@��B�@�u�x�d�r���m�n�����������������B�v
�@�@�b�̃|�C���g�s���m�ȕ��Ɂj
�@�@�@��@�@�u���̔����́A�����Ƃ����Ӗ��Ɨ������Ď��̍l���������܂����E�E�B�v
�@�@�@��A�@�u���̎���́A�����Ƃ�������肽�������̂ł���ˁB�v
�@�@�@��B�@�u�F����̎�~�ߕ����l�X�ł�����A�����̃|�C���g���m�F�����Ă��������B�v
�@�@���@�s���ɂȂ��鎿������Ă݂�
�@�@�@��@�@�u���ɉ������܂����H�v
�@�@�@��A�@�u��̓I�ɁA���A�N���A��������̂��l���܂��傤�B�v
�@�@�@��B�@�u���̌��ŁA���Ȃ��ɏo���邱�Ƃ͉��ł����H�v
�@�@�Y�Y�Y�Y
�@�@�ǂ��ł��A����Ƃ�����b�p�ŁA�v�l���n�܂�悤�ȋC�����܂��B����A����̉�b���c�A�v���W�F�N
�@�@�g�̐i�s�Ɋ������ĉ������B
�@�� Step�R�@ ������U���i�����j���Ȃ���b�p
�@�@�U���∳���ŕ�����ꑮ�͂����邱�Ƃ͏o���܂����A�M���W�͒z���܂���B
�@�@�厖�Ȃ͎̂v�l�𑣂��A�s�����N�������邱�Ƃł��B
�@�@���@�Ƃ������咣��������Ɗۂ߂Ă݂�
�@�@�@�~�@�u�N�͊Ԉ���Ă����v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ӂ߂Ă��܂���B
�@�@�@���@�u�Ԉ���Ă�����������Ȃ��ˁB�v�@�@ �@������Ɗۂ܂�܂�����B
�@�@�@���@�u�Ԉ���Ă���\���͖������ȁH�v�@����ōl�������܂��傤�B
�@�@�@�~�@�u����Ȃ̓���O����A���̕�����Ȃ���B�v�@������O�Ƃ͌���܂���B
�@�@�@���@�u�l�́������Ǝv�����ǁA�N�͂ǂ��v���H�v
�@�@�@�~�@�u�������ǂ��Ȃ���B�v
�@�@�@���@�u���������n�j�����ǁA���������l����������Ƃ����Ɨǂ��Ȃ����ȁH�v
�@�@�@���@�u�������Ⴄ�l�����ˁB����ȊO�͂������ǁB�v�@
�@�@�@���@�u�قƂ�Ǔ����l�������ǁA���������i�P�����j�Ⴂ������ˁB�v
�@�@�@�@�@�@�Ⴂ����������̂ł͂Ȃ��āA��v���镔�����������܂��B
�@�@���@�����ς��鎿��
�@�@�@���@�u�N�͂ǂ��������Ȃ́H�v�@�@�@�@��ꂪ�x�n�t���Ɛӂ߂Ă銴���ł��ˁB
�@�@�@���@�u�������ǂ���������̂��ȁH�v�@�v�d�ōl���Ă��炢�܂��傤�B
�@�@�@�~�~�u�N�͂����_���i����j���ˁB�v �@�@�@�@�@�@�@�l�i�A���i�̔ے�̓p���n���ł���B
�@�@�@���@�u�ǂ����ɖ�肪��������Ȃ����ȁH�v�@������T���Đӂ߂܂��傤�B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�������A����ɂ���Ă̓X�g���[�g�ɓ`����ق����ǂ����Ƃ�����܂��B
�@�@�ł��A������x�o����ς�������Ȃ�A�X�g���[�g�Ȏ咣������̔ے�ɂȂ��邱�Ƃ�����܂��B
�@�@�����ōl���čs�����邱�Ƃ��o���鑊��ɂ́A�܂��́A��������l���Ă��炢�܂��傤��B���̂��߂̃X�L
�@�@�����t�@�V���e�[�V�����Ȃ̂ł��B
�@�@����́A�v�l�𑣂��l���������o���Ă�����b�p�𒆐S�ɉ�����܂������A�t�@�V���e�[�V�����ɂ́A�Η�
�@�@���������A���ʔF���������o������A�W�c�S���Ɏ���Ȃ��悤�ɋq�ϓI���f��^���Ă������ʂ�����܂��B
�@�@����A���������[������������܂��̂ŁA�����҉������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
Skill16�@ �t�@�V���e�[�V��������Q�E�_���v�l��
�@�@�ŋ߁A�悭���ɂ���Z�����̗��R�B����͉�c�ł��B
�@�@����ł͂�����B���Ȃ��͉�c�ɉ������߂Ă��܂����H
�@�@������c�ɋ��߂�̂́A�����̎��_�ɂ��c�_�ƌ��_�B�@�܂莟�̍s���ւ̔[�����̂���ӎv����ł��B
�@�@�ł��A���ۂ̉�c�̏��U��Ԃ�ƁA����ȉ�c�������Ȃ��ł����H
�@�@�� �K�X���������I�ȏ��`�B�ׂ̈̉�c �i���_���Ȃ��j�B
�@�@�� ����̕� �i���̑傫�ȕ��A�|�W�V�����̍������j �̈ӌ����������_���Ă����c�B
�@�@�v�l�𑣂���b�p�A�O�����ɂ����b�p�A���܂��咣���邽�߂̉�b�p��STEP�R�܂łł��Љ�܂�����
�@�@�ŁA����́A�_���I�Ȏv�l�������o�����@���l���܂��B
�@�� STEP�S ��b��_���I�ɂ��Ă݂܂��傤
�@�P�j �_���v�l�̓G�͌��ߕt���A�v�����݂ł��B
�@�@�Ⴆ�A�c�ƕ�̏�ł̉c�ƃ}���̔����B
�@�@�u���̂�������_���ȂB��肾��B�V�������i(�T�[�r�X)���K�v���B�v
�@�@�@���̔����ɁA�F�œ�������Ă��Ă����X������͎v�����܂���B
�@�@�t�@�V���e�[�^�[�Ȃ炱�����₷��ł��傤�B
�@�@�u�ǂ����_���Ȃ̂ł����H�v or �u���Ɣ�ׂă_�����Ɣ��f�����̂ł��傤���H�v
�@�@�u���܂蔄��Ă��Ȃ��B ���g�͂����͂��Ȃ��B�v
�@�@�u���㍂���ڕW�ɑ��ĒႢ�Ƃ������Ƃł����H�v
�@�@ or �u���������āA���g���ǂ��Ɣ��f�����̂ł����H �i���ł��傤���H�v
�@�@�u�����A1�����Ɂ����ʂ͔����ƍl���Ă������ǂ˂��B�����ʂȂB�v
�@�@�u���������ɁA�����ʂƗ\�z�����̂ł����H�v
�@�@ or �u�����͔��ꂽ�̂ł��ˁB ����Ɣ����Ă��ꂽ���X�͉��𗝗R�ɑI�̂ł����H�v
�@�@�Y�Y�Y
�@�@���͂ɏ����Ƃp�b���ōs���悤�ȁA������O�̕��͂Ȃ̂ł����A
�@�@����I�ɂȂ�����c�̐Ȃł́A�����̊m�F��w�ʂ��ǂ����Ă��a���ɂȂ�܂��B
�@�@�K�v�Ȃ̂́A�����̍Ċm�F�B
�@�@�v�����݂Ǝ������������ĂȂ����H�@�����͊m�����H�@���ʊW�͐��������H
�@�@������ĉ�������Ȃ��̂��H�@����Ȏ���𓊂������邱�ƂŁA�_���I�Ȏv�l��ۂ̂��t�@�V���e�[�^
�@�@�[�̖����ł��B
�@�@�_���v�l�𑣂����߂̗�Â���ۂ��߂ɂ́A�ЊO�̕��╔�O�҂��t�@�V���e�[�^�[�����s���̂��a�d�r�s
�@�@�ł��B
�@�@�ł��A�����������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ꎞ�A�����҈ӎ��𔖂ꂳ����ׂɁA�b�������̗ւ��R������Ē��߂Ă���
�@�@������z�����Ȃ���v�l���Ă݂ĉ������B�f�\�V�G�[�V�����ƌ����e�N�j�b�N�ł��B
�@�Q�j�@�_���I�Ȏv�l�𑣂���b��
�@�@�c�_�������Ƃ����Ƙ_���I�ɂ��邽�߂̉�b�����Љ�܂��B
�@�@���t�̒�`���s���m�j
�@�@�@�u������������������Ƃ������t�̎g���������������Ȃ��̂ŁA������Ă��������܂��H�v
�@�@�b�̑O�s���m�j
�@�@�@�u���̂����l����̂��A���܂ł̘b�ɂ͉����O�����������̂ł����H�v
�@�@�����ƈӌ��̍����j
�@�@�@�u����͂��Ȃ��̍l���ł����āA�Ⴄ�l���̕�������������̂ł́H�v
�@�@���������������Ȃ��j
�@�@�@�u�����l���闝�R���A�F����ɂ�������悤�ɉ�����ĉ������B�v
�@�@�@or �u�ے�Ȃ��闝�R���A���m�ɂ��Ă��������܂��B�v
�@�@�s���̂悢�Ⴞ���������Ƃ��Ă���j
�@�@�@�u���Ȃ��̂��������ꍇ�����肻���ł��ˁB�ł��A�����łȂ��ꍇ������܂���ˁB�v
�@�@�߂����ɂ�����Ȃ����Ƃ������Ƃ��Ă���j
�@�@�@�u����ȃP�[�X�͒���������܂��H�@�����Ɛg�߂ň�ʓI�Ȏ���Ő������ĉ������B�v
�@�@�����B�����̊�������Ƃ��Ă���j
�@�@�@�u����͂��̉�Ђ����Œʂ��郋�[���Ȃ̂ł͂���܂��H�@�����ł͕��������Ƃ�����܂��B�v
�@�@���_���s���m�j
�@�@�@�u���_���܂Ƃ߂Ă��������܂��B�v
�@�@�@or �u�E�E�i�����j�Ƃ������Ƃł��ˁB�F�����낵���ł����H�v
�@�@�@or �u�ł́������A���T�܂łɁ����ׂĕ���Ƃ������Ƃł��肢���܂��B�v
�@�@�ǂ��ł��A�@�b�̑O���@�@�A�b�̍����@�@�B�b�̌��_�@���̂R�_�ɓI���i���ċ�̉�����̂ł��B
�@�@�Ƃ͌����Ă��A������U�����Ċ���I�ɂ��Ă͘b���i�݂܂���B�U���ł͂Ȃ��w�E�A�b�₻�̍����̋��
�@�@�������肢��������ł���Ă݂ĉ������B
�@�@�v���o���ĉ������B�t�@�V���e�[�V�����͑Ό��ł͂Ȃ��A�~�������Ăd�������ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill16�@ �t�@�V���e�[�V��������R�E���i�R���t���N�g�j������
�@�@�t�@�V���e�[�V�����̖ړI�́A��c��v���W�F�N�g�́u���ӌ`���v�ł��B
�@�@����́A���̍��ӌ`����j�ޑΗ��i�R���t���N�g�j�̉����ɏœ_�ĂĂ݂܂��B
�@�� �펯��U��Ԃ�
�@�@�܂��A����ł��B
�@�@�i��҂Ƃ��Ă̂��Ȃ����A�Q���҂̑Η������܂��܂Ƃ߂悤�Ƃ��鎞�A�ǂ̂悤�ȕ��������l���܂����H
�@�@�@�E�E�E�@�u�Η�����ӌ��E�咣�̍ő����T��B�v�@����ȓ����������Ǝv���܂��B��������̐���
�@�@�@�@�@�@�Ȃ̂��Ǝv���܂����A���҂��[������ő�����Č������Ă��܂����H
�@�@���ǂ́A���̑傫�ȕ���咣���_���I�ȕ��̈ӌ����ʂ�����A�n�ʂ̍��������̃W���b�W�����g�ɗ�����
�@�@�肵�Ă��܂��H
�@�@�����A�����n�ʂ̍����������肷��̂Ȃ�A�킴�킴�b�������Ɏ��Ԃ��₳���A�ŏ�����n�ʂ̍���
�@�@���Ɏw�����Ă��炤�ق��������I�ł��B
�@�@�ӎv����̏�ɎQ�������Ƃ������� �i�܂�A���o�C���j�ŁA�[���������߂��悤�ȋC�����Ă��A�S����[
�@�@�������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���莖�������X���s�Ɉڂ���Ȃ�����������܂��B�@�E�E�E�o������܂��H
�@�@�ł́A���̏펯�I�Ȃ����ɕs�����Ă��邱�Ƃ͉����H�E�E�l���Ă݂ĉ������B
�@�� �Η��̌����������T��
�@�@�Η��̌�����[�I�Ɍ����ƁA���݂��̎咣�i�_�_�j���قȂ邩��ł��B
�@�@�Ƃ��낪��U�A����I�ɂȂ��Ă��܂��A����̈ӌ������čl���邱�Ƃ͏o���܂���B
�@�@�ӌ����Ε����قǁu����̈ӌ��͎����̍l���ƈႤ�ȁB�v�Ǝv���A�w�Ⴄ�x�@�Ƃ����C�������[�܂����
�@�@�ł��B
�@�@�����ŁA�ȑO��������t�@�V���e�[�^�[�̎d�����v���o���ĉ������B
�@�@�@�@ �Q���҂ɂ�����ƈӌ������킹��B
�@�@ �@�@�E�o���邾���S���ɔ���������@�i�܂��͔ے肹���ɑS���Ŏ咣���j
�@�@ �@�@�E�����̈ӌ���������Ɗm�F����
�@�@�@�A ����I�Ȕ����A�_�_�ɊW�̂Ȃ��咣�͍T��������B
�@�@�@�B �����҂̈ӌ��̓��e�����A�_�_�A���R�A�����W���m�ɂ���B
�@�@�@�C ���̎Q���҂ɔ����҂̈ӌ��𗝉�������B
�@�@�@�D �[���ł��Ȃ��҂ɂ́A�[���ł��Ȃ����R�m�ɂ��Ă��炤�B
�@�@�����A�܂��̓t�@�V���e�[�^�[�Ƃ��āA�Η��̌������_�_�̈Ⴂ�m�ɂ��Ă݂ĉ������B
�@�� ��������n�܂鋦���W
�@�@���́A�Η������̗���̒��ŏd�v�Ȃ̂́A�����B�܂�ӌ��̓��������m�ɂ��邱�Ƃł��B
�@�@�����A�����ڂ��b������Ȃ���Ȃ�Ȃ��c�肪����Ȃ�A���킸�Q���҂������ɂ����ӂ������ȋc�肩
�@�@��n�߂ĉ������B
�@�@���ɁA���݂����悭�m��Ȃ��Q���҂̏ꍇ�A���肪�����Ɠ����l���������Ă���Ǝv����悤�ȉ�b���ς�
�@�@�d�Ȃ�A���݂��ɋ����ӎ����萶���A�Ⴆ���ł�����̈ӌ��Ɏ���݂����Ƃ����C�����ɂȂ�܂��B
�@�@�����A���������Ă��̐}���ł���ˁB�@�i��������O������܂����B�j
�@�@�܂��A�Η������ӌ��̏ꍇ�A���������m�ɏo����A���݂��̈ӌ��̑��� �� �_�_���X�ɖ��m����
�@�@���Ƃ��o���܂��B
�@�@�@�u����l�̈ӌ��ňႤ�����́����ł��ˁB����ȊO�͓����l���ł���ˁB
�@�@�@�@�ł́A�����̕����ɂ��Ă��݂��̎咣���Ċm�F���Ă݂܂��傤�B�v�@�@�E�E�E�E ����Ȋ����ł��B
�@�� ���f����l����
�@�@���������Q���҂���ÂȎ��Ɍ��߂Ă����ׂ����Ƃ�����܂��B
�@�@�@�u������ɕ����������肷��̂��B�v�@�E�E�E�E �ɂ߂ďd�v�ł��B
�@�@���̑傫����n�ʂ̍����ɗ���Ȃ����f����߂�̂ł��B�o����A��c�̖`���ɎQ���ґS����
�@�@���߂�̂��]�܂����̂ł��B
�@�@���v�A�ڋq�����A������ ���X�B���f������m�Ȃ�ŏI��������Ղ����A�c�_�̒E�����h���܂��B
�@�@�Ⴆ�Έȉ��̂悤�ȋc�_�B
�@�@�@�@�u��������̈ӌ��͔�p�I�ɖ�������B�v
�@�@�@�@�u��������̈ӌ������A���������R������B�v
�@�@�@�@�u�l���A��������̂������ၠ�����̋��͂������Ȃ��Ǝv���ȁB�v
�@�@�ꌩ�A�c�_��������Əo���Ă���悤�Ɏv���܂����A
�@�@��������̎咣�Ɓ�������̎咣�������I��Ŕ�r�ł��Ă���ƌ�����ł��傤���B�@���̂�����
�@�@�Ō�Ɍ��_���o���̂́A���ǁA�ŏ�ʂ̕��ł��傤�B
�@�@�厖�Ȃ̂́A���m�Ȕ��f��ł��ꂼ��̎咣���r���邱�Ƃł��B
�@�@�@�u��p�ʂɂ��Ă���l�̈ӌ����r���܂��傤�B�v
�@�@�@�u�ł́A���ʂ��o��܂ł̊��Ԃɂ��Ă���r���Ă݂܂��傤�B�v
�@�@�@�@�Ƃ����悤�ɁA���H���R�Ɨ\�ߍl�������f��ɏƂ炵���킹�Ă������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B
�@�@����ȓ���b�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@�@�ł��C�U�A�c�_�����M���Ă���ƁA���X�����I�Ȕ��f���ł��Ă��Ȃ��Ⴊ�����̂ł��B
�@�@����A���R�Ƃ����c�_�ɂs�q�x���Ă݂ĉ������B
�@�� �����鉻�ŋ��ʔF�������
�@�@�ӌ���ڂɌ�����`�Ő�������B �E�E�E�E �ŋ߂͂��́u�����鉻�v�ł��B
�@�@��c�̎�ނɂ����܂����A�`���[�g��t���[�ŎQ���҂̈ӌ���_�_�A�Ȃ�����܂Ƃ߂āA�Q���ґS
�@�@�����ӌ��̑����⑊�����ڂŕ�����悤�ɂ��܂��B
�@�@�����Ȃ��_�u��Ȃ� �i�~�b�V�[ �� MECE�ƌ����܂��j �A���m�Ɉӌ��₻�̔w�i������ɂ́u�����鉻�v
�@�@�@�i�܂���̨�����j�@���ߓ��ł��B
�@�@�Ⴆ�A�����v���}��n���}�B�g�������Ƃ���܂���ˁB�����p�b�ŏK�������Ƃ̓t�@�V���e�[�V������@
�@�@�ł��g���܂��B
�@�@�����܂œǂ�ŁA�Η�������������@���v��������������������ł��傤�B
�@�@�Ⴆ�ΐ���́A���v�A�ڋq�����A�������̊e�X�ɃE�G�C�g�t���A���_�t�������Ċe�Ă̗D��m�ɂ�
�@�@��B�@�Ă��ǂ����������ł͂Ȃ��A �����B�̖ړI���ʂ����̂Ɉ�ԓs�����ǂ��̂͂ǂꂩ�����m�ɂ�
�@�@��܂��B
�@�@�����b�g�E�f�����b�g��S���Ŋm�F���A�œK�Ă��l����̂��L���ł��B
�@�@�Ⴆ�p�b���K���Ă��A�o�c��c�ɗp������͂܂����܂���B
�@�@�ł����̎���ɋ��߂��Ă���͍̂����I���f�Ȃ̂ł��B�z���C�g�{�[�h�ɏ����o���悤�ȏ�ʂłȂ���
�@�@���A�����̎茳�Łu�����鉻�v���Ă݂ĉ������B
�@�@�������@�����鉻 �i�O���t�B�b�N���j �̗��@�@pdf̧��
�@�� �����܂ł���Α��������L��
�@
�@�@�����ɔ������ċc�_�������A�������Ō��_���o���Ă��[�����͍��܂�܂��B
�@�@��l��[�łȂ��A���_�P�O�_�ŕ������[�o����Ό������������ł��傤�B�@�S���̈ӌ��ŁA�V������Ă�
�@�@���グ���B�@����Ȋ��o���R���Z���T�X�Ȃ̂ł��B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�����u�����t�@�V���e�[�V�������C�̍u�t�̕� (���{̧��ð�����) �H���A
�@�@�R�[�`���O�X�L���̓t�@�V���e�[�V�����ɖ𗧂��A�R�[�`���O���S���n�Ȃ̂ɑ��A�����ȗ���Ŏv�l
�@�@�n�̗�����E���䂵�Ă����̂��t�@�V���e�[�V�����Ƃ̂��Ƃł����B
�@�@�� �PstSTEP�@�@�v�l�̔��U�@�@�ӌ��i�R���e���c�j�������o����̉�����
�@�@�� �QndSTEP�@�@�v�l�̐����@�@�_�_�����A�����W�⍪���𖾂炩�ɂ���
�@�@�� �RrdSTEP�@�@�v�l�̎����@�@�t���[�����č\�z���A�V�����A�C�f�A�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�
�@�@�Ⴆ�Ώ�L�̗���ɉ����āA�v�l�̗���𐧌䂷��Ɨǂ��Ƃ̂��Ƃł������A
�@�@���l�̍l���ł́A�ӌ��������o������Ƃ��ăR�[�`���O�����p���邾���ł͂Ȃ��A����̗���E�C����
�@�@�ɂȂ��čl������A�������q�ϓI�Ɍ����肷��R�[�`���O�̑O�����ȕ����������Ɗ��p���邱�ƂŁA�t�@�V
�@�@���e�[�V�������X�Ɍ��ʓI�ɂȂ�悤�ȋC�����܂��B
�@�@����̌��C�́A�p�b���R�[�`���O����̓I�ɂ͒m��Ȃ����Ŗ����ł������A�p�b�ƃR�[�`���O�̗������w
�@�@���X�ɂƂ��Ă̓t�@�V���e�[�V�����͂��̂������߂��ɑ��݂���B �E�E�E�E ���͂����v���܂��B
�@�@����A���Ȃ��̃`�[���̈ӌ��̐����ɖ𗧂ĂĂ݂ĉ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill18�@ �����̌��̒I����
�@�@�ߋ��̐����̌�������������B�F����̉��ɂ��܂��H
�@�@�������A�ߋ��̐����̌����A���݂̎d���ɖ𗧂\���͂���܂��B
�@�@�ł��A�ł����킹�̍Œ��Ɂu�̂́����̂����ł��܂���������v�ƌ������܂�Ă��A�ō��킹���E������
�@�@��A�b����߂肵���o���̂�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�@���̂Ȃ�A�ߋ��̐����̌��������̑����̓x�e�����Ōo���L�x�ȕ��A�n�ʂ̍������������肵�āA���
�@�@�Ƃ����^�e�Љ�̒��ł́A�����ł��Ȃ����݂�����Ȃ̂ł��B
�@�@���܂�������������^���āA�����ւ̘J�͂��o���邾�����炷�̂̓r�W�l�X�ł���Ώ퓹�Ȃ̂ł����A
�@�@�^���Ė��ɗ����ǂ����̓P�[�X�o�C�P�[�X�B
�@�@�厖�Ȃ͖̂��ɗ�����Ȃ̂��ǂ����A�\���Ȍ����u�����̌��̒I�����v�����邱�Ƃł��B
�@�@�ł́A�ǂ̂悤�ɂ�������̂ł��傤���H
�@�� �P�D�ߋ��̌���
�@�@�ߋ��̐������������������炵�����ʂ́A���������������̂��낤���H
�@�@�\���Ȑ��ʂ��������̂��낤���H
�@�@�ˁ@�Ƃ����A�ǂ��b�͌֒�����A�����b�͖����������Ƃɂ��ꂪ���ł��B
�@�@�@�@ ���ۂɂ́A���s�������炵����������Ȃ����A���X���鐬�ʂ����������m��܂���B
�@�@�@�@ �K���A��̓I�Ȏ���Ŏ������m�F���Ă݂܂��傤�B
�@�� �Q�D����̌���
�@�@�ߋ��̂��������������ƁA���݂͓̏����Ȃ̂��낤���H
�@�@�������͂�����̂��낤���H
�@�@�ˁ@���܂����������Ɠ������{���ɍČ��ł���̂��ƁA���݂̏�F�X�ȗv�f���猟���Ă݂ĉ�
�@�@�@�@ �����B������������A����Ⴄ�����m��܂����B
�@�@�@�@ �Љ�E�o�ς̏A�ڋq�̃j�[�Y�A���Ђ̕������A���ЂƂ̋������A�����Ƃ͏��قȂ�v�f��
�@�@�@�@ ���ł�����܂��B
�@�@�������A�����̌��������ɁA����Ȃ����ł��܂������̂ł����H�Ƃ��A���s�����Ă������ł���B�Ƃ�
�@�@������ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B
�@�@�ł��A
�@�@�u��ɂ��܂��������킯�ł��ˁB�v �Ƃ��A�u�y���������̂ł��ˁB�v �Ƃ����Ă�悤�ɐu�˂�A
�@�@�u���\��ς�������B�v �Ƃ��A�u�o��������������o�����̂���B�v �Ƃ��A�P���ɂ͂��܂��s���Ȃ���������
�@�@������Ă���邩���m��܂���B
�@�� �R�D�u���o���v�͑�R�K�v
�@�@��p��m�E�n�E�Ƃ����u���o���v������������Ȃ��̂͂������s���Ȃ��Ƃł��B
�@�@��ЂƂ��āA����ȏȂ珫���͂Ȃ��ƍl����ׂ��ł��傤�B
�@�@�����̐F�X�ȏɔ����邽�߂ɂ́A���Ȃ��̉�Ђ��A���Ȃ��̃`�[�����A���Ȃ����g���A�u���o���v��
�@�@���₷�K�v������̂ł��B
�@�� �S�D�ߋ��̐����̌������ǂ���
�@�@�N���ɉ����t����ꂽ�ߋ��̂������g���̂͂��������܂��A�ǂ����@���v�����Ȃ����A�s��
�@�@�l�������ɁA�ߋ��̂��������ǂł��Ȃ����ƍl����̂́A���h�Ȑ��U�@�ł��B
�@�@�č��̍L���}���ł���W���b�N�t�H�X�^�[�͒��� �w�A�C�f�A�̃q���g�x �ŁA�S���V�����A�C�f�A��ˑR�v
�@�@�������߂̕��@�Ƀy�[�W�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�����̂����̑g�ݍ��킹�ŐV�������z���l��
�@�@�Ă������Ƃ��Љ�Ă��܂��B
�@�@�_��Ȏv�l���_��Ȕ��z�ݏo���B�܂��_��Ȏv�l��H���`������B����ȓ��e�ł��B
�@�@�����A���P�`�R �ł͉ߋ��̎������瓦��邱�Ƃ�������܂������A�ߋ��������_����̂Ă�
�@�@�����̂ł��B
�@�@���������ǂ����ȂA�ƌ�����ƍ���܂����A
�@�@�l�̌����Ȃ�Ȃ��Ă��邾���ł̓_�����Ƃ������Ƃ����͏\���������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill19�@ �v��̃e�N�j�b�N
�@�@��c�Ŕ����̒������B�悭��������Ⴂ�܂���ˁB
�@�@�{�l�͈ꐶ�����A�b�̓��e��`���悤�Ɛ������Ă���̂ł����A�����Ă��鑤�ɂƂ��ẮA�b���f�B�e
�@�@�B�[���ɂȂ�Ȃ�قLjӖ��s���̐����ɂȂ��Ă��܂��B
�@�@�v����ɉ������������̂��H�@���_���Ɍ����Ă���B�E�E�E����ȐS�̐����������Ă������ł��B
�@�@���́A����̃^�C�g���Ƃ͗����ɁA�b��v��֗��ő������̂���e�N�j�b�N�Ȃǐ��̒��ɂ͑���
�@�@���Ȃ����Ƃ��A�ŏ��ɂ��`�����Ă����܂��B
�@�@�����������Ƃ⎩���̑z�����ǂ����m�ɂ��邩�����ꂪ�v��̃e�N�j�b�N�Ȃ̂ł��B
�@���r�s�d�o�P�@���̘b�������̂ł��傤�H
�@�@�ŏ��ɁA�b���v��ł��Ă��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��A�b���������R���l���Ă݂܂��B
�@�@��P�̗��R�́A�������̂��Ƃ��l���Ă��Ȃ�����ł��B
�@�@��c�̏�ŁA�������̏W���͂���������̂͐��X�Q�O�����炢�ł��B���炭�A�b�͓r���܂ł�������
�@�@�Ă��炦�Ă��܂���B�H��̉�c�Ȃ珮�X�ł��B
�@�@��Q�̗��R�́A�b���v��ł��Ă��Ȃ�����Ȃ̂ł��B
�@�@�`����K�v�̂Ȃ����ƁA���Ŕz��ςނ��Ƃ����X����ׂ��Ă��A���ǂ͖Y�ꋎ���Ă��܂��܂��B
�@�@�X�L������l�������Q�T�Y�p�̗��Z�@�ʼn�����܂������A�l�͍ŏ��̂Q�O���łS�Q����Y��܂��B
�@�@�E�E�E�E�E�E �G�r���O�n�E�X�̖Y�p�Ȑ��ł��B
�@�@���łɌ����ƁA�P���ԂłT�U���A�P���łV�U����Y���̂ł��B
�@�@����I�ɂ���₱���Ƙb�����Ǝ��̂����Ԃ̘Q��ł����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@���r�s�d�o�Q�@�b���ړI�A�l���Ă��܂����H
�@�@����ł́A���̘b���v��Ă��Ȃ��̂��l���Ă݂ĉ������B
�@�@��P�̗��R�́A�������b���ړI�����m�łȂ�����ł��B
�@�@�l�O�Řb�����āA�����Ă��炦�n�j�Ȃ̂��A����Ƃ���c�̏o�Ȏ҂Ɏ����̎咣�𗝉����Ă��炢�A
�@�@���炩�̍s�����N�����Ă��炢�����̂��A����ɂ���Đ����̎d�����ς���Ă���͂��ł��B
�@�@�Ⴂ���A��i�̕��Ɍ���ꂽ���Ƃ͂���܂��H
�@�@�@�u���_���Ɍ����B�v�@�@�u���ǁA���O�͂ǂ��������̂��H�v
�@�@��c�ł����Ă������ł��B
�@�@�@�@�E����𗝉����ė~�����B
�@�@�@�@�E�ꏏ�ɑ���l���ė~�����B
�@�@�@�@�E�ӌ����o���ė~�����B
�@�@�@�@�E���������B�@�@�@�@�@�@�����v�]���b���ړI�m�ɂ��āA�ŏ��ɓ`���܂��傤�B
�@�@���͖`���Ł@�u�����������Ƃ⎩���̑z�����ǂ����m�ɂ��邩�����ꂪ�v��̃e�N�j�b�N�v�@��
�@�@���`�������̂́A����Ɠ������A�b�̃R���Z�v�g���ŏ��ɖ��m�ɂ�������������Ȃ̂ł��B
�@�@�ł́A�b���v��Ă��Ȃ���Q�̗��R�B
�@�@����������̎咣�m�ɂ��邱�ƂɊ���Ă��Ȃ������ł��B
�@�@�b���ړI�͖��m�ɂ����B�ł����̓��e�����܂��`�����Ȃ��B
�@�@�ł��A�O�q�̂悤�ɑ������ɂ���e�N�j�b�N�Ȃǂ���܂���B�v��͊���Ȃ̂ł��B���K���Ă݂�
�@�@���傤�B
�@���r�s�d�o�R�@�g�߂ȗv��Ɋw��
�@�@�u�ČR�ĕҁB���{�A�������ӂ�f�O�B�v�@�u�I����ÁA�h��錻��B�v�@�����A�V���L���̌��o���ł��B
�@�@�s�u���̃��C�h�V���[�̕����ɂ́A�u���[�������A����Ǝw�����\�B�v
�@�@�L���̎咣�E�_�_��ԑg�̓��e�������ɗv�Ă��܂���ˁB
�@�@��ʋL���ł���A�{���̑O�ɍX�ɗv�L�ڂ���Ă��܂��B�ڍׂ�m�肽����A�{����ǂ�
�@�@�i�߂�������A�������Ȃ���Ύ��̋L���Ɉڂ��B
�@�@��c�ł̔����������悤�ɁA
�@�@�@�@�@ ���@�_�A�_�@�_
�@�@�@�@�A �v�@�|
�@�@�@�@�B �ځ@���@�@�Ƃ��������őg�ݗ��ĂĂ݂܂��傤�B
�@�@�Ԃ����{�Ԃł͂Ȃ��A���O�ɑg�ݗ��Ă��s���A������m�F���Ă����B
�@�@�T���Ԃ̃��n�[�T���B���ꂾ���ŁA���Ȃ��̔����͌��Ⴆ��͂��ł��B
�@�@����ɁA�����āA
�@�@�B�ڍו����͂ł��邾���Z�����āA�Ō�ɂ�����x�A�@���_�A�_�_���J��Ԃ��A�i�Ⴂ�ɑ����
�@�@�L���Ɏc��܂��B
�@���r�s�d�o�S�@�������g�̍s����C����v�Ă݂�
�@�@�v��̌��ʓI�ȗ��K�B
�@�@����͎����̓��X�̍s����A�C���A�l����v�Ă݂邱�Ƃł��B
�@�@���ꂪ�ł����J���Ȃ��B�E�E�E�E�m���ɁB
�@�@�ł������ƋC�y�ɍl���A�����̍s���Ƀe�[�}�����^�C�g��������ƍl���Ă݂ĉ������B
�@�@�u���E�̒��S�ň������ԁv�@������ƕ�����ɂ������ǁA���ƂȂ��V�[�����ڂɕ����ԁB
�@�@�f���s�u�h���}�̃^�C�g���A�{�̑薼�B����Ȋ����Ŏ����̍s����v�Ă݂Ă����\�ł��B
�@�@�����̍s���̖ړI��A�咣���N���ɂȂ��Ă��܂��B
�@�@�������A���ꂾ���ł͑厖�Ȃ��̂�������Ă��܂��B
�@�@�ł́A�q���g�ł��B�@�@�E�E�E�E�E�E ���E�̒��S�ň������̂͒N�Ȃ̂ł��傤�H
�@�@�����A�v��ɑ�Ȃ̂́A���m�ɂ��邱���Ȃ̂ł��B
�@�@�Ⴆ�A
�@�@�V�C�̂������̋C�����@�u�������z���܂Ԃ����v�@�Ƃ����悤�Ɉꌾ�ŕ\������B
�@�@�N���Ɂ@�u�܂Ԃ������z�v�@�ƌ����Ă�����ɂ͉��̂��Ƃ�������܂���B
�@�@�ł��A�u���͑��z���܂Ԃ����v�@�ƌ����A���Ȃ��̋C�������v��ē`���܂��B
�@�@�ǂ��ł��A���̂��炢�Ȃ�o����ł��傤�B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�R�c�Y�[�j�[����i�R�����j�X�g�j�̕��͂Ŗʔ������̂�����܂����B
�@�@���炾��A����₱���Ǝ����̉������⌾�������鑧�q�ɃI�J�� (��e) ���ꌾ�B
�@�@�u�₵���ˁA���B�v�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@���ꂼ�v��̐^���ł͂Ȃ����ƁB
�@�@���Ȃ����A�Ȃ������̑z����v�Ă݂����Ȃ�܂��B
�@�@����̎咣��v�邱�Ƃ́A�u��M���� �� ���������v�@�Ƃ����v�l�̌n���A
�@�@�u�l���� �� ���M�����v�@�Ƃ����v�l�̌n�ɕς��邱�Ƃł�����̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill20�@ �������͂ɂ��čl����
�@�@���N�����ƂR�T�ԁB��|���̋G�߂ɂȂ��Ă��܂����B�@�@�i2006�N12���ɏ����Ă��܂��B�j
�@�@�@�E�E�E�E �ƌ����Ă��A���̒��A�N���ɑ�|�������������ł��Ȃ��ł��傤�B
�@�@�Г������Ă��A�����肪�Y��ɕЕt���Ă����������A���ނ��R�̂悤�ɂȂ��Ă�����A������A
�@�@������炪�U�����Ă���������Ă���܂��B
�@�@�ŋ߁A�������͂Ƃ������Ƃ��悭���ɂ��܂����A�d���̌��������߂�閧���B����Ă���炵���̂ŁA��
�@�@�ׂĂ݂܂����B
�@�� �������Ƃ́A���������邱�Ƃł�
�@�@�g�̉��̕Еt���ɂ́A���i�������Ƃ������܂����E�E�E�E�B
�@�@�I�t�B�X�̊��̏オ�����Ⴒ���Ⴕ�Ă�����́A���炭����ɂ��F�X�ȕ��������Ⴒ����Ƃ��Ă���͂��ł��B
�@�@�ȒP�Ɍ����A���̂����Ⴒ����Ƃ́A�u�����፬���̏�ԁv�B
�@�@�l����ɁA�K�v�Ȃ��̂ƕs�K�v�Ȃ��̂��A�핪������Ă��Ȃ���Ԃł��B
�@�@���R�A�����s�����N�������Ƃ��Ă��A���������g���郊�\�[�X�i����E��̎����j�͂ǂ�Ȃ̂��A�T������
�@�@�̂ɋ�J���܂��B�@���ꂪ�A����̍s���͂��Ђł̎d���͂̑������ƂȂ�킯�ł��B
�@�@�������͂�A�������ڂ��d���͂̌���ɂȂ��� �Ə��������̂قƂ�ǂ́A�g�̉��̕��E����c�����邱��
�@�@���A�������g���g���郊�\�[�X �i�����j ��c�����邱�ƂɂȂ���A�s���͂�d���͂����߂�Ƌ����Ă��܂��B
�@�@�����Ⴒ���Ⴕ�Ă���ق������S�n�������A�Ȃ�čl���́A�͂Ȃ��疳������Ă���悤�ł��B
�@�� �������Ƃ́A��̑I�����邱�Ƃł�
�@�@�����g�́A�ƒ�̐F�X�Ȏ��������핪������̂��s���ӂŁA���ł��̂Ă��ɂƂ��Ă������Ȃ̂ł����A
�@�@�U���͂������ɂ�����Ɣ��ɋl�߂ĕ��u�ɂ��܂��Đ������Ă��܂��B
�@�@�������A�d�����Ēu�����ƂƐ������邱�Ƃ́A�S���Ⴄ�悤�ł��B
�@�@�g���镨�Ǝg���Ȃ������A���m�Ȋ��݂�����Ŏ�̑I�����邱�ƁB
�@�@�܂�A����Ȃ����͂������Ǝ̂Ă邱�Ƃ��A�������͂ɂ����鐮���ł��B
�@�@�Ⴆ�A
�@�@������̏��ށA�d�|���蒆�̏��ށA��Ƃ������������ނ͋�ʂ���B��Ƃ�v���W�F�N�g���I��������A
�@�@�A�b�v�f�[�g����Â��Ȃ������ނ͎̂Ă�B ���̈ʂ̎�̑I����́A�������͂̊�{�̂悤�ł��B
�@�� �������Ƃ́A�V������ۂ��Ƃł�
�@�@�������ڂ��K�v�Ȃ͕̂S�����m�B�ł����ꂪ�ł��Ȃ���B�����̕��͂��������ł��傤�B
�@�@���������C�����ł��B
�@�@�ł��A�������ڂ��ł��Ȃ��̂́A���̖ړI���s���m�ł���̂����R�̂悤�ȋC�����܂��B
�@�@�������ڂɂ��d�����������������̂Ȃ�A���̃L�[���[�h�͑N�x�B
�@�@�I�t�B�X�̂ɂ�����g�̉��̐������ڂɂ�����ړI�́A����Ӗ��A�d���ɕK�v�ȏ��̑N�x��ۂ���
�@�@�Ȃ̂ł��B
�@�@�t�@�b�V�����Ɠ����悤�ɁA���͑N�x���ۂ���Ă����A�����̍s���̃Z���X�����߂܂��B
�@�@���Ȃ킿�A�g�̉��̐������� �� ���̎�̑I�� �����������ƂɂȂ���̂ł��B
�@�� �ł͉����A�ǂ�����Ď̂Ă邩
�@�@�������I�Ȑ������ڂ��s�����߂Ɏ̂Ă�ׂ��R�̑z��������܂��B
�@�@�@�@�����������Ȃ��@�@�������g���͂��@�@���ߋ��̐����̌��@�ł��B
�@�@���̂R�������̓�����̂ĂȂ�����́A�d����̌������ɂȂ��鐮�����ڂ͂ł��܂���B
�@�@���㏊�L�������Ă��A�����̔\�͂����߂邱�ƂɎ����邱�Ƃ̂Ȃ�����O��I�Ɏ̂ċ���A�c��̂�
�@�@����͂ƂȂ���̂���B�Ƃ��������ł��B
�@�@�����Ċ̐S�Ȃ̂́A��̑I���f���邽�߂̎��Ԃ͍ŏ����ɂ��邱�ƁB
�@�@�l����l����قǁA�̂Ă��Ȃ��Ȃ邩��ł��B
�@�@���A�d���O�̂P�O���Ԃō������̏��ނ����悤�B�ʂ̋C�����ŁA
�@�@�@�@�@��ΕK�v�ȕ��@�@�A�ǂ��炩�ƌ����ΕK�v�ȕ��@�@�B�K�v�łȂ����@�̂R�ɕ����āA
�@�@�B�͑��S�~���s���A�A�͂����P�ނ����Ȃ���S�~���s���B
�@�@���ނ��Еt�����Ƃ���ŁA��������Ƃ��Ă��̓��̎d�����͂��߂�B�������ł��傤���B
�@�� �������͖�������������A�C�����������ς肳���܂�
�@�@�d���ɏW���ł��Ȃ����̍ő�̗v���́A�ڂ̑O�ɏ��ނ��͂��߂Ƃ����ʂ̕�������A�C���U���Ă��܂�
�@�@���炾�Ə�����Ă��鏑�����������܂��B
�@�@�ł��A�����g�́A������ƈႢ�A�d�|�蒆�̐F�X�ȏ��ނ��Ƃ̗D�揇�ʂ��s���m���ƁA��̎d���ɏW
�@�@���ł����A��������������Ƃ���āA��������������ƂƂ����悤�ɏW���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�@������ɂ���A
�@�@������Ɛg�̉�肪�������ڂ���A�d���̗D�揇�ʁE�[�������m�Ȃ�A��������t��������̂��Ƃ�
�@�@���������������肵�A�����ς肵���C�����Ŏd���ɑł����߂�͂��ł��B
�@�� ���ꑋ���_�͂������͂̌��_
�@�@�r���̊��ꑋ�◎��������u���Ă����ƁA���̌����͊Ǘ�����Ă��Ȃ��Ǝv���A���̃r���͍X�ɍr�炳
�@�@���B�܂����̃r������u����A�X�S�̂ɍr�p���L����X���������Ă��܂��B
�@�@�E�E�E�E�E�@�Ƃ������_���u���ꑋ���_�v�ƌ����܂��B
�@�@�j���[���[�N�̃W�����A�[�j�s���͂��̗��_�Ɋ�Â��A�X�p����r�ꂽ����n���S�̗���������|���A�X
�@�@�S�̂̎�����}���������ł��B�i�������x�@�����啝�ɑ��₵�������Ȃ̂ł����B�j
�@�@���́A�������̊��̎��ӂ̎U�炩��́A���̗��_�̊��ꑋ�◎�����Ɠ����ł��B
�@�@���u������U�炩�肪�ǂ�ǂ�L���邩�ǂ����͕ʂƂ��Ă��A������ƕЕt�����s���A���̏�A�������ڂ�
�@�@�ꂽ��Ԃ��ێ��ł���A�����̋C���������͂̌��������Z�b�g����A���C���M�������܂�͂��ł��B
�@�@�����܂ŗ��_�Ȃ̂ŁA�l���͑傫���Ǝv���܂����A
�@�@�������ڂ̌��ʂ̈�Ƃ��ċC�����̃��Z�b�g���グ����͑����悤�ł��B
�@�� �d���̃v���C�I���e�B �i�D�揇�ʁj �l���Ă��܂���
�@�@���Ǝd���Ɋւ��Č����A�D�揇�ʂ����邱�Ƃ͏o���Ă��A���ׂ����Ƃ���炸�Ɏ̂ĂĂ��܂����Ƃ�
�@�@�ł��܂���B���ɁA�������Ԃɒǂ��Ă���悤�ȕ��́A�g�̉��̐������ڂ��ς�A�d���̐�
�@�@������ �i���D�揇�ʕt���j ���l���Ă݂܂��傤�B
�@�@�� �܂��́A�d���̃��X�g�A�b�v
�@�@�@�D�揇�ʕt���̑����́A�������Ă���d���̑S�̑���͂ނ��Ƃł��B
�@�@�@�����Ă���d�����v�����܂܂ɁA�S�ă��X�g�A�b�v���Ă݂܂��傤�B
�@�@�@�Z�����Z�����ƌ������ɁA�����Z�����̂Ɛu�˂Ă��A�����ƌ����Ȃ������肷��̂́A�d���̍��ڂ�S��
�@�@�@���̒��ł�����Ɣc���ł��Ă��Ȃ����Ƃ������ł��B
�@�@�� ���ɁA�d���̃E�G�C�g�t�� �� �w�@��
�@�@�@�d�v�Ȃ��́A�d�v�ł͂Ȃ����́@�A�ً}�Ȃ��́A�ً}�ł͂Ȃ�����
�@�@�@�@����Ȕ��f��ŁA�d���̃E�G�C�g���l���Ă݂ĉ������B
�@�@�@�@�` �F �d�v���ً}�Ȃ���
�@�@�@�@�a �F �d�v�ł͂Ȃ����A�ً}�Ȃ���
�@�@�@�@�b �F �d�v�����A�ً}�ł͂Ȃ�����
�@�@�@�@�c �F �d�v�ł��A�ً}�ł��Ȃ�����
�@�@�@�@�Ə��ʕt���A���X�g�A�b�v�����d���̍��ڂɂ`����c�̋L����U��܂��B
�@�@�@�@�@�i�}�g���b�N�X������Ɣ���Ղ��Ȃ�܂��B�j
�@�@�� �d���̏��v���Ԃ̔c��
�@�@�@���ߐ�܂ł̎��Ԃł͂Ȃ��A��蒼����s�ӂ̎d�����������ꍇ���l�����đ�܂��ȏ��v���Ԃ�ݒ�
�@�@�@���܂��B�@�����āA�w��̔[��������A��������X�g�ɒNjL���܂��傤�B
�@�@�@����ɂ���āA�b���Ǝv���Ă����d�������ԓI�]�T�������A�`�ł��邱�Ƃ��������邩���m��܂���B
�@�@�� �[�����l�����A���X�g����בւ���
�@�@�@�`���珇�ɁA���v���ԁE�[�����l�����A�d���̃��X�g����בւ��܂��B
�@�@�@�D�揇�ʂ̍������A�[���̑������ɕ��בւ��邱�ƂŁA���Ȃ��̎d���̗D�揇�ʂ͖��m�ɂȂ�܂��B
�@�@�ȏ�̎菇�́A��������Ƃ�낤�Ƃ���ƁA�ʓ|�������Ă��C���N���Ȃ��̂ŁA�ł��邾����G�c�ɁA
�@�@�����������x�ł���Ă݂܂��傤�B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@����Ȃ��Ƃ���Ă��Ȃ���Ǝv���������������m��܂��A�ȑO�A�Z�~�i�[��̍��e��œ�����̉�
�@�@�Ј������Ƙb������@�����A�蒠�̎g�����̘b��ɂȂ����ہA�F�����āA���T�̃X�P�W���[����
�@�@�ɁA���ׂ���ƁA�`�a�b�Ɠ����Ӗ��̗D��x�L���A�����L�����Ă��܂����B
�@�@�������A���T��������邩�A�������̖{��ǂނ��̗\�肪��������܂łт����菑����Ă���������l
�@�@�����āA���Ȃ�����܂������A���̒��ɂ́A�ڕW�Ɍ������āA���H���R�ƍs�����Ă���������ʂɂ���Ƃ�
�@�@�����Ƃł��B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�܂��A�����܂ł��Ȃ��ɂ��Ă��A���Ԃɒǂ��Ă��邩�琮�����ڂ��d���̗D�揇�ʕt�����ł��Ȃ��B
�@�@�@�E�E�E�E�E�E �ł͂Ȃ��āA
�@�@���Ԃɒǂ��Ă��邩�炱���A���܂ɂ͐������ڂ��A�������肵���C�����Ŏd���������I�ɂ���Ă݂Ă�
�@�@�������ł��傤���B
�@�@�����ł͂Ȃ��A�T�P��ł��A���P��ł��A���[�`���̎d�����Еt������ɁA�����̐g�̉���A�d���̓�
�@�@�e�����I�Ƀ`�F�b�N����K��������A����Ȃɋ�ɂł͂Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill21�@ �c�L���Ăԍs���̖@��
�@�@�ǂ����Ƃ��N����ƁA�����Ă��̕��́u�����̓c�C�e��������v�Ȃǂƌ����A�^�⏄�荇���Ɋ��ӂ��܂��B
�@�@�ł��A���ꎫ�T�Œ��ׂ��Ƃ���A�^���Ƃ� �u�l�̈ӎv�z���čK�E�s�K�������炷�́v �̂��Ƃł���A
�@�@�P�Ȃ���R �� ���荇���Ƃ͈قȂ���̂Ȃ̂ł��B
�@�@�Ⴆ�A��ӕ�������肪�����ɏo��Ƃ����̂͏��荇���A�܂���R�ł͂����Ă��^�ł͂���܂���B
�@�@�P�Ȃ���R�ł��܂��������������A�����Ɠw�͂��Ȃ���Ǝ��������߂Ă���ꍇ�͕ʂƂ��āA�����̕��́A
�@�@�^�����������E����̂��ƐS�̕Ћ��ł͐M���Ă���킯�ł��B
�@�@���́A�c�L��^��������s���̖@��������Ƃ����l����������̂ŁA���Љ�Ă݂܂��B
�@�� �C���[�W�͎��̉�����
�@�@���]�Ԃ�I�[�g�o�C�̂悤�ȕs����ȏ�蕨�ł́A�ڂŌ��������Ɍ������Đi��ł����ƌ����܂��B
�@�@�g�̂����R�ƃo�����X����邩��ł��B
�@�@�܂��A�S���w�̐��E�ł́A��������肽���Ǝv���Ă��邱�Ƃ��s�Ȃ��Ă���p��A�����̍s����d������
�@�@�܂������������Ă���C���[�W����ɓ��Ɏ����ƂŁA�����̍s�������ۂɂ��܂������ƌ����Ă��܂��B
�@�@�a�C���U�����鎋�o�C���[�W�����ɕ`�������邱�ƂŁA�a�C�̉����܂����Ƃ�����r�����̌�
�@�@�ʂ�����܂��B�i��w�I�ɂ͏ؖ�����Ă��܂��B�j
�@�@�ǂ����A�C���[�W��`�����Ƃ̓c�L���Ăԑ����ł���A�����̕��ɂƂ��āA�C���[�W�͍s�������[��
�@�@�ƂȂ�悤�ł��B
�@�@�����A���ꂩ���낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ����ۂɎv�������ׂăC���[�W�g���[�j���O���s�����Ƃ́A�s���̃�
�@�@�n�[�T�����s���A���s��h�����߂̊m�F��ƂɂȂ�Ɠ����ɁA���̏�ʂ��[���o�����S�����������Ƃ�
�@�@�����ʂ�����܂��B
�@�@�������A�C���[�W�ƌ����͈قȂ�܂����A�o���邾����̓I�Ɏv�������ׂ邱�ƂŌ��ʂ͑����悤�ł��B
�@�@�����Ă݂ĉ������B
�@�� ��������s������
�@�@�悭�����b�ł����A���͔���Ȃ���ΐ�ɓ�����܂���B
�@�@�������A����������Ƃ����ē���Ƃ͌���܂��A����Ȃ���Γ���m�����[���Ȃ̂͌���I�Ȏ���
�@�@�ł��B
�@�@�M�����u�������ƌ����Ă���킯�ł͂���܂��A��x����Ă݂����Ǝv�������Ƃ́A�䖝���Ă���
�@�@�����������Ƃ���Ă��܂��͂��ł��B
�@�@�X��ŗ~�����Ǝv�������ǏՓ������͂��₾�ȂƔ��킸�ɋA��A����ς蔃�����ƌ��߂ė����s���Ɣ����
�@�@��Ă����B�@����Ȍo���͂���܂��B
�@�@���������ɂ́A��X�ƍl����O�ɁA�܂��͍s�����Ă݂܂��傤�B�@���ꂪ�c�L���Ăԍs���̑����ł��B
�@�@�ƌ����Ă��A�݂������Ȃ��s������ƌ����킯�ł�����܂���B
�@�@���i���玩���Ȃ�̃��X�N���f�≿�l�ςm�ɂ�����ŁA�ǂ�ǂ�s�����Ă݂�B
�@�@���ꂪ�^�C�~���O���Ȃ��R�c�Ȃ̂ł��B
�@�� �p���̌���
�@�@�̏�ɂ��R�N�Ƃ����܂����A�ڕW�Ɍ������ăR�c�R�c�Ɠw�͂𑱂��邱�Ƃ͉����Ɍ����Ă��A �����ւ�
�@�@�ߓ��ł��B
�@�@���ꂱ���A�P�Ȃ鏄�荇���ɂ��܂��Ԃ���m�������đ��債�܂����A�d������ł���Γw�͂̌��ʂƂ�
�@�@�Ēm�������X�ɐςݏd�Ȃ�܂��B
�@�@�ł��A�����܂������Ȃ�����Ƃ����Ă����ɒ��߂Ă��܂����ɂ͌����ăc�L�͏����Ă��Ȃ��̂ł��B
�@�@�A���A���ʂȓw�́B����Ȍ��t������܂��B
�@�@�Ⴆ�A��Ƃɐ��肽���ƌ����̂Ȃ�A�˔\���Ȃ��Ă͎n�܂�܂���B �w�͂̕��������Ԉ���Ă��Ă͉�
�@�@�ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯�ł��B
�@�@�܂��͎����̋C������A�����s�������l������ŁA���ƌ��߂���Ƃ��Ƃ����Ă݂܂��傤�B
�@�� �ŏ��͂�������A�x�[�X�����
�@�@��������s������B�����͌����܂������A�C�P�C�P�ǂ�ǂ�ʼn����x���グ�čs������ƁA���܂��s���Ȃ���
�@�@���������̂������ł��B
�@�@�c�C�e�Ȃ��ƂȂ����������܂����A���́A�ł�����A�ڐ�̖ڕW�ɑ����ĊԈ���������ɐi��ł���̂�
�@�@�C�t���Ȃ�������A�s������̕ω��ɋC������̂��t���čs���Ȃ������肵�Ă���̂ł��B
�@�@�����Ȃ�C�������ǂ�ǂ�������ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�@��U�s���Ɏ��|��������A�����Ȃ�˂��i�܂Ȃ��ŁA������ƌv�������Ă������菀�������ăx�[�X�ƃy
�@�@�[�X�𐮂�����ŏ��X�ɉ����x���グ�Ă����B
�@�@���ꂪ�A���Ȃ��̍s���̃��`�x�[�V���������߁A���͂̕������S���Ċ������܂�Ă����}�������̂ł��B
�@�@�c�L���v��I�ɌĂэ��܂�Ă����B�@����ȏ�Ԃ���荞�݂܂��傤�B
�@�� �g�߂ȖڕW���c�L���Ă�
�@�@�P�N�łP���~���������Ƃ����ڕW�̎������͒Ⴂ�i�Ƃ�����薳���j�ł����A�R�����łP�O���~�߂悤�Ǝv
�@�@���Ύ������͔���I�ɍ��܂�܂��B
�@�@�����Ȃ�傫���ڕW�ł͂Ȃ��A��̓͂��ڕW�������f����A�B�������������邵�A�����ȃc�L���������
�@�@��ł���Ƃ����C�ɂ��Ȃ��ł��傤�B
�@�@�{���Ƀc�L�����邩�ǂ����͕ʂɂ��Ă��A�������O�ɐi�����Ƃ����v���X�v�l�̋C�����������ł���A
�@�@�F�X�Ȃ��ƂŐ����o����ł��傤�B
�@�@�����I�ɖڕW��B���������Ǝv���̂Ȃ�A�S�[������t�ɖڕW�𗧂ĂĂ����Ƃ������@������܂��B
�@�@�@�E �T�N��Ƀr�W�l�X�R�[�`�Ƃ��ēƗ����A�@�l������B�i�S�[���j
�@�@�@�E �S�N��܂łɃN���C�A���g�����ׂR�O�l�o������B
�@�@�@�E �R�N��܂łɂ͔F��R�[�`�̎��i���Ƃ�B
�@�@�@�E �Q�N��܂łɃN���C�A���g�R�l�ɃR�[�`���A���S���w�̊�{���w�ԁB
�@�@�@�E �P�N��܂łɊ�{�I�ȃR�[�`�̕�������B
�@�@����ȋ�̓I�Ȍv��𗧂ĂċN�Ƃ����������R�[�`�̕������������܂��B
�@�@���͂�c�L�ł͂Ȃ��A�v��Ɠw�͂̎����ł���ˁB
�@�� �F�l�̗ւ��c�L������
�@�@�́A�Z���t�R�[�`�̖{���ƁA�����ɂƂ��Ď��Y�ł���P�O�O�l�̒��Ԃ��m�[�g�ɏ����A���Ԃ̊e�l����
�@�@���ɂƂ��Ăǂ��L�v�Ȃ̂��m�ɏ����L���Ə����Ă���܂����B
�@�@�ŏ��͂T�l�ł��P�O�l�ł���������P�A�Q�N�łP�O�O�l�ɂ���Ύ������g�̐����ɂȂ���ƌ����̂ł��B
�@�@�c�O�Ȃ��玄�ɂ́A�͂Ȃ��痘�p����ړI�Ō��������Ԃ��^�̗F�l�ɂȂ�Ƃ͎v���Ȃ������̂ŁA�F�l
�@�@���ɑ��₷���Ƃ͂��܂���ł������A�F�l��������A�c�L�ɏo��`�����X�������ł��傤�B
�@�@�ޏ����P�O�l�ɑ��₷���Ƃ͏o���Ȃ��Ă��A�F�l���P�O�l�ɑ��₷���Ƃ͉\�ł��傤�B
�@�@�����I�g�߂ȖڕW�̘b�͑O���ł����B
�@�@�܂��A�F�l�Ƃ܂ł͌����܂��A�Г��O�̉�ɐϋɓI�ɎQ�����Ēm�l�𑝂₵����A���݂̒m�l�Ƃ�
�@�@�������̋@��𑝂₷�̂��ǂ��ł��傤�B
�@�� �l�ɂ͐e�ɂ���
�@�@�l�ɂ����e�́A�����ɕԂ��Ă��܂��B
�@�@���Ɠ������F�l���ɑ��₷���Ƃ����ȕ����A�l�ɐe�ɂ͏o����ł��傤�B
�@�@�����̕��́A�����Ă��ꂽ���肪�����Ă����珕�������Ǝv���͂��ł��B
�@�@���Ԃ������҂��Đe������̂͗ǂ��Ȃ��ł����A�����ɗ]�T���������͎��͂̕����x�����܂��傤�B
�@�@���Ȃ��ɖ�����������Α�����قǁA�c�L������Ă���`�����X�����܂�܂��B
�@�� �s���ɈӖ�������
�@�@�ȑO�A�E��� �i���v���j �̖@���Ƃ������̂��Љ�����Ƃ�����܂��B
�@�@�����o�����A�K�i����鎞�A�ӎ����č������瓥�ݏo���ƐS���������B�l�W�͗͋������߂�ׂɎ��v��
�@�@��ɂȂ��Ă���B�R�[�q�[�͉E���ɂ����Ɩ����ǂ��Ȃ铙�A�E���̓p���t���̌����Ƃ����b�ł��B
�@�@�^���͂ǂ��Ȃ̂��A���������Ƃǂ��Ȃ̂����͂킩��܂��A�����g�́A���X�����̍s���ƌ��ʂ��ӎ�
�@�@����Ƃ����Ӗ��Ŏ~�߂Ă��܂��B
�@�@���X�����d�������W�X�ƍs���̂���̐������ł����A�����̍s�������Ӗ�������̂ƈӎ���
�@�@�āA�o����ΖڕW�������āA����ƈႤ�����E�����A��N�ƈႤ���N�����ė��N��ڎw���Ă݂ĉ������B
�@�@�T�N�O�A�P�O�N�O�Ɣ�ׂĎ������������Ă��Ȃ��̂��ςł��傤�B
�@�@�����̐����́A�w�͂̌��ʂ��B�����v����A���Ȃ��ɂ͂����A�c�L�Ȃ�ĕK�v����܂���B
�@�@�c�L�i�t���j�⏄�荇�����ĂԂƂ������́A�s���𐬌���������@�̂悤�Ș_���ƂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�@����̘b��̑S�ẮA�������g�ɕ��������ʂ�����������\�͂�����̂��ƁA�������M���邱�Ƃ���{
�@�@�ƂȂ��Ă��邩��ł��B
�@�@�������g�ɂ͉�������������͂�����ƐM����O�������������A�c�L���ĂԃR�c���̂��̂Ȃ̂ł��傤�B
�@�@�����ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
Skill22�@ ���Ԃ������I�Ɋ��p����
�@�@�ȑO�A�X�L������R�S�u���Ԃ����Ȃ��S�̗��R�v�ɂāA���́A���Ԃ�����Ȃ��̂��ɂ���
�@�@������܂����B
�@�@�@�@�@ ����Ɍ��߂�ꂽ��������闝�R�͂Ȃ�
�@�@�@�@�A �Z�����ĕ����I�ɖ���
�@�@�@�@�B �P�Ƀ��[�Y�Ȑ��i
�@�@�@�@�C �[�w�S�����T�{�^�[�W����
�@�@���R�Ɖ������@�͂��ꂼ��ł����A���ʂ��Ă���̂́A�d���⎞�ԂɃR���g���[�������̂ł͂Ȃ��A����
�@�@���d���⎞�Ԃ��R���g���[�����Ă������Ƃ����O�����ȍl�����ł��B
�@�@�ł́A�ǂ�����Ď��Ԃ��R���g���[�����A�����I�Ȋ��p��}��̂��H�@�@���ꂪ����̃e�[�}�ł��B
�@�� �Q�U�Q�̖@���ōl����
�@�@���x���o�Ă���p���g�̂Q�W�̖@���B
�@�@���̗����ɂ��ƁA�Q���̗D��x�̍����d�����A�d���̐��ʂ̂W�����߂Ă���@�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�@�ł́A�c��̂W���̎d���͂��Ȃ��Ă��ǂ��B�Ƃ�����ɂ��s���܂���B
�@�@�����ŁA�^�C���}�l�W�����g�̑��i�K�́A�D�揇�ʂ̒Ⴂ�W���̎d�������������Ƃ���n�߂܂��傤�B
�@�@�W���̎d���́A�T�ˁA
�@�@�@�@�@�@ �D�揇�ʂ͒Ⴂ���A�K�v�Ȏd���B
�@�@�@�@�@�A �D�揇�ʂ��K�v�x���Ⴂ�d���B�@�@�@�@�ɕ��ނ��\�ł��B
�@�@�d�������t�łǂ��ɂ������ɂ��I���Ȃ���Ƃ������́A
�@�@�@�@�@�@�ɓ��Ă͂܂�d���̌������A�@�A�ɓ��Ă͂܂�d���̔p�~�@���������ׂ��ł��B
�@�@�ŋ߂ł͂Q�U�Q�̖@���i�D�G�ȂQ���A�ǂ��������̂U���A���ȂQ���j�Ƃ����l���������邻���ł����A
�@�@���Ȃ��̎d�����A�D�悷�ׂ��Q���A�c���ׂ��U���A�������ׂ��Q���ƒu�������Ă݂�Ɣ���Ղ��Ȃ�܂��B
�@�� �R�̕a�C��r������
�@�@���āA�����̕��́A�^�C���}�l�W�����g�̏�Q�ƂȂ�R�̕a�C������Ă��܂��B
�@�@�܂��͂��̂R�̕a�C��r�����邱�Ƃ��l���ĉ������B
�@�@�P�j ���肬��nj�Q
�@�@����ԍۂɎd����Еt���悤�Ƃ�����A����͂��Ȃ舫���Ȃł��B�w�Z�̏h��Ƃ͈Ⴂ�A�d���͎��X�ƕ�
�@�@���Ă��܂��B�]���āA���T��낤�ƌ��߂��d�����A���ۂɗ��T�o����\���͈�����Ɍ���̂ł��B
�@�@���肬�肬��܂Ŏd���Ɏ肪�����Ȃ��悤�ȕ��́A�B�����ׂ��S�[���Ƃ��̊����m�Ɉӎ����Ă�
�@�@�ĉ������B�S�[������t�Z���A�������X�P�W���[���̂ǂ��ɂ���̂�����Ɋm�F���A�����ׂ����Ƃ��l����
�@�@�K����g�ɂ��܂��傤�B
�@�@�Q�j ������`
�@�@������`�̊F�l�A����ꂽ���Ԃ̒��őS�Ă����Ȃ��͕̂s�\�ł��B
�@�@�u�����v �ł͂Ȃ� �u�i���v ���߂����Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤���B
�@�@�����͈�̐i���ʼn䖝����B�i�������x���d�˂�A�����͊����ɂȂ�܂��B
�@�@�R�j �����őS�Ă�낤�Ƃ���
�@�@�����őS�Ă��Ȃ��ƁA�����̎v���ʂ�̌��ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��B����O�ł��B
�@�@����Ƃ����S�ɗ]�T�������܂��傤�B�ړI���B���o����̂Ȃ瑽���̈Ⴂ�ɂ͖ڂ��Ԃ�̂ł��B
�@�@�����ƁA�������y�Ɏd����C���Ă݂܂��傤�B�����̃~�X�����āA���_�⌴����������Ɨ����o����A
�@�@�{�l�̐����̗ƂƂȂ�͂��ł��B
�@�@�R�̕a�C�A�r���o�������ł����H
�@�@�P�����ɂP�Âł������̂ŁA�����ɓ��Ă͂܂���_���ӎ����čs�����Ă݂ĉ������B
�@�� �d���̐��Y����������
�@�@�d���̐��Y���́A�{�l�̔\���A�d���̐i�ߕ��A�����̂R�v�f�Ō��܂�܂��B
�@�@�������g�̔\�͂��}�Ɍ��シ�邱�Ƃ͂ł��܂��A �d���̐i�ߕ��⓹��ɂ��ẮA �����Ă݂鉿
�@�@�l������܂��B
�@�@�����ł����d���ɒǂ��Ă�����́A����Ȏ��Ԃ͂Ȃ��ƌ�����������܂��A�ق�̂�����Ƃ�������
�@�@������āA�U��Ԃ��Ă݂ĉ������B
�@�@�ł́A�d���̐i�ߕ��B
�@�@�Ⴆ�A��݂����Ɏd����i�߁A�W��ƒ��������܂��s���Ȃ��ƒQ���Ă�����́A�����̎d���̐i�ߕ����A
�@�@����̎d���̐i����l�������X�P�W���[���ɂȂ��Ă��邩��U��Ԃ��Ă݂ĉ������B
�@�@����͂��Ȃ��Ƒō������鏀�����o���Ă��Ȃ����������Ȃ̂�������܂���B
�@�@�ǂ�ȗD�G�ȔO�����ċ����ނ�Ȃ��ᗿ���͍��܂���B
�@�@�u�i���W���v �̌��t�ǂ���A�W��Ƃ̎d���̊��ݍ�����A�d���̗��ꂪ�X���[�Y�ɂȂ�悤�ɁA�d����
�@�@�i��肵�Ă������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B
�@�@����ł́A�����B
�@�@���Ȃ��́A�d�w�b�d�k���g�킸�菑���̕\�ɋL������������d��ŏW�v�����肵�Ă��܂���ł��傤���B
�@�@���̏ꍇ�̂d�w�b�d�k�Ɠ����悤�ɂ��Ȃ��̎d���̌�������}�铹��Ȃ����T���Ă݂ĉ������B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�����Ɠ����悤�Ȏd���A��Ƃ����Ă�������A�ǂ�ȕ��@�Ŏd����i�߂Ă��邩�����T�[�`����ƁA�S�����
�@�@�������ł�������A���ʓI�ȓ�����g���Ă��邱�Ƃ��������邩������܂����B
�@�@���Ђׂ�͍̂���ł��A�E��̐�y�Ȃ狳���Ă���邩���m��܂���B
�@�@���Ȃ��Ƃ��A���̎����̎d���̐i�ߕ����A��ɐ�ɐ������ƖӐM���邱�Ƃ����͎~�߂Ȃ��ƁA�d���̌���
�@�@���͐}��܂���B�@�����v���ĉ������B
�@�� �X�P�W���[���\�Ŏd�����������悤
�@�@������ƑO�ɁA�蒠�p�Ȃ�Č��t�����s�����悤�ȋC�����܂����A���������āA����ȗ��s��������ɂ���
�@�@���܂���ł������H
�@�@�Ƃ͌����A���Ȃ����蒠�̂P���ʂ͎����Ă���ł��傤�B
�@�@��c�E�ō����E�A�|�̗\��A���݉�̗\����L�����Ă܂���ˁB
�@�@���ׁ̈H�@�E�E�E�\����������邽�߂ł���ˁB
�@�@���́A��c����݉�̗\�肾�����L������Ƃ����̂́A�X�P�W���[���\���|�C���g �i�_�j �Ƃ��Ă������p��
�@�@�Ă��Ȃ����ƂȂ̂ł��B
�@�@�Ⴆ�A�蒠�p�̖{�����悤�ɁA���Ȃ��������̖��ɓ��B����܂ł̓��E���W �i�}�C���X�g�[���j����
�@�@��������Ƃ�����A����̓��C�� �i���j �Ƃ��ăX�P�W���[���\�����p���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�@�|�C���g�ƃ|�C���g�����łȂ������H���\���v���W�F�N�g�̊Ǘ��Ɋ��p���Ă�����͑����ł��傤�B�����
�@�@�d���̎菇�̉����ł���ˁB
�@�@�ł������̕�����Ⴄ�d�����m�̌��ˍ����A ���݉�̗\��܂ł���̍H���\�ɏ����Ă�����́A����
�@�@�Ȃ��ł��傤�B
�@�@���Ȃ��̖��܂ʼn�������Ƃ܂ł͌����܂��A
�@�@�������Ȃ����A�d���ɒǂ��č����グ�Ă���Ȃ�A ������Ǝ��Ԃ������āA���Ȃ��̑S�Ă̗\�������
�@�@���邱�ƂŁA�������̎����������邩���m��܂���B
�@�@��x�A
�@�@�������܂łɂ��̂��A�ǂ̍�Ƃ��ǂ̍�ƂɗD�悵�Ă���̂��A���̑S�Ă𖾂炩�ɂ��Ă݂ĉ������B
�@�@�D�݂�����܂����A���ɂP�y�[�W���P�T�Ԃ̎蒠���g�p���Ă�����́A��肠�����A ���J���łP�����̗\��
�@�@�\�Ɏd����ō����̗\��������ڂ������ł��A��X�̗\�肪���������悤�ɂȂ�͂��ł��B
�@�@�Ⴆ�A�����̗\������A��i�⓯���E�����̗\������ŏ����Ă݂�ƁA�@��i�ɏ��F�₷�����ԁA
�@�@���������₷�����ԁA�T�|�[�g�𗊂݂₷�����ԁE�������������Ă���Ǝv���܂��B
�@�@�����Ďd�����������邱�Ƃ̍ő�̖ړI�́A�S�[���m�ɂ��邱�Ƃł͂Ȃ��A�d���ʂ̕��ω���}�邱
�@�@�ƁB�܂蕽�����ł��B
�@�@�d���̏��Ԃ����ւ���A�����i�s�o����d���͓����ɐi�߂�B����ȍH�v�������Ă݂Ă��������B
�@�@���ꂪ�A�^�C���}�l�W�����g�̊�{�ł��B
�@�� �����ƃ^�C���}�l�W�����g���H�v���Ă݂܂��傤
�@�@�� �����o���邱�Ƃ͍������
�@�@�����������邩�͕�����܂���B�����̖Z�����������ɕ��U���邽�߂̒N�ł��m���Ă���s���̊�{�ł��B
�@�@�ł����ꂪ�o���Ȃ��B����ȕ��͎����̂P���Ԃ��ƂĂ��������ƔF�����܂��傤�B
�@�@�� �d�b�͎������炩����
�@�@�d�b��҂̂͐l�̎��Ԃ��ɂ��邱�ƁB����������ł��B
�@�@�ł��A�Ă�Ă��������甲���o�������̂��Ȃ玩������ǂ�ǂ�d�b�������āA�����ŁA�����̎��Ԃ��R���g
�@�@���[�����܂��傤�B
�@�@�� �d���̒����K���m�F����
�@�@����Ȃ�����O�̂��Ƃ������Ă��Ȃ����́A�Ñ�����肻�̂��̂�����Ă���̂�������܂���B
�@�@�ł��d���ɂ͕K�����肪����܂��B
�@�@���Ƃ��]�T�̂���d���ł��A �R���ȓ��Ɏd�グ��̂ƁA �R������Ɏd�グ��̂Ƃł́A���ʂ̉��l���قȂ�
�@�@�܂��B�@�d���̐��ʂɂ͏{�i�����j������B�o���Ă����Ă��������B
�@�@�� �d���̎��Ԃ��L�^���Ă݂�
�@�@�ƌv�������Ƃ����̃��_�������Ă���B�����悤�ɂ��Ȃ�����Ǝ��Ԃ��L�^����A�����̍�Ƃ̃��_
�@�@�������Ă��܂��B�ō����ɂR���Ԏg�����B
�@�@�ړ��ɂQ���Ԏg�����B�c���^�̍쐬�ɂQ���Ԃ��������B���̒�����A�Z�k�o���镔���������Ă���͂��ł��B
�@�@�R�O���őō������I���������͂ǂ�ȏ����������̂��H�@�������������̏��������Ă������B
�@�@����ȍl���������Ă݂ĉ������B
�@�@�� �����������肳����
�@�@���Q�V�ƒ��Q�B�����s����X�g���X�ߑ��ɂ͌��ʂ����B�ł��A���i������Ɩ���Č��C�ȕ��Ȃ�A�v�l�\
�@�@�͂�ቺ������v�f�ł�����܂��B
�@�@�d�����n�߂�O�ɂ�����Ɨ]�T������Ȃ�A���̃E�H�[�~���O�t�o�Ƃ��āA�V����ǂ�A���ނ̐����ł���
�@�@�������v�l�\�̗͂Ր�Ԑ���ۂĂ܂��B
�@�@�Y�Y�Y
�@�@�^�C���}�l�W�����g�Ȃ�Č��t���ƁA�Ǘ��Ǘ��Ǝ����肽���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�@���͎����g�������v���܂��B �ʓ|�Ȃ��Ƃ͂�肽���Ȃ��B �����Ē����͑����Ȃ��B �N�ł������ł��B
�@�@�����ŁA�O�q�̂悤�Ɏ����̎��Ԃ��M�d�ł���ƐM���邱�ƁB
�@�@�����ď��q�����̂悤�ɁA�蒠��g�т̎��ԊǗ��\�t�g���Y��ȊG�����ŃX�P�W���[���������Ď��ԊǗ�
�@�@���̂��̂��y���ށB
�@�@�E�E�݂����ɁA���ԊǗ���d���̍H�v���̂��̂��y���ނ��Ƃ��A�^�C���}�l�W�����g�������������{�Ȃ̂�
�@�@�Ǝ��͎v���܂��B
�@�@�����������A�����ɏo���邱�Ƃ������Ă݂ĉ������B
�@�@�@�Z���t�R�[�`�Q���@�@�@�@�@![]() �@�@�@
�@�@�@![]()